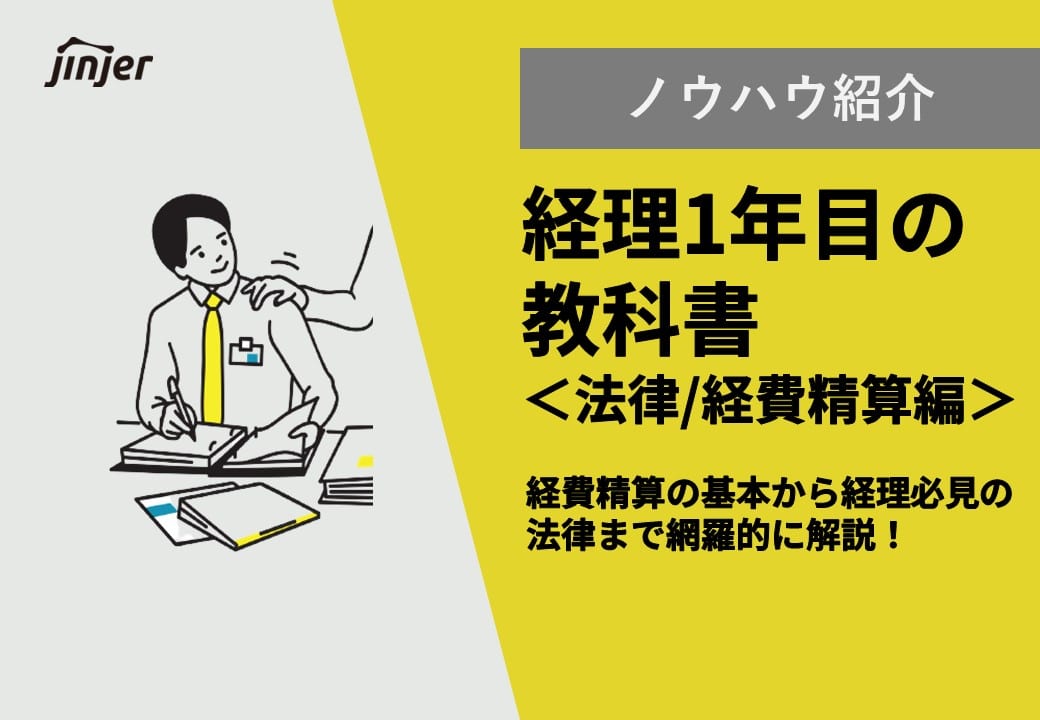貸借対照表と損益計算書の違いとは?活用方法についても解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2022.6.10
jinjer Blog 編集部

貸借対照表と損益計算書は共に「財務三表」に数えられる重要な決算書類です。どちらも企業の経営状況を示した書類ではありますが、2つの表から得られる情報には明確な違いがあります。
それぞれの表から読み取れる経営指標も異なるため、書類ごとの特性を活かして企業分析に役立てることも可能です。
しかし、経営分析をおこなう際は、貸借対照表と損益計算書それぞれの役割を理解しておかなければなりません。
この記事では、貸借対照表と損益計算書の違いや活用方法について分かりやすく解説します。
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
目次
1. 貸借対照表と損益計算書の違い

貸借対照表は「ある一定時点における企業の財務状況」を示す表であり、損益計算書は「一定期間における企業の経営成績」を示す表です。
これら2つの書類を混同しないよう、それぞれの役割をしっかり理解しておくことで企業分析に役立てられるので、どのような違いがあるのかを把握しましょう。
1-1. 貸借対照表は「一定時点における資産と資金のリスト」
貸借対照表とは、ある一定時点(主に決算日)における企業の保有資産と経営資金の調達方法を一覧でまとめた表です。
資金の調達方法には企業の自己資金である「純資産」のほか、借金である「負債」の内約も示されます。つまり、貸借対照表をチェックすることで、決算時点における企業の財務状況が一目でわかるのです。
また、企業の保有資産額と調達資金額は必ず一致する関係あるため、貸借対照表は「バランスシート(BS)」とも呼ばれます。貸借対照表を用いた経営分析では、資産と資金の構成比から経営の安定性や支払い能力を評価します。
貸借対照表は、お金の出どころとそれによって得られた資産を明らかにする表であり、両者に不明な差異があってはなりません。
なお、貸借対照表は左右の2列で構成されており、向かって左列が企業の保有する「資産」、右列が資金の調達方法を示す「負債」や「純資産」が表示される欄です。
また、資産の中でも1年以内の短期で現金化される科目は流動資産、長期で保有する項目は固定資産に区分されます。負債に関しても同様です。
| 資産 | 負債 | |
| 流動資産 |
1年未満の間に現金化される資産 (現金、預金、売掛金、有価証券、商品など) |
1年未満に返済義務がある負債 (短期借入金、買掛金、未払手数料など) |
| 固定資産 |
1年以上の長期で保有する資産 (建物、土地、車両、著作権など) |
1年以上の期間で返済義務がある負債 (長期借入金、社債など)、 |
| 繰越資産 |
長期にわたって効果が及ぶ支出 (開業費、製品開発費など) |
- |
|
純資産 |
返済義務のない企業の自己資金(資本金、資本剰余金、利益剰余金など) *資産・負債には含まない |
|
1-2. 損益計算書は「一定期間の経営成績」
損益計算書は一定期間で発生した収益と経費を一覧で示し、その差額(利益)を明らかにした表です。英語では「Profit and Loss statement」と表記されることから、略してPLとも呼ばれます。収益から経費を差し引いた金額が「当期純利益」となり、その期における企業の経営成績となります。
貸借対照表が決算時点での財務状況を示すのに対し、損益計算書はその期間における収支の内約を示したものです。売上高・利益の推移のほか、経営の効率性を示す収益性の分析などで活用されます。
なお、損益計算書では「経費+当期純利益=収益」となることから、表の左側に経費と当期純利益、右側に収益の勘定科目を表記する方法が一般的です。
また、決算書類として外部に公表する場合は、収益と費用を交互に配置する「報告式」と呼ばれる形式で作成します。
2. 貸借対照表と損益計算書の作り方をわかりやすく解説

貸借対照表と損益計算書は、それぞれ異なる経営指標を示す書類なので作り方も異なります。
基本的に、これらの帳簿を作成するのは、簿記の知識がある方や経理担当者の方ですが、ここでは作り方をわかりやすく簡潔に解説します。
【貸借対照表の作り方】
- 試算表をもとに「資産」「負債」「純資産」に分類する
- 「資産」と「負債」を流動と固定に分ける
- 貸借対照表に記載する
- 左(資産)と右(負債・流動資産)の合計額が合っているか確認する
試算表をもとに作成するので、一見簡単に思えるかもしれません。しかし、例えば「貸倒引当金は「売掛金」や「受取手形」などから控除する形で借方に記載する」「減価償却累計額は固定資産から控除する形で借方に記載する」など細かい注意点があるため、正しく理解するまでは確認しながら作成しましょう。
【損益計算書の作り方】
- 試算表から収益と費用に関する勘定科目と残高金額を抽出する
- 一部の勘定科目は表記を変える(例:売上→売上高 仕入→売上原価)
- 損益計算書の費用と収益に勘定科目と金額を記入する
損益計算書も試算表をもとに作成しますが、貸借対照表ほど複雑な仕訳がなくシンプルな作成方法となっています。とはいえ、「現金や預金などは資産勘定となるため損益計算書には含まない」などの注意点があるので、すべての勘定科目を転記するものではないことを覚えておきましょう。
3. 賃借対照表の勘定科目一覧
 貸借対照表は日々の取引をまとめた書類で、作成する時には「資産の部」「負債の部」「純資産の部」に分類します。
貸借対照表は日々の取引をまとめた書類で、作成する時には「資産の部」「負債の部」「純資産の部」に分類します。
分類は、帳簿の勘定科目に従っておこなうため、それぞれの部にどのような勘定科目が当てはまるのかを知っておくと、スムーズに転記できます。
ここでは、貸借対照表の勘定科目を一覧で紹介するので、作成する際の参考にしてみてください。
3-1. 資産の部
資産の部は、さらに「流動資産」と「固定資産」に分けられるので、それぞれの勘定科目の一覧を見ていきましょう。
| 流動資産 | 固定資産 |
| 現金 小口現金 当座預金 普通預金 定期預金 定期積金 受取手形 売掛金 有価証券 商品 製品 仕掛品 原材料 貯蔵品 前渡金(前払金) 立替金 未収入金(未収金) 仮払金 短期貸付金 仮払消費税 仮払法人税等 |
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 機械装置 工具器具備品 一括償却資産 リース資産 土地 減価償却累計額 ソフトウェア 特許権 差入保証金 保険積立金 投資有価証券 長期貸付金 長期前払費用 出資金 繰延資産 創立費 開業費 |
3-2. 負債の部
負債の部でも、「流動負債」と「固定負債」を分けるので、それぞれの勘定科目を一覧で見ていきましょう。
| 流動負債 | 固定負債 |
| 支払手形 買掛金 短期借入金 未払金 前受金 預り金 仮受金 前受収益 未払費用 仮受消費税 未払消費税等 未払法人税等 買掛金 短期借入金 未払金 前受金 預り金 仮受金 前受収益 未払費用 仮受消費税 未払消費税等 未払法人税等 固定資産 |
退職給付引当金 長期借入金 |
3-3. 純資産の部
純資産の部の勘定科目一覧は以下のようになります。
| 純資産の部 |
|
評価・換算差額等 株主資本 |
4. 損益計算書の勘定科目一覧

損益計算書を作成する時には、試算表の勘定科目を「収益の部」「費用の部」に分類します。
損益計算書の分類も帳簿の勘定科目に従っておこなうため、スムーズに作成するにはそれぞれの部にどのような勘定科目が当てはまるのかを知っておくことが望ましいといえるでしょう。
ここでは、損益計算書の勘定科目を一覧で紹介するので、作成する際の参考にしてみてください。
4-1. 収益の部
収益の部の勘定科目一覧は以下のようになります。
| 収益の部 | |
| 売上高 | 売上高 売掛金 受取手形 |
| 営業利益 | |
| 営業外収益 | 受取利息 受取配当金 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 雑収入 |
| 経常利益 | |
| 特別利益 | 固定資産売却益 投資有価証券売却益 貸倒引当金戻入額 |
| 税引前当期純利益 | |
| 当期純利益 | |
4-2. 費用の部
費用の部の勘定科目一覧は以下のようになります。
| 費用の部 | |
| 売上原価 | 仕入高 仕入値引高 仕入割戻し高 |
| 販売費及び一般管理費 | 役員報酬 給料 賞与 退職金 法定福利費 福利厚生費 販売促進費 外注費 広告宣伝費 荷造運賃 会議費 交際費 寄附金 旅費交通費 通信費 新聞図書費 地代家賃 水道光熱費 修繕費 消耗品費 事務用品費 賃借料 減価償却費 |
| 営業外費用 | 支払利息 有価証券評価損 創立費償却 開業費償却 雑損失 |
| 特別損失 | 固定資産売却損 固定資産除却損 投資有価証券売却損 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税、事業税 |
5. 貸借対照表と損益計算書の活用方法

ここでは貸借対照表、損益計算書それぞれの活用方法を解説します。
一般的におこなわれている分析方法を押さえ、経営分析に役立てましょう。
5-1. 貸借対照表は企業の支払い能力や経営の安定性を確認する
貸借対照表は、企業の支払い能力や経営の安定性の分析に有効です。ここでは代表的な分析方法を紹介します。
・流動比率
流動比率は短期で現金化される流動資産と返済期限が短い流動負債の比率です。流動比率が120〜130%程度の値であれば支払いに余裕があると判断できます。
流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
・固定比率
固定比率は長期で保有する固定資産に対する自己資本(純資産)の比率を示したものです。固定資産を自己資本で賄えていれば余計な借金がなく安定した経営が望めます。
固定比率(%)=固定資産÷自己資本(純資産)×100
関連記事:貸借対照表における純資産とは?経営状況を判断する方法も紹介
・自己資本比率
自己資本比率は総資産(負債+純資産)に対する純資産の比率を示す値です。自己資本比率が高い企業は借金そのものが少なく、健全な資金繰りができていると考えられます。
自己資本比率(%)=(負債+純資産)÷純資産×100
関連記事:貸借対照表における自己資本や経営状況を分析する方法を解説
5-2. 損益計算書では企業の利益率(収益性)を確認する
損益計算書は売上に対する利益率(収益性)の分析に有効です。
ここでは、経営分析で頻繁に用いられる3つの利益率を紹介します。なお、損益計算書では費用を段階的に差し引くため、各段階で収益性をチェックすることで問題のあるコストの洗い出しも可能です。
・粗利率
粗利は総売上高から売上原価を差し引いた状態の利益です。総売上高に対して粗利額が少ないケースは粗利率が低いと考えられます。
粗利率(%)=粗利÷総売上高×100
・営業利益率
営業利益は粗利額から販売管理費を差し引いた「本業の儲け」を表す利益です。販売管理費には広告費用や人件費、交際費などが含まれるため、営業利益率が低い場合は包括的な業務効率改善も視野に入れましょう。
営業利益率(%)=営業利益÷総売上高×100
・経常利益率
経常利益は、本業の儲けを表す営業利益に本業以外の損益も加えた利益です。企業活動全体を通して得られた利益であり、業績を評価するうえでも特に重要視されます。
経常利益率(%)=経常利益÷総売上高×100
6. 個人事業主でも貸借対照表と損益計算書は必要?

貸借対照表や損益計算書は、作成手順はシンプルだとしても、簿記の知識や仕訳の経験がないと作成に時間と手間がかかります。そのため、個人事業主によっては作るのが面倒と感じることがあるかもしれません。
しかし、青色申告で55万円もしくは65万円の控除を受ける場合には必ず必要な書類になります。
貸借対照表は、青色申告をする際に提出する青色申告決算書に含まれる書類なので、作成をしないと控除が受けられません。また、青色申告決算書では損益計算書を記入する欄もあるため、損益計算書も必要です。
控除を受けるための要件は他にもありますが、貸借対照表と損益計算書がないと10万円までの控除しか受けられないので、しっかりと節税対策をおこないたいという個人事業主の方は作成する必要があるといえるでしょう。
貸借対照表や損益計算書の作成は企業会計原則で定められています。また、作成した書類は、社会法によって税務署や株主への開示義務があるので注意が必要です。更に、会計書類の電子保管にあたっては電子帳簿保存法によって要件が定められています。このように、決算書類の作成から保管までには多くの法律や原則に則っておこなわなければなりません。そのため、経理担当者は業務をおこなう際の基本知識として、関連する法律についても知っておく必要があるでしょう。
当サイトで無料配布している「経理1年目の教科書」では、経理担当者や個人事業主が押さえておくべき業務の基本や法律について解説しています。ふと疑問が浮かんだときにすぐに読み返せるよう、ダウンロードして保管しておくのがおすすめです。興味がある方は、ぜひこちらからご覧ください。
7. 貸借対照表と損益計算書の違いを把握して経営分析に役立てよう

今回は貸借対照表と損益計算書の違いや、各書類の役割について解説しました。
貸借対照表は資産・資金のリストであり、企業の財務状況を示す書類です。一方、損益計算書は企業の収支の内約を示し、当期純利益などの経営成績を表します。どちらの書類も、企業会計原則において作成が義務付けられているものですが、正確に作成することで、自社の経営状態や資金繰りの問題などを把握できます。
また、それぞれの表から読み取れる経営指標も異なるため、貸借対照表と損益の特性を活かして企業分析に役立てましょう。
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04