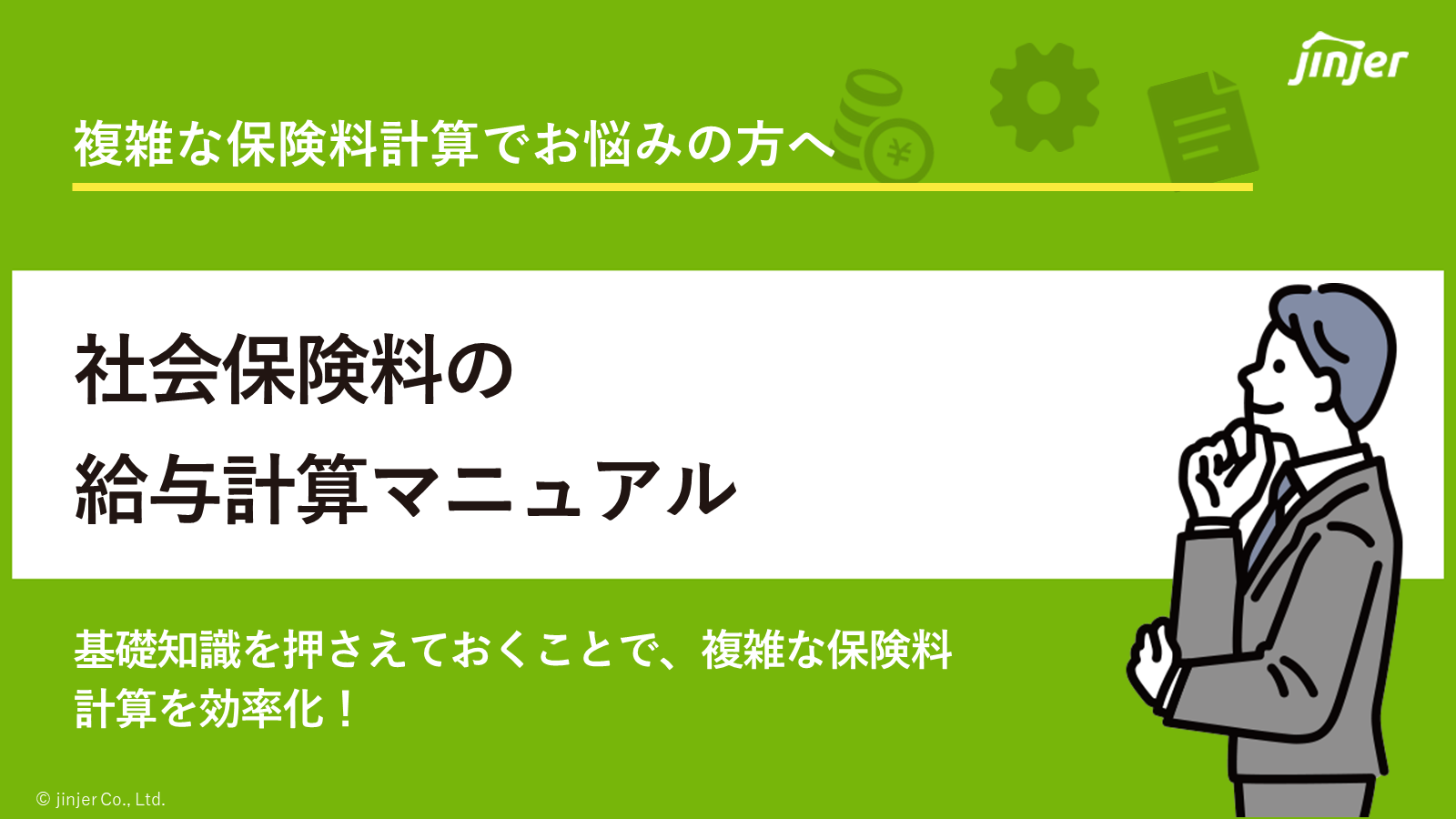退職日で社会保険料はどれだけ変わる?月末、15日付(月中)の途中退職の場合も紹介
更新日: 2024.4.22
公開日: 2022.3.18
OHSUGI

給与から控除する社会保険料というのは、従業員がいつ退職するかによって控除額が異なります。
特に、月末の退職では前月分と退職月分、2カ月分の保険料を控除する必要があるため、計算を間違えないように注意しなければいけません。
ここでは、退職日による保険料額の差や月の途中で退職するときの注意点、退職後に従業員が支払う社会保険料の種類を解説します。
目次
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
1. 退職日により社会保険料の差が決まる


社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)は、従業員がいつ退職したかによって、給与から控除する額が変わってきます。具体的にいうと、月末に退職するか、月末より1日前のいずれかの日に退職するかによって控除額が異なります。
ここでは、5月に退職する従業員を例に、退職日により社会保険料額がどのように変わるかを解説します。
1-1. 月末の1日前(30日)に退職したとき
5月30日(月末1日前)に退職する場合であれば、社会保険資格喪失日は5月31日となります。社会保険料というのは、控除する月の前月分を給与から差し引いて支払いますが、このケースでは退職月と資格喪失の月が同月になるので、社会保険料の支払いは4月(前月)分のみとなります。
そのため、退職する月であっても、従業員支払い分は給与から控除し、会社負担分と合わせて納付するという通常の処理方法で問題ありません。
1-2. 月中の15日に退職したとき
月中となる15日付で退職した場合、1-1の月末の1日前(30日)の退職と基本的には同じく、前月分までの社会保険料を納めれば良いことになります。例えば5月15日に退職した場合、資格喪失日は16日となるため、4月分の社会保険料を納めることになります。
1-3. 月末に退職したとき
5月31日に退職した場合は社会保険資格喪失日が6月1日になるので、4月(前月)分と、5月(退職月)分の社会保険料を支払わなければいけません。
なお、従業員は社会保険料の支払いの仕組みを知らない可能性があるので、社会保険料が2ヵ月分控除されていることに対しクレームをいってくるかもしれません。このようなトラブルを防ぐためにも、社会保険料は退職月の給与から2カ月分まとめて控除する場合は、事前に従業員に伝えておくことをおすすめします。
また、従業員の中には手取りが減るのを嫌って、月末1日前の退職を申し出るケースもあります。再就職まで1日でも日が開くと、国民年金保険と国民健康保険への加入が必要になるので、転職先が決まっていない従業員には事前に説明しておきましょう。
1-4. 社会保険上の退職日に平日・休日の差はない
退職日は、平日・休日どちらでも、実務上の違いはありません。
例えば、30〜31日が祝日であったとしても、社会保険上の退職日が29日になることはありません。
ただし、会社の休日に退職日が重なる場合は健康保険証の回収を前倒しにするか、後日郵送してもらうかしっかりとした取り決めをしておきましょう。担当者は、資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」と「保険者証」を年金事務所に提出する必要があります。健康保険証が回収できないと資格喪失の手続きが遅れてしまうので、必ず回収する手段を決めておいてください。
1-5. 社会保険料は日割り計算ではなく月割りで計算する
社会保険料は日割り計算ではなく、1ヵ月単位の月割りで計算して納付します。そのため、極端な例になりますが、1日だけしか在籍していないとしても、社会保険料は1ヵ月分を支払わなければなりません。
つまり、月末前と月末では退職日が1日違うだけで保険料額に1ヵ月分もの違いが生まれてしまうことになります。
退職をした従業員の健康保険証は回収するので、例え1ヵ月分の社会保険料を払っていても健康保険は使えないため、「社会保険料は月割り計算」ということを従業員にしっかり理解してもらいましょう。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
2. 社会保険料の締日は退職日の翌日


退職日が月末かそれ以外の日付かにより、社会保険料額に差が出るのは、社会保険料の締め日(資格喪失日)の考え方によるものです。
社会保険料の締め日は、「退職日」ではなく、「退職日の翌日」です。
また、社会保険料は退職日の翌日が含まれる月の前月分まで発生します。
具体例を上げると、退職日5月31日がなら、社会保険料の締め日は6月1日となり、前月である5月分まで保険料が発生します。
社会保険料は通常、当月分の給料から前月分の保険料を控除します。
しかし、月末退職の場合は例外的に、前月分と当月分の保険料を退職月の給与から控除できます。n本章で解説した内容は、社会保険料の算出方法や保険料が決定するタイミングなどの基礎知識を知っているうえで理解できる内容になります。当サイトでは、上述した社会保険料の基礎知識から計算方法、効率的に業務を行う方法までを解説した資料を無料で配布しております。
社会保険料に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
3. 月の途中退職では社会保険料にどのような差が出るのか?


月の途中で退職しても、基本的には前月分の社会保険料を従業員の給与から控除すれば問題ありません。
しかし、入社当月に退職するなど稀なケースでは、処理方法が異なるため注意が必要です。
3-1. 入社した当月に退職したとき
社会保険は入社日が資格取得日となるため、その月分から保険料を納めますが、月の途中から入社したときも同じ対応になります。
例えば、4月3日に入社して4月5日に退社した従業員がいれば、2日間しか出勤していなくても、1カ月分の社会保険料を納めなくてはいけません。
本来同一の月に資格の取得と喪失があれば、当月の給与から保険料を控除できます。
しかし、給与が少なく保険料を控除できないときは、従業員から後日徴収する必要があるので、退職前に伝えておくようにしましょう。
3-2. 入社当月に退職し、同じ月に社会保険に加入した場合
入社した当月に退職した従業員が、同じ月に厚生年金保険や国民年金保険に加入した場合、支払った保険料は還付されます。実務ではこのケースがほとんどでしょう。
同月内に取得と喪失が2回ある場合、年金保険料を二重に支払うこととなるため、新しく取得した資格が優先されます。会社は従業員の給与から控除した分の保険料を返還しなければいけません。
なお、健康保険の場合、このような制度はありません。
3-3. 賞与を受け取って退職したとき
社会保険料は給与だけでなく、賞与からも控除が必要です。しかし、控除は「退職する月の末日に会社に在籍している」というのがポイントになるので、退職日によって控除するかどうかが変わってきます。
例えば、7月10日に賞与を支給して、7月20日(末日以外の日)に退職をするのであれば、賞与から保険料を控除する必要はありません。一方、7月31日(末日)に退職をする場合は控除する必要があるので間違えないようにしましょう。
3-4. 健康保険証の扱い
健康保険の資格は退職日の翌日に喪失するので、従業員に「資格喪失の説明」をおこなって健康保険証を速やかに回収しましょう。従業員は健康保険証がないことに不安を感じるかもしれませんが、病気や怪我をしたとしても、退職日以降は保険証が使えなくなります。
資格喪失に退職日は関係ないため、月の途中の退職であっても保険証は使えません。
なお、従業員が誤って資格喪失後に保険証を医療機関で使用したときは、後日、従業員本人に請求が届きます。
4. 退職後に従業員が加入する社会保険の種類と注意点


退職後、従業員が支払う保険料は加入する制度により異なります。
説明を間違えるとトラブルにつながる部分でもあるため、人事・労務担当者も加入制度を正しく把握しておきましょう。
4-1. 退職後に加入する社会保険の種類
退職後、従業員が加入する社会保険には下記の種類があります。
【年金保険】
- 転職先の厚生年金(第2号被保険者)
- 国民年金保険(第1号被保険者)
- 配偶者の扶養(国民年金)(第3号被保険者)
【健康保険】 - 転職先の保険制度(協会けんぽ・健康保険組合)
- 健康保険の任意継続
- 市区町村の国民健康保険
- 健康保険加入者の被扶養者
従業員が健康保険の任意継続をしたいと申し出た場合、下記の2つの手続きが考えられます。 - 協会けんぽに加入している会社 :従業員自身が任意継続の手続きをする
- 健康保険組合に加入している会社:人事担当者、または、従業員本人が任意継続の手続きをする
会社が健康保険組合に加入している場合、会社側で任意継続の手続きが必要なこともあるため確認しましょう。
関連記事:社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険の特徴について
4-2. 退職後、国民健康保険や任意継続被保険者になるときの注意点
従業員が退職後、国民健康保険や任意継続保険に加入する場合、退職日によって、本人が負担する保険料額が変わります。
月末退職の場合:退職月の保険料は、半分を会社が負担する
月末以外の場合:退職月の保険料は、全額従業員が負担する
会社側は、資格喪失月の健康保険料を支払う必要はありません。
そのため、月中に従業員が退職し、次に加入する保険が国民健康保険や任意継続保険の場合、保険料は全額自己負担となります。このことを、従業員が知らないまま月中に退職をした場合、保険料を払えないというケースがあるかもしれないので、しっかりと説明しておくことをおすすめします。
4-3. 退職後、扶養に入る場合の注意点
退職後、配偶者の扶養に入るケースでは、月中に退職した方が従業員本人の社会保険料負担額を減らせます。
月末退職の場合:退職月の保険料は給料から控除する
月末以外の場合:退職月の保険料は扶養に加入するため負担なし
このように、月末以外の日付で退職した方が、従業員本人の手取り額を増やすことが可能になるのです。そのため、このことを従業員が知らずに月末退職をした場合、後になって「知らなかった」などのトラブルが起こる可能性があるため、事前に説明しておきましょう。
5. 退職時の社会保険料は間違いのないように給与から控除しよう


退職時の社会保険料は変則的な控除方法となるため、正確な方法をしっかり把握しておく必要があります。また、トラブル防止のためにも、社会保険料控除の仕組みは前もって従業員に説明しておきましょう。
もう一つの注意点は、退職後に従業員がどのような社会保険制度に加入するかにより、手続き方法が異なるケースがあるということです。退職時の社会保険料の計算方法や手続きはケースによって変わることがあるので、人事や経理担当者はそれぞれの違いを理解し、従業員からの問い合わせがあれば説明できるように準備しておくことをおすすめします。
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25