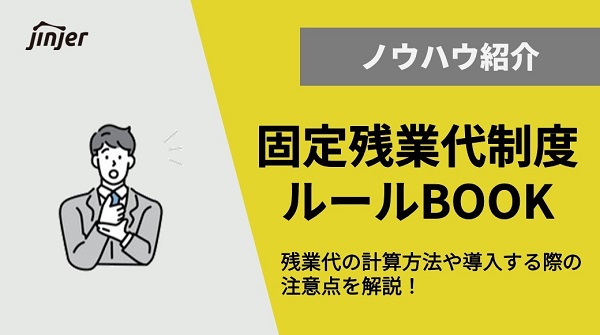固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
更新日: 2024.3.7
公開日: 2021.9.7
OHSUGI

残業の有無に関係なく固定給に含まれる「固定残業代」の上限は45時間といわれています。45時間を超えた時間を設定していると、違法と判断される可能性があります。
本記事では、なぜ上限が45時間なのか、45時間超えが認められることはあるのか、残業時間が45時間を超えたときのリスクなどについて解説します。
関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
「固定残業って何時間まで大丈夫なの?」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし残業の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
1. 固定残業代の上限は45時間?

まずは固定残業代の上限や、上限を超えてしまった際の問題を正確に把握しておきましょう。固定残業制にはマイナスのイメージを持つ人が少なくありません。会社に悪影響が出ないように、適正な労働環境を維持する重要なポイントです。
1-1. 固定残業代の上限
固定残業代とは、実際の残業時間に関わらず、一定時間分の時間外労働に対して毎月定額で残業手当を支払う制度のことです。固定残業代を導入する際は、時間外労働の時間を設定しなくてはいけません。
時間外手当を払わずに長時間勤務ができると考え、設定時間を50時間や100時間にすることは不可能です。なぜなら、労働基準法第32条で労働時間は1日8時間・週40時間と決まっていて、原則として時間外労働は認められていないからです。
しかし時間外労働は、業務量によって避けることが難しい場合も多々あります。そこで、労使間で36協定を結び、労働基準監督署に届出をすることによって、時間外労働が認められるようになります。
ただし時間外労働も制限なく命じられるわけではなく、原則として月45時間・年間360時間が上限とされています。時間外労働の制限が月45時間であるため、固定残業代の上限も45時間と考えるのが妥当です。
なお、固定残業代の支給額は労働基準法等で明言されていないため、45時間を超えた固定残業代に設定したからといってただちに違法になるとは限りません。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
1-2. 上限を超えた場合の問題
固定残業制の残業時間は45時間が妥当であるとお話をしました。しかし、労使協定の内容によってはこの上限を超えた残業時間を設定することが可能です。繁忙期などに限定して45時間を超える残業時間を設定している企業も少なくありません。
しかし、長時間の勤務は従業員の負担を大きくします。継続すれば肉体的・精神的な問題を抱えやすくなるため、長時間の時間外勤務が常態化しないように気をつけましょう。
また、固定残業代を45時間以上に設定している場合、従業員や求職者から「違法な時間外労働を強いる企業なのではないか」と思われ、マイナスイメージにつながる可能性はあります。また、そもそも36協定を結んでいない状態で時間外労働をさせることは違法であるため、注意しましょう。
時間外労働については、2019年の働き方改革関連法で上限が設けられ、罰則付きで規制されるようになったことも知っておく必要があります。
当サイトでは、残業時間の定義と法改正による上限規制をまとめた資料を無料で配布しております。残業時間の定義や上限規制の内容について不安な点がある方は、こちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご確認ください。
参考:働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)|厚生労働省
2. 残業時間の45時間超えが認められる場合と認められない場合
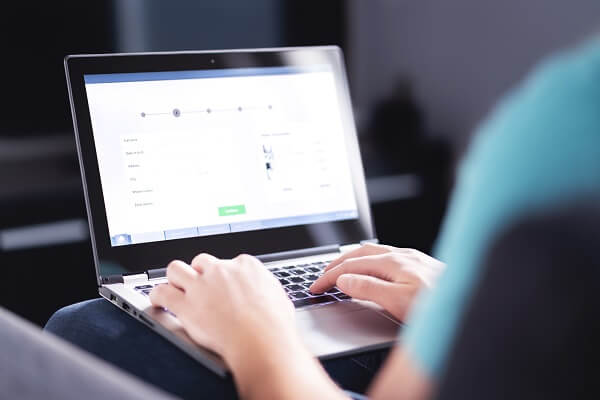
労働基準法により、時間外労働は45時間が上限とされています。しかし、この上限は特定のケースにおいて超えることが認められています。45時間超えが認められるケースと認められないケースを知っておきましょう。
2-1. 残業時間の45時間越えが認められるケース
45時間の上限を超えて時間外労働を設定できるのは、特別条項付きの36協定を結んでいる場合です。
特別条項付き36協定を締結済みであれば、月45時間・年間360時間の制限を超えて時間外労働ができます。
しかし無制限に時間外労働ができるわけではなく、以下のような条件があります。
- 1ヵ月の上限時間:100時間未満
- 1年間の上限時間:720時間以内
- 時間外労働時間の2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月平均:いずれも80時間以内
- 時間外労働が45時間を超えるのは1年のうち6ヵ月以内
例えばある月の時間外労働が90時間で、その翌月も90時間だと、1ヵ月の上限時間には収まっていますが、2ヵ月平均が90時間で、80時間を超えてしまうため、違法です。
また月45時間・年間360時間の制限は時間外労働に対してですが、月100時間・年間720時間の制限は時間外労働に加えて、法定休日に働いた場合に適用される休日労働も含みます。
例えば時間外労働が40時間でも、休日労働が60時間を超えていれば、合わせて100時間を超えるため違法になります。この辺りは少し複雑になっているため注意が必要です。
また特別条項付きの36協定が結ばれていれば、45時間を超える時間外労働がいつでも認められるわけではありません。認められるには特別な事情が必要です。
特別な事情とは具体的でなくてはならず、例として次のようなケースが挙げられます。
- 予算・決算業務
- ボーナス商戦
- 納期がひっ迫している
- 大規模クレームへの対応
- 機械トラブルへの対応
繁忙期や避けようのないトラブルへの対応などが該当します。また、こうした理由がある場合でも、従業員の健康面を考えて時間外労働は可能な限り短くすることが望まれます。
関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!上限時間や違反した際の罰則を解説
2-2. 残業時間の45時間越えが認められないケース
特別条項付き36協定を結んでいる場合でも、45時間超えの残業時間が認められないケースがあります。
特別な事情がない場合や、あったとしても「業務上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」などといったものは抽象的で、いつでも起こり得るものである場合です。これらは特別な事情とは認められず、45時間を超えた残業を命じることに正当性がなくなります。
違法になる以上罰則が発生する恐れもあるため、45時間を超える残業を命じる場合や設定する場合は、必ず具体的で特別な事情を提示できるように意識しましょう。
当サイトでは、本章で解説した残業時間の上限規則に関して、残業の定義から残業管理の課題解決方法までを解説した資料を無料で配布しております。自社の残業管理に不安な点がある方は、こちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご確認ください。
3. 従業員の残業時間が45時間を超える5つのリスク

45時間を超える残業は法律上の問題もありますが、長時間の時間外労働により引き起こされる従業員のリスクについても考えなければなりません。ここでは、起こりうるリスクをいくつか挙げてみましょう。
3-1. 従業員のやる気が失われる
時間外労働が長ければ長いほど、心身は疲弊して従業員のやる気が失われてしまいます。会社とのエンゲージメントも低下するでしょう。
「やる気がないくらい普通のことだ」「どこの企業でもあることだ」と思うかもしれませんが、モチベーションの低さは伝染するうえにさまざまな悪影響をもたらします。
さらに、よりやりがいのある職場や、働きやすい職場、条件の良い職場を求めて人材の流出が起こる可能性も高くなるでしょう。
3-2. コストが増大する
時間外労働が増えれば、当然支払わなくてはならない時間外手当も増えていきます。加えて、従業員が残っている間の光熱費も発生するため、人件費を中心にあらゆるコストが高くなっていきます。
前述したやる気の消失により業務効率も低下し始めている場合は、無駄な長時間勤務でコストだけが増え、業績は上がらない状況になります。このような状態は企業にとって大きな損失であり、業績悪化のきっかけになりかねないでしょう。
3-3. 従業員の健康が損なわれる
過重な労働が続けば、従業員がうつ病をはじめとした精神疾患にかかってしまう恐れもあります。精神疾患は一度発症すると長引き、簡単に治る病気ではありません。
短くても数ヵ月、最悪数年かかってしまうこともあり、休職する人も出てます。そうなるとそれまでの間、貴重な人材が減ってしまうばかりか、休職した従業員の手当も必要です。
病気になった従業員やその家族から、訴訟を起こされるリスクもあることを覚えておきましょう。
3-4. 従業員を失うリスクが上がる
長時間の勤務で肉体的・精神的に追い詰められた従業員は、体調を崩すだけでなく過労死・自死に至るケースが考えられます。いずれの場合も会社にとっては大きなダメージになるでしょう。
特に過労死や自死の場合は、問題が非常に大きくなる可能性があります。
厚生省が発表している「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」によると、時間外労働が45時間を超えれば超えるほど、脳・心臓疾患といった過労死との関連性が高まるとされています。
さらに時間外労働が100時間、または2〜6ヵ月平均で80時間を超えると、過労死との関連性が強く疑われるようになります。
時間外労働の時間数だけで一律に過労死が認定されるわけではありませんが、45時間を超えて働かせた場合、過労死と認定される可能性が高まっていくことは認識しておく必要があるでしょう。
従業員が過労死したと認定されれば、当然会社の責任が問われます。遺族から損害賠償や慰謝料を求めて民事裁判を起こされる可能性は高くなります。
3-5. 企業の信用が失墜する恐れがある
長時間勤務が常態化していたり、激務によって従業員が体調を崩したりしていることが知られると、「ブラック企業」の烙印を押されてしまうでしょう。近年はSNSでこういったネガティブな情報は短時間で広がります。
ブラック企業であると知って求人に応募する人はおらず、離職者も増えるでしょう。炎上するような事態になれば、不買運動も起きるかもしれません。人材不足や売り上げの低迷により、企業の存続そのものが危ぶまれる恐れがあります。
認可が必要な事業である場合は、最悪事業認可の取り消しも考えられます。そうなってしまうと、今まで積み重ねてきた企業の信用が一瞬で崩壊し、それらを回復することは簡単ではありません。
4. 従業員のやる気と健康のために固定残業代は45時間以内に抑えよう

固定残業の上限は、必ずしも違法になるとは限らないものの45時間までに押さえておくのが妥当です。
それ以上の時間外労働を強いていると、従業員が病気になる、過労死する、ブラック企業といわれてしまうなど、さまざまなリスクが増大していきます。起こりうるリスクをよく検討して、適切な固定残業の時間を設定することが大切です。
関連記事:固定残業代とは?制度の仕組みや導入のポイントを分かりやすく解説
関連記事:みなし残業制度とは?定義やメリット・デメリットを詳しく解説
「固定残業って何時間まで大丈夫なの?」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし残業の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25