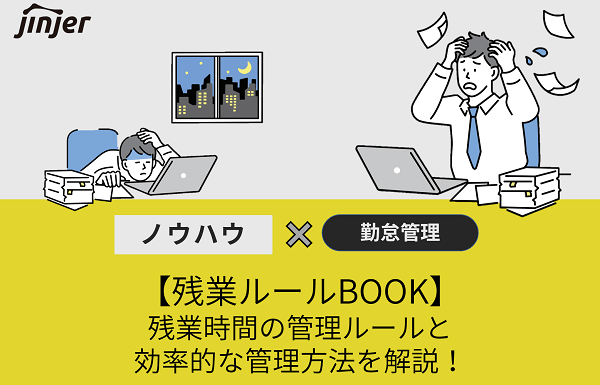残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

残業という言葉を私たちは日常的に使いますが、厳密な定義は、私たちのイメージと少し違っています。「残業代が支払われない!」といったトラブルの一部は、残業時間の定義を理解していないことが原因かもしれません。
この記事では、労働法における厳密な意味での残業時間についての説明をするとともに、さらに理解を深めるためのポイントまで紹介しています。労働者、使用者の双方に役立つ内容となっています。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 残業時間の定義を理解してトラブルを回避しよう

「残業」と聞くと、終業時間を超えて働いた時間をイメージされる方が多いでしょう。しかし、より厳密に分けると残業は「法定内残業」と「時間外労働(法定外残業)」の2つに分けられます。このうち、割増賃金の支払い義務があり、労働時間に上限規制が設けられているのは「時間外労働」です。
「法定内残業」と「時間外労働」の違いをご説明する前に、「所定労働時間」と「法定労働時間」についておさらいしておきましょう。
1-1. 所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間とは、各企業の就業規則に定められている労働時間を指します。対して法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間で「1日8時間、週40時間まで」という上限が設けられています。
例えば、就業規則にて勤務時間は10時~16時と定められていた場合、6時間が所定労働時間になります。
多くの企業では所定労働時間が8時間であるため、所定労働時間と法定労働時間は同じものであると混同しがちですが、異なる労働時間です。
【関連記事】労働時間とは?社会人が今さら聞けない基本情報を徹底解説!
1-2. 労働基準法における残業の定義は時間外労働
所定労働時間と法定労働時間の違いを確認できたうえで、法定内残業と時間外労働についてご説明します。
法定内残業とは、所定労働時間を超え、法定労働時間以内で働いた時間です。一方、時間外労働は法定労働時間を超えて働いた時間になります。
労働基準法に基づく残業とは時間外労働のことであり、「1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間」を指します。私たちが日常的な会話で口にする残業(勤務時間を超えて働いた時間)と厳密には考え方が異なるため、違いを理解しておきましょう。
残業時間の定義や法律の内容をわかりやすく解説した「残業管理のルールBOOK」はこちらからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
2. 残業時間の仕組みを理解するポイント

残業時間の理解を深めるには、定義を理解したうえでさらに3つのポイントを確認しておく必要があります。労働基準法で残業がどのように扱われているのかが分かれば、残業時間に対する正しい認識を持つことができるでしょう。
2-1. 時間外労働を命じるためには36協定を締結する必要がある
残業についての国の見解は、「勝手に残業をさせてはならない」というものです。企業が労働者に時間外労働をさせる場合は、事前に36協定を締結しなくてはなりません。
36協定は、労働組合(または労働者の過半数代表者)と使用者が残業に関する合意事項をまとめた書類です。残業を命じるにあたり、36協定が締結されているのは勿論ですが、過半数代表者の選任などに問題があると、36協定そのものが無効となることもあります。
もし、36協定の締結をしないで労働者に残業をさせてしまうと、刑事罰をともなう罰則が科される恐れがあります。また、36協定を締結した場合でも、原則として月45時間、年360時間を超える時間外労働はさせられません。
次に紹介する特別条項付き36協定が締結された場合に限り、基準を上回る残業を命じられるケースがあるのです。
【関連記事】36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
2-2. 残業時間には上限規制がある
特別条項付き36協定は、業務の性質上、臨時的に法律の限度時間を超えて残業をさせなければならない事情がある場合に、例外的に限度時間を超えられる、という内容の協定です。
特別条項がなければ、月45時間、年360時間が限度ですが、とくに業務が逼迫している時は労使の協議をおこなうことにより特別条項を付けると月100時間未満、年720時間以内が残業時間の限度となります。また、特別条項を適用して45時間を超えて残業を命じられるのは一年につき6ヶ月までであり、休日出勤させた時間を含め2~6か月間の残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなくてはなりません。
これらの上限を守らずに残業時間の規制を超過して従業員を働かせると法律違反となり、罰金30万円以下または6ヶ月以下の懲役が罰則として課せられます。知らずに超過してしまっていても法律違反に該当することは変わりありませんので、厳格な勤怠管理をおこなう必要があります。
第1章でも解説しましたが、残業時間に関する定義を誤って認識してしまうと、時間外労働の計算が正しくできず、知らないうちに法律違反になる可能性があります。そのため、まずは法定内残業や法定外残業の定義と違いをきちんと理解しておきましょう。
【関連記事】残業の最新情報!上限や違反罰則など知らないとまずい基礎知識
3. 時間外労働には割増賃金の支払いが必要


時間外労働には25%以上の割増率で割増賃金を支払う必要があります。一方、「残業」であっても法定内残業には割増賃金を支払う必要がありません。時間外労働に対する割増賃金は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた場合に支払いの義務があるためです。割増賃金の支払いは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなども対象です。
時間外労働に対する割増賃金は、以下の計算式によって求めることができます。
残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率(1.25以上)
1時間あたりの基礎賃金は、時給制の従業員であれば時給を利用します。月給制の従業員であれば、月給から個人的事情に基づいて支給されていることなどにより家族手当や通勤手当などといった労働基準法や労働基準法施行規則で定められた賃金を除いた金額を月の平均所定労働時間で割った数値が1時間あたりの基礎賃金となります。
なお、月の時間外労働が60時間を超える場合の残業に対しては、50%以上の割増率で賃金を支払わなければなりません。
月の平均所定労働時間は以下の記事で詳しい計算方法を解説していますので、確認しておきたい方は、ぜひご一読ください。
【関連記事】月の所定労働時間|平均の出し方や残業時間の上限について詳しく解説
【関連記事】残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説
3-1. 時間外労働を10時間した場合
10時間の時間外労働は、月45時間の範囲内です。そのため、割増率は25%以上です。時間外労働にあたる10時間を計算する際は、時給換算した金額に25%以上をかけます。
例えば、時給換算した給与が1,900円であった場合、1時間あたりの割増賃金は2,375円です。そのため、10時間の時間外労働に対しての残業代は次のとおりです。
- 10時間×2,375円=23,750円
3-2. 法定休日労働を7時間した場合
法定休日に出勤して労働した場合は残業としては扱われません。法定休日に労働をした場合は休日労働として扱われます。休日労働の割増率は35%です。時給換算した給与が1,900円であれば割増賃金は2,565円です。
そのため、休日労働を7時間した場合の残業代は次のとおりです。
7時間×2,565円=17,955円
3-3. 時間外労働を20時間、時間外の深夜労働を3時間した場合
時間外労働が20時間であれば割増賃金率は25%です。一方、時間外かつ深夜に勤務した場合は、時間外労働の割増賃金率と深夜手当をつけなければなりません。時間外の割増賃金率、深夜手当はどちらも25%なので割増賃金率は50%です。
例えば、時給換算した給与が1,900円の場合、時間あたりの時間外労働の割増賃金は2,375円です。一方、時間外労働かつ深夜労働の割増賃金は2,850円です。
時間外労働を20時間、時間外の深夜労働を3時間した場合の残業代は次のようになります。
- 時間外労働:20時間×2,375円=47,500円
- 時間外の深夜労働:3時間×2,850円=8,550
- 時間外労働・時間外の深夜労働の合計:47,500円+8,550円=56,050円
3-4. 時間外労働を68時間した場合
時間外労働を68時間した場合、60時間は25%以上の割増率です。一方、60時間をオーバーした部分は50%以上の割増率が求められます。
時給換算が1,900円の場合、1時間あたりの残業代は2,375円です。対して60時間をオーバーしている部分の1時間あたりの残業代は2,940円です。
そのため、時間外労働を68時間した場合の残業代は次のように計算可能です。
- 60時間の時間外労働:60時間×2,375円=142,500円
- 60時間を超える時間外労働:8時間×2,940円=23,520円
- 時間外労働の合計:142,500円+23,520円=166,020円
4. 注意!これも残業時間にあたります


残業時間の定義について確認したところで、「実は残業にあたる」という時間をご紹介します。何が残業時間にあたるかを正確に把握しておかなくては、残業代未払いの問題に発展しかねません。盲点になりやすい残業時間についても、おさえておきましょう。
4-1. 朝の掃除や制服への着替え時間は「朝残業」
「残業」というと、終業時間を超えて労働した時間をイメージしがちですが、最初にご説明した通り残業=時間外労働は「法定労働時間を超えて労働があった時間」です。
したがって、9~18時が定時の企業で朝8時に出社して仕事をはじめ、18時に退社した場合は朝に早く出社して仕事をした1時間分が時間外労働となります。
同じく、制服に着替える時間や上司の指示や会社の決まりとしておこなう朝の掃除時間なども使用者の指揮命令下にある「労働時間」とみなされ、時間外労働であれば残業代の支払いが必要になります。
4-2. 年俸制でも残業代は必要
年俸制は1年あたりの給与を月々に分割して支払う制度です。「1年分の給与があらかじめ決まっている」というイメージから残業代が発生しないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、時間外労働が発生した場合は割り増し分を上乗せして残業代を支払わなければなりません。
4-3. 参加が強制の研修や学習時間
参加が強制となっている社内研修や、上司から指示を受けて行った学習による時間は「使用者の指揮命令下にある時間」として労働時間に該当します。厚生労働省では労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。
もし社内研修や学習時間を終業時間後に設けているのならば、時間外労働にあたり割増賃金の支払い義務が発生する可能性があるため、注意しましょう。
参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省 岡山労働局
4-4. サービス残業の是正も大切
労働時間にあてはまらないものの、実質的に従業員が「サービス残業」となる労働を行っていないかを確認することも、勤怠管理をする上で大切なことです。
サービス残業にあたるものの例として、従業員が仕事を個人的に持ち帰って家で業務をおこなうことが挙げられます。また、管理職には残業代の支払いが必要ないからといって「名ばかり管理職」にされ適切に賃金が支払われていない従業員がいる場合もあります。
特に注意しておきたいことは、残業時間は1分単位で記録し残業代の計算をする必要がある点です。15分や30分のまるめ、切り捨て処理は違法になり、適切な残業代計算ができないとサービス残業になってしまう可能性があります。
ただし、一ヶ月の合計残業時間に対して30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる処理は例外的に認められています。
【関連記事】1分刻みは常識!タイムカードで残業時間を正しく計算する方法
5. 残業時間への理解を深め不要なトラブルを防止しよう

企業は従業員の健康を守らなければなりません。そのため、従業員にとって負担になる残業時間について、しっかりとルールを把握しておく必要があります。例えば、朝の掃除や制服への着替え時間は朝残業とみなされる、参加が強制の研修や学習時間も残業とみなされるなど、ルールを把握しておかなければ残業代未払いにつながりかねません。企業として成長するには、労使のどちらの立場であっても残業時間に関する理解を深め、正しい知識を持つことが大切です。
【関連記事】残業申請で正しい勤怠管理|ルールの作り方と運用方法、見直し方も紹介
【関連記事】残業削減対策の具体的な方法・対策と期待できる効果について解説
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25