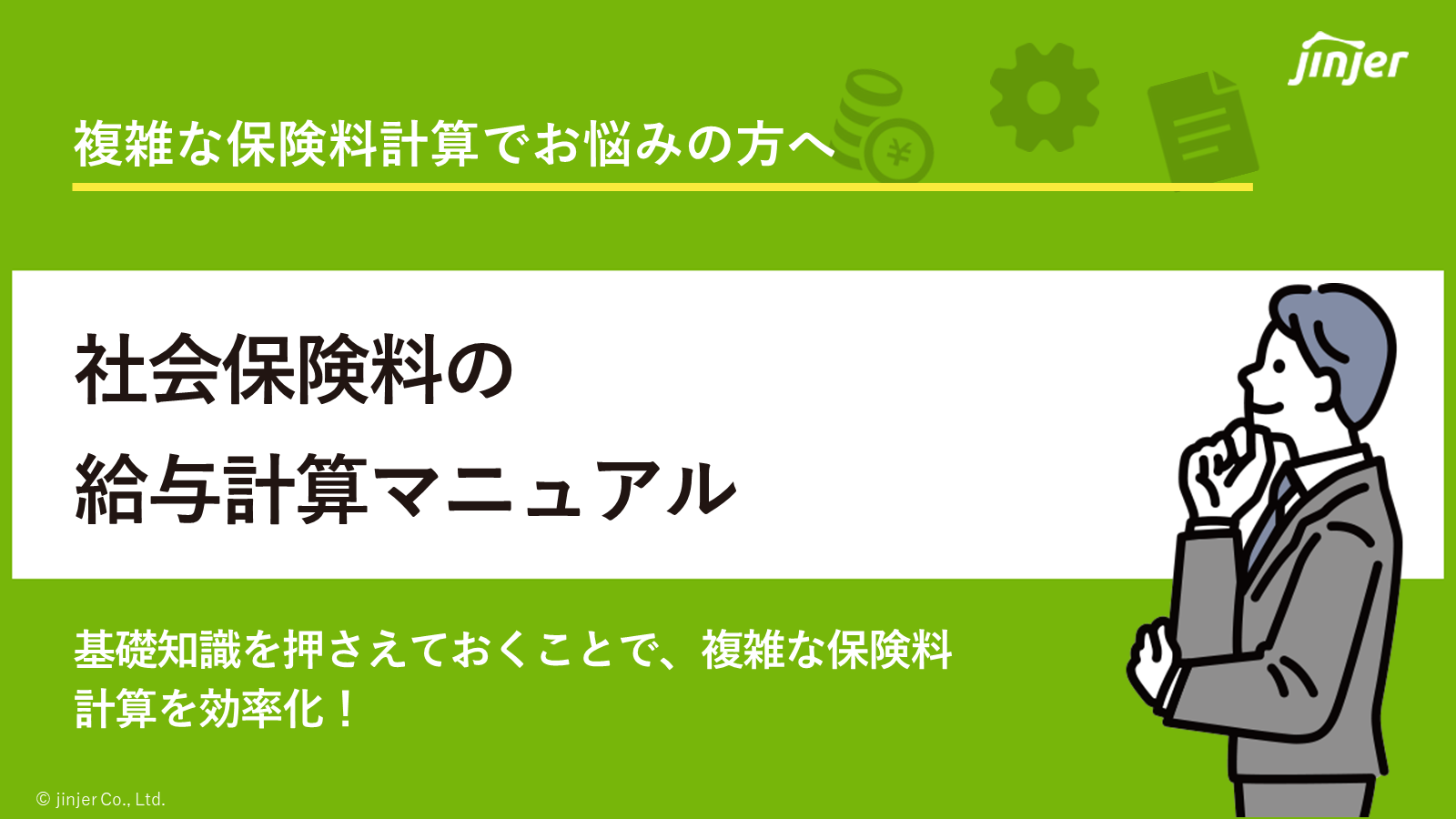社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
更新日: 2024.7.8
公開日: 2020.12.10
OHSUGI

健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入している従業員は、毎月収入に応じて定められた社会保険料を納付する必要があります。
サラリーマンの場合、企業が給与から社会保険料を控除し、代わりに納付する「特別徴収」がおこなわれるため、企業は給与計算の際、従業員ごとに社会保険料を算出する必要があります。
初めて給与計算をおこなうときは、社会保険料の正しい算出方法をあらかじめ覚えておきましょう。
今回は、給与計算で社会保険料を算出する方法や、計算時の注意点をまとめました。
【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
1. 社会保険料とは


社会保険料とは、人生で直面するさまざまなリスクに対し、必要なお金やサービスを支給する制度である社会保険にかかる保険料のことを指します。
人は誰でも、生きている中で傷病や労働災害、退職・失業などの憂き目に遭うリスクを抱えています。そんな万一の場合に備え、保険料という形で集めた財源を活用し、人々の生活を支えるのが社会保険の目的です。
社会保険は公的な制度であり、国民は加入を義務づけられると共に、保険料を納付する責務を負っています。
1-1. 社会保険料徴収の対象となる人とは
社会保険には、厚生年金や健康保険、介護保険、雇用保険が含まれています。
保険の種類によって加入の条件が異なるため、注意しましょう。
それぞれ詳しく解説します。
厚生年金と健康保険への加入が義務付けられている人
厚生年金と健康保険への加入が義務付けられている事業所の条件は以下のとおりです。
- 従業員が1人以上いる法人事業所
- 従業員が常時5人以上いる、法定16業種の個人事業所
個人事業の場合は、農林水産業、自由業、宗教業、一部のサービス業などは適用対象になりません。
加入が義務付けられている事務所に勤めている正社員、または以下の条件に当てはまる場合は、厚生年金と健康保険への加入が義務付けられています。
- 適用事業所(事業所単位での条件を満たす事業所)に使用されている従業員
- 週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数が、正社員の4分の3以上ある従業員
また、週あたりの労働時間が正社員の4分の3未満の短期労働者でも、対象となる場合があります。
次の条件を満たしている従業員がいないかも確認しましょう。
- 社会保険の被保険者が常時101人以上であること(※2024年9月末まで)
- 所定労働時間が週20時間を超えている
- 月給88,000円(年収106万円)以上ある
- 学生ではないこと(休学中、夜間学生を除く)
- 雇用期間が2か月以上見込まれること
法改正により、令和4年10月から特定適用事業所の適用要件が「501人以上の適用事業所」から「101人以上の適用事業所」に改正されています。
2024年10月から社会保険料の加入条件が拡大
上記にも記載があるとおり、2024年9月末までは被保険者数が101人以上の企業でしたが、2024年10月からの社会保険料の加入条件が拡大され、被保険者数が51人以上の企業になるため注意が必要です。
参考:「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」|日本年金機構
とくに社会保険料は給与から控除して支払うため、この法改正によって適用範囲が変更されることによって対象従業員の給与にも大きく関係します。確認ミスや漏れによるトラブルがないように対応しなければなりません。
当サイトでは「社会保険料を抜けもれなく控除したい」という担当者の方の役に立つ、最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。ガイドブックでは加入条件をわかりやすく図解していますので、参考にしたい方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:新入社員が入社した場合の社会保険料の手続きと計算方法についてわかりやすく解説
介護保険への加入が義務付けられている人
介護保険への加入には「40歳以上」という規定があります。そのため、先述の「厚生年金と健康保険への加入が義務付けられる要件」に加えて、40歳以上である条件を満たした人が加入しなければなりません。
また、介護保険の徴収は「40歳に達した日(月)」から始まります。ただし、40歳に達した日は厳密には「誕生日の前日」を指しているため、1日生まれの人が40歳を迎えた場合には、誕生月の前月から介護保険への加入が必要です。注意しましょう。
雇用保険への加入が義務付けられている人
雇用保険は従業員の雇用を維持できなくなった際に、従業員の生活維持と再就職の支援をおこなうための保険です。
週20時間以上勤務し、31日以上引き続き雇用される見込みある人は雇用保険に加入させる必要があります。
ただし、短期契約で雇用契約を結び、更新の見込みがないなど、31日以上雇用しない場合は、加入しなくてもよい場合もあります。
以下に加入条件をまとめたので、確認しましょう。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
パート、アルバイトなどの雇用形態は加入条件に含まれていないので注意
従業員の雇用形態が正社員でなくとも、そのほかの条件を満たす場合は社会保険への加入が必要です。
パートやアルバイトで働く従業員の中には、「自分はどれだけ働いても、社会保険の対象にはならない」と思っている可能性もあるため、雇用契約時にきちんと確認する必要があるでしょう。
2. 社会保険料の決め方


雇用保険料以外の社会保険料を決める際は、次の計算式を用いて算出します。
毎月の保険料額 = 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 = 標準賞与額 × 保険料率
ただし、雇用保険料のみ標準報酬月額や標準賞与額を用いずに算出するので注意が必要です。
本章では、社会保険料を算出するためのベースとなる、標準報酬月額と標準賞与額を解説します。
2-1. 標準報酬月額の算出
社会保険料の計算式に欠かせない標準報酬月額とは、給与などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分したものです。標準報酬月額が決まるタイミングは大まかに4パターンに分かれるので、それぞれ理解しましょう。
①入社時
新たに入社した従業員の場合、手続きをおこなうタイミングではまだ給与の支払いはされておりません。そのため、被保険者の資格を取得した人の1か月の報酬見込額を算出し、標準報酬月額の等級区分にあてはめて決定します。
②定時決定
民間企業の給与は景気や社会情勢によって変動しますので、毎年4~6月の3ヶ月間の賃金をベースに、同年9月に見直しをおこなっています。改定は年に一度きりですので、9月~翌年8月までの一年間は、原則として同じ標準報酬月額を用いて社会保険料を計算することになります。
なお、社会保険の被保険者がいる企業は、6月に標準報酬月額を見直したうえで、毎年7月10日までに「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出する必要があります。
これを定時決定といい、同年9月の改定以降は、提出した算定基礎届の内容をもとに、従業員一人ひとりの社会保険料を算出します。
③随時改定
昇給や降給などの給与体系の変更や通勤手当の変更などで固定的賃金が変動し、変動した月以降に継続した3か月間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額の等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときに随時改定をおこないます。
④育児休業等終了時
育児休業等を終えた後、固定的賃金が変動していなくても育児等を理由に報酬が低下し、現在の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合に改定します。
標準報酬月額の区分や等級は加入している健康保険の種類によって異なりますが、ここでは最も加入率の高い全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているものとして、標準報酬月額の調べ方を説明します。
協会けんぽでは、社会保険料の計算に用いる標準報酬月額の区分や等級、適用される保険料率を、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」として公式HPで公開しています。
なお、健康保険の保険料率は都道府県によって異なりますので、社会保険料を計算する際は、事業所があるエリアに対応した保険料額表をチェックします。
社会保険は原則として、事業所単位で適用する決まりになっていますので、本社とは別のエリアに支社・支店がある場合は、それぞれのエリアに応じた保険料額表を利用することになります。
【標準報酬月額の算出に不可欠な賃金支払基礎日数の解説はコチラ▶ 賃金支払基礎日数とは?基本となる数え方と間違えやすいケースを徹底解説】
【賞与と雇用保険料の関係をおさらいしたい方はコチラ▶雇用保険料は賞与から引かれる?退職後の雇用保険料や社会保険料の種類】
2-2. 標準賞与額の算出
標準賞与額とは、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額のことで、厚生年金保険料に関しては支給1回につき150万円が上限となります。また、健康保険の上限は、年間の累計で573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となっており、上限の考え方が月単位と年単位で異なるため注意が必要です。
もし同じ月に2回以上支給された場合は、合算して考えることになるので注意が必要です。
標準賞与額を考える際に対象となる賞与は、賃金や賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として、年3回以下の回数で支給されるものになります。
3. 給与計算における社会保険料の計算方法

ここでは、社会保険料の計算方法について、例題を用いて解説します。
3-1. 社会保険料の内訳
計算方法を確認する前に、まずは社会保険料に含まれるものの種類を確認しておきましょう。
企業が従業員の給与から源泉徴収(天引き)できる社会保険には、以下の種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
それぞれ保険料率は異なりますが、雇用保険以外の基本的な計算式は以下のとおりです。
保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2
従業員ひとりあたりの社会保険料は標準報酬月額×保険料率で算出できますが、保険料は事業主と従業員で折半する決まりになっています。給与計算で控除するのは従業員が負担する分だけなので、計算式の最後に、求めた保険料を2で割る必要があります。
なお、雇用保険については企業側と従業員側で保険料率が異なり労使折半ではないため、注意しましょう。
3-1. 健康保険の計算シミュレーション
では実際に、協会けんぽの健康保険に加入している人の社会保険料を、保険料額表を用いて計算してみましょう。
たとえば一例として、以下のような条件で働く従業員がいるとします。
- 事業所所在地:東京
- 年齢:40歳
- 4~6月の平均報酬月額:24万円
協会けんぽの保険料額によると、上記従業員の標準報酬等級は19、標準報酬月額は24万円です。
これに健康保険の保険料率を乗じますが、介護保険第2号被保険者であるかどうかによって、適用される保険料率が異なります。
40~64歳までの方は介護保険第2号被保険者に該当するため、上記従業員の健康保険料を計算する場合は、11.82%(令和5年度)の保険料率が適用されます。
以上のことから、この従業員が負担する健康保険料は24万円×11.82%÷2=14,184円となります。
もしこの従業員の年齢が30歳だった場合、介護保険第2号被保険者には該当しないため、保険料率は10.00%です。その場合の健康保険料は24万円×10.00%÷2=12,000円となります。
3-2. 厚生年金保険料の計算シミュレーション
厚生年金保険料の計算にも、健康保険と同じ「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用します。
厚生年金保険料に関しては、都道府県による区別がなく、全国一律の保険料率が適用されます。厚生年金保険料率は平成29年9月で引き上げが終了し、以後は18.30%に固定されています。
たとえば報酬月額が24万円の人が負担する厚生年金保険料は、以下の計算式で算出します。
24万円(標準報酬月額)×18.300%÷2=21,960円
なお、健康保険と厚生年金保険の保険料については、保険料額表にて、等級・区分ごとに保険料の全額と折半額が掲載されています。
つまり、実際に給与計算をおこなう際は、提出した算定基礎届の内容と保険料額表を照合し、従業員ごとに標準報酬月額を割り出せば、簡単に社会保険料を調べることが可能です。
【厚生年金保険料を理解したい方はコチラ▶ 厚生年金保険料とは?概要と計算方法、法改正などによる注意点を解説】
3-3. 介護保険料の計算シミュレーション
40歳以上になると、要介護状態や要支援状態になった時に介護サービスを受けられる「介護保険」に加入することになります。
介護保険料率は、単年度で収支のバランスがとれるよう、介護保険第2号被保険者(40~64歳の人)の総報酬額総額の見込みや、介護納付金の額、国庫補助額等などをもとに、毎年3月に改定がおこなわれます。
協会けんぽの令和5年3月分の介護保険料率は1.82%ですので、納付すべき介護保険料は以下の計算式で算出します。
介護保険料(従業員負担分)= 標準報酬月額 × 1.82% ÷ 2
ただし、介護保険料は健康保険と一体的に徴収される決まりになっているため、実際には健康保険料率に介護保険料率を上乗せする形で計算をおこないましょう。
たとえば令和5年の健康保険料率は東京都の場合で10.00%ですが、40~64歳の人は介護保険料率の1.82%を上乗せし、11.82%を乗じて計算します。
健康保険料と共に、介護保険料も算出できますので、個別に介護保険の計算をおこなう必要はありません。
3-4. 雇用保険料の計算シミュレーション
健康保険料や厚生年金保険料の計算には標準報酬月額を用いますが、雇用保険は総支給額をベースにします。
具体的な計算式は以下の通りです。
雇用保険料 = 総支給額 × 保険料率
保険料率は厚生労働省から毎年発表されており、令和6年は15.5/1,000が適用されます。[注1]
なお、雇用保険料は事業主と従業員で按分する仕組みになっており、15.5/1,000のうち、9.5/1000を事業主が、残り6/1,000を従業員がそれぞれ負担します。
たとえば、令和6年のある月の総支給額が25万円だった人の雇用保険料は、25万円×0.60%=1,500円です。
【年末調整の計算方法が知りたい方はコチラ▶年末調整の計算方法は?|計算の流れと注意すべきポイントをご紹介】
【社会保険料の控除について解説している記事はコチラ▶社会保険料控除とは?対象となる社会保険料の種類や必要な書類について】
【雇用保険料の計算方法が知りたい方はコチラ▶雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点】
4. 社会保険料の計算で注意したい2つのポイント

社会保険料を計算するにあたり、注意したいポイントをまとめました。
4-1. 従業員の年齢に注意
健康保険料の計算に用いる保険料率は、介護保険に加入しているか否かによって異なります。
40歳になると介護保険料の徴収が開始され、健康保険料率がアップしますので、忘れずに反映するようにしましょう。
【65歳以上でも雇用保険料の納付が必要になりました▶【最新版】65歳以上の雇用保険料の改正内容とは?給与計算ルールについても解説
4-2. 昇降給や手当発生に注意
標準報酬月額は4~6月分の平均報酬月額によって算定されますが、昇・降給または手当の支給により、他の3ヶ月の平均報酬月額が大幅に増減した場合、標準報酬月額の変更手続きをおこなう必要があります。
具体的には、2等級以上の差が出た場合に届出が必要になりますので、昇・降給や手当発生時は、等級に大きな変更はないかどうか確認しましょう。
給与計算の業務は従業員のステータスに影響を受けやすく、エクセルで関数をコピーするだけの単純作業では済みません。そのような場合には、従業員のデータや勤怠管理と連動して社会保険料を計算できる給与計算システムを導入すると、より正確かつスピーディに社会保険料を算出できるでしょう。
当サイトでは給与計算システムジンジャー給与を例に、給与計算システムのサービス内容が分かる資料を無料で配布しております。システムを導入することによって社会保険料を計算する手間が減らせそうと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
4-3. 社会保険料率の改定に注意
社会保険料は、毎年ではありませんが改訂されることがあります。例えば令和3年度だと、介護保険料率が全国的に引き上げがおこなわれております。
各社会保険によって、引き上げがおこなわれるか否かは異なるため、注意が必要です。
システムを導入していない企業の場合は、保険料率の更新を忘れてしまい、給与支払いに過不足が生じるなどのミスが生じる可能性が高くなってしまいます。
保険料の過不足は、後日対応すれば問題ありませんが、従業員からの信頼は損なう可能性が非常に高いので、給与計算業務においてミスをしないように細心の注意を払いながら業務にあたりましょう。
【改定後の社会保険の料率を確認したい方はコチラ▶【2024年度】社会保険の料率や改定タイミング、計算方法について徹底解説!】
5. 社会保険料の計算は慎重かつ丁寧におこなおう

社会保険料の多くは、標準報酬月額さえわかれば、簡単に計算することができます。
ただ、適用される保険料率は、事業所のあるエリアや従業員の年齢などによって異なりますので、計算する際は正しい保険料率を用いているかどうか、しっかり確認することが大切です。
計算ミスが不安な場合は、従業員のデータや勤怠管理と連動して社会保険料を計算できる給与計算システムを導入すると、より正確かつスピーディに社会保険料を算出できるでしょう。
【住民税の計算について知りたい方はコチラ▶給与計算における住民税とは|住民税の計算・納付・注意点について解説】
【所得税の計算について知りたい方はコチラ▶所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説】
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25