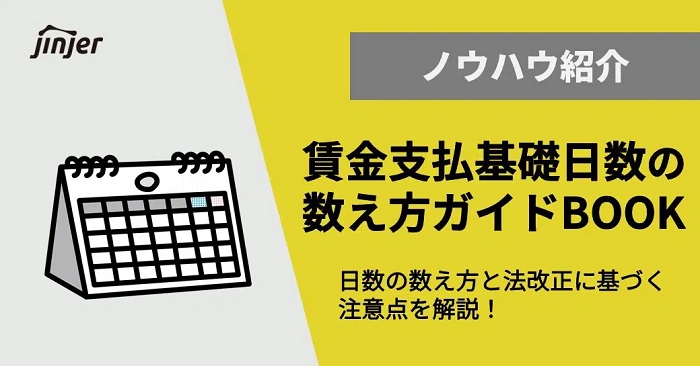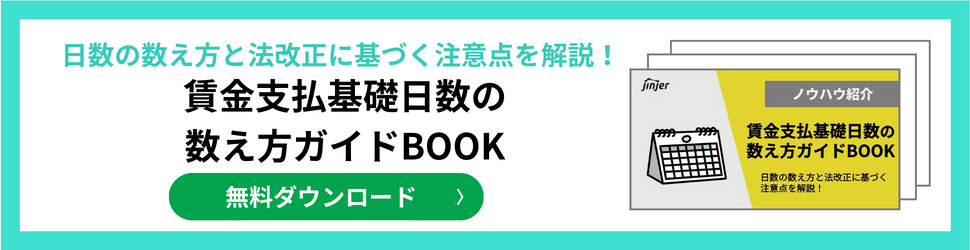賃金支払基礎日数とは?基本となる数え方と間違えやすいケースを徹底解説
更新日: 2024.4.12
公開日: 2021.12.23
YOSHIDA
賃金支払基礎日数とは、賃金や報酬の支払対象の労働日数のことです。失業保険の受給資格を確認したり、社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める際に必要となるため、正しく理解しなければなりません。
本記事では、賃金支払基礎日数の定義や数え方だけでなく、控除・免除が適用されたり有給休暇を取得した際などの、イレギュラー時の扱いまで解説します。
パート・アルバイト従業員や、所定労働日数が通常よりも短い従業員の賃金支払基礎日数の数え方でお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは賃金支払基礎日数の数え方や、注意点をまとめた資料を無料で配布しております。
所定労働日数が短い従業員の賃金支払基礎日数の数え方を知りたい、計算が誤っていないか確認したいという方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
目次
1. 賃金支払基礎日数はいつ必要?


賃金支払基礎日数とは、「企業が従業員に賃金を支払う対象となった日数」を指します。
通常時はあまり意識しないかもしれませんが、従業員が退職した際に離職票(離職証明書)を発行する場合や、社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める際に必要となるため、覚えておきましょう。
1-1. 離職票にある「基礎日数」と「賃金支払基礎日数」の違い
離職票には、「基礎日数」と「賃金支払基礎日数」のそれぞれを記載する欄があります。
「基礎日数」と検索しても、よくわからなかった、という方もいるのではないでしょうか。
「被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数」は、「被保険者対象期間」のなかで、賃金支払の対象となった日数を指しているのです。そのため、被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数には、休日や欠勤日などは省いて計算します。
しかし、完全月給制にしているなど、欠勤しても給与に反映されない場合は全ての日が賃金基礎日数に含まれます。
2. 給与計算における賃金支払基礎日数は何日以上必要?


賃金支払基礎日数は、月給制や日給制、時間給制の制度ごとに日数の数え方が異なるため、注意しましょう。
賃金支払基礎日数を使用する場面は、以下のとおりです。
①雇用(失業)保険の受給資格を確認する
②社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める
1-1. 雇用(失業)保険の受給資格を確認する
失業保険の受給資格は、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上あること」ですが、この被保険者期間は賃金支払基礎日数をもとに考えられます。
具体的には、被保険者期間の算入方法は「(当記事で解説する)賃金支払基礎日数が11日以上である月を1ヵ月と計算する」となっています。
こちらの算入方法は2020年8月に改正され、上記の条文に一文加えられており、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を計算する」というようになっているので、注意が必要です。
1-2. 社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める
標準報酬月額は、4月から6月までの3ヶ月間の報酬で計算します。もし該当月の賃金支払基礎日数が17日未満である場合は、標準報酬月額の計算に下回った月は使えません。
そのため、上記のようなことが起きた場合は、条件を満たしている2か月間で標準報酬月額を求めるという形になります。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
1-3. 支払基礎日数が不足している場合
ゲガや病気、介護などで長期間休職していた場合、上述した雇用保険の受給資格を満たせない場合や社会保険料を算出するための「標準報酬月額」を求められる月が存在しない可能性があります。
その場合は、どのように対応したら良いのでしょうか。それぞれ確認しましょう。
雇用保険の受給資格が満たせない場合
雇用保険は先述のとおり、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上あること」が条件となります。しかし、なんらかの理由で1年以上休職していた場合はこの要件を満たすことができません。そのため、「30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間」を最長で4年間まで遡って受給資格の判断期間とすることが可能とされています。
ただし、雇用保険はそもそも「就労の意思と能力があって就職活動をしているが、まだ雇用先が決まっていない人」に支給されます。ケガや病気、子育てなどの理由で就労できない場合は支給されないため、注意しましょう。
「標準報酬月額」を算出できる期間がない場合
先述のとおり、標準報酬月額は4月から6月までの3ヶ月間の報酬で算出します。しかし、3ヶ月とも算出期間として認められない場合は、「従前の標準報酬月額」を使用しましょう。
参考:保険者決定|日本年金機構
2. 賃金支払基礎日数の数え方


支払基礎日数の数え方は給与形態により異なり、大まかには以下の2つに分けられます。
①月給制・週給制の場合
②日給制・時間給制の場合
2-1. 月給制・週給制の支払基礎日数
月給制・週給制の場合は、暦日数がそのまま賃金支払基礎日数になります。
例えば、末締め・翌月15日払いで4月分給与を5月15日に支給した場合、5月の支払基礎日数は30日です。(4月は30日あるため)
2-2. 日給制・時間給制の支払基礎日数
日給制・時間給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。
この場合、標準報酬月額を求められる基準の17日以上であることが難しいケースも多く見られますが、その場合は、15日以上であることが標準報酬月額を算出する際の条件へと変わります。
詳しくはこの後のパートタイマー従業員の扱いで解説します。
3. 賃金支払基礎日数の数え方を間違えやすいケース


月や週単位で給与を支給するか、1日単位で考えるかによって数え方が異なることは上述しましたが、有給休暇取得時や休職期間の扱いなど、イレギュラー対応が必要なケースも複数あります。
賃金支払基礎日数を間違えてしまうと、従業員トラブルのもとになりうるので本章で理解しましょう。
3-1. 土日の扱い
土日の扱いについては、日にち単位で数えるか月・週単位で数えるかで異なります。
日給制などの日にち単位で考える場合は、土日に働いた際は含めますが、働いていなければ当然含めません。
一方、週・月単位で考える場合は、暦日数がそのまま基礎日数になるため、土日に働いていないとしても含めます。
3-2. 欠勤控除が適用される場合の扱い
欠勤控除が適用される場合、週給制・月給制の計算方法が変わります。
今までは暦日数を基礎日数としていましたが、欠勤控除が適用される場合は、就業規則等に基づき定められた「所定労働日数」から「欠勤日数」を引くことで、賃金支払基礎日数を算出できます。
例えば、所定労働日数が22日、欠勤日数が4日である場合は、賃金支払基礎日数は18日になります。ここで起きやすいのは、暦日数から欠勤日数を引いてしまうというパターンです。
ベースとなる日数が、暦日数から所定労働日数に変わるということを覚えておきましょう。
3-3. パートタイマー従業員の扱い
パートタイマー従業員の賃金支払基礎日数の数え方は、日給制や時間給制と同じく出勤日数がそのまま賃金支払基礎日数に該当します。
ここで間違えやすいのが、本記事でも触れた「標準報酬月額」を算出する場合の扱いが異なる点です。
- 4月から6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月がある場合:該当する月の報酬月額の平均で標準報酬を算定する
- 4月から6月の間に、支払基礎日数が全て17日未満であり、15日以上17日未満の月がある場合:酬月額の平均で標準報酬を算定する
このように、所定労働日数が通常の従業員よりも少ない場合は、計算の方法が少し複雑になります。「一度見ただけでは覚えられない」「いつでも確認できるようにしたい」という方に向け、本記事の内容をスライド形式でわかりやすくまとめた「賃金支払基礎日数の数え方ガイドBOOK」を無料で配布しております。賃金支払基礎日数の数え方に不安のある方は、こちらからダウンロードしてご過靴用ください。
3-4. 有給休暇を取得した際の扱い
年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、「使用者から賃金が支払われる」休暇日のことであるため、賃金支払基礎日数には含まれます。
賃金支払基礎日数の意味を理解することで、考え方で間違えることはなくなるため、定義から理解するようにしましょう。
3-5. 休職・産休期間の扱い
一般的に賃金の支払いが発生しない休職や産休の期間は、賃金支払基礎日数をカウントする際に含まれません。
休職の主な事由として、業務時間外での事故や病気が考えられます。これらのような休職と有給休暇は、会社を休んでいるという点では同じですが、賃金の支払いの有無が異なります。
前述したように、賃金の支払いの有無によって基礎日数が決まるので、この原則を忘れずに間違えないようにしましょう。
4. 賃金支払基礎日数の算出方法を再度確認しておこう


賃金支払基礎日数とは、賃金や報酬を支払う対象となった日のことを指し、失業手当の受給資格の確認で使用したり、社会保険料の計算で用いる標準報酬月額を決める際に使用するため、理解しておかなければなりません。
賃金形態によって異なるだけでなく、有給休暇や休職など、算入されたり除外されたりと複雑な仕組みになっているため注意が必要です。
本記事を通して、賃金支払基礎日数の算出方法を理解しましょう。
パート・アルバイト従業員や、所定労働日数が通常よりも短い従業員の賃金支払基礎日数の数え方でお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは賃金支払基礎日数の数え方や、注意点をまとめた資料を無料で配布しております。
所定労働日数が短い従業員の賃金支払基礎日数の数え方を知りたい、計算が誤っていないか確認したいという方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25