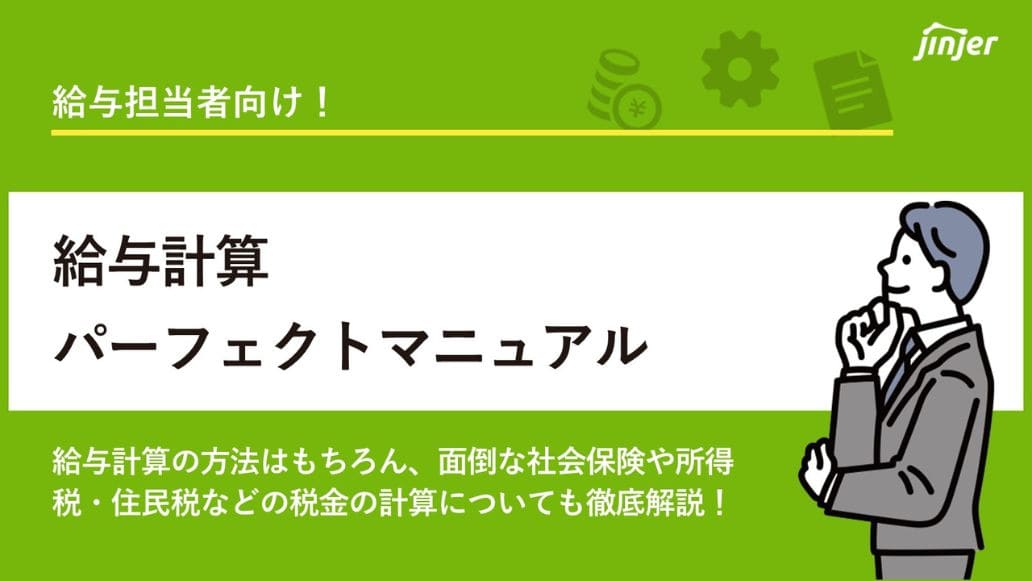給与計算方法を11ステップに分けて解説!注意点・効率化のポイントも

雇用している従業員に正確な賃金を支払うためには、勤怠表などの書類をもとに、給与計算をおこなう必要があります。
給与計算の方法を間違えると、賃金の未払いや過払いといった重大なミスにつながりますので、正しい計算方法と流れをつかんでおきましょう。
今回は、給与計算の概要から計算方法、給与計算業務をミスなく楽にこなせる方法まで徹底解説します。
目次
「自社の給与計算の方法があっているか不安」
「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」
「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」
など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。
給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。
1. 給与計算とは

給与計算とは、従業員の給与を計算し、支払う業務のことです。給与担当者は従業員に給料を支払うべく、毎月総支給額や控除額の計算をおこないます。
1-1. 給与で支払われるもの
給与計算をスムーズにおこなう基礎的な考え方として、まずは給与計算の構造を覚える必要があります。単に支給額を計算するだけでなく、差し引くべき項目や手当など複数存在するので、業務をおこなう前に事前に理解しておきましょう。
会社単位では支払いのタイミング(月給or日給)、従業員単位ではそれぞれ基礎日数に相違があるため、情報をインプットした上でスムーズに給与計算をおこなう方法を紹介します。
①基本給
残業手当や通勤手当、役職手当等の各種手当など、業績に応じて支給される給与を除いた基本賃金を表しています。
②手当(役職手当、家族手当、住宅手当、資格手当など)
特定の条件を満たした人に支払われる報酬です。
例えば、特定の役職に就いた人が受け取れる「役職手当」や、家賃援助をおこなう「住宅手当」など、該当する場合に従業員に支払われます。
③変動的な給与支給額(残業代・休日割増代・深夜割増代)
時間外労働(残業代)における割増賃金は、「各労働者の1時間あたりの賃金(基礎となる賃金)×時間外労働時間数×割増率」で算出します。各割増率や計算方法の詳細は後述の「4-2. 時間外手当の計算」で解説します。
労働基準法37条で定められている割増率は最低限守るラインで、企業によっては最低ラインの割増率をさらに上回る条件を設けている場合もあります。社則・就業規則・会社との労働契約内容などを確認し、条件や支給額などをきちんと確認しましょう。
▼より詳しく割増賃金の計算方法が知りたい方はこちら
割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説
1-2. 給与計算の構造とは
給与計算の基本的な仕組みは、以下の計算式で表すことができます。
総支給額-控除額=差引支給額(手取り額)
- 総支給額(額面):基本給に残業代などの各種手当をプラスした金額のこと
- 控除額:税金と社会保険料のこと(会社によって親睦会費などの特別な項目を設けていることも)
- 差引支給額(手取り額):従業員の銀行口座に振り込む金額のこと
例えば、20万円の給与総支給額から控除額の3万円を引いて、手取り額である17万円を銀行口座に振り込むというのが、給与計算の基本的な仕組みです。
1-3. 給与計算担当者(経理担当)の業務内容
給与計算担当者の業務内容は、所得税や住民税など税額を正しく管理することや従業員の年末調整、給与の支払いなど、常に労務や税務のリスクと隣り合わせでおこなう必要があります。
従業員と会社、県や国などの社会をつなぐ大切なポジションなので責任は重いですが、その分やりがいを感じられます。
会社のディフェンスポジションの役職が、年間を通してどのような仕事をしているかさらに知りたい方は、関連記事をご覧ください。
関連記事:給与計算とは?業務内容ややり方・流れ、基礎知識をわかりやすく解説
関連記事:給与計算における年末調整の流れと注意すべきポイント3つ
関連記事:給与計算の初心者がこれだけは押さえるべき3つのポイント
関連記事:給与計算の基礎が初心者でも分かる!基礎知識や流れ・計算方法を徹底解説!
2. 給与計算の事前準備の手順


前章で話したような大きなリスクから逃れるためにも、給与計算をおこなう際は、事前に総支給額や控除額の計算に必要な情報やものを用意しておきましょう。
2-1. 就業規則・給与規程の確認
就業規則とは、従業員が働く上でのルールや、労働条件を定めたもので給与に関する規定も書かれています。従業員が10人以上の事業所は、就業規則を作成して労基署に届け出ることが法律で義務づけられているため、必ず作成しなければいけません。従業員10人未満の場合は、作成や届け出の義務はありませんが、賃金含め従業員と企業間でルールを設けることで、トラブルが起きにくい環境をつくることができるため、作成することをおすすめします。給与計算の担当者になった際は、まず自社の就業規則・給与規程を確認しましょう。
2-2. 従業員情報の収集・更新
給与計算には、従業員の情報が必要となります。勤続年数や職種、役職などによって基本給や手当が変わることが多いためです。
また家族の増減がある場合、扶養状況によっては家族手当や所得の控除額が変わり、勤務地の変更・転居があれば通勤手当が変わります。給与に関わる従業員情報については、毎月の給与計算前に収集・更新しておきましょう。
2-3. 社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入状況
社会保険は、国民の生活を守るための制度で法人や要件を満たした個人事業主に雇われる人であって、所定労働時間や労働日数などの要件を満たした人は役員も含めて加入の義務があります。
保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。企業が加入している保険によって保険料率は異なるため、必ず確認しましょう。
また、介護保険のみ40歳以上の従業員が納税の対象となります。該当者が誰なのか分かるようにしておかなければなりません。
毎月納付する必要があるため、誰がどの保険料を払うのかすぐに把握できる状態にしておきましょう。
2-4. 労働保険(雇用保険、労災保険)の加入状況
労働保険は労働者を守るための保険であるため、原則として使用者=役員は加入できません。
雇用保険は、給与の総支給額に雇用保険料率をかけて算出します。雇用保険料率は厚生労働省から毎年発表されており、事業内容によって保険料率が異なります。また、労働者が負担する割合と企業が負担する割合もそれぞれ発表されているため、忘れないように確認しましょう。
一方、労災保険の、保険料はすべて会社負担となります。保険料率は事業内容によって異なります。こちらも厚生労働省から発表されており、定期的に改定されているため、年に1回は必ず確認しましょう。
3. 給与計算の計算方法11ステップを徹底解説!

従業員に支払う賃金を算出するための給与の計算方法を、流れに沿ってご紹介します。
3-1. 労働時間の集計
勤怠表やタイムカードなどをチェックし、従業員ごとに1ヶ月分の労働時間を集計します。
定時で働いた場合の給与は基本給に含まれますが、それ以外の時間帯に働いた場合は、別途時間外手当が支給されます。
一般的に、残業手当や深夜手当、休日手当などは、定時内で働いた場合より賃金が割増されますので、それぞれ分けて計算する必要があります。
労働時間を集計する際は、定時内の労働時間と、それ以外の労働時間を混同して集計しないよう注意しましょう。
【労働時間の計算方法を詳しく知りたい方はコチラ▶労働時間の正しい計算方法についてわかりやすく解説】
3-2. 時間外手当の計算
残業や深夜勤務、休日出勤などの時間外勤務があった場合は、基本給とは別に、時間外手当の計算をおこないます。
時間外手当の計算式は以下のとおりです。
時間外手当=時間外の労働時間×1時間あたりの賃金×割増率
正社員は時給制ではありませんので、1時間あたりの賃金は月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間で算出します。
ここでいう月給とは、基本給だけでなく、役職手当や資格手当などの固定給も含まれます。
割増率については、労働基準法によって以下の基準が設けられています。
|
労働時間 |
時間 |
割増率 |
|
時間外労働(法定内残業) |
1日8時間、週40時間超 |
割増しなし |
|
時間外労働(法定外残業) |
1日8時間、週40時間超 |
25% |
|
1ヵ月に60時間超 |
月60時間を超える時間外労働 |
50% |
|
法定休日労働 |
法定休日の労働時間 |
35% |
|
深夜労働 |
22:00~翌5:00までの労働時間 |
25% |
なお、時間外手当は重複して発生するケースもあり、以下の組み合わせが可能です。
|
労働時間 |
時間 |
割増率 |
|
時間外労働+深夜労働 |
時間外労働(25%)+深夜労働の時間(25%) |
50% |
|
法定休日労働+深夜労働 |
法定休日労働(35%)+深夜労働の時間(25%) |
60% |
|
1ヵ月に60時間超+深夜労働 |
1ヵ月に60時間超(50%)+深夜労働の時間(25%) |
75% |
例えば残業が深夜(午後10時~翌午前5時)に及んだ場合、残業の割増率25%と、深夜勤務の割増率25%が重複し、合計50%の割増率が適用されます。
同様に、休日出勤が深夜に及んだ場合は休日出勤の割増率35%+深夜勤務の割増率25%=60%の割増率が適用されることになります。
ただし、労働基準法で定められている休日(法定休日)には、法定労働時間が存在しないため、休日出勤の割増率と残業の割増率が重複することはありません。
例えば通常勤務日の定時が9時~18時の人が、休日に9時~19時まで働いた場合でも、適用されるのは休日出勤の割増のみで、18時~19時までの1時間に時間外の割増はつかないので要注意です。
ちなみに、労働基準法で定められた時間外労働に対する割増率は、あくまで最低限のラインです。
企業によっては時間外労働について、より高い割増率を適用しているところもありますので、事前に就業規則を必ず確認しておきましょう。
3-3. その他手当の計算
時間外手当の他にも、企業によっては通勤手当や家族手当などの各種手当てが支給されます。通勤手当に関しては、支給額によって所得税の課税対象になるかどうかが変化します。
電車やバスなどの交通機関を利用している場合は月15万円まで、マイカー通勤の場合は片道距離に応じて4,200円~31,600円までがそれぞれ課税対象外になります。
それ以上支給した分については所得税の課税対象となりますので、計算時に間違えないよう注意しましょう。
なお、家族手当の規定は企業ごとに異なりますので、あらかじめ就業規則で計算方法を確認する必要があります。
3-4. 総支給額の計算
1~3で計算した支給額を合算し、総支給額を算出します。総支給額の計算式は以下のとおりです。
総支給額=基本給+所定外手当(割増賃金)+各種手当
3-5. 雇用保険料の計算
雇用保険料は、従業員と事業主で分けて負担しているため、総支給額から従業員負担分の雇用保険料を控除する必要があります。雇用保険料の計算式は以下のとおりです。
雇用保険料=総支給額×雇用保険料率
雇用保険料率は厚生労働省から毎年発表されており、業種や年度によって異なります。
2024年も4月に雇用保険料率の改正がおこなわれたため、正確な保険料率を確認しておきましょう。
参考:【最新版】65歳以上の雇用保険料の改正内容とは?給与計算ルールについても解説
3-6. 健康保険料の計算
社会保険のひとつである健康保険の保険料は、従業員と事業主とで折半して負担します。「協会けんぽ」の会社の健康保険料の計算式は以下のとおりです。
健康保険料(個人負担額)= 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2
標準報酬月額とは、従業員が事業主から受け取る毎月の報酬を区切りの良い幅で区分したものです。
標準報酬月額は保険者が協会けんぽの場合にはHPで公開されている健康保険・厚生年金保険の保険料額表で確認できます。標準報酬月額がわかったら、都道府県ごとに定められている保険料率を乗じて計算します。
例えば、東京の場合、2020年3月分から適用されている健康保険料率は、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合は11.66%、それ以外の人は9.87%となります。[※注4]
なお、介護保険第2号被保険者については、介護保険料率1.79%(2020年3月分~適用分)が上乗せされています。
東京で働く30歳の人の4~6月の平均給与が25万円の場合、標準報酬月額は26万円ですので、26万円×11.66%÷2=15,158円が健康保険料となり、総支給額から控除されます。
【社会保険料と給与計算について詳しくはコチラ▶給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説】
3-7. 厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料は、社会保険料と同じく、標準報酬月額をベースにして計算します。
ただ、社会保険料は都道府県や介護保険第2号被保険者か否かで保険料率が異なるのに対し、厚生年金保険料は2017年9月より一律に固定されました。
2020年3月分から適用される保険料額表によると、厚生年金保険料率は18.300%なので、賃金が25万円の人の厚生年金保険料は47,580円、個人が負担する額は23,790円となります。[※注4]
なお、健康保険・厚生年金保険の保険料額表には、標準報酬月額ごとに、健康保険料と厚生年金保険料の「全額」と「折半額」がそれぞれ掲載されています。
つまり、従業員の月給に該当する標準報酬月額がわかれば、いちいち計算しなくても、総支給額から控除すべき健康保険料・厚生年金保険料を確認することが可能です。
3-8. 住民税の計算
従業員が支払う住民税については、市町村役場から郵送されてくる「住民税特別徴収税額の通知書」を確認すれば、控除すべき納税額がわかります。
そのため、特に計算は必要なく、その他の控除と一緒に総支給額から差し引くだけで問題ありません。
【住民税の計算について知りたい方はコチラ▶給与計算における住民税とは|住民税の計算・納付・注意点について解説】
3-9. 源泉所得税の計算
毎月の給与から控除される所得税(源泉所得税)は、雇用保険料や社会保険料を控除した後の報酬金額に、所定の所得税率をかけて計算します。
なお、被扶養者のいる従業員は、給与額からさらに一定の額が控除されますので、同じ給与でも扶養者のいない人とでは納税額に違いが出ます。
源泉所得税については、国税庁が毎年公表している「源泉徴収税額表」を利用すれば、いちいち計算しなくても従業員ごとの納税額を確認することが可能です。[※注5]
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員については、社会保険料控除後の報酬額と、「甲」欄にある扶養親族等の数の行が交差した箇所をチェックすれば、その月の源泉所得税がわかります。
ちなみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は「乙」欄、日雇いなどの従業員は「丙」欄が適用されます。
【所得税の計算について知りたい方はコチラ▶所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説】
3-10. その他控除の計算
企業が独自に控除制度を設けている場合は、就業規則に則って計算をおこないます。
例えば社宅利用料や、共済会費などがこれに該当します。
3-11. 差引支給額の計算
総支給額から、各種控除額を差し引き、実際に従業員の口座に支給される「差引給与額」を計算します。
ここまで給与の計算方法を解説してきましたが、所得税・住民税などの税金の計算や保険料控除の計算など、複雑な計算が続くために自社の給与計算方法があっているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。本資料では給与計算の基礎や手順はもちろん、間違えやすい社会保険や所得税・住民税の保険料率や計算方法についても図解形式でわかりやすく解説しています。給与計算の担当者にとっては、いつでも確認できるマニュアルとして有効に活用できますので、興味のある方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
4. 給与計算で把握しておくべき4つのポイント


給与計算をおこなう際は次の4つのポイントを把握しておきましょう。
- 賃金支払いの五原則
- 社会保険ほかの要件
- 従業員の勤怠情報
- 事業所がある地域のルール
4-1. 賃金支払いの五原則
賃金支払いには次の5つの原則が設けられています。
- 通貨で
- 直接労働者に
- 全額を
- 毎月1回以上
- 一定の期日を定めて支払う
つまり、企業は従業員に対して、毎月最低1回は決まった日に全額通貨で直接給与を支払うことが義務付けられているといえます。この原則にそわなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます。なお、時間外労働などで発生した割増賃金を支払えなかった場合は30万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役が科せられてしまいます。
賃金支払いの五原則では直接支払うことを定めています。しかし、従業員の同意が得られれば賃金の口座振り込みも可能です。
関連記事:給料の締め日とは?支払日との違いや決めるポイント・変更の注意点を解説
4-2. 社会保険ほかの要件
給与計算は従業員の労働時間だけを計算するわけではありません。次のような社会保険も算出する必要があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
健康保険や厚生年金保険などの加入には要件があるため、誰が加入対象なのかを把握しておきましょう。また、社会保険料を計算する際は、従業員の年齢や昇降給や手当、社会保険料率の改定に注意が必要です。これらに変更があると社会保険料にも変更が発生します。
4-3. 従業員の勤怠情報
給与計算をするには従業員の勤怠情報が欠かせません。従業員の勤怠情報を確認する際は所定の労働時間だけでなく、時間外労働や休日労働などもチェックしましょう。時間外労働や休日労働は割増賃金の支払いが必要です。対象の従業員が時間外労働を何時間したのか、どれくらいの割増賃金が必要なのかを確認しておく必要があります。
4-4. 事業所がある地域のルール
大規模な企業の場合、事業者が全国に点在しているケースがあります。このような場合、事業所がある地域のルールに従うようにしましょう。例えば協会けんぽの保険料率のように都道府県で異なるルールがあるので、各地のルールに従うことが大切です。
また、地域ごとに異なるということでいえば、最低賃金も挙げられます。最低賃金は地域によって異なり、最低賃金を下回る給与の場合、50万円以下の罰金が科せられます。
5. 給与計算をおこなう際の3つのリスク

給与計算業務は、3つのリスクと隣り合わせにあるため、重要な役割になります。給与計算の方法を説明する前に、まずは給与計算業務の重要性について理解しましょう。
5-1. 計算・入力ミス、法令の改正による税務リスク
給与計算において、最も注意したいのが計算や入力のミスです。
ささいな計算ミス、入力ミスでも、従業員の賃金に過不足が発生する原因になりますし、税金なら追徴課税される可能性もあります。
給与計算に用いる計算式は特に複雑なものではありませんが、たった1つ数字や桁を間違えただけで大きなトラブルに発展するおそれがありますので、入念かつ慎重に計算することが大切です。
また、雇用保険料や社会保険料は、法令の改正によって料率が変動することがあります。
数年変わらないこともあれば、2年連続で改定されることもありますので、法令改正の情報は逐一チェックし、常に最新の情報を反映させるようにしましょう。
5-2. 残業代の未払い等による労務リスク
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた残業を「時間外労働」といいます。そして、時間外労働に対しては、法定の割増賃金を支払わなければなりません。
また、深夜帯(22時~翌5時)に労働する場合には、深夜手当として割増賃金を上乗せします。1カ月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金は、「時間外」「休日」「深夜」ごとに割増率が異なります。
【残業と割増賃金の関係を詳しく知りたい方はコチラ▶残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説】
5-3. 個人情報の漏えいリスク
給与計算業務で扱う情報には、従業員の個人情報が多く含まれます。個人情報を扱う事業者に対しては、個人情報保護法が適用されます。法改正が2017年5月におこなわれ、「1件でも個人情報を取り扱っている事業者」であれば適用されるようになりました。
ここまで給与計算の業務内容とリスクについて説明しましたが、「給与計算の業務がおおく、リスクも大きい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今では多くの企業が給与計算システムを導入しており、ミスの低減だけでなくコア業務に集中する環境を手に入れています。
当サイトでは給与計算システムジンジャー給与を例に、給与計算システムの導入で何ができるようになるか分かる資料を無料で配布しております。システムの導入によって給与計算の悩みを解決できそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
6. 給与計算のミスが発生した場合の対応


給与計算は毎月どの企業でもおこなわれる業務ですが、専門性が高くミスが許されないので、業務を負担に感じている方もいるかもしれません。
訂正業務が必要になったり税金や保険料の訂正申請が必要になったりと、給与計算にミスがあると余計な業務が増えてしまうことになります。
そこで本章では、ミスをしてしまった場合に取るべき行動とその後の対応について解説します。
6-1. 気づいたらすぐお詫びを入れる
給与計算は、従業員に支払う賃金や、雇用保険・社会保険などに関わる大切な業務ですので、ささいなミスも許されません。しかし、人がおこなう作業に「絶対」はなく、ときとして計算間違いや計算漏れが発生することもあります。
もし給与計算にミスが発覚したら、従業員に対してお詫びすると共に、以下の2点に気を付けながら適切な対応をおこないましょう。
①お詫びのタイミングは、ミスに気付いたあとすぐに!
②お詫びするときは、ミスの内容や今後の対応も伝える
ここで重要になるのが「同じミスを繰り返さない」ということです。一度起きてしまったことを再発することがないようしっかり対策をしましょう。
関連記事:給与計算で間違いが発覚したときのお詫びで注意すべきこと
関連記事:給与計算でミスしたときの対処法は?要因とその防止策もご紹介
6-2. ダブルチェックなどミスの防止対策をする
給与計算では、極力ミスを防ぐ必要があります。ここでは、給与計算のミスを事前に防ぐための5つの施策を解説します。
①保険料率の改定把握には年間スケジュールを作成
② 扶養変更・異動などの入力忘れを防止するにはダブルチェック
③ 控除項目の変更忘れ防止にはチェックリストを活用
④月額変更届の届出忘れ防ぐためにマニュアルを作成
⑤日割り計算を間違えの防止には給与計算システムを導入
より詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
関連記事:給与計算におけるダブルチェックの重要性と精度を上げる方法
関連記事:給与計算のミスを防止する5つの施策を原因別に解説
7. 給与計算を自動化し、ミスなく効率よくおこなう方法


人事の方の中には、給与計算業務に追われるという経験がある方も多いことでしょう。
「給与計算をもっと効率的におこないたい」
「給与計算におけるミスやトラブルを回避したい」
など、給与計算における悩みを抱えている企業もあるのではないでしょうか。
本章では、このような悩みの解決法を紹介します。この記事で紹介する「給与計算を効率的におこなう方法」の中から自社にあった形を導入することで、日々の給与計算を効率的にできるでしょう。
関連記事:給与計算が辛くてやりたくない人に知っておいてほしい4つの考え方
関連記事:給与計算のDXを進めるには?効果や手順を詳しく解説
7-1. エクセル管理
エクセルを使って給与計算をおこなう方法は、大きく分けて2つあります。
まず1つ目は、自分で給与計算用のシートを作成する方法です。
自分の好みに合わせてレイアウトできますし、カスタマイズも自由自在ですので、使い勝手の良い給与計算システムに仕上げることができます。ただし、一から給与計算用のエクセルシートを作成するのは手間と時間がかかりますし、エクセルに関するそれなりの知識も必要です。
もし仕様にミスがあった場合、正確な給与計算ができず、賃金の過不足が出てしまうおそれがあります。また、場合によっては従業員とのトラブルに発展する可能性もあるので、よほどのこだわりがない限りは、給与計算シートを自作するのはやめた方が無難です。
2つ目は、既存の給与計算用エクセルシートをダウンロードして使用する方法です。
「給与計算 エクセルシート」などのキーワードでネット検索すると、無償で配布されている給与計算用エクセルシートがたくさんヒットします。
デザインやレイアウト、機能はシートごとに異なりますが、給与計算に必要な項目や基本的な機能は網羅されていますので、エクセル初心者でも簡単に使いこなすことができます。
パソコンにダウンロード&インストールすればすぐに使えるようになりますので、手間ひまかけずにエクセルで給与計算したいという方は、既存の給与計算シートを活用することをおすすめします。
▼より詳しく知りたい方はコチラをクリック
給与計算をエクセルで行う方法とは?4つのコツと注意点を解説
7-2. 社労士や税理士などのアウトソーシング(代行)
給与計算の効率化において、アウトソーシングを取り入れている企業は増えている傾向にあります。まずは、メリットやデメリットを把握した上で、取り入れる必要があるか否かを考えましょう。
アウトソーシングのメリット
①正確かつスピーディに給与計算できる
②メインの業務に集中できる
③法改正にしっかり対応できる
④経理コストを削減できる
アウトソーシングのデメリット
①社内のリソースを利用することになる
②従業員の個人情報が流出するおそれ
給与計算をアウトソーシングに委託すると、手間をかけずに正確な給与計算をおこなうことができます。一方で、自社に給与計算のノウハウが蓄積されない、セキュリティに不安が残るなど、いくつかのデメリットもあります。
安心して給与計算を委託したいのなら、実績の有無やセキュリティ体制をチェックし、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
関連記事:給与計算のアウトソーシング・代行のメリット・デメリットと相場をご紹介
関連記事:社労士の給与計算業務とは|相場ややり方、準備すべきことをご紹介
関連記事:給与計算は誰に頼む?税理士、社労士の違いとは
関連記事:給与計算業務に資格は必要?気になる真相を詳しく解説
7-3. 勤怠給与システムや給与計算システムの導入
勤怠管理システムと給与計算システムの連携をおこなうことで、普段手打ち入力が必要だった作業を極端に減らすことが可能です。基本的に給与計算システムを使うためには勤怠データが必要なので、同時に導入することがおすすめです。
システム導入するメリット
- 勤怠管理を元に自動で給与計算がおこなえる
- 人事の業務軽減につながる
- 法改正の対応がスムーズにおこなえる
人がマニュアルでやっていたからこそ起きがちだったミスを、システムを導入することで軽減させることが可能です。もし給与計算が辛く、やりたくないと感じる場合は、アウトソーシングやシステムの導入を検討しましょう。
関連記事:勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務効率をアップしよう
関連記事:給与計算を自動化するメリット・デメリット、具体的な方法や手順も紹介
関連記事:給与計算ソフトとは?機能やメリット・デメリット、選ぶポイント6つなどから解説
8. 給与計算システムの選び方


給与計算システムを選ぶ際は次のようなポイントを押さえておきましょう。
- どのような業務ができるか
- 作成できる帳簿の範囲
- 他のシステムと連携できるか
8-1. どのような業務ができるか
給与計算システムを選ぶ際は、導入を検討しているシステムがどのような業務に対応しているかを確認しましょう。一般的に給与計算システムは給与の自動計算が可能なシステムです。しかし、システムによってはそれ以外の業務が可能なケースもあります。例えば給与に限らず、人事についての業務を効率化できるシステムもあります。そのため、導入しようとしているシステムが基本的な業務以外に、どのような業務ができるかを確認しましょう。
8-2. 作成できる帳簿の範囲
給与計算システムのなかには給与明細や賞与明細はもちろん、源泉徴収票や社会保険提出書類、給与支払報告書などの帳簿を作成できるシステムもあります。帳簿をシステム上で作成できれば、スピーディにデータを共有できるだけでなく、ペーパーレス化を促進できます。
まずは自社でどのような帳簿が必要なのかを把握して、それにあったシステムを選ぶようにましょう。また、システムを自社の帳簿に合わせてカスタイムが可能の確認も必要です。
8-3. 他のシステムと連携できるか
給与計算システムは他のシステムと連携できるかどうかも大きなチェックポイントです。給与計算システムを勤怠管理システムや会計システム、経費精算システムなどと連携させることで、給与計算以外の業務を効率的に進められます。例えば給与計算システムを経費精算システムと連携させることで、給与計算と一緒に経費精算もできるため、作業効率を高められます。
9. 給与計算の正しい方法と流れを確認してミスを未然に防止しよう

給与計算の項目は複数にわたるうえ、それぞれ計算方法に違いがあります。
計算方法を誤ると、賃金や納税額に過不足が発生する原因になりますので、正しい方法と手順を理解してから作業に取りかかりましょう。
ただ、手書きやエクセルで給与計算するとヒューマンエラーが起こりやすいので、正確性やスピードを重視するなら、給与計算ソフトの導入をおすすめします。
給与計算のミスを無くしたい、ダブルチェックの手間を減らしたいという場合は、給与計算をシステム化やアウトソース化を検討してみてください。
【給与計算の流れを知りたい方はコチラ▶給与計算業務の流れ|月間と年間のスケジュールも紹介!】
【給与計算は端数処理にも注意!▶給与計算の端数処理で気をつけるべき3つのポイント】
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25