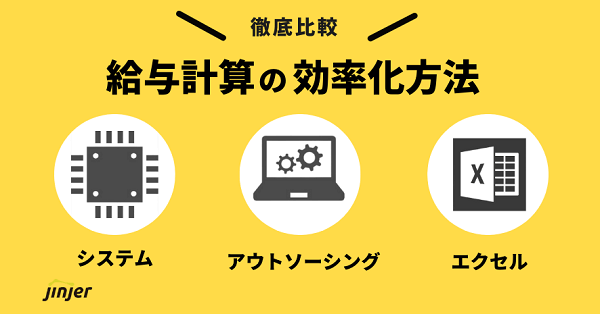給与計算の代行・アウトソーシングのメリット・デメリットと相場をご紹介
更新日: 2024.4.12
公開日: 2020.12.10
OHSUGI
給与計算は、従業員一人ひとりに支払う給与を算出するため、経理の中でも特に時間と手間のかかる業務です。
また、社会保険料や税金など、専門的な労務知識を常に念頭に置く必要があり、少しのミスが大きな失敗につながることもあります。
このような理由から、近年では給与計算システムの導入やアウトソーシングを検討する企業が年々増えてきています。
今回は、そんな給与計算をより効率化するため、給与計算システムやアウトソーシングの検討における各メリット・デメリットや、選定におけるポイントをご紹介します。
【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】
給与計算のアウトソーシングでは従業員数が増えるとその分費用も高くなるため、従業員が増えてきた企業様では「どうにか内製化して給与計算にかかるコストを削減できないか?」とお悩みになることがあるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは給与計算システム・Excel・アウトソーシングのメリット・デメリットや、システムで給与計算がどのように効率化できるかをまとめた資料を無料で配布しております。
給与計算システム・Excel・アウトソーシングのどれが自社に合っているかを比較検討したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 給与計算の代行・アウトソーシングとは


アウトソーシングとは、企業の定型業務を外部に委託するということです。
アウトソーシングを検討する前に小さな企業では、Excelや給与計算ソフトで管理していることも多いようですが、従業員数が増えると計算が複雑になり、時間もかかっていきます。また、専門的な知識が必要なわりに、業務に割く時間もかかりますし、売上に繋がる業務ではありませんので、企業としては貴重な人材をもっと中心的な業務に集約したいというのが本音ではないでしょうか。
ひと言で給与計算業務をアウトソーシングすると言っても、どこまで外部に委託するかは企業によってもさまざまでしょう。毎月の給与計算業務のみを外部委託する場合もあれば、社会保険の資格取得・喪失の手続きなどまで頼む場合もあります。
本章では、まずは給与計算のアウトソーシングの歴史や業務内容などをご紹介します。
1-1. 給与計算代行・アウトソーシングの利用率
給与計算代行・アウトソーシングは、もともと欧米で、弁護士や会計士など外部の専門家に業務をアウトソーシングする風土があるために発展したサービスでした。
日本企業に広まり始めたのは、1990年代のバブル崩壊以降になります。グローバル化が進み、あらゆる面で合理化・効率化を迫られたことで、給与関連業務を社内でおこなうことの必然性が改めて問い直されたという背景があります。
また、昨今における労働者人口の減少や多様な働き方の実現のため、さらなる業務の効率化が求められています。そのため、給与計算業務の代行やアウトソーシングの利用率は増加していくことが予想されるでしょう。
1-2. 給与計算アウトソーシングに頼めること
給与計算の業務は、毎月のお給料の計算・支払いだけでなく、年末調整、住民税の計算まで多岐にわたります。それらの中で基本的に頼める業務を4点にまとめましたのでご紹介します。
①給与計算代行
②振込・納税代行
③年末調整代行
④住民税更新代行
年末調整の準備と申請が始まる11月や、納付する税の金額が変わることがある6月と9月は、給与計算の担当者が忙しくなる時期です。忙しくなるタイミングのみ代行を依頼したり。日々の業務を減らすためにも毎月の給与計算代行を依頼することもできます。
1-3. アウトソーシングと業務委託の違い
アウトソーシングと業務委託は一見同じように思われますが、その内容は全く異なるものです。仕事を依頼する際に重要な内容になるので理解しておきましょう。
アウトソーシングは、業務を代行するという点では同じですが、その方法はあくまでも依頼先の方法に添ったものとなります。すなわち具体的な進め方は依頼先に一任され、結果のみが評価されるのがアウトソーシングです。
対して業務委託は、基本的に決められた業務を代行しておこなうことで、その業務マニュアルは依頼元により作成されます。すなわち、業務委託とは与えられた業務内容を代わりにおこなうことで、作業量を増やしたい場合などに用いられるというわけです。
2. 給与計算のアウトソーシング・代行のメリット

給与計算の効率化において、アウトソーシングを取り入れている企業は増えている傾向にあります。まずは、アウトソーシングを導入することでのメリットを考えてみましょう。
給与計算のアウトソーシングを導入するメリットは大きく次のとおりです。
- 正確かつスピーディに給与計算できる
- メインの業務に集中できる
- 法改正にしっかり対応できる
- 経理コストを削減できる
2-1. 正確かつスピーディに給与計算できる
給与計算を請け負っている業者は、経理に関する専門的な知識とスキルを兼ね備えています。その豊富な知識と実績を活かし、正確かつスピーディに処理ができます。
給与計算ミスは、賃金や各種保険料の未払い・過払いにつながる可能性があるため、作業を依頼することで、トラブルのリスクを軽減できます。
2-2. メインの業務に集中できる
給与計算に着手している間は、タスクの納期が遅れたり、優先順位が高い仕事に手を付けられなかったりなど、業務効率が低下する恐れがあります。
しかし、アウトソーシングによって、本来の業務に集中できるため、社員一人ひとりの作業効率が上がり、場合によっては業績・売上アップにも繋げられるでしょう。
2-3. 法改正にしっかり対応できる
法改正の情報を正しく把握できず、古い料率や控除額を用いて給与計算してしまった場合、賃金や各種保険料の未払い・過払いが生じます。
アウトソーシングをおこなうことで、専門家が法改正の情報を収集し、適切に対応、正しいルールに則って給与計算ができるため、未払い・過払いなどの無駄な出費を防ぐことができます。
2-4. 経理コストを削減できる
新たに経理を任せる人材を採用する場合、求人広告費や人材紹介会社に支払う報酬代、広報物の制作費など、さまざまなコストが必要になります。
経理未経験者を雇った場合は、人材教育にも時間と費用をかけなければならないため、初期投資は決して安いものではありません。
アウトソーシングにも費用はかかりますが、求人や教育が不要なぶん、トータルコストを削減することができます。
3. 給与計算のアウトソーシング・代行のデメリット


給与計算のアウトソーシングを採用することで正確かつスピーディな給与計算が可能になります。しかし、給与計算をアウトソーシングすることで、次のようなデメリットも考えられるでしょう。
- 業務負担が残ることがある
- 自社内にノウハウが蓄積されない
- 従業員の個人情報が流出する恐れがある
それぞれ詳細を解説します。
3-1. 業務負担が残ることがある
一部分だけアウトソーシングした場合にありがちなのが、代行会社とのやり取りに手間がかかったり、利用しているシステムが連携できていなかったりと、かえって作業負担が増えたというケースもあります。
ただし、こちらは業務範囲の設定やどこまでをアウトソーシングするかを、初期段階でしっかりと切り分けていないことが原因で起きがちだそうです。委託先の企業としっかり業務範囲の設定・業務フローなどを、導入の段階で定めておくことでデメリットになることを防げるでしょう。
3-2. 自社内にノウハウが蓄積されない
給与計算を丸ごと全部アウトソーシングした場合には、ノウハウが蓄積されないという可能性もあります。給与に関する労務事項や社会保険、税制などの専門知識を保有する人がいなくなってしまうことも考えられます。
給与計算業務全体をアウトソーシングする場合であっても、ノウハウを蓄積できるような仕組みや契約にする方法を考えたほうがよいでしょう。
3-3. 従業員の個人情報が流出する恐れがある
給与計算業務をアウトソーシングするということは、社外に自社の従業員の個人情報を渡すことになります。契約書上で情報漏洩等の措置について記載するのは当たり前の内容になりますが、思わぬところで情報が漏れてしまうことも考えられます。
最新の注意を払ってもミスは起きてしまう場合があるので、給与計算や勤怠管理の業務で問題を起きないようにするためには、アウトソーシングや代行ではなく、システムを導入することが有効で、人的要因での漏洩リスクを最小限まで減らせます。
4. 給与計算をアウトソーシングする際の料金相場

アウトソーシングに当てられる予算は企業ごとに異なるかと思います。ここでは、アウトソーシングの相場をご紹介していきます。
4-1. 給与計算のみ委託する場合の料金相場
あくまでも一般的な料金の相場になりますが、従業員数が50名規模の企業の場合、1ヵ月4~6万が相場となります。これを年間にすると、約48~72万が相場になります。
4-2. 年間の特殊業務を追加で依頼する場合
給与計算以外の業務を依頼する際は、オプションとして料金が追加されます。
例えば、毎月の給与計算に付け加え、オプションとして年末調整や、住民税更新などの特殊業務を依頼するとき、従業員数が50名規模の企業では、1ヵ月10~20万が相場となります。
これを年間にすると、120~240万が相場です。あくまでも相場のため、代行・アウトソーシング先によって料金は異なりますが、自社の予算も踏まえて検討するとよいでしょう。
5. 勤怠給与のアウトソーシングに向いている企業


ここまで紹介した給与計算の業務をアウトソーシングするメリット・デメリットを踏まえ、どのような企業がアウトソーシングに向いているのかご紹介します。
5-1. 人事労務の専門的な知識を持った担当者がいない企業
給与計算業務は、税務リスクや労務リスク、情報漏洩リスクなどと常に背中合わせであるため、法律に則ったうえで正確におこなう必要があります。社内でおこなう場合、専門知識を持った従業員を確保しましょう。
その理由は、以下の2つです。
- 雇用保険料率・社会保険料率・最低賃金の変更などに対応する必要がある
- 誤った知識で、残業代の計算ミス、給与未払いが発生するおそれがある
法改正が随時あるだけでなく、毎年6月・9月に住民税や社会保険料の納付金額に見直しがあるなど、常に情報を最新かつ正しい知識にする必要があります。
しかし、内容が複雑なケースが多いので、人事・労務に関する知識を兼ね備えた人材でなければ業務の荷が重たくなってしまいます。
5-2. 担当者がメインの業務に注力できていない企業
2点目は、給与計算業務を社内でおこなっていることで、担当者がコア業務に注力ができていないと感じている企業です。
よくあるケースとして、経営の三要素である「ヒト・モノ・カネ」の中のヒトに大きくかかわる人事部や総務部の従業員が兼任でおこなっていたり、または経営者自身が給与計算をおこなっていることがあります。
給与計算をアウトソーシングすることで、現在人事部が給与計算をおこなっている場合はコア業務である採用評価教育、総務部であれば社内環境の整備改善などの業務に注力できるようになります。また、現在経営者自身がおこなっている場合も同様に、経営者が本来注力すべき事業のグロースに注力できるようになります。
5-3. 給与計算の担当者が1名しかいない中小企業
給与計算の担当者が1名しかいないと、給与計算担当が休職・退職した際に業務が滞るおそれがあります。
もし、現在このような状況である場合は、アウトソーシングを利用することを推奨します。給与計算をアウトソーシングしていれば、休職・退職などの外部要因にで滞ることなく、契約期間は責務を全うしてもらえるので、安心して本業に時間を割くことができます。
何より給与計算は毎月必ずおこなう業務で、従業員の給与支給に関わります。常に安定して、業務を回せる状態にしておくことが必然です。
6. 企業規模別の給与計算アウトソーシングの選び方


給与計算のアウトソーシングは大手だからといった理由ではなく、企業規模に応じて選ぶようにしましょう。ここでは大企業向けの給与計算アウトソーシング、中小企業向けの給与計算アウトソーシングについて解説します。
6-1. 大企業向けの給与計算アウトソーシング
中小企業庁によれば、中小企業とされる企業の規模は次のとおりです。
- 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
- 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
- サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
つまり、上記に該当しない企業は大企業として扱われます。例えばサービス業であれば常時使用する従業員が100人を超える企業が大企業です。このように大企業になると、多くの従業員を抱えることになります。そのため、給与計算の件数はもちろん、取り扱う人事データや個人情報の件数も増えてしまいます。大企業が給与計算をアウトソーシング導入するのであれば、多くの件数、情報量に対応できるだけの人員と専門性を備えたアウトソース先を選びましょう。
6-2. 中小企業向けの給与計算アウトソーシング
先述のとおり、給与計算のアウトソーシングは中小企業に適しています。給与計算のアウトソーシング先のなかには、中小企業に特化した会社もあります。中小企業が給与計算をアウトソーシングするのであれば、自社の規模に特化したアウトソーシング先を選ぶようにしましょう。
また、従業員の人数が10人程度の企業であれば、顧問税理士や社会保険労務士と顧問契約を結ぶのがおすすめです。顧問契約を結んだ顧問税理士や社会保険労務士であれば、社内の体制や状況を把握しているため、手厚いケアが期待できます。
7. 給与計算をアウトソーシングする際のポイント

給与計算のアウトソーシングを請け負っている業者は複数あります。しかし、それぞれサービス内容や料金体系が異なるため、それぞれの特徴を把握しておくく必要があります。
委託してから後悔することのないよう、給与計算のアウトソーシングを依頼する会社は慎重に選びましょう。
ここでは、給与計算をアウトソーシングする会社を選ぶ時のポイントを4つご紹介します。
7-1. 委託できる業務範囲で選ぶ
給与計算のアウトソーシングを請け負っている業者の中には、オプションとして社会保険手続きの代行、給与明細書の発行などに対応しているところもあります。
経理業務は多岐にわたるため、「給与計算だけでなく、ほかの業務も一任したい!」と考える場合、委託できる業務範囲が広い業者を選ぶことがおすすめです。
7-2. 実績が豊富なところを選ぶ
給与計算には、数字の正確さはもちろん、納期に間に合うスピードも求められます。
実績や経験が豊富な業者ほど、スピードや正確さに信頼ができる会社です。公式サイトなどを確認して、過去の事例や実績数をチェックしてみましょう。
7-3. セキュリティ体制が整っているところを選ぶ
給与計算で扱う書類やデータには、企業データや従業員の個人情報が掲載されています。
書類やデータを紛失したり、盗難されたりなどによって、企業にとって大きな損害につながる可能性があります。セキュリティや個人情報保護を徹底している会社を選ぶことが大切です。
業者の公式サイトに掲載されているセキュリティへの取り組みをチェックするか、もしくは個人情報の保護体制が整っていることを示す「プライバシーマーク」の有無を確認すると、セキュリティレベルの高さを判断することができます。
7-4. 費用感で選ぶ
給与計算の代行・アウトソーシングの相場感は先に記載した通りとなります。企業ごとに課題感が異なるため、アウトソーシング先によって値段は異なります。
自社の予算に合わせつつ、給与計算のどこを依頼したいのか、よく検討する必要があるでしょう。
7-5. 注意点:対応できる企業規模に制限がある場合も
アウトソーシング先によっては、対応できる従業員数に上限を設けている場合もあります。
上記でご紹介した4つの観点で確認したうえで選んだアウトソーシング先が、実は企業規模的に対応が難しい、と回答される場合もあり得ます。
せっかく調べて選定したのに、またはじめから探しなおさなければならない、なんてことが起こらないように、問い合わせるタイミングであらかじめ対応できる規模を確認をしておくと安心です。
また、規模感だけでなく何か制約事項がないかを先回りして確認しておくとより安心です。
8. 給与計算をアウトソーシングした場合の流れ


最後に、給与計算をアウトソーシングした場合、どのような流れで給与計算業務を進めていくことになるのかご紹介します。
アウトソーシングをご検討中の方はぜひご一読いただき、イメージを持ってもらえればと思います。
※あくまで一例となります。アウトソーシング先によって対応する業務範囲は異なるため、詳細は検討中のアウトソーシング先にてご確認ください。
- 【自社】勤怠データを従業員から回収する
- 【自社】回収した勤怠データに誤りがないか確認し確定・集計する
- 【自社】集計した勤怠データを外注先に連携する
- 【外注先】受領したデータを元に給与を算出する
- 【外注先】給与明細書を発行する
- 【外注先】振込データを作成する
- 【外注先】帳票類を作成する
- 【自社】振込データを確認し、給与振込手続きを実施する
- 【自社】給与明細を従業員へ配布する
- 【自社】帳票を確認する
9. 委託先は丁寧に選ぼう

給与計算をアウトソーシングに委託すると、手間をかけずに正確な給与計算をおこなうことができます。
一方で、自社に給与計算のノウハウが蓄積されない、セキュリティに不安が残るなど、いくつかのデメリットもあります。
安心して給与計算を委託したいのなら、実績の有無やセキュリティ体制をチェックし、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
給与計算のすべてをアウトソーシングするのに抵抗を感じる場合は、便利な給与計算システムの導入を検討してみるのもおすすめです。
【給与計算の代行に関する資格はコチラ▶給与計算の代行に資格は必要?気になる真相を詳しく解説】
【自動で給与計算をしてくれる勤怠管理システムについて知りたい方はコチラ▶勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務の効率化をアップしよう】
【エクセルで効率的に給与計算する方法はコチラ▶給与計算をエクセルで行う方法とは?4つのコツと注意点を解説】
関連サイト:【一人社長向け】はじめての経理外注ガイド|おすすめサービス4選も紹介 | タスカル
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25