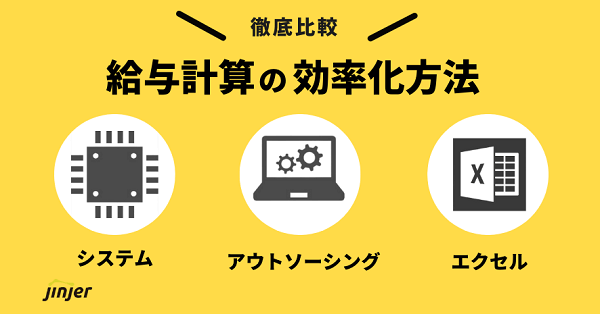給与計算が辛くてやりたくない人に知っておいてほしい4つの考え方
更新日: 2024.3.7
公開日: 2020.12.14
jinjer Blog編集部

人事や経理の仕事のなかでも正確性が求められるのが、「給与計算」です。スタッフの労働に対する給与を計算するため、計算をする際にミスや遅れがあっては大変です。
さらに、給与計算は大量の数字を扱う仕事なので、細かい作業が苦手な方は仕事を苦痛に感じることがあるかもしれません。
今回は、給与計算をやりたくないと思ってしまう心理と気持の切り替え方について解説していきます。給与計算の仕事が辛くなってしまったときは、ぜひ参考にしてみてください。
【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】
給与計算の効率化方法を徹底比較!
給与計算は間違いが許されない、確認作業が何回も必要な業務です。特に一人で給与計算を担っていると、そのプレッシャーは計り知れないものでしょう。
「ミスをなくせるなら給与計算システムも気になるけど、本当に使う必要があるの?」という方に向け、当サイトでは給与計算システム・Excel・アウトソーシングのメリット・デメリットや、システムで給与計算がどのように効率化できるかをまとめた資料を無料で配布しております。
給与計算システム・Excel・アウトソーシングを比較検討したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 給与計算をやりたくないと思う心理

どうして給与計算をしている人は、仕事をやりたくないと思ってしまうのでしょうか。まずは、その心理についてみていきましょう。
1-1. 専門知識が必要でミスが許されないプレッシャー
給与計算の業務をおこなう際は、労働基準法や所得税法などの多くの法律を知っておく必要があります。法律は定期的に改正されるため、最新情報を常に把握・勉強しなければなりません。
また、就業規則を頭に入れておく必要があるため、ほかの業務と比べても非常に専門知識が必要とされる業務です。
給与の支払いは税金なども関わってくるうえに従業員の信頼を左右するため、決してミスが許されません。専門性が高くミスが許されないプレッシャーこそが、給与計算をやりたくないと思わせてしまう大きな理由なのです。
法的な観点でも、「賃金支払いの5原則」を守れなかった場合は違法となってしまいます。例えば会社が取り決めた給料日に給与が支払われなかった場合、「毎月1回以上払いの原則」の原則に反してしまうため、違法とみなされることがあるのです。
賃金支払いの5原則や罰則について詳しくは以下の記事にて解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事:賃金支払いの5原則とは?例外や守られないときの罰則について
1-2. 毎月のルーティンワークで飽きてしまう
仕事の多くはルーティーンワークですが、とくに給与計算は同じことの繰り返しなので、飽きやすい業務になっています。
同じ事務であっても、総務や営業事務としての業務は社員やお客さんを相手にするため、給与計算に比べるとまだ飽きにくい傾向にあります。
一方で給与計算は数字の計算処理がメインになるため、同じ業務の繰り返しになりやすく飽きやすい傾向にあります。
1-3. コツコツ作業が苦手
そもそも、数字を扱う細かい作業やコツコツ作業の多い事務仕事が嫌いな方は、給与計算の仕事に向いていない可能性が高いです。自分の適性に合っていない仕事をすれば、当然ストレスが大きくなっていくでしょう。
もしもどんな方法を試しても気持ちの切り替えができないときは、給与計算以外の仕事をさせてもらえないか上司に相談してみるのもひとつの手です。
1-4. 評価に繋がりづらい
給与計算業務は工程がたくさんありながら正確性が重視され、責任の伴う業務であるにもかかわらず、給与計算業務に対して直接評価されることが無く、モチベーションを保てないという方も多いのではないでしょうか。
給与の受け取りが当たり前になってしまっている中で、「細かな作業への努力を認めてほしい」、「少なくとも感謝されたい」と感じることもあるでしょう。なんて感じてしまう時もありますよね。
1-5. 給与計算業務はなくなってしまう?
自動化やデジタル化の進展により、一部の繰り返し作業やルーティン業務は効率化される可能性がありますが、勤怠の修正や従業員の昇給・異動などにともなう給与の変更の反映は自動化が難しく、すべての工程の自動化は難しいと考えられています。
仕事が無くなってしまうかも、と心配をされていた方は、自動化が難しい業務に注力すると安心です。
1-6.毎月発生する作業のためなかなか休めない
給与計算業務が毎月あるため、気軽に休めないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
従業員の給与情報は社内の機密情報であり、給与計算業務の担当者は限られています。業務をできる人数が少ない場合が多く、急な休みが取りづらかったり、休むことに後ろめたい気持ちがあったりするのではないでしょうか?
体調を崩して仕事ができなくなってしまっては意味がありません。自身の心身の健康を整えることも仕事の一部です。
毎月発生する業務だからこそ、事前にスケジュールを組んでしまったり、周りの上司やチームメンバーの協力を仰ぎながらお休みを計画しましょう。
2. 給料計算をやりたくないと思うときの気持の切り替え方4つ

それでは、給与計算の仕事をやりたくないと思ったとき、どのようにして気持ちを切り替えたらいいのでしょうか。気持ちを切り替えてモチベーションをアップする方法を、4つご紹介していきます。
2-1. 自分の仕事が従業員を支えていると考えてみる
数字とにらめっこをしているとついつい忘れてしまいがちですが、給与計算の仕事をしている方が相手にしているのは、ただの電卓やパソコンではありません。
電卓パソコンの向こう側には、給与を受け取る従業員やその家族がいることを忘れないようにしましょう。従業員やその家族の生活を支えるために、給与計算の仕事は欠かせない重要な業務です。
あなたにとっては慣れた毎月のルーティンワークでも、従業員にとって給料日は毎月の頑張りが賃金となって現れる楽しみな日です。
あなたの給与計算が従業員のモチベーションや生活の支えになっていることを考えると、少しはやる気になるかもしれません。
2-2. 任せてもらえている意味を考える
先ほどもご紹介したように、給与計算は専門性が高くミスが許されない仕事です。そんな仕事を任せてもらえている意味を考えると、気持ちを切り替えられるかもしれません。
万が一ミスをして気持ちが落ち込むことがあっても、継続して業務を任せてもらえているということは、上司があなたを信頼しているということを理解しておきましょう。
社員や会社のお金を動かす業務は、誰にでもできることではありません。上司から評価されて信用されていることを自覚し、前向きに給与計算に取り組んでみてはいかがでしょうか。
2-3. 目標や自分へのご褒美を設定する
もしも給与計算の仕事に対するやる気がどうしても出ない場合は、毎日小さな目標を設定することがおすすめです。達成したときのご褒美も決めておき、ご褒美のために仕事を頑張っていきましょう。
小さな目標をたくさん達成すると達成感によってモチベーションが上がりますし、ご褒美があると苦手な仕事をこなす活力になります。
2-4. 気分転換をする
やる気が出なくて集中ができないときは、一旦別のことをして気分転換をすることも有効です。気分転換の方法としては、例えば以下のようなことが挙げられます。
- ストレッチや軽い運動
- 15分程度の仮眠
- デスク周りの整理整頓
簡単な方法ばかりですが、気持ちのリセットとしては有効な方法です。毎日の業務で行き詰まったときは、ぜひ試してみてください。
3. 給与計算をしたくないときはアウトソーシングがおすすめ

専門性が高くミスが許されない給与計算は、ルーティンワークになりやすく神経を使うため、やりたくないと感じてしまう方も多いです。やりたくないと感じてしまったときは、本記事で紹介した気持ちを切り替える方法を試してみてください。
給与計算業務の工数を減らしたいのであれば、アウトソーシングで給与計算を自動化する方法がおすすめです。
人件費コストを削減しつつ正確な計算が可能で、従業員をコア業務に集中させることが可能となります。メリットが豊富な給与計算のアウトソーシングを、ぜひご活用ください。
【給与計算のアウトソーシングについて知りたい方はコチラ▶給与計算のアウトソーシング・代行のメリット・デメリットと相場をご紹介】
【自動で給与計算をしてくれる勤怠管理システムについて知りたい方はコチラ▶勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務の効率化をアップしよう】
給与計算の効率化方法を徹底比較!
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25