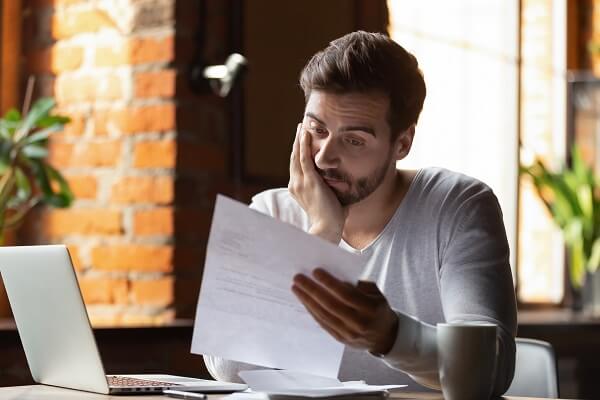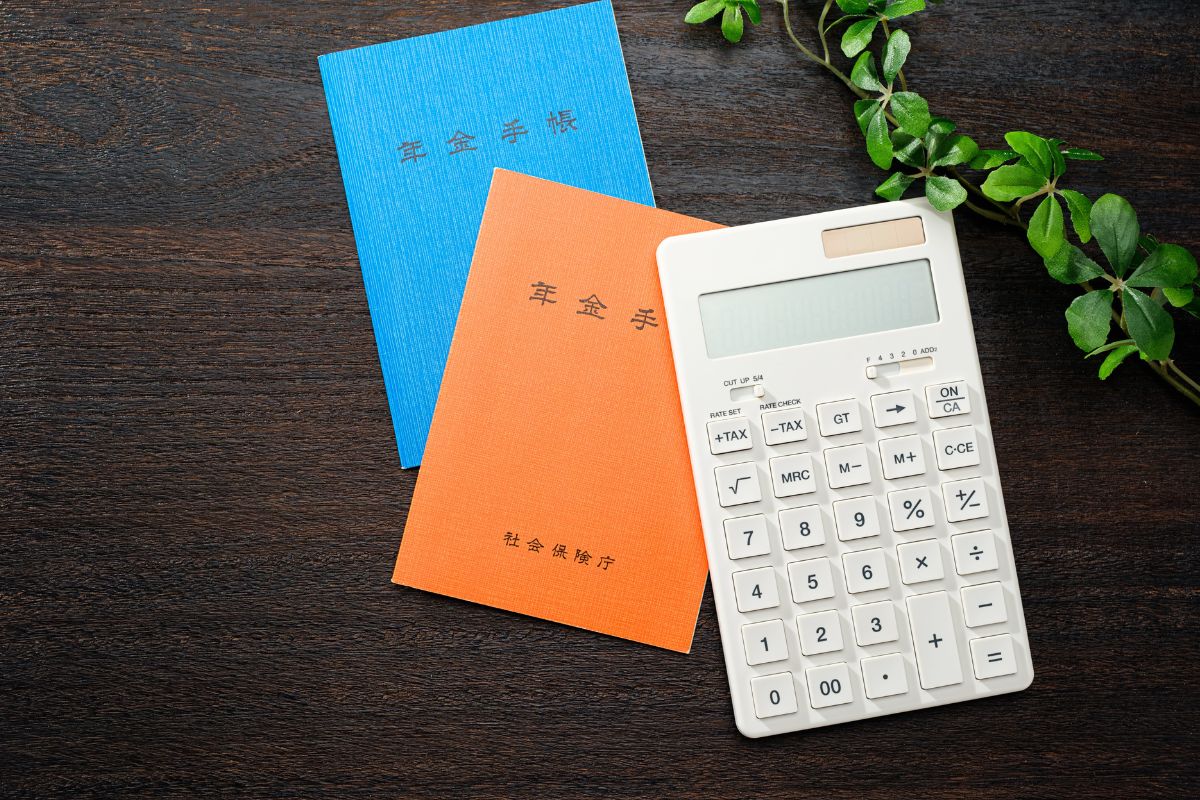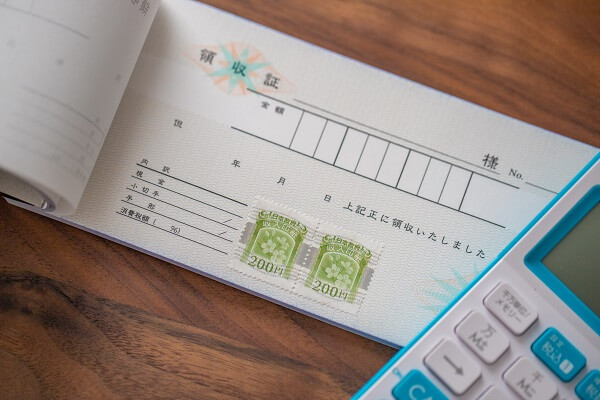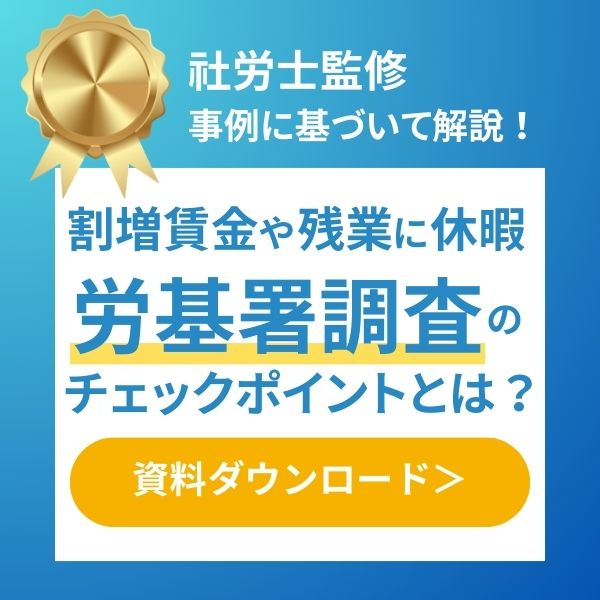みなし残業制度とは?ルールやメリット・デメリットを詳しく解説!
更新日: 2024.11.26
公開日: 2021.9.7
OHSUGI
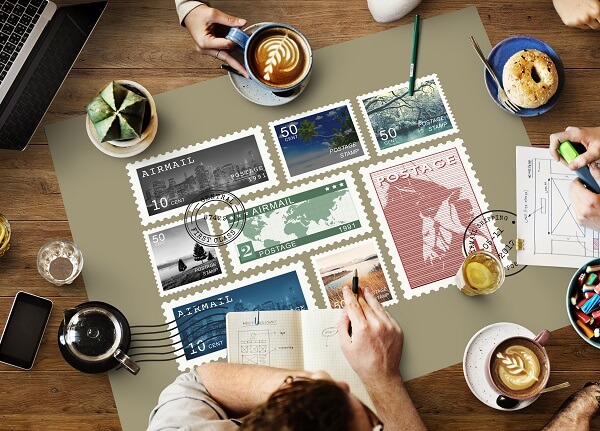
残業代も含まれる人件費は、会社にとって最も大きな割合を占める費用の一つです。
毎月の人件費の変動が大きいと感じていたり、残業手当の計算が煩雑化していたりする企業は、みなし残業の導入が問題の解決につながるかもしれません。
本記事では、みなし残業の定義やメリット・デメリット、さらには導入のポイントや注意点を紹介します。
【関連記事】残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。 法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひこちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
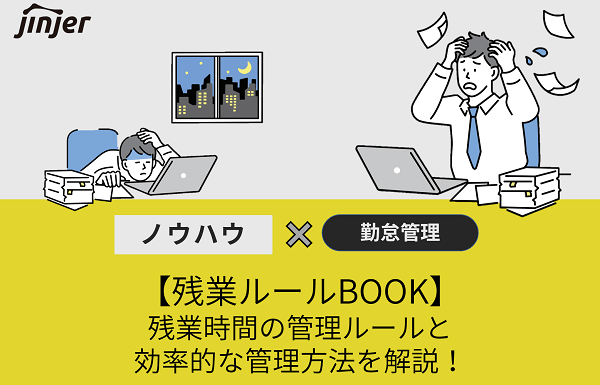
1. みなし残業(固定残業)とは
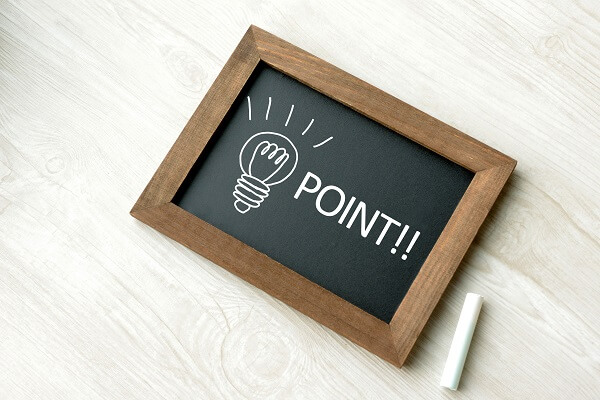
みなし残業は、残業代の計算業務の負担が大きい会社や、社員に支払う残業代が経営を圧迫していると感じる企業に有益です。ここでは、みなし残業の意味や概要を紹介するので、導入を検討する前にみなし残業ついて理解しておきましょう。
1-1. 残業時間の計算を「みなし時間」でおこなうこと
みなし残業(固定残業制)とは、給与にあらかじめ残業(時間外労働)手当を含める給与形態です。毎月の残業時間を「みなし残業時間」と設定し、それに基づいて固定の残業手当を支給します。
みなし残業時間より時間外労働時間が少なくても、残業手当の減額はありません。しかし、超過分については支払う義務があるため注意しましょう。例えば、みなし残業時間が25時間で実際の残業時間が20時間でも、雇用主は25時間分の残業手当を払います。一方、30時間働いた場合、超過した5時間分については別途残業手当の支給が必要です。
1-2. 労働基準法の割増賃金が適用されない
みなし残業代にはすでに割増率が適応されているため、みなし残業時間内であれば、追加で割増率を適用する必要がありません。
ただし、規定のみなし残業時間から超過した分の残業時間に対しては、割増賃金を支払う必要があります。
例えば、みなし残業時間を20時間で設定している場合、20時間以内であれば割増率をさらに適用する必要がありません。20時間を超過した分から、追加で割増賃金の支払いをおこないましょう。
割増賃金が払われずに残業を続けている状態を、サービス残業といいます。サービス残業は法律違反になるだけでなく、2019年の働き方改革関連法が制定されてからは、残業に上限規制が設けられたので、そちらも法律違反に該当する可能性があるため注意が必要です。
当サイトでは、みなし残業制度や固定残業制度を採用する際の注意点や適切な運用方法をまとめた「行程残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。自社の残業管理に不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
2. みなし労働時間制の種類
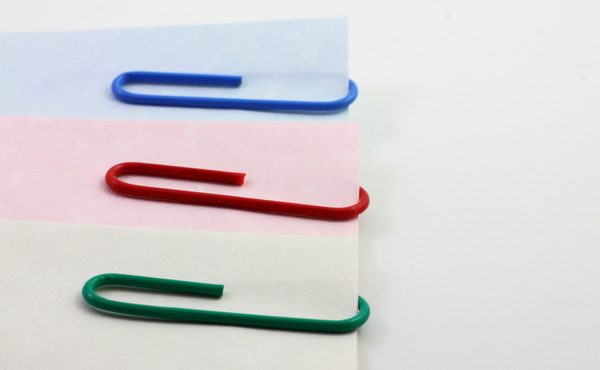
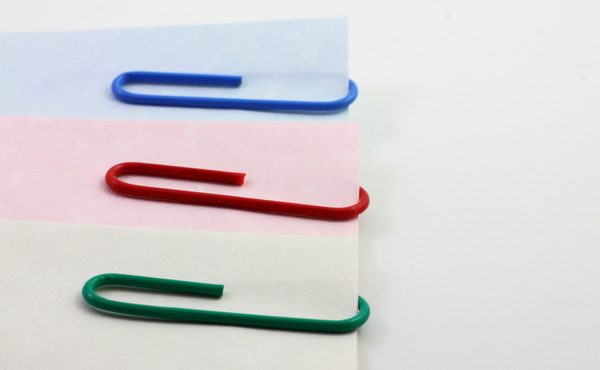
「みなし残業」と似た言葉に「みなし労働時間制」が挙げられます。
みなし労働時間制は実際の労働時間にかかわらず、「一定の時間働いた」とみなし、その時間分の賃金を支払います。
みなし労働時間制では所定労働時間を超えた時間をみなし労働時間として設定することもあります。その場合には残業代が発生します。
みなし労働時間制は大きく分けて、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」の2種類があります。さらに裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に2つに分けることができます。
ここでは、計3つのみなし労働時間制について詳しく解説します。
2-1.事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制とは、外回りの営業などで直行直帰が多いなど、会社が社員の労働時間を正確に把握するのが難しい場合に導入される制度です。
ただし、外回りであっても会社からの細かい指示によって働いているなど、ある程度労働時間の配分が確定している場合、この労働時間制は適用できないので注意しておきましょう。
2-2.専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制とは、会社が業務進行に関して細かい指示を出すことが難しく、労働時間や時間配分、業務内容を個人に委ねる必要がある場合に導入される裁量労働制です。
厚生労働大臣から指定されている、デザイナーや弁護士、研究者などの19種の特定専門職に限ってこの裁量労働制が認められています。
2-3.企画業務型裁量労働制
企画業務型も専門業務型と同様、個人の裁量に委ねる必要がある場合に導入される裁量労働制です。
ただし、この裁量労働制に関しては、事業の運営などをおこなう部門での企画立案や調査、分析などをおこなう業務の場合に適応が認められています。
3. みなし残業のメリット

みなし残業を適切に導入することによって、企業は費用・業務効率の面でメリットを実感しやすくなります。では、どのようなメリットがあるのか、具体的に見ていきましょう。
3-1. 残業代の計算が効率化する
みなし残業時間が適切に設定されている場合、社員の残業代計算の手間が軽減します。大幅な工数削減となり、給与担当者の業務効率化につながるでしょう。
ただし、残業時間の設定が適切に行われない場合は、残業時間の超過が頻繁に発生するかもしれません。この場合は、通常の残業と同様に、個々の超過時間等を把握する必要があります。
【関連記事】固定残業代とは?制度の仕組みや導入のポイントを分かりやすく解説
3-2. 人件費を把握しやすくなる
残業代が月々の給与に含まれる場合、人件費の把握が容易となります。残業代による人件費の変動が起こりにくく、企業は支出の見通しをより正確に立てやすくなるでしょう。
人件費は、企業支出のなかでも高い比率を占める支出です。大幅な増減があると、企業は支出予測を修正しなければなりません。人件費についてあらかじめ見通しが立てられるということは、経営上大きなメリットとなるでしょう。
3-3. 社員のモチベーション向上が期待できる
社員の業務に対するモチベーションが上がりやすいのも、企業にとっては大きなメリットといえます。
会社がみなし時間を定めていた場合、従業員は残業をゼロにしようと努力してくれる可能性があります。そのため、率先して業務効率化を考えるようになり、ムダな工程が発生しにくくなるかもしれません。
全社的に社員の意識が高まれば、企業全体の作業効率向上や残業時間の削減も実現できるでしょう。
4. みなし残業のデメリット

みなし残業は「給与に残業代が含まれる」点がネックとなります。企業のデメリットとして懸念されるのはどのようなことなのか、具体的に見ていきましょう。
4-1. みなし残業時間未満の労働にも残業代を支払わなければならない
企業の状況やみなし時間の設定によっては、残業手当の負担が増加する恐れがあります。
みなし残業は、「何時間働いても残業代は一律」という主旨の制度ではありません。みなし時間を超過した残業は、通常通り従業員に支払う必要があります。
みなし残業を採用しても残業が減らない場合は、その分コストが上乗せされます。そのため、みなし残業を導入しない場合よりも、人件費が増えるケースもあるでしょう。
4-2. サービス残業が増える可能性がある
みなし残業時間を超える残業が発生した場合、従業員は超過した分の残業代を追加で請求する権利があります。
しかし、みなし残業制を導入している場合、みなし時間を超過しても、社内の暗黙のルールとしてサービス残業が増える傾向にあります。
また、「超過分の残業代は支払われない」という誤った認識を持っている場合、自主的にサービス残業をすることもあるでしょう。
サービス残業が増えると従業員のモチベーションが下がり、離職率が高まる可能性も出てきます。
企業としては、できる限りみなし残業時間内に従業員を退勤させるために、決まった時間にPCがシャットダウンされる仕組みを作るなどの工夫をする必要があるでしょう。
4-3. みなし残業に対する不満
従業員が、みなし残業について正しく理解していないと、「みなし時間分も必ず働かなければならない」というような誤解が生じます。このような誤解があると、業務が終了していても会社に残ることになるため、不満を感じる従業員もでてくる可能性があります。また、みなし残業の制度を「おかしい」と感じる従業員もでてくるかもしれません。
このような不満を持つと、従業員はやる気をなくしてしまい業務効率が下がるリスクがあるので注意しましょう。
このデメリットを回避するには、みなし残業に関して従業員が正しく理解できるように、仕組みやルールをしっかり周知させることが大切です。
5. みなし残業制の導入のポイント


みなし残業を自社に導入する際は、制度を社員に周知すること、残業の有無・時間を適切に把握することが重要です。ここでは、みなし残業を導入するときのポイントを紹介します。
5-1. 月45時間を目安にみなし残業時間を設定する
正式には、みなし残業時間に制限はありません。
しかし、36協定において法定外労働時間の上限が原則45時間と定められていることから、みなし残業時間も45時間以内に収めることが望ましいとされています。
特別条項付き36協定を結べば、45時間を超えて残業させることも可能ですが、みなし残業時間が多すぎると人材採用に悪影響を及ぼす可能性もあるので、45時間以内に収めておく方が良いでしょう。
5-2. 就業規則・雇用契約書にみなし残業の詳細を明記する
みなし残業は法令上の根拠がなく、制度はあくまでも「企業が任意に行うもの」とみなされます。
トラブルがあっても根拠を提示できるよう、企業は制度の内容について就業規則や雇用契約書に記載し、従業員の理解を得ておかなければなりません。
明記しておきたいのは、以下の内容です。
- みなし残業代を除く基本給の額
- みなし残業時間
- みなし残業代の金額の計算方法
- みなし残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うこと
なお、社員への周知の努力を怠った場合、みなし残業は法的に無効とされることもあります。
5-3. 残業時間を正しく把握できるツールを導入する
みなし残業を導入すると、より厳密に個人の労働時間を把握する必要があります。「みなし時間内に収まっているかいないか」「収まっていない場合、何時間分超過したか」などをそれぞれ確認する必要があり、給与担当者を混乱させることもあるでしょう。
これを未然に防ぐには、適切な勤怠管理ツールが不可欠です。個々の残業時間を一元的に把握できる、使い勝手のよいツールを選びましょう。
5-4. みなし残業時間を適切に設定する
みなし時間は企業の自由裁量で決定できますが、労働基準法の定める時間外労働の上限を超えてはいけません。
労働基準法では「36協定」によって、労働者の時間外労働は原則月45時間までと定められています。みなし時間は、この範囲内で設定しましょう。
法の定める時間外労働の上限を超えた場合、労働基準法違反として労働基準監督署より指導が入る恐れがあります。ただし、特別な事情がある場合は月100時間未満・年間720時間以内の残業が認められます。(45時間を越えてもよいのは年間6ヵ月まで)
関連記事:みなし残業の上限とは?種類やトラブルについても解説
6. みなし残業制の導入で違法になる場合


安易にみなし残業を導入すると、労働基準法に抵触しトラブルとなる可能性があります。制度を導入する際は、最低賃金・労働時間に注意することが必要です。
みなし残業を導入する際、注意したいポイントを紹介します。
6-1. 最低賃金を下回っている
最低賃金法第4条により、企業は社員に「最低賃金」を支払わなければならない決まりです。みなし残業代と合わせて社員の給与を設定するときは、最低賃金に抵触しないよう注意が必要です。
最低賃金は各都道府県によって異なるため、都道府県労働局や会社や事業所の労働基準監督署で確認しましょう。
6-2. 雇用契約書や就業規則にみなし残業制の詳細を明記していない
雇用契約書や就業規則に、みなし残業制の詳細を記載しないのは違法です。
しっかりと対象の従業員全員に周知をおこない、雇用契約書にて合意してもらう必要があります。
固定残業代については、前項にて紹介した項目を最低限記載するようにしておきましょう。
6-3. 労働時間を適切に管理できていない
労働基準法において、労働時間の管理は雇用主の義務とされていますが、これまでのみなし労働時間制では、使用者による労働時間の把握が除外されていました。
しかし、2019年4月に働き方改革関連法である労働安全衛生法が改正され、みなし労働時間制が適用される労働者の労働時間把握が義務付けられています。「労働時間の把握義務違反」に対しての罰則はありませんが、「月45時間、年360時間」を超えて労働をさせてしまった場合は、「半年以内の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。
タイムカードや勤怠管理システムを利用するなど工夫をして、適切に労働時間を管理するようにしましょう。
6-4. みなし残業超過分の残業代を支払っていない
みなし残業時間を超える残業がおこなわれた場合、雇用主は超過分の残業代を支払う義務があります。
労働時間を適切に把握せず、深夜労働や休日労働における割増賃金の支給をおこなわなかった場合、「未払い残業代の請求」や「残業拒否」など従業員とのトラブルに発展する可能性があります。
また、超過分の残業代を支払わないと従業員からの信頼を失うリスクもあるため、正確な労働時間を把握して未払いがないように注意しましょう。
7. みなし残業の導入は法に則っておこなうことが重要

みなし残業は、社員の給与にあらかじめ「一定時間分」の残業手当を含めて支給する労働契約です。このような契約は、企業にとって、残業代の計算が容易なる・予算の見通しを立てやすくなるなどのメリットがあるでしょう。
ただし、みなし時間は「国の定める時間外労働上限を超えないようにする」「最低賃金を下回らないようにする」など、労働基準法に則って設定しなければなりません。労働基準法に違反した「みなし残業」は無効になることもあるため、導入の際は違法になっていないか、自社の規定をしっかりと確認しましょう。
関連記事:みなし残業と固定残業の違いとは?それぞれの定義を紹介
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。 法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひこちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
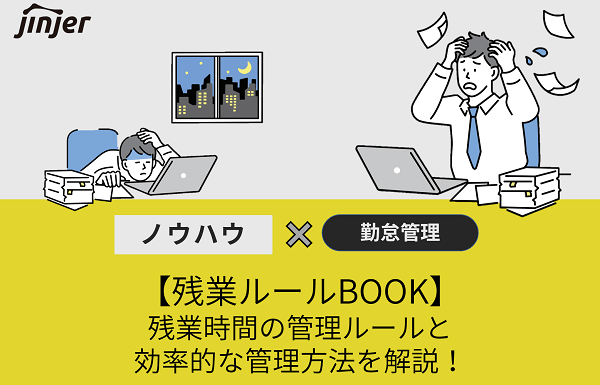
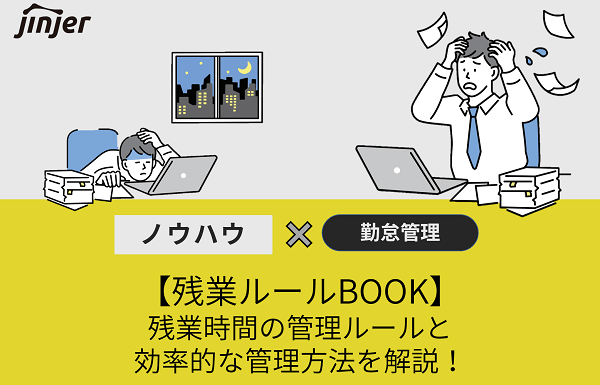
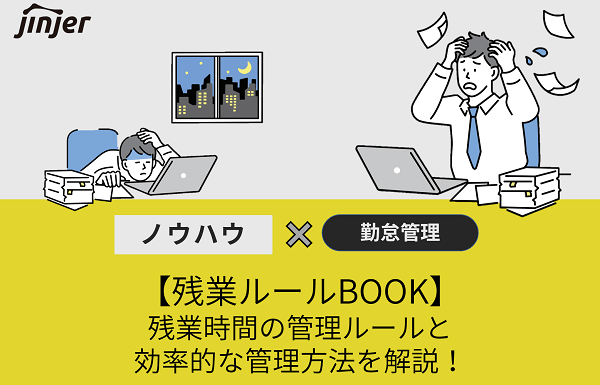
勤怠・給与計算のピックアップ
-



【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.11.15
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.11.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.10.31
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.11.19
残業の関連記事
-


残業代単価の計算方法と勤務形態ごとの考え方をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.06更新日:2024.11.15
-


ノー残業デーを導入する会社のメリット・デメリットを解説!形骸化させない継続のコツとは
勤怠・給与計算公開日:2022.03.05更新日:2024.12.09
-

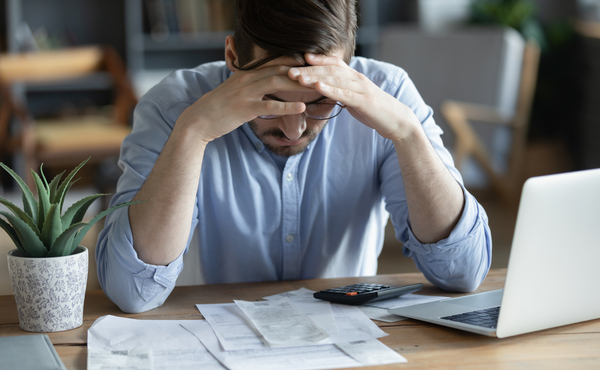
残業手当とは?割増率や計算方法、残業代の未払い発生時の対応を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.04更新日:2024.12.09