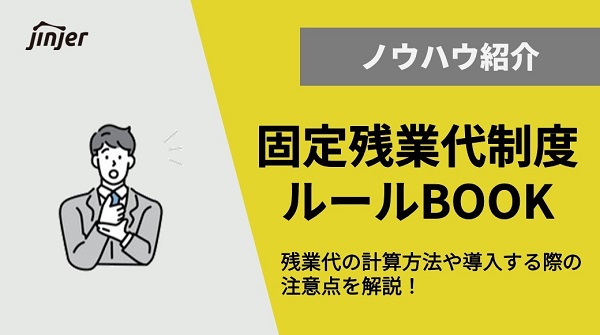みなし労働と固定残業の違いとは?それぞれの定義を紹介
更新日: 2024.5.30
公開日: 2021.9.8
OHSUGI

みなし労働と固定残業の違いを正しく理解している人は、あまり多くないかもしれません。
これらの制度を導入すれば「残業代を支払わなくて済む」と誤解している人も多くみられます。確かに残業代を支払わなくてよいケースもありますが、そうではないケースのほうが多く、きちんと理解しておかないと大きなトラブルにつながりかねません。
そこで、今回はみなし労働と固定残業の違いなどについて解説します。
関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
「固定残業とみなし労働の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし労働の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし労働の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
1. みなし労働とは

みなし労働とはみなし労働時間制に基づく考え方で、労働時間の計算が難しい場合に、実際の労働時間にかかわらず特定の労働時間を働いたものと「みなす」制度です。
この制度を導入すると、基本的に時間外労働があったとしても「残業手当」として残業代を支払う必要はありません。
みなし残業(みなし労働時間制)が適用される制度は「事業場外労働制」と「裁量労働制」の2種類があります。
1-1. 事業場外労働制
事業場外労働制は労働基準法第38の2で定められている「事業場外労働のみなし労働時間制」のことです。営業職や記者など会社の外で働くため、労働時間の計算が難しい職種に用いられています。
ただし、営業職なら必ず事業場外労働制が使えるというわけではありません。事業場外労働制が使えるかどうかは、基本的に「監督者の目が届くか」「労働時間の計算が困難であるか」という2点を考慮して決められます。
たとえば、外で働いていても、次のような場合は監督者の目が届くとされています。
- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
- 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
- 事業場において、訪問先、貴社時刻等当日の業務の具体的な指示を受けた後、事業場外で指示通りに従事し、その後事業場に戻る場合
また、最近増えているテレワークで事業場外労働制が導入されるケースもあります。この場合も導入については一定の基準が示されています。
- 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅でおこなわれること
- 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくとされていないこと
- 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいておこなわれていないこと
テレワークの場合、私生活と仕事が混在している環境が必要です。たとえば、自宅で仕事をしていても、仕事が個室で行われて私生活と分離している場合は、労働時間の計算が困難とはいえません。
携帯電話やパソコンなどの情報通信機器が発達した現代では、電話やメールで具体的な指示がおこなわれていることも多いです。そのため、パソコンの使用履歴や携帯電話の通話記録などから労働時間を把握することも可能となっています。
つまり、事業場外労働制の必要性は減少し、導入のハードルが高くなっているのが現状といえるでしょう。
参考:労働基準法第三十八条の二|e-Gov法令検索
参考:「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために|厚生労働省
1-2. 裁量労働制
次に裁量労働制について解説します。裁量労働制は忙しさに波がある職種に適用されています。裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つがあります。
専門業務型裁量労働制は業種が具体的な19種類に限られています。
- 新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究
- 情報処理システムの分析または設計
- 新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集、放送番組の制作のための取材もしくは編集
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考察
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューザー
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの制作
- 証券アナリスト
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
- 教授研究の業務(主として研究に従事する者に限る)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
企画業務型裁量労働制が適用されるのは、具体的な職種ではなくやや抽象的な条件で決められます。その条件とは「本社・本店等」で「知識・経験のある労働者」が次の4つすべてに当てはまる業務をおこなった場合です。
- 事業の運営に関すること
- 企画、立案、調査委、分析業務
- 労働者の大きな裁量がある
- 業務の遂行手段や時間半分について具体的な指示が必要ない
専門業務型裁量労働制を導入する場合は、労使協定の締結及び労働基準監督署への届け出が必要です。企画業務型裁量労働制の場合は、労使委員会の設置及び労働基準監督署への届け出、労働者本人の同意が必要です。
このように、裁量労働制は導入のハードルが高いといえます。現状の導入率は事業外労働制が11.4%であるのに対して、専門業務型裁量労働制が1.8%、企画型裁量労働制が0.8%とかなり低調です。
参考: 専門業務型裁量労働制|厚生労働省
参考:「企画業務型裁量労働制」の適正な導入のために|厚生労働省
参考:令和2年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省
関連記事:裁量労働制とは?労働時間管理における3つのポイントを徹底解説
2. 固定残業とは

固定残業とは、実際の残業時間にかかわらず一定時間分の時間外手当を毎月定額で支払う制度です。
たとえば、20時間の時間外労働を見込んだ固定残業の場合、時間外労働が20時間までは追加で時間外手当が支払われることはありません。ただし、みなし労働とは異なり、20時間を超えた分については時間外手当を支払う必要があります。
固定残業を導入するためにはみなし労働のような職種による制限はなく、導入のハードルは高くありません。しかし、就業規則や雇用契約書に以下を明記する必要があります。
- 固定残業制が残業手当の定額払いであり、他の賃金とは区別されていること
- 固定残業代に何時間分の時間外手当が含まれているか
- 固定残業分の時間外労働を超える場合は、別に時間外手当を支払うこと
固定残業の導入前から働いている従業員に対しては給与辞令や労働条件変更通知書などで固定残業制を導入することを周知しなければいけません。
固定残業代制度は、制度の内容を人事担当者が正しく理解したうえで、従業員に理解を得て適切に運用しなくては、従業員とのトラブルになりかねません。当サイトでは、固定残業代制度を適切に運用するポイントをまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料配布しておりますので、制度導入に不安のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
関連記事:固定残業代とは?制度の仕組みや導入のポイントを分かりやすく解説
3. みなし労働や固定残業でよくある誤解

ここでは、みなし労働や固定残業でよくある誤解をいくつか挙げ、それぞれについて詳しく解説します。
3-1. いくら残業しても残業手当を支払わなくてよい?
固定残業の場合、見込んだ時間数をオーバーして時間外労働をした場合、その分の時間外手当を支払う必要があります。たとえば、固定残業20時間を見込んでいた場合に30時間残業をしたとすると、10時間分の時間外手当を支払わなくてはいけません。
一方、みなし労働は基本的にいくら残業をしても残業手当として給与を支払う義務はありません。ただし、義務がないからといって支払わないまま放置することは、社会通念上好ましくないと言えるでしょう。また、その人に与えられた仕事が、そもそも「見込み労働時間では終わらない内容である」と判断された場合は、超過した分だけ時間外手当を支払う必要があります。
また、休日や深夜労働に対する割増手当はみなし労働でも支払わなくてはいけません。
3-2. 残業の上限がない?
固定残業、みなし労働ともに、残業時間の上限については明確な定めがありません。しかし、36協定における残業時間の上限が原則月45時間となっています。そのため、固定残業、みなし労働どちらも月の残業時間の上限は45時間としましょう。
過去には月45時間を超えるみなし労働の一部が無効と認められた判例もあります。また、月45時間を超える残業を科すと従業員の離職や応募者の減少などにつながりかねません。
参考:ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル(自然退職)事件|全国労働基準関係団体連合会
3-2. 内勤と外勤が混在する場合はどうなるか
事業場外労働制の場合で会社内での勤務と外回りの勤務が混在する場合、みなし労働が適用されるのは外回りの勤務のみです。会社内での仕事はみなし労働時間の範囲外となるため、1日8時間・週40時間の制限を超える場合は時間外手当を支払わなくてはなりません。
3-3. いつ休んでもよい?
裁量労働制は「いつでも休める」「休みやすい」と思われがちです。しかし、裁量が認められているのは労働日の始業時間と終業時間で、労働日を好きに選べるわけではありません。
事業場外労働制や固定残業制の場合も、労働日が決まっています。そのため、裁量労働制と同様、勝手に休むことはできません。
4. みなし残業制度を導入するポイント


みなし残業制度を導入するには次のようなポイントを押さえておきましょう。
- 就業規則に明記する
- みなし労働の時間を規定する
- 従業員の労働時間を適切に管理する
4-1. 就業規則に明記する
みなし残業制度を導入するには就業規則への明記が必要です。みなし労働における固定の残業代は賃金にあたります。賃金については就業規則への明記が必要です。賃金については就業規則だけでなく雇用契約書への明記も求められます。そのため、就業規則に加えて雇用契約書にもみなし労働における残業代について明記しましょう。
4-2. みなし労働の時間を規定する
みなし残業制度の導入にあたっては、どれだけの時間がみなし労働にあたるか、残業時間を規定しましょう。みなし労働を規定しておけば、規定時間を超過した分の残業代を計算しやすくなります。
みなし労働の時間を規定し、超過した分は改めて残業代を支払う必要があることを管理者や総務担当者に伝えておきましょう。
4-3. 従業員の労働時間を適切に管理する
みなし労働であっても、従業員の労働時間を適切に管理しましょう。管理を疎かにしてしまうと、超過した残業時間の把握に時間を要してしまう恐れがあります。また、労働時間を適切に管理しないと、長時間労働により従業員のモチベーション低下や離職につながりかねません。
5. みなし労働と固定残業は制度についてしっかり理解してから導入しましょう


みなし労働と固定残業の違いについて解説しました。誤解されがちですが、みなし労働と固定残業は残業手当を支払わなくてよい制度ではありません。人件費を減らす目的でこれらの制度を導入しても、思うように費用を削減できないでしょう。
また、制度について誤解している人も少なくありません。後のトラブルを避けるためにも、企業側は制度の目的を正しく理解してから導入することが大切です。
関連記事:みなし残業制度とは?定義やメリット・デメリットを詳しく解説
「固定残業とみなし労働の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし労働の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし労働の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
残業の関連記事
-


残業代単価の計算方法と勤務形態ごとの考え方をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.06更新日:2024.10.17
-


ノー残業デーを導入するメリット・デメリットと継続のコツ
勤怠・給与計算公開日:2022.03.05更新日:2024.01.15
-

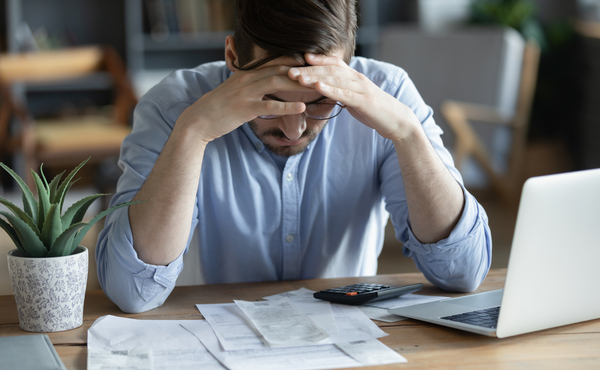
残業手当の計算方法や割増率、未払い発生時の対応を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.04更新日:2024.09.03