法人カードと会計ソフトを連携するメリットや使い方について
更新日: 2024.2.29
公開日: 2022.1.13
jinjer Blog 編集部

法人カードと会計ソフトを連携すれば、カードの利用明細を自動でシステムに反映し、仕訳までおこなうため、経理部門の手間削減やミス防止に役立ちます。
この記事では、法人カードと会計ソフトを連携するメリットやおすすめの会計システムとその使い方を解説します。
1. 法人カードと会計ソフトを連携する3つのメリット

法人カードと会計ソフトを連携できれば、会社で利用している法人カードの支払いデータをそのまま会計ソフトに反映できます。
もちろん、会計ソフトによっては、利用データの仕分けまで自動でおこなうため、経理業務の手間を大きく削減することが可能です。双方を連携させるメリットを3つ紹介します。
1-1. 経理業務を効率化し手間を削減できる
法人カードと会計ソフトを連携させる大きなメリットは、経理業務の手間を削減できる点です。
データを元に、ある程度自動で経費の仕分けができるため、経理担当者は勘定科目に誤りがないか、経費の私的利用はないかなどを確認するだけでよくなります。そのため、労働時間の大幅な削減につながります。
関連記事:法人カードで経費精算を行うメリット・デメリットや手順とは
1-2. 手入力によるミスを防止できる
領収証を見ながら日付・金額・取引内容を一つ一つ手で入力すると、どうしても人為的ミスが発生しやすくなります。
また、数字の反転のように、手入力で生じたミスは後から確認しても見つけづらい点もデメリットです。
法人カードで利用した明細をそのまま落とし込めれば、金額や日付のように重要で細かな入力が不要になる分、ミスの削減にもつながります。
1-3. 初心者でも会計業務がしやすくなる
仕分け方法や勘定科目は、企業によっても使っているものが異なります。
そのため、経理部門の担当者が移動や退職などすると、引継ぎだけでも相当な手間と時間がかかります。
ですが、法人カードと会計ソフトを連携し、ある程度自動で仕分けができる仕組みがあれば、新人スタッフも比較的早く仕事を覚えられるでしょう。
経理業務を人に所属させず、システムで管理すれば、急な人事異動にも対応しやすくなります。
2. 自動連携できる会計ソフトの注意事項

最後に、会計ソフトの自動連携をする際の注意事項を解説します。
2-1. クラウド型・インストール型で取り込めるカードに差がある
会計ソフトはクラウド型の方が、対応している法人カードが多い傾向にあります。
また、同じカード会社でも、個人カードのみ対応しているケースもあるため、事前に詳しく確認しましょう。
2-2. 金融機関によっては連携まで数日かかる
金融機関によっては、連携の際、事前に申し込みをして金融機関のIDとPWの発行が必要なケースもあります。
その場合、連携まで数日かかることもあるため、余裕を持って取り組みましょう。
2-3. 経費精算システムの方が連携しやすい可能性も
最後に、法人カードとの連携のしやすさだけ見れば、経費精算システムの方が対応するカードが多かったり、使いやすかったりするケースもあります。
また、経費精算システムは、会計ソフトと連携できるものも多数あります。
そのため、経理業務を効率化したい場合、会計ソフトに限らず、他にも法人カードと連携できる仕組みはないか、探してみるのもおすすめです。
3. 法人カードと会計ソフトを連携して、経理業務を効率化しよう

法人カードと会計ソフトを連携すれば、利用データを自動で反映し、仕分けができるため、経理業務の効率化に役立ちます。
ただし、会計ソフトの中には連携できる法人カードが少ないものもあるため、その際は経理精算システムなどを経由し、連携するのがおすすめです。
法人カードの自動取り込み機能を活用し、経理業務を効率化しましょう。
「中長期的に法人カード導入を検討しているけどなにからはじめたらいいかわからない」
「法人カードを実際に利用するイメージをつけたい」
「法人カード連携した経費精算システムの導入を検討している」
などなど法人カードをもちいた経費精算の効率化に興味がある方に、実際の法人カード導入の手順からそのメリット、また 法人カードを用いた精算業務の効率化方法まで網羅的に解説している資料を配布しております。
資料は無料ですので、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
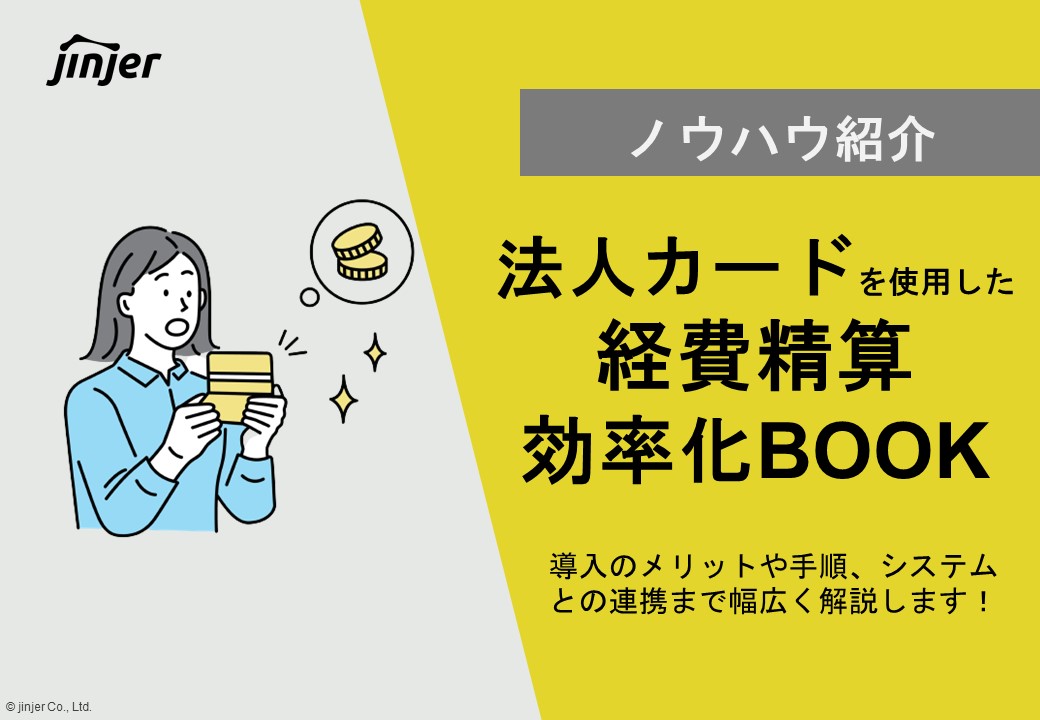
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
法人カードの関連記事
-

法人カードで仕訳できる勘定科目の種類やポイント
経費管理公開日:2022.01.13更新日:2024.05.08
-

法人カードを導入する企業の目的とは?メリットや経費精算時の注意点を解説
経費管理公開日:2022.01.13更新日:2024.06.24
-

コーポレートカードの特徴とは?法人カードにおける特徴やメリットについて
経費管理公開日:2022.01.13更新日:2024.07.01




























