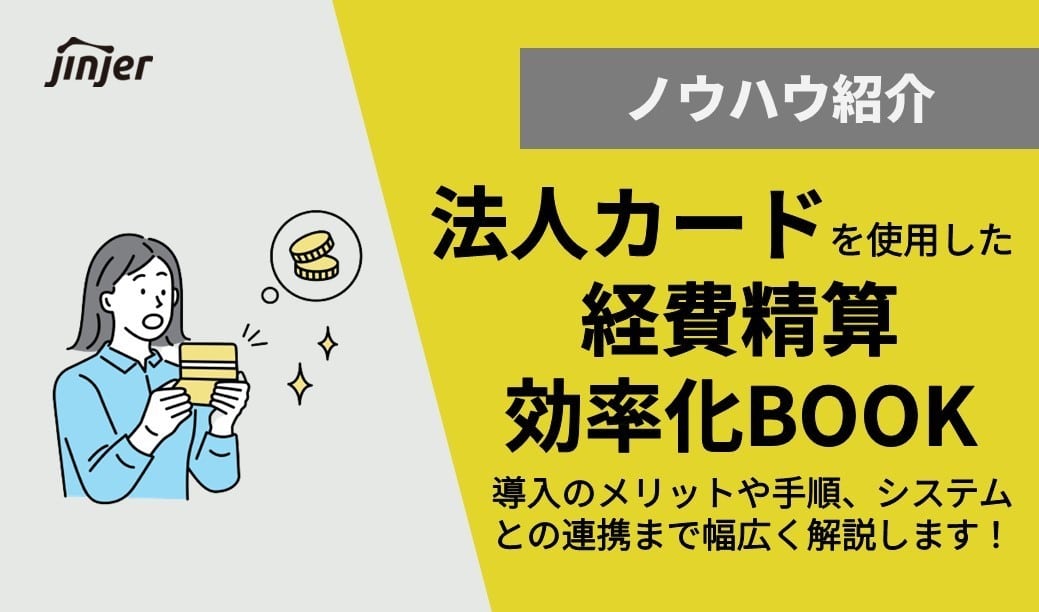法人カードで経費精算をおこなうメリット・デメリットや手順とは
更新日: 2024.2.29
公開日: 2022.1.13
jinjer Blog 編集部

経費精算にクレジットカードを利用している会社は多いですが、一般的な個人カードではなく、法人カードを使用するとより多くのメリットを得ることができます。
特に経費精算にかかる手間や時間に悩まされている方は、法人カードの導入を積極的に検討してみましょう。
今回は、法人カードで経費精算をおこなうメリット・デメリットや、経費精算に法人カードを利用する際の手順について解説します。
目次
1. 法人カードで経費精算をおこなうメリット

会社の経費精算に法人カードを使うと、以下のようなメリットがあります。
メリット1. 経費精算を効率化できる
社員が業務に必要な備品を購入したり、出張の際に公共交通機関や宿泊施設などを使用したりする際に現金で決済すると、経費の立替払いや領収書の管理、精算書の作成および提出など、さまざまな手続きが必要になります。
経費を利用した社員本人はもちろん、精算書の受取・承認をおこなう上司や、仕訳処理および支払いをおこなう経理担当者にも大きな負担がかかってしまい、場合によっては本業に支障を来すこともあります。
法人カードの場合、会社で利用している経費精算ソフトや会計ソフトと連携すれば、カードの精算データがリアルタイムで自動反映されるため、領収書のチェックや精算書の作成、仕訳処理といった一連のプロセスを大幅に簡略化できます。
これまで経費精算業務にかかっていたマンパワーを本来の業務に向けることができるため、労働生産性の向上にもつながるところが大きな利点です。
メリット2. 小口現金や立替・仮払いを廃止できる
経理業務の中でも小口現金の管理は、経理担当者にとって手間のかかる業務の一つです。特に、現金の出し入れが多い事業所だと、残高が合わないといったミスも起こりやすくなります。
法人カードであれば、社員カードを追加発行して社員にクレジットカードを持たせることもできるので、業務に必要な経費をカード精算できるようになれば、小口現金の管理負担を減らすことが可能です。
同様に、社員への現金受け渡しがなくなれば、立替や仮払いなど精算手続きの頻度も減らすことができるでしょう。
精算は社長が持つ本カードに集約されるため支払い口座は1本で済み、利用データも一元管理できるので経費精算の手間を大幅にカットできます。
メリット3. 経費精算の入力ミスを軽減できる
経費を現金でやり取りすると、途中で紛失したり、盗難に遭ったりする危険性があります。
また、手作業による経費精算は記入漏れや記入ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、あとから修正した場合は二度手間になってしまいます。
法人カードで経費精算をおこなえば、いつ・どこで・誰が・何に・いくらお金を遣ったのか、詳細なデータが会計ソフトや経費精算ソフトに自動入力されるため、人的ミスを未然に防ぐことができます。
また、現金によるやり取りは一切発生しないので、現金の紛失・盗難といったトラブルリスクも回避することが可能です。
メリット4. キャッシュフローにゆとりができる
現金決済の場合、月末などに一気に精算すると社員に負担がかかるため、経費で商品やサービスを利用する場合、その都度精算するのが一般的です。
そのため、時期を問わず常に口座からの支払いがあり、キャッシュフローが安定しにくい状態になります。
法人カードなら、毎月決まった締め日までにかかった経費が翌月の決まった支払い日に引き落とされるので、利用した日と支払い日までに一定の猶予が生まれます。
支払い日までは法人口座に入っている金額を一定に保つことができるため、キャッシュフローにゆとりを持たることが可能です。
メリット5. 経費精算の透明性が高まる
社員が個人的に発行した私的カードで経費の決済をおこなう場合、社員が私用で利用した分と、経費決済に利用した分が混在してしまいます。
カードの明細書をチェックする側も、ぱっと見ただけでは私的の利用分か、経費分か判別するのは難しく、経費精算業務に余計な手間がかかってしまうほか、場合によっては経費の不正利用を見過ごす原因となってしまうこともあります。
法人カードを利用すれば、社員の私的なクレジットカードを使わずに済みます。明細書も一つにまとめられるので、明細書チェックの手間が省けると共に、経費の不正利用防止にも繋げることができるでしょう。
メリット6. 付帯サービスの活用で経費の節約ができる
個人向けクレジットカードと同じく、法人カードにもさまざまな付帯サービスが付いています。
サービス内容は発行するカードによって異なりますが、法人カードだけにビジネス向けの付帯サービスが多く、日常業務はもちろん、出張や接待にも役立てることができます。
以下では、代表的な法人カードの付帯サービスをいくつかピックアップしてご紹介します。
● 海外旅行損害保険
● ショッピング保険
● ETCカードの複数枚発行
● レストラン・レジャーの優待サービス
● 空港ラウンジサービス
● 公共交通機関のオンライン予約サービス
● 24時間コンシェルジュサービス・デスクサービス
海外出張の多い会社なら、海外旅行損害保険や空港ラウンジサービス、公共交通機関のオンライン予約サービスを無料で利用できるのは便利ですし、初めて行く場所でわからないことがあったらコンシェルジュサービスやデスクサービスを利用することで適切なアドバイスやサポートを受けられます。
また、ショッピング保険があれば、カードを使って物品を購入した場合に補償を受けられるので、高額なオフィス用品なども安心して購入できます。
他にも、レストランやレジャーを優待価格で利用できるサービスもあり、接待に活用すれば経費の削減になります。
さらに、法人カードには一般的なクレジットカード同様、独自のポイント制度が採用されており、カードの利用金額に応じてポイントやマイルが付与されます。
貯まったポイント・マイルは現金や商品、航空券などと交換できるため、実質上のキャッシュバックとなり、経費の節約につながります。
2. 法人カードで経費精算をおこなうデメリット

会社の経費精算に法人カードを利用すると、さまざまなメリットがある一方、いくつか注意しなければならない点もあります。
ここでは、法人カードで経費精算をおこなう場合に想定されるデメリットやリスクをご紹介します。
デメリット1. 年会費が発生する
個人向けクレジットカードの中には、年会費が永年無料になっているものも多く、カードの保有そのものにコストが発生することはありません。
一方、法人カードのほとんどは年会費が有料になっており、カード利用の有無にかかわらず、毎年一定の会費を支払う必要があります。
年会費はカードによって異なるので一概にいくらとはいえませんが、利用限度額の大きいカードや、ステータス性の高いカードの場合、3万円以上の年会費が発生することもあります。
中には年会費が1,000円~2,000円程度とリーズナブルなものもありますが、利用限度額や社員カードの発行数が少ない可能性があるため、年会費だけにとらわれず、自社のニーズに合っているかどうかもきちんとチェックしましょう。
デメリット2. 分割払い・リボ払いに対応していないカードもある
個人向けクレジットカードの場合、ほとんどは分割払いやリボ払いに対応しており、月々の返済額を少額に抑えることが可能です。
しかし、法人カードでは分割払いやリボ払いに対応していないケースもあります。
その場合、決済は原則として一括払いとなるため、口座の残金チェックをしなくてはいいけません。
なお、最近は分割払いやリボ払いに対応している法人カードもいくつかあるので、「必要に応じて支払い方法を使い分けたい」という方は、法人カードを選ぶ際に分割払い・リボ払いができるかどうか確認しておきましょう。
デメリット3. キャッシングに対応していないカードもある
個人向けクレジットカードの多くは、買い物するときの決済だけでなく、決められた範囲内でお金を借り入れる「キャッシング機能」が付帯されています。
銀行ATMやコンビニATMなどで手軽にお金を借りられるため、急な出費があるときなどに重宝しますが、法人カードの場合、キャッシング機能が付帯されていないケースが多いようです。
分割払いやリボ払い同様、近年はキャッシング可能な法人カードも出てきていますが、数はあまり多くないので、選択肢は少なくなってしまう点に注意が必要です。
デメリット4. 個人向けカードに比べるとポイント還元率が低め
クレジットカードは、利用額に応じてカード会社独自のポイントが付与されるところが大きなメリットです。
ただ、法人カードの場合、個人向けクレジットカードに比べると利用額に対するポイント還元率が低い傾向にあります。
ポイントは各種商品のほか、現金や金券などにも交換できるため、ポイント還元率が少ない法人カードはキャッシュバック率が低くなってしまうところが残念なところです。
なお、法人カードによってはポイント機能そのものが付帯されていないケースもあります。
ポイント還元率が低いとはいえ、事業では毎月多額の経費が発生するので、ポイント機能付きの法人カードを利用した方が節約効果は高くなるでしょう。
3. 法人カードで経費精算をおこなうための手順
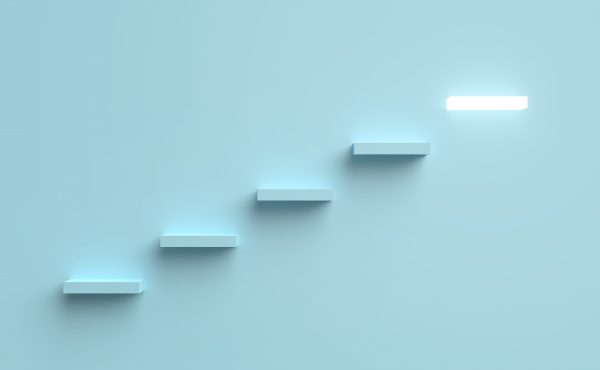
法人カードを使って経費精算するためには、まず法人カードを作るところから始めなくてはいけません。また、社員それぞれにカードを持たせるのであれば、追加カードの発行手続きも必要です。
ここでは、法人カードや社員用の追加カードを作成する手順を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1. 申込用紙またはオンラインフォームでカード発行申請をおこなう
申込用紙またはオンラインフォームを使ってカードの申込みをおこないます。
より簡単かつスピーディに申し込みたいのなら、オンラインフォームを利用した申込みがおすすめです。
オンラインフォームでは、代表者の氏名や住所、連絡先のほか、会社名や年収などの情報を明記します。
ステップ2. 必要書類を提出する
法人カードを申し込むときは、以下の書類が必要になります。
・代表者の本人確認書類の写し
・登記簿謄本(写しでも可)
本人確認書類は顔写真付きのもので、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが挙げられます。
一方の登記簿謄本はたいていの場合、「6ヵ月以内に発行されたもの」という条件がつきます。
登記簿謄本は法務局窓口のほか、「登記・供託オンライン申請システム内にある「かんたん証明書請求」から交付を請求することもできます。
受取は登記所の窓口か、あるいは郵送してもらうこともできますので、都合の良い方法を選びましょう。
なお、必要書類の提出は郵送のほか、カード会社によってはWEBアップロードに対応しているところもあります。
その場合、必要書類をカメラ機能を使ってアップロードするだけで良いので、わざわざ郵送する手間を省くことができます。
ステップ3. カード会社の審査を受ける
申込書や必要書類がカード会社に到着すると、所定の審査がおこなわれます。
審査では会社の経歴や実績、事業収入、代表者の信用情報などがチェックされ、一定水準をクリアすれば審査をパスすることができます。
審査の結果はメールまたは書面で通知されますが、受かった場合はカードの発行をもって通知に代えるケースも多いようです。
ステップ4. 法人カードの発行
申込書に記載した住所宛に法人カードが郵送されます。
審査に合格してからカードが到着するまでの日数はカード会社によって異なり、7営業日程度で発行されるケースもあれば、1ヵ月程度かかるところもあります。
ステップ5. 社員カードの発行
社員用カードを発行する場合は、法人カードの使用者を追加する手続きをおこないます。
専用の「使用者追加届」などを提出し、必要なぶんだけ追加カードの発行を依頼しましょう。
追加カードの支払いは代表者が所有するメインカードに集約されますので、追加カードは一般的に審査なしで発行することができます。
なお、追加カードの発行枚数や発行費、年会費などはカードによって異なります。
特に、カードを持たせたい社員に対して、追加カード発行枚数が不足している場合、カードのない社員の経費精算は現金決済か、あるいは他のクレジットカードを持たせるしかなくなり、経理業務に余計な手間がかかる原因となります。
社員カードを発行するのなら、まずは必要な枚数のカードを発行できるかどうかを優先的にチェックしましょう。
4. 経費精算システムに連携するのもおすすめ

経理業務の効率化を目的に法人カードを発行するのなら、会社で使っている経費精算システムと連携させるのがおすすめです。
経費精算システムと連携させると、カード利用データが自動でシステムに取り込まれるため、明細書を見ながら手入力する手間と時間を省けます。
ただ、法人カードと経費精算システムには相性があり、特定のシステムでないと連携できない場合があります。
連携可能な経費精算システムはカードによって異なるため、すでに会社で経費精算システムを導入している場合は、自社システムに対応した法人カードを選ぶことが大切です。
法人カードの発行と同時に経費精算システムを導入する場合も、互いの相性をチェックし、連携可能かどうかをしっかり確認しておきましょう。
5. 法人カードを経費精算に利用する前に準備したいこと

法人カードを作成したとしても、事前に社内でカード利用のルールが決められていなければ、逆に経理業務の負担を招く原因になることも想定されます。
法人カードを経費精算に利用する場合は、事前に以下のことを準備しておくと、スムーズかつ適切に運用しやすくなるでしょう。
5-1. カードを利用する範囲をあらかじめ決めておく
近年はキャッシュレス化が進み、ほとんどの店舗・サービスでクレジットカード決済が可能となりました。
決済の手間が省けるのは大きな利点ですが、そのぶん簡単に使われやすいというリスクをはらんでいます。
法人カードの利用目的はあくまで経費精算ですので、業務で使わないもの、必要ないものの決済にカードを使われるのは避けたいところです。
そのため、社員用に追加カードを発行する場合は、どこからどこまでが経費として認められるのか、あらためて周知させることが大切です。
もちろん、社長とて例外ではありませんので、会社用の法人カードと、社長個人が利用する個人カードはしっかり区別して使うことを心がけましょう。
5-2. 個別に利用上限額を設定しておく
社員カードの支払いはメインの法人カードに集約されるため、複数の社員があちこちで決済すると、ひと月あたりの引き落としが多額になってしまうおそれがあります。
法人カードの多くは、社員カード一枚ごとに上限額を設定することができるので、それぞれの担当業務を考慮しながら、適切な利用額を決めておくのが望ましいでしょう。
6. 法人カードで経費精算をおこなう上での注意点

法人カードを導入すれば、さまざまな面において経費精算が効率化されるのが魅力です。しかしながら、法人カードを用いて経費精算をおこなう際にいくつか注意すべき点もあります。
次に紹介する注意点を踏まえて、法人カードを上手く活用していきましょう。
6-1. 二重計上に気をつける
クレジットカードで支払うと領収書とクレジット売上票が発行されますが、それぞれ別々に管理してしまうと、経費を二重計上する恐れがあるため注意が必要です。
税務調査の際に、計上ミスであったとしても不正とみなされてペナルティを受ける可能性もあります。
領収書とクレジット売上票はホチキス留めにしてまとめるなどして、バラバラにならないよう管理しましょう。
6-2. クレジット売上票を廃棄しない
税務調査でクレジットカードで決済した経費について指摘を受けた際に、クレジット売上票があることで説明がしやすくなるため捨てずに保管しておきましょう。
経理側だけで周知するのではなく、社員カードをもつ社員たちにも、クレジット売上票や領収書を安易に廃棄しないことを周知しておくことが必要です。
7. 法人カードで支払った経費の領収書について

法人は、取引をおこなう際に作成、受領した帳簿書類等を保存しておくことが法令によって義務づけられています。
帳簿書類とは、総勘定元帳や仕訳帳、発注書や契約書、そして領収書を意味しているため、領収書は正しく保管しておく必要があります。
しかし、法人カードは基本的に翌月以降の支払日に口座から自動で引き落とされる仕組みになっているため、管理方法が通常とは少し異なります。
7-1. 国税庁による領収書の見解
国税庁の見解では領収書とは「その受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書」となっているため、取引が正式に終了していない段階では、正式な「領収書」として発行することは認められておりません。
領収書でなければ国税関係書類として利用することはできませんので、基本的に法人カードで決済された領収書は不要となります。
7-2. 法人カードで領収書が必要になる場合
法人カードで支払いをおこなった際に、基本的に領収書は不要と述べましたが、会計処理をおこなうにあたって、支払いの証拠が必要な場合もあるでしょう。
その場合は法人カード支払いをおこなった際に発行される「クレジットカード売上票」、または「レシート」を残しておくことが良いでしょう。
関連記事:法人カードで領収書が不要になるケースとは?採用するメリット・デメリットについて
8. 法人カードで経費精算をおこなうと、業務効率アップやエラー防止に役立つ

法人カードをで経費精算をおこなうと、経費の利用データを一元管理できるようになるため、経理業務にかかる時間と手間を省くことができます。
また、経費精算システムと連携すれば、利用データの自動取り込みが可能となるため、明細書を見てデータを手入力する労力を省けるのはもちろん、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの予防にもつながります。
個人向けクレジットカードに比べると、「年会費が発生する」「リボ払いや分割払い、キャッシングに対応しているカードが少ない」といったデメリットはありますが、経費精算に係る業務全般を効率化できるのは何よりの魅力です。
カードの利用限度額や追加カードの発行枚数、年会費、付帯サービス、対応する経費精算システムなどは法人カードの種類によって異なりますので、自社のニーズや利用している計精算システムなどに合わせて適切な法人カードを選択しましょう。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04