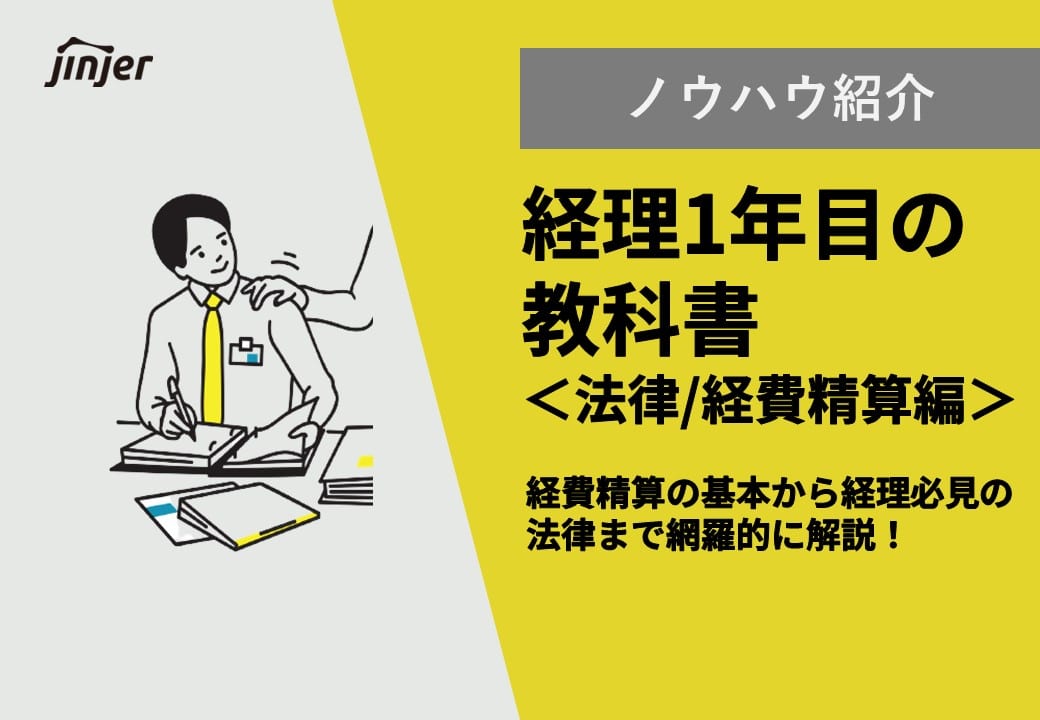経費精算のルールはなぜ必要?規定の作成方法や注意点を解説
更新日: 2024.7.12
公開日: 2023.5.10
jinjer Blog 編集部

経費精算というのは、不正やトラブルなどの課題があります。これらの課題を解決するには、ルールを明確にすることが重要になるため、経費精算規定を定めましょう。経費精算規定を適切に作成しておけば、経費精算に関する不正やトラブルを防ぐ効果が期待できます。
本記事では、経費精算のルールを定める目的とともに、経費精算規定の具体的な記載項目や科目別の注意点について解説していくので、経費精算規定の作成や見直しにお役立てください。
法改正に完全対応!これ一冊で経理業務は完全理解!!
「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。
特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
1. 経費精算規程とは?
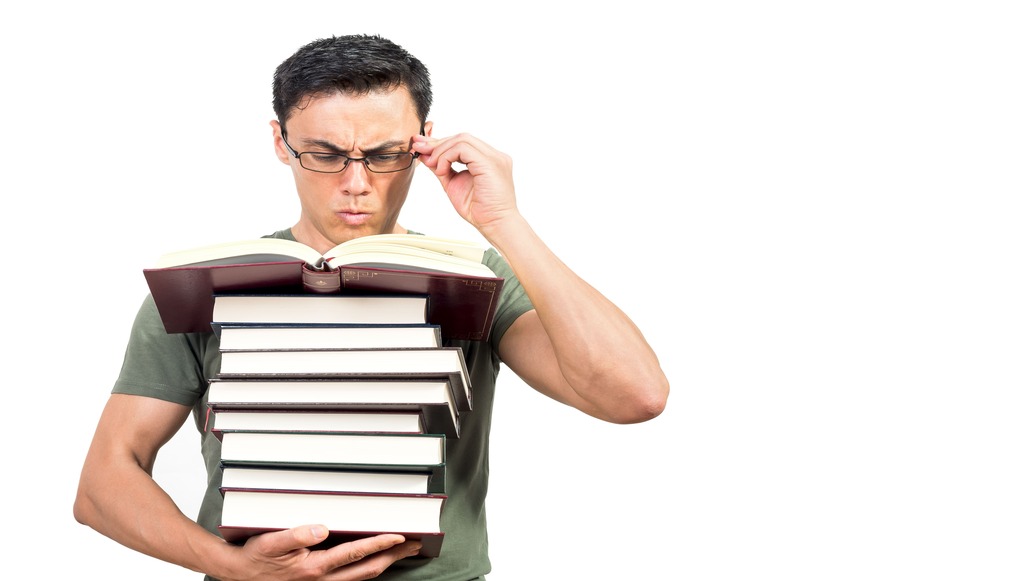
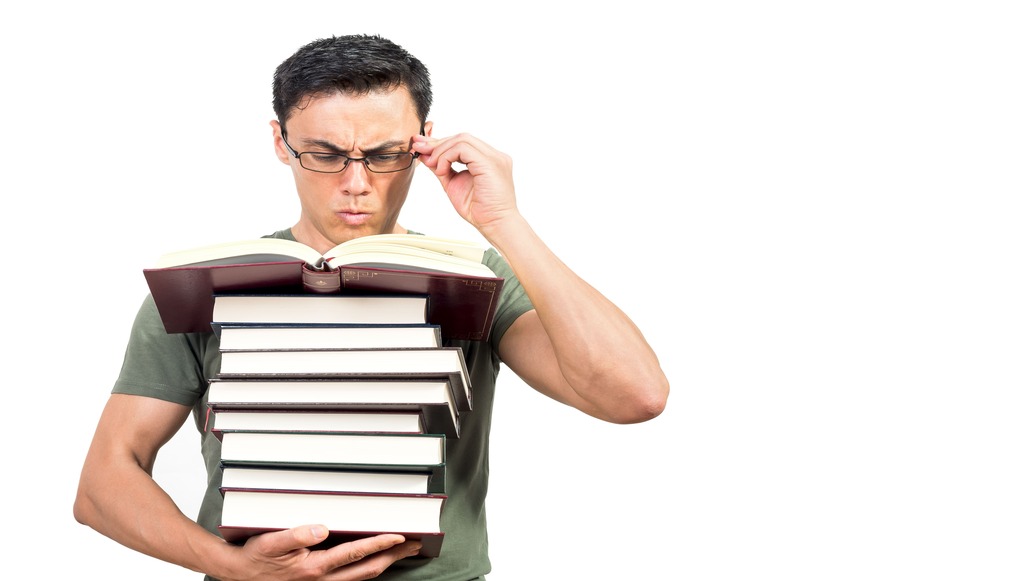
経費精算規程とは、企業が定める経費精算のルールです。就業規則や賃金規程のような「社内規程」のひとつであり、経費に関する決まりが記載されています。経費精算規程を確認することで「どのような支出が経費として認められるのか」「経費はどのように精算すれば良いのか」が明確になるでしょう。
交通費や出張費といった経費の精算は、どこの企業でも必ず発生します。あらかじめ経費精算規程を作成し、従業員に周知しておくことが大切です。経費精算規程があれば、経費精算時に従業員が迷うことがなくなりますし、経理担当者の業務もスムーズになるでしょう。
2. 経費精算規程が必要な理由


経費精算規程は、企業にとっても従業員にとっても有用な規定です。しかし、有用とわかっていても、作成するのは大変なので、後回しになっていることもあるのではないでしょうか。
そこで、ここでは例え時間がかかる作業であっても、経費精算規程を作成すべき5つの理由を紹介します。
2-1. 経費をしっかり管理するため
経費精算規程には、「何が経費として認められるか」が明文化されているため、経費をより厳格に管理できます。
明確な規定がないと、「取引先との約束に遅れそうなときに利用したタクシーは経費になるか」といった細かい判断を場当たり的におこなうことになりかねません。これでは、本来経費として認められない支出まで経費計上されてしまう恐れがあります。
無駄な支出を省き、本当に必要な経費のみ支払うためには、そのための規定が必要になるのです。
2-2. 不正を防ぐ
経費精算規程は、従業員による不正の防止にも役立ちます。
規定を明確にしておけば、実際には経費として認められないものを経費として水増し請求するのが困難になるでしょう。故意におこなった不正でなくても、うっかり「本来とは異なるルートで交通費の申請をしてしまった」といったことがあるかもしれません。経費に関する不正行為は、経費の水増しによる脱税とみなされたり、社会的な信用の失墜につながったりする恐れもあります。
このようなリスクを軽減するためにも、事前に経費精算規程を定めておく必要があるのです。
2‐3. 節税につながる
企業が経費計上する支出には、法人税が非課税になるものと課税されるものの2種類があります。
経費精算規程を設けて両者を明確に分類し、正しく申告することは節税につながる可能性があるのです。どれだけ黒字の企業であっても、節税対策は必要不可欠なので、経費精算規程の策定も必要といえます。
また、経費精算をきっちりせずに給与に上乗せした場合、従業員が負担する所得税や住民税が増加します。一方、経費として精算すればいくら受け取っても非課税です。経費精算規程にのっとった経費精算は、従業員にもメリットがあるといえるでしょう。
2‐4. 誰でも公平に経費精算できる
経費精算規程があれば、「申請したタイミングや部署によって対応が違う」といった不公平感がなくなります。従業員によっては、不公平感を持つと仕事へのモチベーションが落ちることもあるため、間接的な生産性の低下を招く恐れがあるので注意が必要です。
担当者の経験の長さや権限に関係なく、ルールに基づいた経費精算をすることはコンプライアンス遵守の観点からも重要です。
2‐5. 経理担当者の業務がスムーズになる
経理担当者にとっても、経費精算規程の作成はメリットになります。
対処が難しい、もしくは判断しづらいケースについても、あらかじめルールが明確になっていれば、それに沿った対応が取れることでタイムロスを防ぐことができます。また、経費精算のルールに納得しない従業員がいたとしても、規定があればそれを根拠に説明ができるので、不要なトラブル防止にもつながります。
3. 経費精算規程に記載すべき項目


経費精算規程の具体的なフォーマットや記載項目、記載内容は、それぞれの企業が自由に定められます。ただし、あまりにも項目が多すぎると、逆に担当者の手間を増やしてしまうかもしれません。逆に少なすぎると、ルールがあいまいで業務効率が下がってしまう可能性もあるため、適切に決める必要があります。
そこでここでは、一般的に経費精算規程に記載しておいた方がよいと考えられる8つの項目を紹介します。
3‐1. 経費に該当する支出の種類
まずは、何が経費に該当するのかを明確にしておく必要があります。
例えば「定期券の範囲内での移動にかかる交通費は経費に該当しない」といった規定がないと、定期券を持っている従業員が営業交通費を余分に精算できてしまいます。何が経費になって、何がならないのかを規定しておくことが大切です。
3‐2. 精算可能な上限金額
一度に精算可能な経費の金額を定めておくと、高額な経費精算を防げます。
ただし、出張など高額な経費精算が必要になることもあるでしょう。このようなケースが考えられる場合は、「一定額を超える場合は稟議を通す必要がある」と規定しておくのがおすすめです。
3‐3. 決裁権者の条件
経費精算のためには、通常、上司の決裁が必要です。
そのため、決済が必要であるということと、だれが決裁権を持つのかを明記しておきましょう。合わせて、自己決裁(自己承認)の禁止規定を設けておくと不正が起こりにくくなります。
3‐4. 経費精算期限
過去を遡っての承認は、領収書などの書類を紛失しやすいというリスクがあります。そのため、経費精算がいつまでできるのか、期限を設けておくことも重要です。
ただし、経理部の都合だけで期限を決めてしまうと、申請者への負担が大きくなるかもしれません。特に営業部などデスクワークをする時間が取りにくい部署がある場合は、業務フローを考慮して期限を決めましょう。
3‐5. 領収書の添付ルール
経費精算には、不正を防ぐため原則として領収書の添付が必須です。また、税務署の調査が入った場合は提出が求められるので、添付を義務付ける旨を明言しておきましょう。
また、電車賃のようにそもそも領収書がない場合や、紛失してしまった場合どのように対処すれば良いのかも規定しておきます。この点をあいまいにして、精算したりしなかったりすると、「領収書を添付しなくても精算できる」と思ってしまう従業員がでてくるかもしれません。このようなケースは不正につながりやすいので、必ずルールとして決めておく必要があります。
3‐6. 科目別のルール
経費精算のルールは、支出の種類によって異なることがあります。
科目別に異なるルールがある場合、それに沿った対応を取るように明記しておくと良いでしょう。
3‐7. 例外の禁止
経費精算で担当者の権限による例外を認めてしまうと、規定が形骸化しかねません。規程が形骸化すると、業務が馴れ合いになってしまう可能性があります。
そのため、「原則領収書が必要だが、ない場合はこのように対応すること」というように、あらかじめ経費精算規程に明記されたケース以外の例外は認めない、などの旨を明記しておきましょう。
3‐8. 具体的なフォーマット
経費精算書の具体的なフォーマットを作成し、添付しておくとわかりやすいでしょう。
「簡単な内容だからわかるだろう」と思うかもしれませんが、理解力というのは人によって違います。特に、書類関係を扱わない部署や新入社員などは、何をどのように記入すればいいか迷ってしまうかもしれません。記入の際にミスや間違いがあれば、逆に差し戻し作業の手間がかかってしまいます。
フォーマットは簡単に作成できるので、手間を減らすためにも添付しておくことをおすすめします。
4. 科目別の注意点


経費精算は、科目によって注意点が異なります。
その中でも特に間違えやすい、もしくは認識が異なりやすいのが下記の項目です。
- 交通費
- 出張費
- 交際費
ここでは、この3つの科目の精算について、規定を作成する際に注意しておきたいポイントを解説します。
4-1. 交通費の注意点
交通費は、移動手段別に規定を定める必要があるでしょう。目的地まで複数の経路が存在する場合、水増し請求などの不正につながる可能性もあります。「原則として、最安値の経路を使用すること」など、規定で使用可能な経路を限定させることが重要です。
この科目は移動手段によって注意点が異なるため、確認しましょう。
電車・バス
電車やバスは領収書が発行されないため、不正受給を防ぐための厳密な規定が必要です。「最安値経路で移動する」「定期券の範囲内は支払わない」といった条件を設けるのがよいでしょう。従業員の負担を軽減するために「最安値経路と○分以上の時間差がある場合は合理的な経路の利用を認める」といった規定を設ける場合もあります。
タクシー
タクシーは費用が高額になりやすいです。また、電車やバスなどの公共交通機関でも移動できる可能性が高いでしょう。
そのため、「最寄り駅から○km以上離れており、バスが1時間に2本以下しかない場合」など、利用可能な条件を定義する必要があります。なお、取引先担当者を送迎した場合は、交通費ではなく交際費として処理しなければなりません。
新幹線、飛行機、船など
新幹線や飛行機、船などについても、料金が高額なため、利用できるシーンや座席のクラスについて規定しておく必要があります。
4-2. 出張費の注意点
出張費については、以下を定めておくのがおすすめです。
- 出張の定義(○km以上の移動が生じる、宿泊を伴うなど)
- 宿泊費の上限
- 日当の金額
- 食事代の金額や日当に含まれるか否か
- 出張時の仮払い規定
- 予期せぬトラブルによってやむなく出張が延長になった場合の対応方法
4-3. 交際費の注意点
交際費とは、取引先との会食などの科目です。
税法上、損金にできる金額が1人あたり5,000円までと定められているため、経費精算規定にも「交際費は1人あたり5,000円(税抜)まで」などと明記しておく必要があるでしょう。また、確かに交際費であることを明らかにするために「相手先」「相手先の人数」「参加者氏名」の記載が必要です。
6. 経費精算のルールを決めて不正やトラブルをなくそう


経費精算規程を作成し、ルールを明確にすることで、経費精算に関する不正やトラブルを防ぎましょう。経費精算の対応方法に迷うことがなくなれば、経理業務の効率化にもつながります。
経費精算規程があるにもかかわらずトラブルが起こる場合、規程に問題があるか、規程が周知されていない、あるいは守られていない可能性があるでしょう。この機会に、経費精算規程の内容や運用方法を見直してみてください。
法改正に完全対応!これ一冊で経理業務は完全理解!!
「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。
特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04