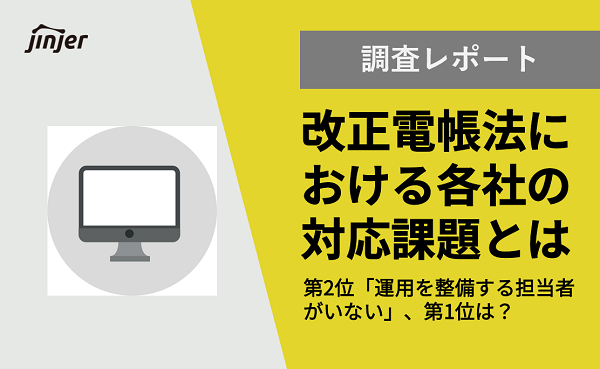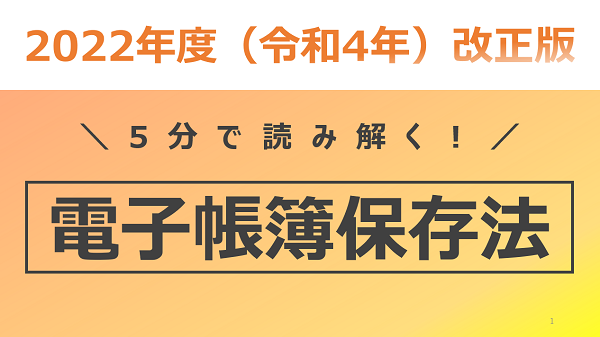電子帳簿保存法に猶予が設けられた理由は?改正内容や対応策を解説
更新日: 2024.3.5
公開日: 2022.4.10
jinjer Blog 編集部

電子帳簿保存法の改正により、各企業の経理担当の方は、様々な対応に追われていることと思います。
ただ、電子帳簿保存法の改正は一部内容に猶予期間が設けられて延期されたため、今すぐに対応しなければならないことと、猶予期間中に対応すればよいことに分かれています。
それぞれの改正内容について、延期になったのかどうかを把握しておくことで、対応の順番を適切に判断することができます。
業務負荷の増大を最小限に抑えることができるメリットもあります。
この記事では、電子帳簿保存法の改正内容や、電子帳簿保存法に猶予が設けられた理由、電子帳簿保存法への対応策について説明します。
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
1. 電子帳簿保存法の猶予期間とは

改正電子帳簿保存法によって電子取引に関する書類は紙での保存が原則禁止になりました。そのため、次のような要件を満たしたうえで電子データとして保存する必要があります。
真実性の要件
- ① タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
- ② 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過したのち速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
- ③ 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
- ④ 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う
可視性の要件
- 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備付け、画面・書面に整然とした形式及び、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
- 検索機能を確保すること
しかし、すべての企業が要件を満たしたうえでの電子データ保存に対応できるわけではありません。そのため、2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は、以下の2つの条件を満たしていれば、紙出力での保存も許可するというような猶予期間が設けられました。
- 所轄税務署長が、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができかなったことについて、やむを得ない事情があると認める
- 当該保存義務者が、当該電磁的記録の出力書面の提示、又は提示の求めに応じることができるようにしている
しかし猶予期間が延長されない可能性もあります。そのため、いつまでに対応すればいいのかを把握して、早めに改正電子帳簿保存法に対応しましょう。
1-1. 猶予期間が設けられた理由
電子取引の保存についての猶予期間が設けられた理由として考えられるのが、経費処理を紙でおこなっている企業の多さです。経費処理を紙でおこなっている企業は依然に多く、法改正に対応するためのシステム改修などが間に合わないという状況でした。そのため、2年間の猶予期間が設けられたと考えられます。
猶予についての許可や届出は不要です。しかし、猶予を受けるには相当の理由が必要です。猶予に値する相当の理由として考えられるのは次のようなケースです。
- 経済的な負担が多く電子データでの保存に対応できない:電子帳簿保存法に対応したシステムを導入する費用がない
- 人手不足により電子データでの保存に対応できない:人手が足らず電子帳簿保存法に対応できる従業員がいない
2. 電子帳簿保存法の改正内容

改正電子帳簿保存法によって改正された内容は、電子取引の電子データ保存義務化だけではありません。以下も改正点です。
- 国税関係帳簿・書類の要件緩和
- 罰則規定の強化
2-1. 国税関係帳簿・書類の要件緩和
国税関係帳簿・書類の要件緩和の内容は、大きく以下の5つに分類することができます。
- 事前承認制度の廃止
- システム要件の緩和と優良保存認定制度の新設
- 検索項目を「日付」「取引金額」「取引先」の3項目に限定
- 適正事務処理要件の廃止
- スキャナ保存のタイムスタンプ要件緩和
緩和や廃止となっている内容が多いので、事務処理の観点からは業務負担が軽減されることも多いでしょう。
2-2. 罰則規定の強化
上述したように事前承認制度が廃止される代わりに、万が一、税務処理上の不備が見受けられた場合のペナルティは強化されます。
隠ぺいや改ざんなどの悪質性があると認められた場合の申告漏れや過少申告に対しては、課される重加算税が10%加重されることになります。
電子取引においてもスキャナ保存と同じ罰則が設けられるため、注意が必要です。
2-3. 2024年1月から更に緩和される
令和5年度の税制大綱で発表された案をもとに、電子帳簿保存法が再度改正されて、更なる要件緩和が決まっています。2024年1月から適用されるため、確認しておきましょう。
主な変更内容は以下のとおりです。
| 電子帳簿保存要件 | 「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲を限定 |
| スキャナ保存要件 |
解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になる ※解像度や階調などの規定は変更していないため注意 |
| 入力者等情報の確認要件が不要になる | |
| 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定 | |
| 電子取引データ保存要件 | 検索機能が不要となる対象者を拡大 |
| 宥恕措置の終了と猶予措置の整備 |
現在の猶予期間(宥恕措置)の終了が確定しているため、注意しましょう。
3. 猶予期間にすべき電子帳簿保存法への対応策

改正電子帳簿保存法に対応するためには、データの電子保存に対して全社的にどのような姿勢で臨むかということを、まず決めておく必要があります。電子取引における書類の電子データでの保存義務は2年の猶予が設けられていますが、今後も未対応が認められるわけではありません。あくまで猶予期間のため、その間に次のような対応を取りましょう。
- 自社の状況を把握する
- データを保存する方法を決める
- データの保存場所を決める
- 業務フローを確立する
3-1. 自社の状況を把握する
自社で電子取引による書類をどのように取り扱っているのか、状況を把握しましょう。その際は次のような情報を整理します。
- 電子取引している書類はなにか
- どのような方法で書類を受領しているか
- 書類をどこに保存しているのか
- 月に受け取っている件数は何件か
電子取引されている書類は企業によってさまざまです。請求書や領収書だけでなく、納品書や見積書なども受領している企業もあるでしょう。しかし、すべての書類を、いきなり電子データでの保存に切り替えるのは困難と予想されます。そのため、請求書や領収書といった経理業務に大きくかかわる書類から対応してくのがおすすめです。
3-2. データを保存する方法を決める
電子取引による書類を電子データとして保存するには、保存方法を決める必要があります。電子取引による書類を電子データとして保存するには次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 1. タイムスタンプが付与された書類を受領する
- 2. タイムスタンプを付与する
- 3. 訂正削除の記録が残るもしくは訂正削除ができないシステムを導入する
- 4. 訂正削除防止についての事務処理規程を備え付ける
1、2はタイムスタンプの導入費用が、3は専用システムの導入費用がかかります。コストを理由に電子取引によるで書類の電子データ保存に対応できないのであれば4を採用しましょう。4であれば導入費用は不要です。しかし、事務処理の規定を設けるためには従業員が電子帳簿保存法への理解を深める必要があります。
3-3. データの保存場所を決める
電子データの保存方法を決めたら、次にどこにデータを保存するかを決めましょう。データの保存先としてクラウドシステムや自社サーバーが挙げられます。クラウドシステムや自社サーバーに保存する際は、検索要件を満たす必要があります。電子データは取引年月日、取引金額、取引先という3つの条件で検索できるようにしておきましょう。
なお、検索要件を満たすには専用のシステムを導入する以外にも、ファイル名に規則性をもたせる、Excelで索引簿を作成するといった対応でも認められます。システム導入費用がネックであれば、自社で対応することも検討してみましょう。
3-4. 業務フローを確立する
電子データをプリントアウトして経理作業をしていた企業の場合、データで処理をする際の業務フローを確立する必要があります。この際、どのようにしてデータを上長や経理担当者が確認するかという点を解消しなければなりません。例えばメールで経理担当者にデータを送付するような業務フローにする、システム上でデータを経理担当者に共有できる業務フローにするなどが考えられます。
どのような業務フローで進めていくか、経理担当者だけでなく関連する部署の上長らと協議したうえで決定しましょう。
4. 2年間の猶予期間にしっかりと対応しておくことが重要

最近ではオンラインで取引を行うケースも増えていることから、電子帳簿保存法の改正は、ほぼすべての企業に影響があると言っても過言ではありません。
ただ、法改正に関する認知度があまり高くなかったことも相まって、2022年1月1日までに改正電子帳簿保存法に対応できるだけの対策をおこなえていない企業も多いことでしょう。
現在設けられている猶予期間(宥恕措置)の間に、対策を考えて社内で対応していくことが求められます。
電子取引に限らず、それぞれの対応方針を決めておかなければ、その後の対応も曖昧になってしまうでしょう。まずは全社的な方針を明らかにすることが重要です。
猶予期間も残りわずか!
改正版電子帳簿保存法のその対応方法を徹底解説!
「そもそも電子帳簿保存法に関して基礎から理解したい」
「22年度の改正内容について知りたい」
「猶予期間内に具体的にどう電子帳簿保存法に対応すれば良いかわからない」
など電子帳簿保存法に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「5分で読み解く!電子帳簿保存法」という資料を無料配布しております。電子帳簿保存法の基礎知識から2022年の改正内容、またその対応方法まで網羅的に解説しております。義務化される猶予期間中に正確に電子帳簿保存法に対応したい方には大変参考になる内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04