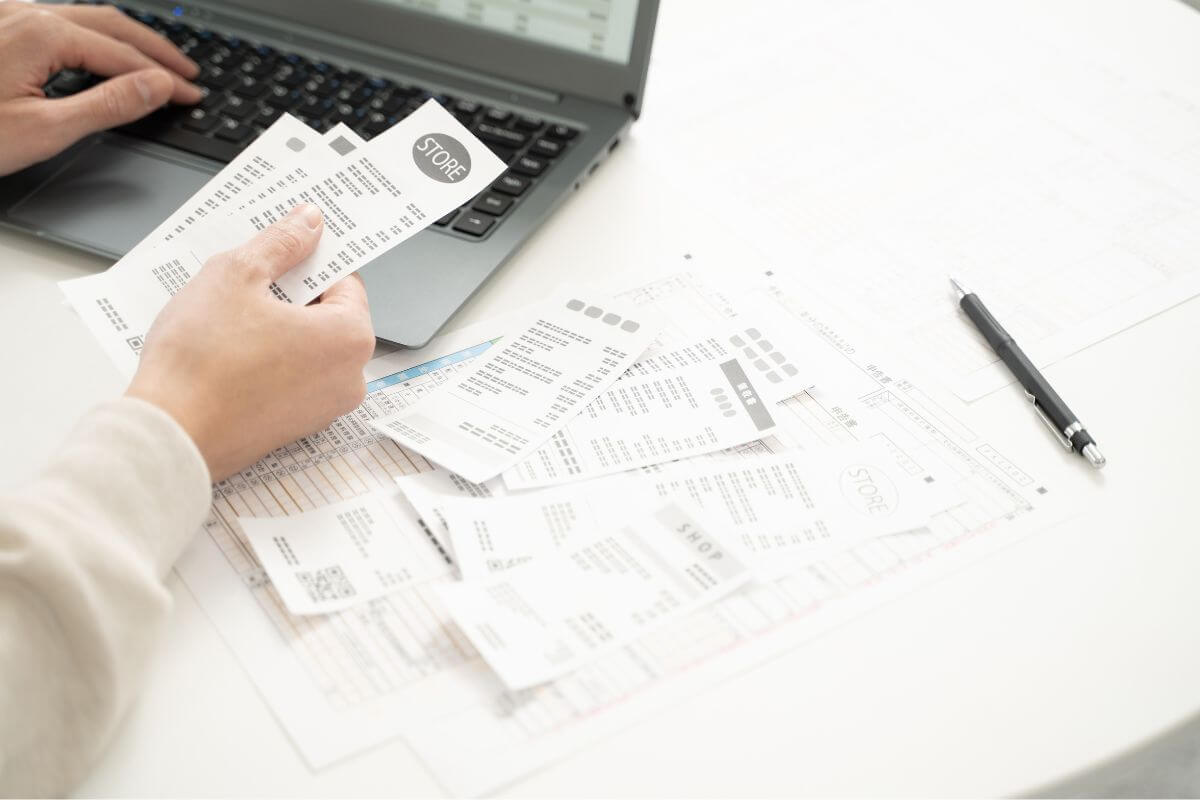納品書の保管期間は7年?10年?期限や保管方法について徹底解説
更新日: 2024.10.10
公開日: 2022.4.13
MEGURO
納品書は商品やサービスを提供した際に発行されます。領収書のように経理上の処理の際に必ずしも必要とするものではないため、それほど重要ではないと思われるかもしれません。
しかし、納品書は一定期間保管することが法律により定められています。そこで今回はそんな納品書の保管期間や保存方法などについて詳しく解説します。
目次
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無についてなどなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてぜひご覧ください。
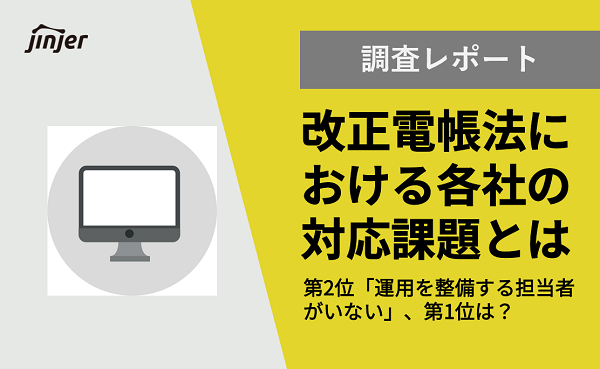
1. 納品書とは?発行目的と必要性を解説

納品書の保管期間について解説する前に、まずは納品書がどういった意味を持つ書類であるのかをおさらいしておきましょう。
1-1. 納品書とは、正しく納品されていることを確認するためのもの
納品書は、取引先との間で商品やサービスのやりとりがあった際に、受注側から発注側へと発行される書類のことを指します。納品書には以下の内容が記載されていることが一般的です。
- 注文者(または会社)の名前
- 納品書発行元の名前
- 発行年月日
- 商品(サービス)名ごとの数量や料金、税額など
- 合計金額
受注側は商品やサービスが納品された際、納品書を見ることで発注した商品やサービスがきちんと納品されているかどうか確認ができます。
1-2. 法的には「納品書発行」の義務はない
納品書には「必ず発行しなければならない」という法的なルールはなく、実際に納品書を発行せずに取引をしているというケースも少なくありません。
しかし、納品書は法務の観点から見ると契約上の義務を履行した事実の証拠となったり、代金が未回収となった場合のトラブル解決に役立てることができるものです。
また、経理の観点でも納品書は売上や仕入、経費の根拠資料としても利用できます。
2. 納品書の保管期限

先ほどもお伝えしたとおり、納品書は必ず発行しなければならないものではありません。しかし、発行された納品書は、領収書や請求書と同様に取引の証拠となる証憑書類にあたるため、法律により一定期間の保管が義務付けられているのです。
では、ここからは納品書の保管期限について詳しく解説していきます。
2-1. 税法による保管期限は7年
まず、税法による保管期間についてです。
法人税法施行規則では、納品書は7年間の保管が必要と定められています。これは納品書に関わらず、帳簿書類、つまり見積書や契約書、注文書、送り状、領収書なども同様です。
そして、保管期限の「7年」というのはいつからの期間を指すのかについてですが、これは納品書の発行日から7年ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限日の翌日から7年間です。
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば決算日が3月31日の会社の場合、2021年の12月に発行され、受け取った納品書があるとします。
法人税の申告期限は原則として決算日の2ヶ月後ですので、確定申告の提出期限は2022年の5月31日ということになります。そして、この翌日からカウントして7年間ですので、納品書の保管期限は2028年の5月31日までということになります。
ここでのポイントは確定申告の提出期限日です。この会社の場合、2021年4月から2022年3月31日の間に受け取った納品書については、全て2028年の5月31日まで保管する必要があるのです。
なお、法人で赤字部分を翌年の利益から控除することのできる「欠損金の繰越控除」を適用する場合においては、保管期限は10年となります。
期限が経過した納品書については破棄しても何ら問題はありません。しかし、万が一保管期限内に破棄してしまい、さらにその事実が税務調査等で発覚した場合、経費として計上していた費用が認められなくなる可能性があります。
そして、その場合は税金を追加で支払うことにもなりかねないため、取扱いには注意が必要です。
2-2. 会社法による保管期限は10年
次は、会社法による保管期間についてです。会社法では、貸借対照表や損益計算書などの計算書類は、作成をして10年間は保管するように義務付けられています。
なお、この場合も法人税法の場合と同様、保管期間は納品書の発行日ではなく、決算の締め日の翌日からの10年間となっています。
2-3. 個人事業主の場合は5年
先にご紹介した法人税法や会社法は法人の場合にのみ適用されるため、当然ながら個人事業主に対しては適用されません。個人事業主の場合は所得税法が適用され、納品書については5年間の保管が必要となります。
なお、所得税法第六十三条では保管される書類について「現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のもの」と書かれています。
2-4. なぜ税法と会社法で保管期間が異なるのか
先述のとおり、納品書の保管期間は税法と会社法で異なります。この期間の違いは、それぞれの法律の目的が異なるためです。
税法は「納税の義務」を果たすための法律で、納税額の計算ミスや脱税などによる請求権の時効を迎える7年間の保管が必要となっています。
対して会社法は「会社経営をより柔軟かつ機動力を高める」ための法律です。安定して会社経営をおこなうためにも、契約上のトラブルにおける時効を考慮しなければなりません。そのため、会社法では、契約上のトラブルが発生した場合の時効が一番長い10年間を保存期間として定めているのです。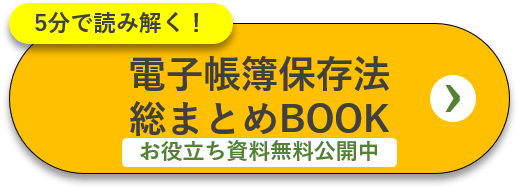
3. 納品書の保管方法は電子帳簿保存法で定められている

ここまで納品書の保管期間について解説してきましたが、ここからは納品書の保管方法について解説していきましょう。
納品書の保管方法については、納品書の送付や受領の方法によって異なるため、注意しましょう。
ここでは、電子帳簿保存法によって定められている保管方法について解説します。
3-1. 紙媒体で送付・受領した場合の保管方法
納品書を紙媒体で送付または受領した場合、紙媒体のまま保管するほか、PDFなどの電子データにして保管することも可能です。
紙による保管は手間やコストがかかるうえ、経年劣化する可能性があるなどのデメリットがあります。そのため、近年は次にご紹介する電子データによる保管を選ぶ企業が増えています。
ただし、電子帳簿保存法による「スキャナ保存」の要件を満たす必要があるため、注意しましょう。
3-2. 電子データで送付・受領した場合の保管方法
電子データで送付・受領した場合、電子帳簿保存法により、電子データのまま保管することが義務付けられています。
そのため、プリントアウトして紙媒体で保管することは認められません。
また、このとき「電子取引データ保存要件」を満たす必要があるため、注意が必要です。
要件について詳しく確認したい方は下記の記事をご確認ください。
ここで紹介している電子取引データ保存要件は電子帳簿保存法で定義されていますが、そもそも電子帳簿保存法がどんな法律なのか、またどのように会社で対応すれば良いかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「5分でわかる電子帳簿保存法」という資料を無料配布しております。本資料では電子帳簿保存法に関する概要から、対応方法、また具体的な改正内容などをわかりやすく解説しています。そのため電子帳簿保存法の基礎知識を得られるのはもちろん、会社としてどのような対応をすればよいかも理解することができます。大変参考になる資料となっておりますので、興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説
4. 納品書を電子化するメリット・デメリット

納品書を電子化することによるメリットとしては、まずファイリングの手間や、仕入れ管理システムへの入力が省けることが挙げられるでしょう。また、必要なデータを素早く検索できるようにもなります。
さらに、納品書を多く取り扱う会社の場合、ファイルを保管しておく場所を大幅に削減し、紛失の防止にもなるでしょう。
納品書を電子化することによるデメリットとしては、紙での保管の場合とは異なるセキュリティ対策が必要になることです。電子データ化は省スペースになりますが、例えばUSBメモリーなどに大量のデータを保管していた場合は、膨大な量のデータを簡単に持ち出されてしまう恐れがあります。
また、場合によってはサイバー攻撃を受ける可能性もあります。
5. 納品書の保管期間は7年!電子データで快適に

納品書は必ずしも発行しなければならないわけではないものの、発行されたものについては最低でも7年間という長い期間保管する必要があります。
納品書の保管は原則として紙での保管になりますが、大量の納品書を保管しなければならない場合は電子データによる保管がおすすめです。セキュリティ対策を万全にし、コストや手間を削減する快適な保管方法を実現しましょう。
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正内容と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
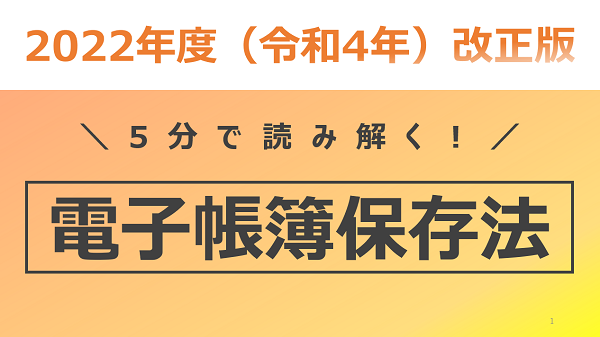
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
領収書の関連記事
-

領収書の役割とは?いつ使うもの?意味や定義、書き方を解説!
経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07
-

領収書の作成でおさえておくべきポイントは?必要なものや項目を解説
経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07
-

領収書はPDFでも有効?PDFでの発行方法やメリット、原本の保存について解説
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.10.07