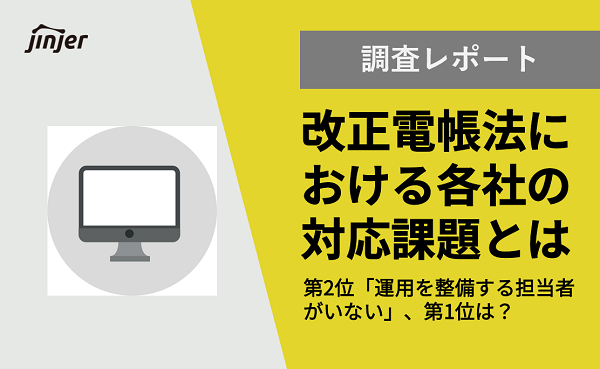【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説
更新日: 2024.5.29
公開日: 2020.11.9
jinjer Blog 編集部

電子帳簿保存法により、電子契約書の取り交わしをおこなった場合は、電子データでの保存が義務付けられています。データを適切に管理しなければ、法律違反になってしまうでしょう。保存要件を正しく理解しなければなりません。
そこで今回は、帳簿保存法についての概要と改正内容、申請方法までわかりやすく解説します。
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
目次
1. 電子帳簿保存法の概要
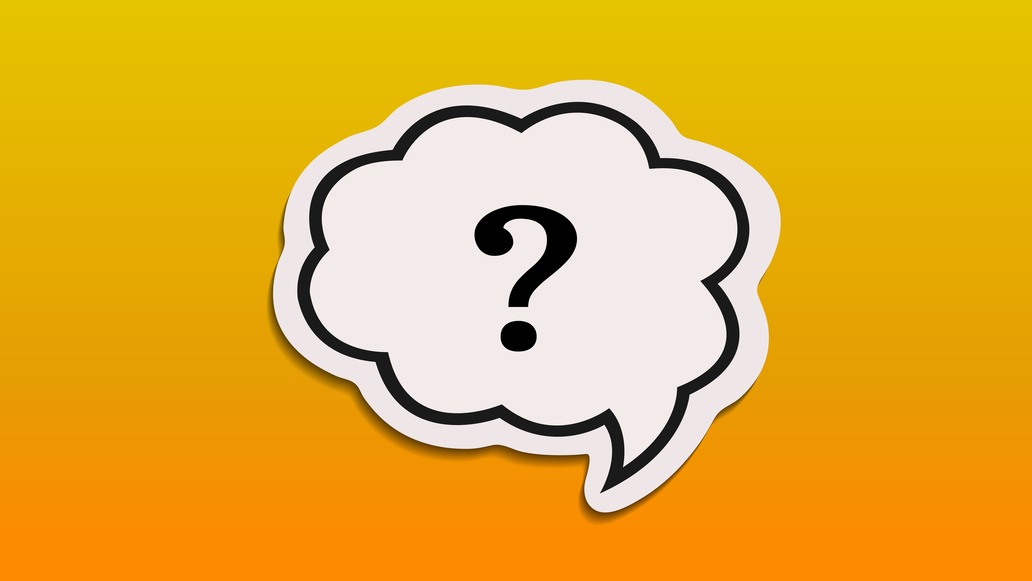
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿・書類を一定の条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。本法律は、パソコンがビジネス・日常ともに普及した1998年に制定されたのち、技術革新や業務負荷の軽減を目的に改定されてきました。
電子帳簿保存法では、以下の3つの要件を定めています。
- スキャナ保存要件(書面で交付・受領した書類を電子保存するための要件)
- 電子取引データ保存要件(電子データで交付・受領した書類の保存要件)
- 電子帳簿保存要件(電子データで国税関係帳簿の作成・保管の要件)
電子保存する書類の種類や発行方法によって要件が異なるため、注意しましょう。
2. 電子帳簿保存法の対象となる書類

電子帳簿保存法は、前述のとおり国税関係帳簿・書類を電子データで作成・管理する要件をまとめています。本法律の対象外の書類は、別法で定められた規定に従う必要があるため注意しましょう。
電子帳簿保存法の対象となる書類は以下のとおりです。
| 受領方法 | 分類 | 対象書類 | |
| 電子データで作成・受領した場合 | 書面で作成・受領した場合 | ||
| 電子保存できる | スキャナ保存できない | 帳簿 | 仕訳帳、売上・仕入帳、経費帳、現金出納帳、買掛帳、売掛帳、総勘定元帳、固定資産台帳など |
| 決算書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表、他決算に関する書類 | ||
| 電子データ保存しなければならない | 電子保存できる | 重要書類に分類される証憑類 | モノやお金の流れに直結する書類
例)納品書、領収書、請求書、契約書、契約の申込書など |
| 一般書類に分類される証憑類 | モノやお金の流れに直結しない書類
例)注文書、見積書、検収書など |
||
電子帳簿保存法は、書面で作成・受領した書類は書面での保存も認めていますが、電子データで作成・受領した書類を書面で保存することは認めていません。
また、書面で作成した帳簿類や決算書類を電子データにすることもできないため、注意しましょう。帳簿類や決算書類を電子保存するためには、一貫して電子データで作成する必要があります。
3. 電子帳簿保存法に対応するための保存要件
 先述したとおり、電子帳簿保存法の要件は、対象書類の種類や作成・受領方法により「スキャナ保存要件」「電子取引データ保存要件」「電子帳簿保存要件」の3つに分けられています。本章では、それぞれの要件についてくわしく解説します。
先述したとおり、電子帳簿保存法の要件は、対象書類の種類や作成・受領方法により「スキャナ保存要件」「電子取引データ保存要件」「電子帳簿保存要件」の3つに分けられています。本章では、それぞれの要件についてくわしく解説します。
3-1. スキャナ保存要件
スキャナ保存要件は、書面でやり取りした書類を電子データで保存するための保存要件を取りまとめたものです。受領した書類はもちろん、自社で発行した書類も要件を満たすことで電子保存に切り替えることができます。
スキャナ保存要件は以下のとおりです。
| 保存要件 | |
| 真実性の確保 | 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け |
| 解像度と階調の下限制限 | 見読可能性の確保 |
| 大きさ、解像度、階調情報の保存 | 帳簿との相互関連性の確保 |
| 検索機能の確保 | 税務署長の承認[※1] |
[※1]2022年1月1日以前に締結した契約書類を電子化する場合
真実性の確保
真実性の確保とは、「保存された電子データが改ざんされていないこと」を証明することを指します。具体的には、以下の要件を守る必要があるので、確認しましょう。
| 保存要件 | 詳細 |
| 入力期間の制限 | 早期入力方式:おおむね7営業日以内 業務サイクル方式:最長2か月と7営業日以内※各社の事務処理規程の定める期間によって異なる |
| タイムスタンプの付与 | 書類をスキャナ保存したときに、タイムスタンプを付与する
※入力期間の制限と業務規程の整備を守っている場合は不要 |
| 業務規程の整備 | 下記のいずれかを満たす
訂正または削除の事実と内容の確認がおこなえるシステムを利用 訂正または削除自体がおこなえないシステムの利用 書類の受領から入力までの事務処理規程を定めて、規程に則った運用をおこなう |
| 入力者等情報の確認 | スキャナ保存実行者や、その監督者情報の記録 |
※2024年1月より、入力者情報の確認は不要となります。
解像度と階調の下限制限
契約書類をスキャナ保存するにあたり、解像度と階調にも決まりがあります。スキャナ機器や設定によっては基準に満たない場合があるため、注意しましょう。
ただし、「見積書」や「注文書」など一部の書類はグレースケールでの保存も認められています。
大きさ、解像度、階調情報の保存
解像度や階調に関しては、下限制限を守るだけでなく、データと合わせて情報を保存しておく必要があります。大きさに関しても同様なので、注意しましょう。
※2024年1月より、大きさや解像度、階調に関する情報の保存は不要となります。
検索機能の確保
電子帳簿保存法に対応するにあたって、ファイルに検索機能を持たせることも義務付けられています。取引年月日や金額、取引先名などの条件を複数組み合わせて範囲検索できなければなりません。
ただし、税務職員からの求めに応じてデータをダウンロードできる場合は、要件が緩和されます。その反面、1つでも求めに応じられない場合は、電磁的記録による保存(スキャナ保存)が認められません。データの不備には注意しましょう。
| 保存要件 | 詳細 |
| 「取引年月日」、「その他の日付」、「取引金額」及び「取引先」を検索条件として設定できること | 必須条件 |
| 日付又は金額に係る記録項目について、その範囲を指定して検索できること | 税務職員の求めに応じて、保存データをダウンロードできる場合は不要 |
| 2種類以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること |
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け
電子帳簿保存に対応するにあたって、管理システムなどを用いることもあるでしょう。税務調査などで税務職員が初めて使用するシステムに戸惑うことがないよう、「システムの概要を説明する書類」と「操作マニュアル」を用意しておく必要があります。
これらの用意も電子帳簿保存法で義務付けられているため、必ず対応しましょう。
見読可能性の確保
見読可能性の確保とは「必要に応じて内容を確認できること」を証明することを指します。調査員などの求めに応じて、速やかにモニタへの出力やプリンターでの印刷をおこなえる必要があります。
「全てのモニタを業務で使用しているため、すぐに出力できない」「パソコンとプリンターが接続されておらず、手間取ってしまう」など、速やかに提示できない場合は違反と見なされるおそれがあるため注意しましょう。
帳簿との相互関連性の確保
スキャナ保存した国税関係書類は、その書類に関連する国税関係帳簿の記録との関連性が確認できるようにしておく必要があります。
税務署長の承認
電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日以降に作成・受領した書類や一般書類は、税務署長の承認がなくともスキャナ保存することが可能です。
しかし、法改正前に作成・受領した重要書類をスキャナ保存する場合や、改正前の要件でスキャナ保存していた企業は、事前に税務署長の承認を得る必要があるため、注意しましょう。
| 承認が必要となる条件 | 詳細 |
| タイムスタンプの付与 | 入力期間の制限(最長2ヶ月と7日以内) |
| 業務規程の整備 | 訂正、または削除の事実と内容の確認 |
参照:はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)|国税庁
関連記事:改正電子帳簿保存法における事前申請が不要になるのはいつから?改正点や保存要件も解説
3-2. 電子取引データ保存要件
電子取引データとは、Web上で送付・受領した書類を指します。受発注は書面で受け付けた場合も、領収書や請求書は電子データで発行している場合は電子取引データとして、保存しなければなりません。
2023年現在は宥恕措置がとられているため、印刷して書面で保存することも認められています。ですが、2024年1月1日からは保存要件に従って保管する必要があるため、注意しましょう。
電子取引データの保存要件は以下のとおりです。
| 承認が必要となる条件 |
| システムの操作説明書や手順書の用意 |
| 見読可能装置の備付け |
| 検索機能の確保 |
システムの操作説明書や手順書の用意
スキャナ保存要件と同様に、電子取引においても、説明書や手順書の用意が義務付けられています。自社開発システムではない場合は、ベンダーから受け取れるでしょう。書面に印刷する必要はありませんが、すぐにマニュアルを確認できるようにしておく必要があります。
見読可能装置の備付け
電子取引においても、見読可能性の確保が必要となっています。具体的には、電子取引の書類を速やかにモニタへ出力や、プリンターでの印刷ができるようにしておかなければなりません。
検索機能の確保
電子帳簿保存法に対応するにあたって、電子取引もファイルに検索機能を持たせることも義務付けられています。取引年月日や金額、取引先名などの条件を複数組み合わせて範囲検索できなければなりません。
ただし、2期前の売上高が1,000万円以下の企業に関しては、調査員の求めに応じて電子データをダウンロードできる場合のみ、検索機能の確保は不要となっています。
とはいえ、一定の検索機能を設けなければ、書類の管理ができなくなるため、ファイル名やフォルダの管理は必要と言えるでしょう。
データの真実性を担保する措置
電子データの真実性を担保するために、不正を防止する仕組みが必須です。以下のいずれかを満たせば良いとされているので、確認しましょう。
- 受領者・発行者いずれかのタイムスタンプ付与
- データ訂正や削除の履歴が残る、又は訂正削除ができないシステムの利用
- 不正な訂正や削除を防止する事務処理規程
参照:電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)|国税庁
タイムスタンプについて詳しく知りたい方は下記の記事もあわせてご確認ください。
参考記事:電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?費用や導入手順をくわしく解説
3-3. 電子帳簿保存要件
コンピュータを使用して作成する帳簿は電子保存が認められています。ただし、一部でも手書きの記録がある場合は、電子保存が認められないため、注意しましょう。
e-Taxでの申請または優良な電子帳簿の保存の場合は最大65万円の控除を受けられる場合があります。事前の申請・承認やより多くの要件を満たす必要があるなど、簡単ではありませんが、認められた場合の利益は大きいでしょう。
電子帳簿保存の保存要件は以下のとおりです。
| 承認が必要となる条件 | 詳細 |
| 見読可能装置の備付け | – |
| システムの操作説明書や手順書の用意 | – |
| 税務職員の求めに応じて、保存データをダウンロードできる | 以下の要件を全て満たす場合は不要
|
さらに、優良な電子帳簿と認められるためには、先述した「電子帳簿の保存要件」に加えて以下の要件も満たす必要があります。
| 承認が必要となる条件 | 詳細 |
| 記録の訂正・削除をおこなった場合、履歴と変更内容が記録されるシステムを使用する | – |
| 通常の処理期間を経過した後で入力した場合、その事実が確認できるシステムを使用する | – |
| 電子化した帳簿と、関連する他の帳簿との関連性を相互に確認できる | – |
| 「取引年月日」、「その他の日付」、「取引金額」及び「取引先」を検索条件として設定できる | – |
| 日付又は金額に係る記録項目について、その範囲を指定して検索できること | 税務職員の求めに応じて、保存データをダウンロードできる場合は不要 |
| 2種類以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること |
4. 2024年1月以降の変更点

2022年12月16日に発表された「令和5年度 税制改正大綱」に基づき、電子帳簿保存法の要件が緩和される予定です。
本章では、税制改正大綱の概要と電子帳簿保存法の変更点について解説します。
4-1. 税制改正大綱とは?
税制改正大綱とは、「制定するべき法律や改正するべき法案」について与党がまとめた草案のことです。毎年12月に税制改正大綱が発表されたのち、国会に提出されます。国会で可決された場合、法改正がなされるのです。今後に備えるためにも、変更案を押さえておく必要があるでしょう。
4-2. スキャナ保存要件の変更点
スキャナ保存要件の変更点は以下のとおりです。
- 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になる
- 入力者情報の確認が不要になる
- 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が限定される
それぞれ詳しく解説します。
解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になる
現在のスキャナ保存要件では、保存データに解像度や階調、大きさに関する情報が保存されている必要があります。
今回の税制改正大綱では、解像度や階調の下限制限はあるものの、保存データに記録する必要がなくなりました。
入力者情報の確認が不要になる
現時点では「スキャナ保存の実行者」や実行者の上司などの「直接管理者」いずれかを入力者情報として記録しなければなりません。
今回の変更点で、この入力者情報の確認も不要となる見込みです。
帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が限定される
スキャナ保存をおこなう場合、帳簿との相互関連性を持たせることが義務付けられています。
2022年時点の法律では、スキャナ保存する全ての国税関係書類が対象でしたが、今回の税制改正大綱で、「重要書類」のみに限定されると発表されました。これにより、検収書や注文書などの一般書類は紐づける必要がなくなります。
請求書や領収書などの重要書類は、引き続き帳簿と相互関連性を持たせる必要があるため、注意しましょう。
4-3. 電子取引データ保存要件の変更点
電子取引データの保存要件の変更も発表されています。変更点は以下のとおりです。
- 検索機能の用意が不要となる対象者の拡大
- 宥恕措置の廃止
- 猶予措置の整備
各項目について詳しく解説します。
検索機能の用意が不要となる対象者の拡大
電子取引データの保存要件の一つに「検索機能の確保」があります。
電子帳簿保存法に対応するにあたって、電子取引もファイルに検索機能を持たせることも義務付けられています。
今回の変更で、2年前の売上高が「1,000万円以下の事業者」から「5,000万円以下の事業者」に対象範囲が拡大されました。
宥恕措置の廃止
2023年12月31日で、宥恕措置の廃止されます。
2020年の法改正から、電子データで作成・受領した書類は電子データで保管することが義務付けられています。ただし、運用フローの見直しやシステムの入れ替えなどの対応が間に合わない企業が多くありました。そのため、令和4年度の税制改正の「宥恕措置」で、期間限定の書面保存も認めていたのです。今回の税制改正で宥恕措置が廃止されるため、電子データで作成・受領した書類は電子データで保管しなければなりません。
猶予措置の整備
前述の宥恕措置に代わり「猶予措置」が整備されました。これにより、以下の要件を満たす場合のみ電子データの保存要件を満たしていなくとも電子保存できるようになります。
電子データ保存の要件を満たせない相当の理由があることを所轄税務署の税務署長が認める場合
税務調査等で、電子データの「ダウンロードの求め」及び「電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出」に応じることができる場合
ただし、「相当の理由」の詳細については公表されていません。認められない可能性があるため、宥恕措置の間に電子取引データの保存要件を満たして管理できる環境を整えていく必要があるでしょう。
4-4. 電子帳簿保存要件の変更点
電子帳簿の保存要件においては、「過少申告加算税の軽減措置」の対象範囲について言及されています。
過少申告加算税は、確定申告で実際の納税額よりも少なく申告してしまった場合に科せられる税です。納税額に間違いがあった場合、最大で差額の15%の加算税が科せられますが、「優良な電子帳簿」として作成していた場合は加算税の軽減措置を受けることができます。
2022年時点では、軽減措置を受けるためには「青色申告」に必要な帳簿全てを電子化させる必要がありました。今回の税制改正大綱によって、電子化させる帳簿の範囲が限定されます。
変更内容は以下のとおりです。
| 税制改正大綱による変更前 |
|
| 税制改正大綱による変更後 |
|
関連記事:過少申告加算税とは?計算方法や過少申告加算税が課されないケースも解説
参照:電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~(令和5年4月)|国税庁
5. e-文書法と電子帳簿保存法の違い
 e-文書法と電子帳簿保存法の大きな違いの1つとして、電子化に当たり承認が必要かどうかがあります。電子帳簿保存法に則って国税関係書類を電子化する場合は、税務署長の申請して承認を受ける必要がありますが、e-文書法の場合は承認が必要ありません。
e-文書法と電子帳簿保存法の大きな違いの1つとして、電子化に当たり承認が必要かどうかがあります。電子帳簿保存法に則って国税関係書類を電子化する場合は、税務署長の申請して承認を受ける必要がありますが、e-文書法の場合は承認が必要ありません。
関連記事:電子帳簿保存法とe-文書法って何が違うの?スキャナ保存できる書類は?疑問を解決
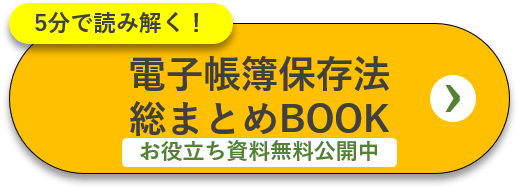
6. 電子帳簿保存法に違反してしまった場合の罰則は?
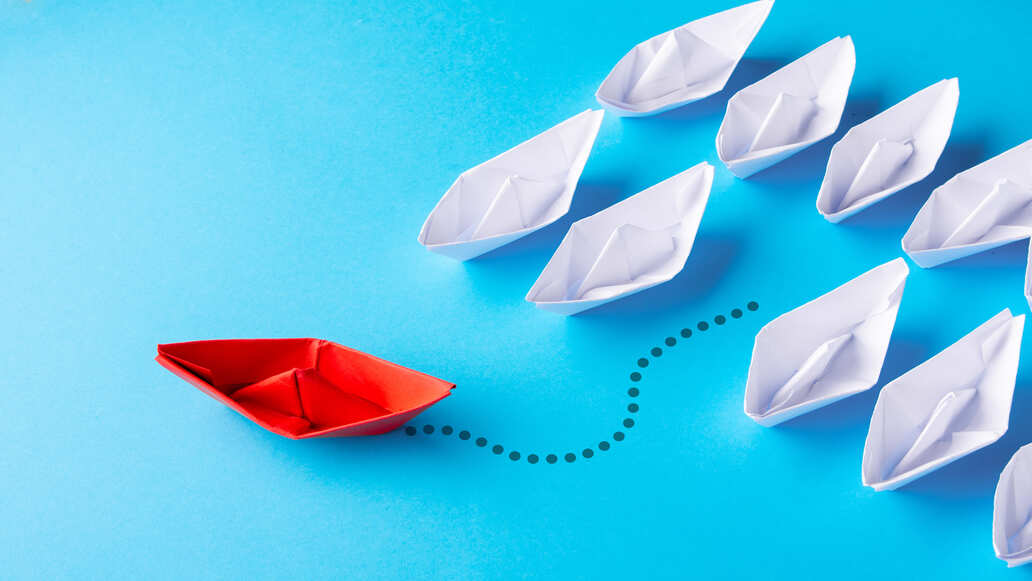
電子帳簿保存法に違反した場合、罰則を課される可能性があります。具体的にどのような罰則があるのかを解説します。
6-1. 青色申告の承認を取り消される
青色申告は、最大65万円の特別控除をはじめとしたさまざまな税金に関する特例が適用されることが特徴です。
この青色申告の承認が取り消されてしまうと、これらの特例が受けられないだけでなく、欠損金の繰越しもできなくなります。
同時に、青色申告の承認が解除されたという事実が、会社としての信用を著しく損なってしまうことにも注意が必要です。
6-2. 追徴課税や推計課税を課される
青色申告の承認が取り消されると白色申告者となってしまいますが、白色申告では、青色申告に適用されていた特例がないだけでなく、「推計課税」が課されます。
「推計課税」とは、税務署が推計して所得税や法人税の額を決定し課税をおこなうことです。
推計であるため、いわば税務署の言い値で税額が決められてしまうことになり、会社としては痛い出費となるでしょう。
また、書類のデータ化や保存をきちんと行っていないということは、それ以外の国税関係帳簿書類も定められた方法で保管していないとみなされる可能性があります。
そこから、各税法の違反が疑われたり、違反しているとみなされたりすれば、さらに厳しい追及を受け、追徴課税を納めなければならない結果になる恐れもあります。
6-3. 会社法により過料が科せられる場合もある
会社が電子帳簿保存法以外にも遵守すべき法律として、会社法があります。
会社法第976条には帳簿や書類の記録・保存についての規定があり、ここに規定されている保存義務に違反したり、虚偽の記帳を行ったりした場合は、100万円以下の過料が科せられます。
そのため、帳簿や書類の保存に関しては、電子帳簿保存法だけでなく、会社法についてもきちんと確認しておきましょう。
関連記事:電子帳簿保存法って違反したら罰則はあるの?リスクと要件を解説
関連記事:65万円の青色申告特別控除を受けるには電子帳簿保存法が必須な理由
7. 経費精算システムを活用して業務を楽にしよう

電子帳簿保存法の緩和によって、今までよりもさらに書類の電子化のハードルが下がりました。
今後は電子化がより実務に活用できるようになるでしょう。
システム導入や電子帳簿保存法への対応は時間がかかりますので、早めに調べておくことをおすすめします。
関連記事:電子帳簿保存法で経費精算は楽になる?その方法や注意点を解説
関連記事:電子帳簿保存法のメリットを簡単に理解したい!基礎知識やデメリットもわかりやすく解説
関連記事:電子帳簿保存法のここが知りたい!領収書に署名が必要な理由2つ
2020年、2022年の電子帳簿保存法改正を
わかりやすく総まとめ!
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月改正と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
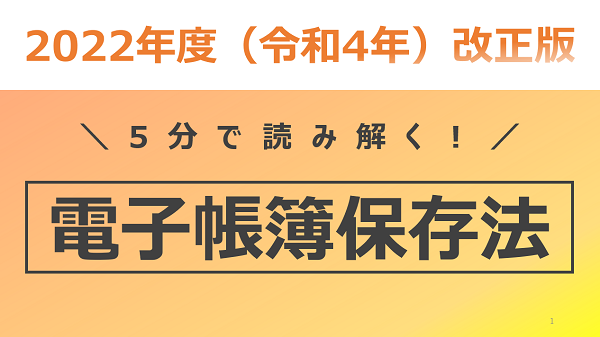
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04