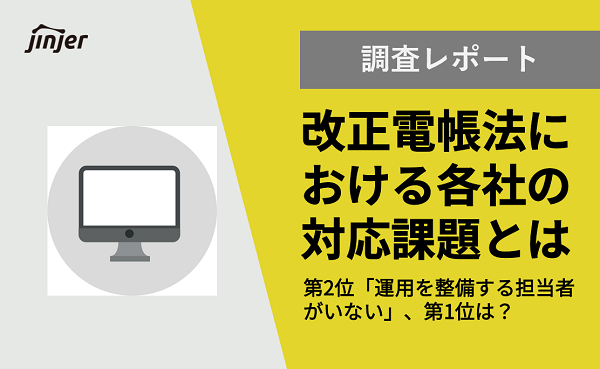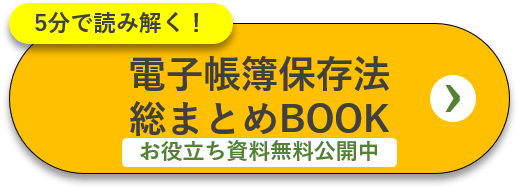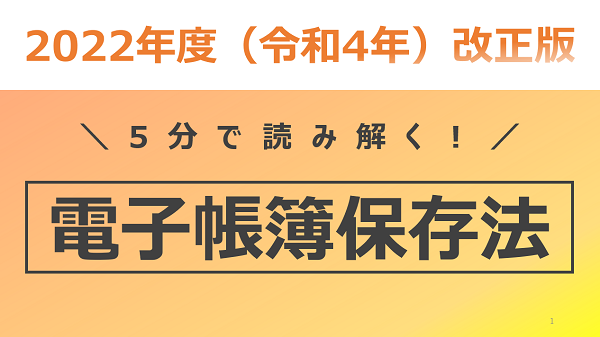電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?費用や導入手順をくわしく解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2020.11.9
jinjer Blog 編集部
電子データで領収書などの保存をする場合、必ずタイムスタンプが必要になります。そして、電子データにタイムスタンプを付与してもらうには、一定の費用がかかります。
この記事では、費用の目安やタイムスタンプの導入方法等を分かりやすくまとめています。電子帳簿保存法の理解も深まりますので、是非、最後まで読んでみてください。
▼そもそもタイムスタンプについて知りたい方はこちら
電子帳簿保存法のタイムスタンプって何?最新の要件や改正内容を解説
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
目次
1. 電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割

電子帳簿保存法は国税関係帳簿・書類を、一定の要件を満たせば電子保存することを認める法律です。電子帳簿保存法の保存要件の一つに「タイムスタンプの付与」があります。この「タイムスタンプ」とはなんでしょうか。
本章では、タイムスタンプについて詳しく解説します。
1-1. タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、電子データの存在と改ざんされていないことを証明するしくみです。
その名のとおり、電子データの書類にスタンプを押した日時と「ハッシュ値」と呼ばれる文字列を付与しています。このハッシュ値はデータの書き換えをおこなうと、文字列(ハッシュ値)も変更されるため、「タイムスタンプを付与した後に、電子データを編集しているかどうか」を判断することができるのです。
参考記事:ハッシュ値・ハッシュ関数とは?基本から使い方までわかりやすく解説
1-2. 電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとは、時刻認証局が付与するデータのこと
タイムスタンプは、画像データに付与された時刻を含む情報のことで、ある時刻から情報が改変されていないことを証明する情報です。
たとえば、2020年10月30日に画像データにタイムスタンプが付与されたとすると、その後、画像データに改変が加えられると、タイムスタンプの情報で「改変された」と分かるようになっています。
タイムスタンプがなければ、技術的には、領収書などの画像データの改変が可能になります。
そのようなデータでは、正式な書類としては認められないので、タイムスタンプを付与するように決められているのです。
1-3. 電子帳簿保存法のタイムスタンプを導入するメリットは大きい
タイムスタンプに費用がかかることから、勿体ないという意識が働くかもしれません。しかし、紙の書類をいつまでも保存する必要がなくなり、書類紛失のリスクもなくなります。
とくに、規模の大きい企業が本支店間で書類の郵送をさせているような場合は、輸送費の削減効果が大きくなります。
これを機会に経費精算の仕組みを見直したりすれば、業務の効率化も目指せるでしょう。
増加する費用や手間と、削減できる費用や手間を総合的に考えて、タイムスタンプを導入するかどうかを決めるのがいいと思います。
2. 2020年の電子帳簿保存法の改正で変化したこと

電子帳簿保存法は2020年に改正され、タイムスタンプについても緩和されました。
ここでは、電子帳簿保存法改正によって変化したタイムスタンプについて解説いたします。
2-1. 条件を満たせばタイムスタンプが不要になる
電子帳簿保存法においてタイムスタンプが不要になる条件は大きく2つあります。
1つ目は、タイムスタンプ付きのファイルを受領した場合です。
以前の法令では、受領後に自社でタイムスタンプを付与するか、事務処理規定に沿った保存をおこなう必要がありましたが、今後は受領側のタイムスタンプが一部不要となります。
2つ目は、以下の要件を満たしている場合です。
- 通常の事務処理期間(最長2か月と概ね7営業日以内)に保存している
- 訂正や修正した場合履歴が残るシステム、もしくは修正や訂正がおこなえないシステムを利用する
先述のとおり、タイムスタンプは「データが正しい状態で存在すること」と「データの改ざんがおこなわれていないこと」を証明するための仕組みです。その2つを証明できるのであれば、タイムスタンプが付与されていなくとも保存できることが案内されています。
2-2.タイムスタンプの付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内に
2021年の改正でさらなる緩和がおこなわれ、タイムスタンプの付与期間が見直されました。正確な期間は各企業の業務サイクルにより異なりますが、最長約2か月と概ね7営業日以内と明言されています。
ここまで読んで、改正された電子帳簿保存法でどのようにタイムスタンプ要件が変わったのかよくわからないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方にむけて、当サイトでは「5分で読み解く電子帳簿保存法」という資料を無料配布しております。本資料では電子帳簿保存法におけるタイムスタンプ要件の変更や、電子帳簿保存法にのっとったタイムスタンプの対応方法などをわかりやすく解説しております。今後タイムスタンプを用いて電子帳簿保存法に対応したいと考えている担当者にとっては大変参考になる内容となっておりますので、興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3. タイムスタンプの付与順序は?
上記で説明した通り、電子上でのデータの改ざんを防ぐために必要なものが「タイムスタンプ」です。
データにタイムスタンプを付与することによって証明を付けることで、データに信憑性を持たせることができます。
ここでは、タイムスタンプの付与順序について解説いたします。
3-1. 自書の署名が記載されている領収書を準備する
タイムスタンプを使用する際は、まずタイムスタンプを押すための領収書を準備しましょう。領収書には必要な情報を記載しておきましょう。
3-2. 領収書を電子化する
領収書が準備できたら、次はスキャナーやスマホ、デジカメなどで領収書を電子化しましょう。
画質などに制限がありますので注意して撮影しましょう。
3-3. 画像をアップロード
撮影やスキャンが完了したら、タイムスタンプのシステムに画像をアップロードしましょう。
3-4. タイムスタンプが付与される
確認が完了したら、画像にタイムスタンプが付与されます。
4. 電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの費用は?

電子帳簿保存法のタイムスタンプの導入には、一定の費用がかかります。依頼する業者によりかかる費用に違いがありますが、ざっくりと費用の目安と種類について紹介します。
4-1. タイムスタンプ導入における初期費用
タイムスタンプの導入時にかかる初期費用は、発生する場合としない場合とがあります。
会員登録に数千円から1万円程度の費用がかかるケースや、システムの導入に10万円から30万円程度の初期費用が発生するものもあります。
初期費用がかからない方がいいと思うかもしれませんが、タイムスタンプの発行ごとにかかる従量料金も合わせて検討する必要があります。
初期費用が安いぶん、ランニングコストがかかる業者もあるので、自社に合ったサービスを選ぶことが大切になります。
4-2. タイムスタンプの発行ごとにかかる費用の目安は10円程度
タイムスタンプの発行ごとにかかる費用は、業者によりばらつきはありますが、概ね10円程度というのが目安になります。
ただし、業者によっては、タイムスタンプ発行の上限回数に応じたコース設定を設けて、月々固定の費用でサービスの提供をしているケースもあります。
従量料金についても、費用の大小だけで判断するのはよくありません。サービスによっては、会計ソフトとの連携ができたり、自動仕分け機能が備わっているものもあります。
仕訳する取引が多い企業ほど、快適に利用できるサービスにメリットが大きくなると思われます。
4-3. 電子帳簿保存法の基本と新しい手続きに慣れるまでの期間も費用として認識すること
タイムスタンプの発行手続きを経理担当者だけがするのかどうかでも異なりますが、新しい制度の理解と手続きに慣れるまでの人件費も費用と考えられます。
最終的には、手続きの簡略化で人件費の削減が目指せるものですが、慣れるまでは、かえって時間がかかることもあります。
電子帳簿保存法も十分に理解しておかなければ、正式な電子データではないと否定されてしまうリスクが生じます。
まずは、電子帳簿保存法の基本をしっかりと理解して、タイムスタンプ導入のメリットとデメリットを洗い出してみるのもいいと思います。
5. 電子帳簿保存法のタイムスタンプ導入方法

タイムスタンプの導入までには、大きく2つのステップがあります。全体の流れを理解しておくとスムーズになりますので、ここでしっかりと確認しておきましょう。
5-1. タイムスタンプを導入するメリットがあるかどうかの検討
タイムスタンプを導入するべきかどうかは、企業ごとに判断するしかありません。
一般には、経費の精算の業務で残業をする社員がいたり、領収書の保管場所に困っているかどうか、領収書の検索に苦労しているなら、メリットがあると考えられます。
まずは、社内で「どんな課題が解決できるか?」を洗い出して、導入にかかる費用と比較してみるのがおすすめです。
なお、タイムスタンプを導入するかどうかを討する際は、国税庁の「電子帳簿保存法Q&A」が参考になります。制度の基本を理解できますので、参考にしながら検討するといいと思います。
5-2. タイムスタンプで利用するサービスの選定
タイムスタンプのサービスには、クラウド型、オンプレミス型の2種類があります。
クラウド型のサービスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。オンプレミス型は、自社のパソコンにシステムをインストールするので、システムを買わないといけないからです。
スマートフォンなどでアクセスしやすいのも、クラウド型のサービスの特徴になります。
ただし、クラウド型は、セキュリティに問題がある可能性があり、システムのカスタマイズも容易にはできません。
このような特徴の違いを考慮しつつ、自社に合ったサービスを選ぶようにしましょう。
6. 電子帳簿保存法のセミナーや勉強会に参加するのもおすすめ

タイムスタンプの導入をするかどうかで迷ったら、セミナーや勉強会に参加するのもいいと思います。
分かりやすい解説が受けられる上、疑問点の質問も可能なことが多いです。導入の検討にあたり、行き詰ってしまった場合にセミナー等の参加も検討してみてください。
関連記事:電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの仕組みを徹底解説
関連記事:電子帳簿保存法に基づくタイムスタンプを付した契約書作成方法
2020年、2022年の電子帳簿保存法改正を
わかりやすく総まとめ!
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04