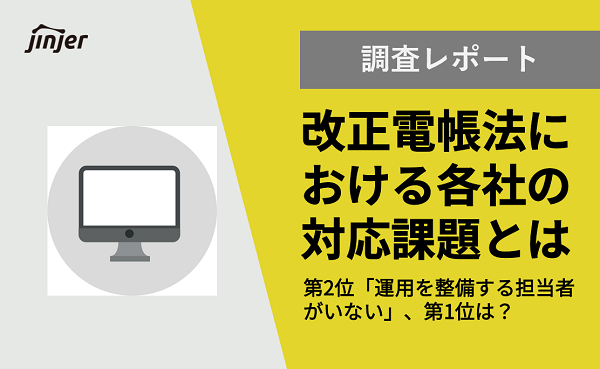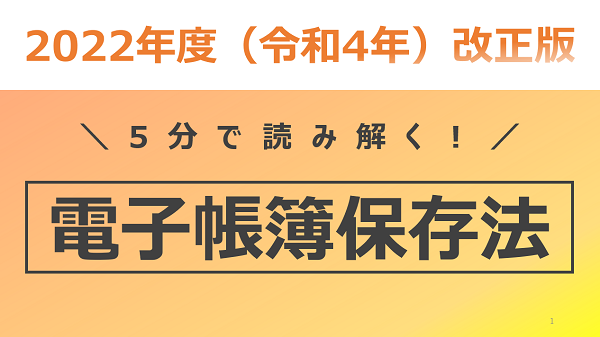電子帳簿保存法のメリット・デメリットは?簡単でわかりやすく解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2020.11.9
jinjer Blog 編集部
現代はパソコンやインターネットの普及にともない、ほとんどの企業がビジネスのあらゆるシーンでコンピュータ処理をおこなっています。
しかし、かつての日本では国税関係帳簿書類を紙で保存することが義務づけられていたため、コンピュータで作成した帳簿書類をわざわざ印刷し、物理的に保存しなければなりませんでした。
そこで政府では、新しい時代の流れに対応するため、平成10年度の税制改正の一環として、新たに電子帳簿保存法を施行するに至りました。
また、最近では電子帳簿保存法の改正による経費精算業務の変化が注目を集めており、経理部の業務効率化に大きく関わってくる法律になります。
今回は企業が電子帳簿保存法を適用することのメリット・デメリットや、適用するための方法について解説します。
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
目次
1. 電子帳簿保存法はどのような法律?

電子帳簿保存法と最近よく耳にしますが、そもそも内容が難しく、いまいち法律のポイントがわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、電子帳簿保存法の基礎知識についてわかりやすく解説いたします。
1-1. 電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律です。
電子帳簿保存法は1998年7月に制定され、2005年3月に一部改変されました。このタイミングで「スキャンデータが電子データとして認められる」ようになりました。
2016年には「スマートフォンやデジタルカメラで撮影した領収書や請求書のデータ保存が可能」になるなど、より企業が対応しやすい形へと年々変化をしています。
2020年10月におこなわれた改正
2020年の改正では、キャッシュレス決済の普及に伴って、以下の2点が緩和されました。
(1)発行者のタイムスタンプがあれば受領側でのタイムスタンプが不要に
(2)クレジットカードやICカードの利用明細が領収書の代わりとして使用できる
2024年1月から改正予定の内容
電子帳簿保存法は2024年1月に改正されることが予定されています。主な変更点は以下のとおりです。
| 電子帳簿保存要件 | 「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲を限定 |
| スキャナ保存要件 | 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になる
※解像度や階調などの規定は変更していないため注意 |
| 入力者等情報の確認要件が不要になる | |
| 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定 | |
| 電子取引データ保存要件 | 検索機能が不要となる対象者を拡大 |
| 宥恕措置の終了と猶予措置の整備 |
1-2. 電子帳簿保存法が定めていること
電子帳簿保存法が定めていることは大きく3つです。
① 国税関係帳簿や決算書類を電子保存する場合(電子帳簿保存)
仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係帳簿は、最初から最後まで一貫してPCで作成した場合に限り電子保存が認められています。
一部でも手書きの箇所が含まれる場合は電子保存できないため、注意しましょう。
② 電子データで送付・受領した国税関係書類の保存(電子データ保存)
PDFなどの電子データで送付や受領した国税関係書類は、電子データによる保存が義務付けられています。
③ 紙で送付・受領した国税関係書類の電子保存(スキャナ保存)
パソコンで作成して郵送などの紙媒体で送付・受領した書類は、②の電子データで送付・受領した書類と保存要件が異なります。
ここまで読んでそもそも電子帳簿保存法がどんな法律なのか、またどのように会社で対応すれば良いかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは5分でわかる電子帳簿保存法という資料を無料配布しております。本資料では電子帳簿保存法に関する概要から、対応方法、また具体的な改正内容などをわかりやすく解説しています。そのため電子帳簿保存法の基礎知識を得られるのはもちろん、会社としてどのような対応をすればよいかも理解することができます。大変参考になる資料となっておりますので、興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:参考記事:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説
2. 電子保存・スキャナ保存が認められている書類
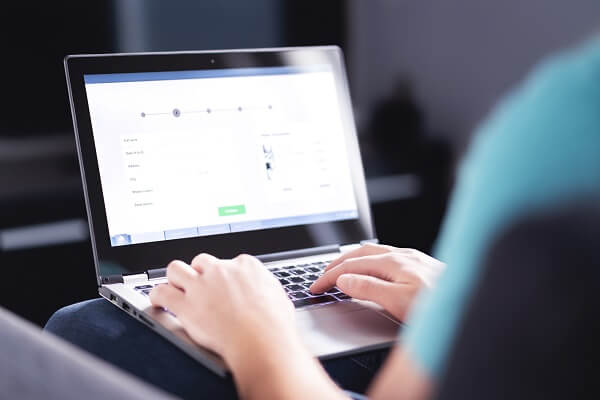
電子帳簿保存法によって電子化保存が認められている書類は以下の通りです。
電子化を考えている方は、どの書類が電子化できるのかしっかりと理解しておくとよいでしょう。
2-1. 電子保存が認められている書類の一覧
電子保存が認められている書類の一覧は下記のとおりです。
| 分類 |
対応する保存要件 |
帳簿・書類の例 |
|
| 電子データで作成・受領 | 紙媒体で作成・受領 | ||
| 国税関係帳簿 | 電子帳簿保存要件 | 電子保存不可 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金・買掛金元帳固定資産台帳、売上・仕入帳など |
| 決算書類 | 電子帳簿保存要件 | 電子保存不可 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、その他決算に関して作成した書類 |
| 重要書類 | 電子取引データ保存要件 | スキャナ保存要件 | 領収書、契約書、請求書、納品書 など |
| 一般書類 | 電子取引データ保存要件 | スキャナ保存要件 | 見積書、注文書、検収書 など |
書類の分類によって要件が異なるため、注意しましょう。
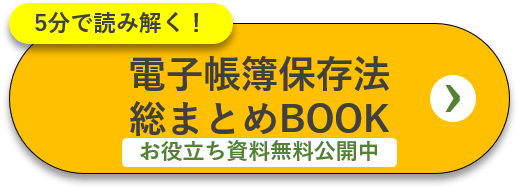
3. 電子帳簿保存法のメリット・デメリット

企業の会計処理に電子帳簿保存法を適用することのメリットとデメリットについて紹介します。
3-1. 電子帳簿保存法のメリット
電子帳簿保存法に対応することで得られるメリットは以下のとおりです。
① オフィスの省スペース化
日本では、法人は取引記録を帳簿につけ、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間にわたって保存することが義務づけられています。[注1]
なお、赤字経営で繰越欠損金が出た場合は、平成20年4月1日以後に修了した欠損金の生じた事業年度については9年間、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度については10年間にわたり、帳簿の保存が必要になります。
国税帳簿書類は一般的にファイルやバインダーなどに綴じ、キャビネット等で保管しますが、7年ないし10年もの間保管し続けるとなると、書類の数は膨大になり、少なからずオフィスのスペースを占有してしまいます。
帳簿書類を電子データ化すれば、紙で残す必要がなくなり、オフィスの省スペース化を図ることができます。
② 経理業務の効率化
大半の企業は帳簿書類を年度ごとに分けて保管しますが、たくさんある書類の中から目当ての一枚を探し出すのはかなりの手間と時間がかかります。
書類探しに手間取っていると、そのぶん他の作業が滞ってしまうため、業務効率が低下する一因になることも。
その点、帳簿書類を電子データとして保存しておけば、検索機能を使って目当ての書類を簡単に探し出すことができます。
業務効率が上がれば、生産性アップにもつながり、売上や業績にも良い影響をもたらします。
また、紙の帳簿を閲覧するのはオフィス内に限られますが、帳簿書類を電子化してクラウド上に保管しておけば、場所や時間を問わず帳簿書類にアクセスできるようになります。
たとえばスマホやタブレットなどを使って帳簿書類の電子データを呼び出せば、取引先や出張先からでも簡単に帳簿書類を閲覧することが可能です。
いちいちオフィスに戻る手間がなくなり、時間を効率よく使えるようになるところも電子帳簿保存法を適用する大きなメリットといえます。
③ コスト削減
紙の帳簿を作成するには、用紙のほか、印刷に使うインクも用意しなければなりません。
さらには、保管用としてファイルやバインダー、キャビネットなども購入する必要があり、保管が長期間に及ぶほど経費もかさむ傾向にあります。
帳簿書類を電子データとしてコンピュータに保存すれば、印刷や保管にかかるコストを大幅に節約できるため、経費削減につながります。
④ 環境問題への配慮
企業は自社の利潤を追求するだけでなく、消費者や投資家、さらには社会全体からの要求に対して責任を果たす姿勢を求められます。
これを企業の社会的責任(CSR)といい、昨今では企業イメージの向上や取引先との関係強化に欠かせない活動とされています。
CSR活動の種類は多岐に亘りますが、中でも代表的なものがエコ活動による環境問題への貢献です。
電子帳簿保存法の適用により、企業のペーパーレス化が進めば、貴重な紙資源を節約して省エネ・エコを推進することができます。
⑤ セキュリティの強化
帳簿書類はオフィス内のキャビネット等に保管し、無人になる時はオフィス・キャビネットの双方を施錠して盗難に備えます。
ただ、鍵が物理的にこじ開けられてしまった場合、悪意ある第三者に帳簿書類を盗まれてしまうおそれがあります。
盗難だけでなく、オフィスレイアウトを変更する際や、引っ越しの際に書類を紛失してしまう可能性もゼロではありません。
帳簿書類を電子データ化し、クラウド上で保存したうえで閲覧制限を設ければ、第三者にデータを盗まれる心配がなく、セキュリティを強化できます。
クラウド上のデータはIDやパスワードを管理していれば、いつでも引き出すことができるので、引っ越しやレイアウト変更にともなう紛失のリスクも少なく、安心してデータを保管できます。
3-2. 電子帳簿保存法のデメリット
先述のとおり、電子帳簿保存法に対応することで多くのメリットを享受できる反面、デメリットも少なからず存在します。
後で後悔することがないよう、確認したうえで検討を進めるようにしましょう。
① システムの導入コスト
帳簿書類を電子データ化するには、コンピュータやシステムの導入が必要不可欠です。
パソコンなどの購入費や、ソフトウェアやクラウドシステムの導入費用といった初期コストはもちろん、継続的に運用するにはそれなりのランニングコストもかかります。
電子帳簿保存法の適用によって削減できるコストも少なくありませんが、一方で新たな初期コストや維持費がかかることも念頭に置いておきましょう。
② 所定のルールに基づいたデータ管理が必要
電子帳簿保存法を適用するには、所定の要件を満たす必要があります。
くわしくは後述しますが、要件を満たすにはデータ管理に関する基本的な知識やスキルが必要不可欠です。
もともとコンピュータスキルに長けている人なら問題ありませんが、慣れていない方が作業すると紙の帳簿を作成するより手間や時間がかかってしまうこともあります。
③ システム障害のリスク
電子データはコンピュータのHDDやサーバー上で保存・管理するため、パソコン自体がクラッシュしたり、サーバーがシステムダウンしたりすると、データが失われる可能性があります。
一度失ったデータを復元するのは非常に難しく、バックアップ体制を徹底していなかった場合、データを永久に失ってしまうこともあるので要注意です。
4. 電子帳簿保存法を適用するためには

国税関係帳簿を電子帳簿として保存するには、真実性と可視性を確保する必要があります。
具体的には以下の要件を満たさなければなりません。
紙媒体の書類を電子化する場合と、電子取引データを保存する場合で要件に違いがあります。注意しましょう。
| 要件 | 電子取引データ保存 | スキャナ保存要件 | |
| 重要書類 | 一般書類[注2] | ||
| 入力期間の制限 | 最長で2ヶ月と7営業日以内
※事務処理規程によって異なる |
最長で2ヶ月と7営業日以内
※事務処理規程によって異なる |
適時入力可能 |
| 解像度および階調の下限制限 | 定めなし | 解像度 200dpi 以上
赤・青・緑それぞれ256階調以上 |
解像度 200dpi 以上
グレースケール保存も可 |
| タイムスタンプの付与 | 以下のいずれかの措置をおこなう
|
入力期間内に付与する
※入力期間内に記載していることが確認できる場合は不要 |
重要書類の要件と同様 |
| 読み取り情報の保存 | 定めなし | 以下の情報を保存する
|
以下の情報を保存する
|
| バージョン管理 | 以下のいずれかの措置をおこなう
|
以下のいずれかの措置をおこなう
|
重要書類の要件と同様 |
| 入力者等情報の確認 | 定めなし | 記録事項の入力をおこなう者、もしくはその監督者の情報を記録・確認できるようにすること | 重要書類の要件と同様 |
| 帳簿との相互関連性 | 定めなし | 国税関係書類と国税関係帳簿の記録内容と相互に関連性を確認できるようにすること | 重要書類の要件と同様 |
| 見読可能装置の備付け | パソコンやディスプレイ、プリンター類とそれらの操作説明書の備付けたうえで、速やかに利用できる状態であること | 以下のものを備付ける
|
重要書類の要件と同様
※グレースケールで保存している場合はカラー対応していなくとも良い |
| 利用するシステムの操作説明書の備付け | システムの操作説明書の備付け | システムの操作説明書や事務処理マニュアルの備付け | 重要書類の要件と同様 |
| 検索機能の確保 | 以下の要件を満たすこと
※税務調査員によるダウンロードの求めに応じることができる場合、2と3の要件は不要 |
以下の要件を満たすこと
|
重要書類の要件と同様 |
[注2]事務処理規程を定めたうえで、運用方法をまとめたマニュアルを備付けている場合に限る
※2024年1月より電子帳簿保存法の内容が改正される予定です。上記の表は2023年現在の法令に則って作成されているため、ご注意ください。
5. 電子帳簿保存法にはメリットがたくさんある

電子帳簿保存法を適用すると、紙の帳簿を作成・保存・管理する手間が省けるため、業務効率化につながります。
作成・管理にかかるコストや、保管スペースの節約にも役立ちますので、帳簿書類の管理にお悩みの方は、積極的に電子帳簿保存法の適用を検討しましょう。
2020年、2022年の電子帳簿保存法改正を
わかりやすく総まとめ!
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04