電子帳簿保存法とe-文書法って何が違うの?関係性は?疑問を総まとめ
更新日: 2024.10.10
公開日: 2020.11.9
jinjer Blog 編集部

税務上の重要文書や商法・証券取引などで保管が必要な文書を電子化保存できれば、文書の保管場所にも困らず、大量の文書のなかから必要な情報をすぐに検索して取り出せて便利です。
従来は紙媒体でしか保存を認められていなかった文書を電子化するには、e-文書法についての理解を深めることが必須です。
今回はe-文書法とはどのようなものか、また電子帳簿保存法との違いについて解説いたします。
目次
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無についてなどなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてぜひご覧ください。
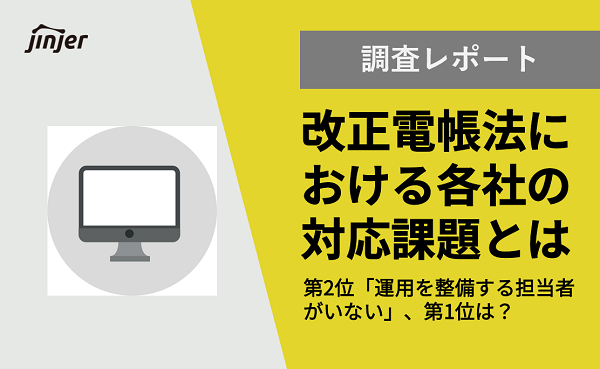
1. e-文書法とは

e-文書法は2005年に施行された法律で、商法や税法などで保管が義務付けられた文書の電子保存を認める法律です。
法人税法や会社法・商法・証券取引法などで保管が義務付けられている文書・帳簿・請求書・領収書などが対象となります。
従来は紙媒体での保存が義務付けられていた文書について、電子化ファイルによる保存を容認する法律で、電子文書法とも呼ばれています。
2. e-文書法で電子化できる書類、できない書類は?
e-文書法では、次のとおり対象となる文書と対象外の文書があります。
| 対象となる文書 |
|
| 対象外の文書 | 緊急時にすぐ解読可能である必要性が高いもの(船舶に備える手引書など) きわめて現物性が高いもの(許可証・免許証など) 条約による制限があるもの |
対象となる文書を電子化するためには、法令要件を満たす必要があります。
要件を満たせば、書類を紙媒体のままファイリングする必要はなくなり、膨大な書類を保管するスペースも削減できます。また、電子化でデータの検索性が高くなるでしょう。
関連記事:【2022年】電子帳簿保存法の緩和で変わる領収書の管理と注意点
3. 電子帳簿保存法とe-文書法の違い
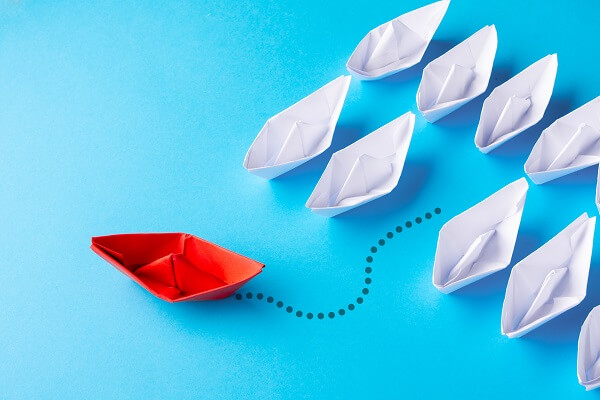
e-文書法と似たような法律に電子帳簿保存法(1998年施行)がありますが、この2つの法律の大きな違いは「適用文書の範囲」です。
3-1. e-文書法は、複数の監督省庁が管轄する法律(約250)が対象
e-文書法は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律を指した通称です。
医療や保険関係、証券や建築に関係する保存義務のある法定文書から、対象外に含まれる書類を除いて、全ての書類を電子化することを認めています。
そのため、電子帳簿保存法が対象としている「国税関係帳簿」や「国税関係書類」も対象範囲に含まれているのです。
後述する4つの基本要件を定めているものの、詳細な要件については各文書に関連している法律や省庁からの通達などに委ねられているので、注意しましょう。
3-2. 電子帳簿保存法は国税関係帳簿と書類に限定された法律
電子帳簿保存法は、一定の要件を満たせば、国税関係帳簿や決算書類、国税関係書類の電子保存を認める法律です。
ただし、「過去分重要書類」を電子保存する場合は申請と承認が必要となるため注意しましょう。
国税関係書類や帳簿はe-文書法の対象文書でもありますが、電子帳簿保存法の要件を満たせば、必然的にe-文書法の要件も満たせるようになっているため、特に意識しなくても問題ありません。
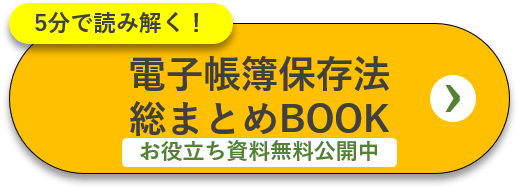
4. e-文書法の要件に関するポイント

e-文書法の要件は関連する各府省令によって異なります。
ここでは例として、経済産業省による4つの技術的基本要件についてご紹介します。
電子化保存に際してこれらの要件すべてを満たす必要はなく、見読性以外は対象文書の種類によって要件が変わるケースがほとんどです。
4-1. 見読性
電子化されたデータについて、必要なときにすぐに表示・書面出力が可能な状態であることが求められます。
パソコンのモニターに表示できたり、プリンターで出力した場合の解像度や階調が適切で明瞭でなくてはなりません。可視性と表現されることもあります。
4-2. 検索性
必要なデータをすぐに引き出せて、文書に活用できるように検索性が高い状態で保管されなくてはなりません。
4-3. 完全性
保存期間中にデータの滅失や毀損が発生しないよう措置が取られている必要があります。内容の改変・消去を防ぎ、発生した場合はその事実がわかるようにします。
電子署名とタイムスタンプの使用により、原本が正しい日付で、ありのままに保存されている(改ざんされていない)と証明されなくてはなりません。
4-4. 機密性
不正アクセスができない措置がされていることが必要です。許可されていない人物によるデータへのアクセスを抑止しなくてはなりません。
5. e-文書法は商法・会社法上保管義務のある文書を電子化保存するための法律

e-文書法は、商法・会社法などで保管が必要な文書をスキャンなどで電子化保管するための法律です。
e-文書法の要件は、対象となる文書を管轄する各府省令によって変わりますが、見読性・検索性・完全性・機密性などがあります。
書類のペーパーレス化を進めることで、文書のファイリング、保管する手間が省け、膨大なデータのなかから必要な情報を抽出しやすくなるというメリットがあげられます。
要件を正しく理解して、日々の業務を効率化しましょう。
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正内容と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
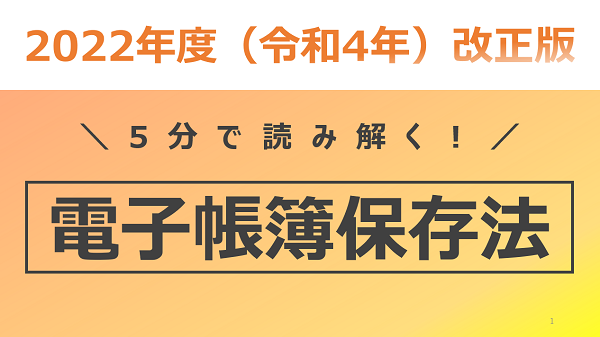
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
業務のお悩み解決法の関連記事
-

人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-

経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-

経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
電子帳簿保存法の関連記事
-

電子帳簿保存法第10条のポイントをわかりやすく!対象や範囲、保存要件を解説
経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07
-

改正電子帳簿保存法における事前申請が不要になるのはいつから?改正点や保存要件も解説
経費管理公開日:2023.09.28更新日:2024.10.11
-

電子帳簿保存法の事務処理規程とは?必要な理由や作成方法を解説
経費管理公開日:2023.09.21更新日:2024.10.11






























