領収書の発行義務とは?発行するときの注意点や再発行できないときの対処法
更新日: 2025.6.18 公開日: 2022.4.11 jinjer Blog 編集部

経費精算をする上で必要となる領収書。しかし、領収書は商品やサービスの代金を支払った場合には必ず発行されるものなのでしょうか。また、領収書が手元にない場合、取引先に依頼をすれば再発行は必ずできるものなのでしょうか。
今回は、そんな領収書の発行に関する疑問について詳しく解説します。

申請書のチェック、差し戻しの連絡、会計ソフトへの手入力…。毎月発生するこれらの定型業務に、貴重な時間を奪われていないでしょうか。
「ジンジャー経費」なら、経費精算のプロセスを自動化し、従業員と管理部門双方の負担を軽減します。
本資料では、貴社の課題を解決するヒントを分かりやすく解説します。
◆この資料でわかること
- 領収書の自動読み取り(AI-OCR)で入力作業を削減する方法
- スマホ活用で、場所を選ばずに申請・承認できるフローの構築
- 規定違反の申請を自動で検知し、ガバナンスを強化する方法
定型業務に追わている、経費精算業務のDXに興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 領収書の発行義務は「同時履行」がポイント


領収書は代金を支払って商品やサービスを購入したという証明となる書類です。
そして、領収書は民法486条により「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。ここでいう「弁済したもの」とは、代金を支払った人のことで、代金を支払った人は代金を受け取った人に対して領収書の発行を請求でき、さらに請求をされた人には領収書を発行する義務が生じます。
なお、過去の判例により領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われるという「同時履行の原則」があります。そのため、代金を受け取る側が領収書の発行を拒否する場合、代金を支払う側は代金の支払いを拒否することが可能です。
2. クレジットカード決済の場合発行義務はなし


あらゆる場面でキャッシュレス化が加速する近年、クレジットカードによる決済がメインという人が増えていますが、クレジットカード決済の場合、商品やサービスを提供した事業者側に領収書を発行する義務はありません。
なぜなら、クレジットカード決済の場合、商品やサービスを購入した人はクレジットカード会社を通して事業者に代金の支払いをしており「同時履行の原則」に該当していないためです。
そのため、クレジットカード決済の領収書として事業者が領収書を発行したとしても、税務署の観点では正式な領収書として見なされず、この場合はクレジットカード決済をした際に受け取る「利用控え」が支払いの証明になります。
また、後日カード会社から発行される「利用明細書」については、あくまでも「代金を立て替えた事実の証明」という位置づけであるため、「利用明細書」のみでは完全な支払いの証明にはなりません。
一方、銀行振込による決済については現金と同様に領収書の発行義務が生じます。
3. 領収書を発行する際の注意点


私たちが普段何気なく扱っている領収書。しかし、領収書は支払いの事実を証明する非常に大切な書類であり、書き方や扱い方にはきちんと決まりがあるのです。ここからはそんな領収書を発行する際の注意点をご紹介していきます。
3-1. 注意点1:正しい形式で記載する
領収書を法的効力のある書類にするために、次の1~5までの内容は必ず記載しましょう。なお、2023年からはインボイス制度が施行される予定で、その際には税額の項目をより詳細に記載することとなっています。
領収書にはタイトル、つまり「領収書」と明記する必要があります。位置は書類の上部中央、または上部左に記載します。領収書を受領する相手の名前あるいは会社名を記載します。(株)ではなく「株式会社」とするなど、正式名称を記載します。
金額は改ざんを防ぐために、数字には3桁ごとに「,」を打ち、数字の頭には「¥」または「金」を、末尾には「‐」または「也」を記載します。
但し書きには取引の内容を記載します。例えば「文具代として」「書籍代として」など、内容は具体的に記載し、「お品代」などといった曖昧な表現は避けます。領収書を発行する人の名前あるいは会社名、さらに住所や連絡先を記載します。住所印を用いても構いません。
3-2. 注意点2:クレジットカード決済であることを明記する
前述のとおり、クレジットカード決済の場合は事業者側に領収書を発行する義務はありません。しかし代金を支払う側から領収証の発行を求められた場合に、事業者側がその要望に応じることは可能です。
その際に注意すべきは、クレジットカード会社が後日領収書を発行することによって領収書が2重発行にならないようにすることです。
このような場合においては、領収書に発行日時、あて名、金額、但し書き、発行者名を記載するとともに、「クレジットカード払い」と明記しましょう。
なお、クレジットカード決済時にこのような領収書を発行することは可能ですが、この領収書については金銭の受領事実がないため正式書類とはなりません。したがって本来5万円以上の取引に必要な収入印紙についても貼付は不要です。
3-3. 注意点3:書き間違えた場合はなるべく再発行する
領収書の内容を書き間違えてしまった場合は、不備のある個所に二重線を引いた上に訂正印や会社の角印などを押し、さらに正しい内容を書くことで訂正ができます。
しかし、トラブル回避のために訂正を認めていない企業もあるため、可能な限り再発行をする方が安心でしょう。
3-4. 注意点4:控えを保管する
法人の場合、領収書は確定申告提出期限の翌日より7年間保管することが法人税法で定められており、控えについても同様です。
複写式の領収書の場合は領収書の作成と同時に控えが作成されますが、複写式の領収書でない場合は同じ領収書を2枚作成し、領収書と控えに割り印をする形で作成が可能です。
4. 領収書の再発行義務はない


前述のとおり、代金を受け取った側は代金を支払った側に領収書を発行する義務がありますが、再発行については規定がされておらず、再発行の義務もありません。
また、領収書を再発行することは経費の架空計上や不正利用の発生にもつながりかねないため、再発行に応じていない事業者も少なくないのです。
5. 領収書の再発行ができない場合の対応策


領収書を紛失してしまった場合、領収書の発行元に再発行が可能かどうかを尋ねてみること自体には問題はありません。しかし、発行元に領収書の再発行義務はないため、再発行に応じてもらえない可能性も十分に考えられます。
ここからは、領収書の再発行ができなかった場合の対応策についてご紹介します。
5-1. 対応策1:レシートで代用
領収書は発行日時、金額、但し書き、発行者名の4項目が記載されていることで法的効力を持ちますが、レシートにこの4項目が記載されていれば領収書の代用が可能です。ただし、会社によっては経費精算を行う上でレシートを不可としているケースもあります。
5-2. 対応策2:利用明細で代用
支払い方法がクレジットカード決済や銀行振込の場合は、利用明細や通帳記録も領収書の代用として使用が可能です。なお、請求書については証明書類のひとつにはなるものの、基本的に代金の支払い前に発行されるものであるため、証明力は弱くなります。
5-3. 対応策3:出金伝票で代用
レシートなどが用意できない場合には出金伝票で代用をします。出金伝票には代金を支払った日付、金額、代金を受け取った側の名称や所在地を記載します。その際は領収書を紛失した旨を余白部分などに記載しておきましょう。
6. 正しい知識で領収書のトラブルをなくそう


事業者にとって領収書は経費を計上するために欠かせないものであり、商品やサービスを受け取る側には発行義務が生じます。また、領収書に法的効力を持たせるためには正しいルールに沿って発行をする必要があるため、領収書を発行する側、受け取る側の両方が正しい知識を身に付けておく必要があります。
経費精算や確定申告の際に慌てることのないよう、領収書に関する正しい知識の周知徹底を行いましょう。



申請書のチェック、差し戻しの連絡、会計ソフトへの手入力…。毎月発生するこれらの定型業務に、貴重な時間を奪われていないでしょうか。
「ジンジャー経費」なら、経費精算のプロセスを自動化し、従業員と管理部門双方の負担を軽減します。
本資料では、貴社の課題を解決するヒントを分かりやすく解説します。
◆この資料でわかること
- 領収書の自動読み取り(AI-OCR)で入力作業を削減する方法
- スマホ活用で、場所を選ばずに申請・承認できるフローの構築
- 規定違反の申請を自動で検知し、ガバナンスを強化する方法
定型業務に追わている、経費精算業務のDXに興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
経費管理のピックアップ
-


非公開: 電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2025.08.27
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2025.06.18
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2025.06.18
-


非公開: 小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2025.08.27
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2025.06.16
-


非公開: 経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2025.08.27
領収書の関連記事
-


領収書のもらい方!個人事業主と会社員がそれぞれ気を付けるべきポイントとは
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2025.06.25
-

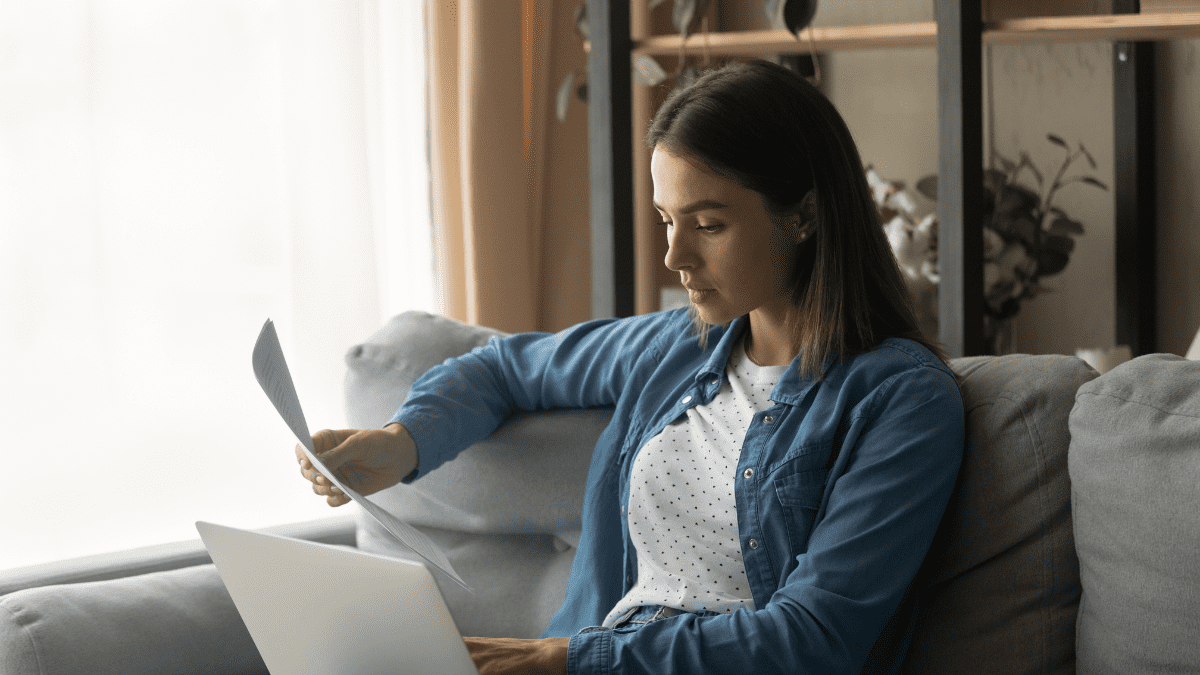
領収書の偽造や改ざんにあたる行為や罪とは?不正への対応方法や偽造の防ぎ方も解説
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2025.06.25
-


領収書スキャンのやり方!原本の保管の必要性やスキャナ保存の要件を解説
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2025.06.25





















