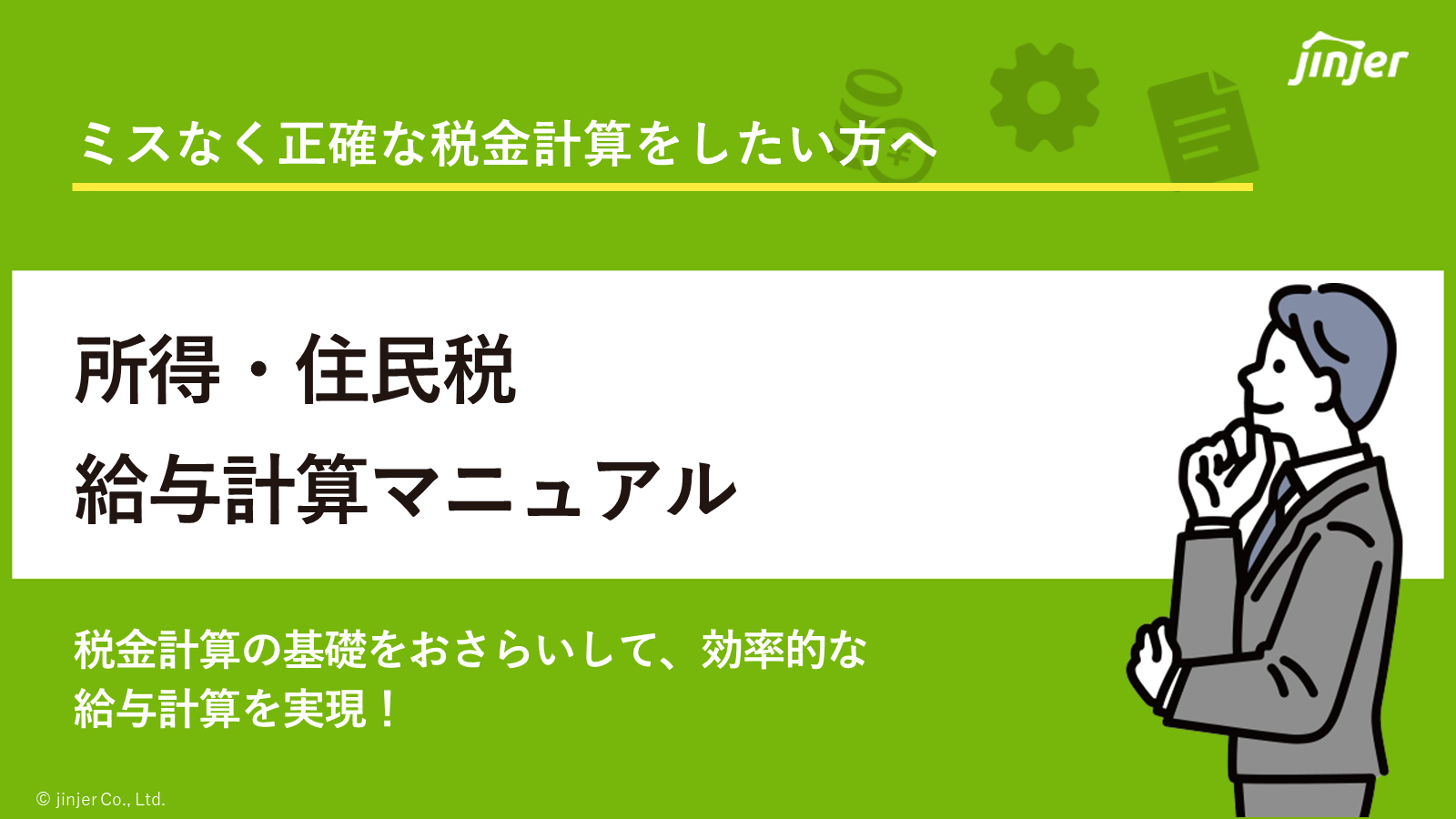通勤手当の対象となる通勤手段と計算方法について
更新日: 2024.3.5
公開日: 2022.3.7
OHSUGI

通勤手当は、労働基準法で定めるはっきりとした規定がなく、企業側が自由に決めることが可能です。そのため、担当者は通勤手当の支給基準や計算方法について、従業員にしっかり説明できる知識量が求められます。また、通勤手当の支給額によっては非課税対象となるので、支給基準についてしっかり把握しておくことも重要な業務です。
とはいえ、労働基準法での法規がないため、何を把握しておけばいいのかわからない担当者の方もいるかもしれません。そこで今回は、通勤手当の対象となる通勤手段やその計算方法、手段ごとの課税などについて解説していきます。
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 通勤手当とは

通勤手当とは、会社側が従業員の通勤にかかる費用を手当として払うものです。通勤手当の負担の割合や上限の有無などは会社によって異なりますが、ほとんどの会社では通勤手当を支払っています。
会社に行くための費用なので、通勤手当の支給に関する法律があると思う方もいるかもしれません。しかし、労働基準法では支払義務などは定められておらず、就業規則や就業規則の一部に賃金規程を定めればよいとされています。
通勤手当と似ているものに「交通費」というのがありますが、通勤手当は「通勤をするためにかかる費用」に対する支給で、交通費は「業務上の移動でかかる費用」への支給という大きな違いがあります。また、交通費は非課税ですが、「給与所得」となる通勤手当は一定の範囲を超えると所得税が課税されるという点も違うので混合しないようにしましょう。
2. 通勤手当の対象となる通勤手段

通勤手当の対象となる通勤手段は、各企業ごとに就業規則などで決められています。一般的な通勤手段としては、以下のようなものが挙げられます。
- 公共交通機関(電車、バスなど)での通勤
- 自家用車(車や自転車など)での通勤
- 徒歩での通勤
では、それぞれの通勤手段の手当はどのように決められているのでしょうか。
2-1. 通勤手当の決め方
結論からいうと、通勤手当の決め方について、明確な規程はありません。徒歩の場合は「歩き」になるので費用は発生しない、電車やバスなど公共交通機関は、定期券代で計算というのが一般的な考え方です。
会社によって、決め方がもっとも異なるのが自家用車です。自家用車の場合は、距離単価をあらかじめ決めて、自宅から会社までの往復距離で算出する、通勤手当の上限を決めて支給するなどさまざまな決め方があります。決め方は自由ですが、ガソリン代は変動するため、マイカー通勤の従業員が多い場合は双方が納得できる計算方法にすることをおすすめします。
また、通勤手当の計算方法や支給方法を決定したら、就業規則に記載する必要があります。就業規則に記載する際には、通勤手当の受給条件を具体的にわかりやすく記載するようにしましょう。
3. 通勤手当の計算方法

通勤手当の計算方法は、交通手段によって異なります。ここでは、それぞれの計算方法ついて順に解説していきます。
3-1. 自家用車で通勤する場合
自家用車で通勤する場合は、ガソリン単価を用いて通勤手当を計算する方法があります。
【ガソリン単価で1ヶ月の通勤手当を計算する場合】
1ヶ月の通勤手当=往復分の通勤距離×1ヶ月の勤務日数×ガソリン単価
正社員の場合は公共交通機関を利用する際の定期代と同様に、決められた月の支給額を固定することをおすすめします。なお、ガソリン単価については、企業側が決めるのが一般的です。以下のような計算式でおおよそのガソリン単価を調べることができます。
【おおよそのガソリン単価】
ガソリン単価(1km)=ガソリン1Lあたりの値段÷ガソリン1Lあたりの走行可能距離
ガソリン単価とは別に、距離単価を用いた計算方法もあります。
【距離単価を用いて通勤手当を算出する場合】
1ヶ月分の通勤手当=往復分の通勤距離×距離単価 × 1ヶ月の勤務日数
ガソリン単価と同様に、距離単価においても企業側が自由に決めることができ、ガソリン単価よりも1km当たりの単価が曖昧なことが多いです。そのため、距離単価と比較するとガソリン単価の方が比較的正確な通勤手当の算出方法といえるでしょう。
3-2. 公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合
公共交通機関を利用する場合は、定められた月数分の通勤定期券に相当する金額を手当として支給されることが一般的です。企業によっては、就業規則に「通勤手当の額は公共交通機関を合理的に利用した場合の通勤定期券の額に準ずる」ことを定め、一律に支給するケースで対応しているところもあります。
また、回数券やICカードを利用する場合、計算方法は少し複雑です。
【回数券を利用する場合の計算式】
1ヶ月の通勤手当=(回数券1冊分の価格×1ヶ月当たりの所要枚数)÷当該回数券の枚数
【ICカードを利用する場合の計算式】
運賃等相当額=(支給月数に応じた通勤のために負担する運賃の額の合計÷支給月数)×支給月数
注意点として、ICカードの種類によっては、特典として電車の運賃が割引されるものもあります。特典が付くものだと、場合によっては不正受給となる可能性があるため注意が必要です。そのため、ICカードを通勤手当や交通費として利用する場合は、会社の規定に従ったICカードまたは、PASMOやSuicaなどに限定することをおすすめします。
3-3. 自転車や徒歩で通勤する場合
自転車や徒歩の場合は、金銭の負担が発生しないため、通勤手当をもらえるかどうかは、就業規則で企業側に決定権があります。一般的に徒歩の場合は支給されません。
自転車の場合は徒歩と比較すると通勤手当が支給されるケースが多いようです。理由としては、所得税法に「給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの」と定められていることが挙げられます。
自転車は交通用具として扱われることが多いため、自家用車と同様の計算方法で支給されるケースが一般的です。
4. 通勤手当の課税について
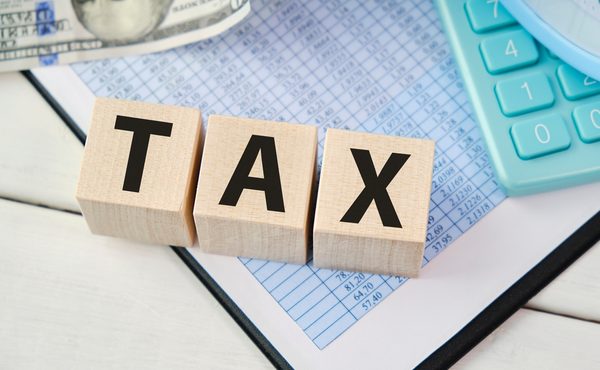
企業が、従業員に支払う基本給以外の諸手当は、給与所得の一部と考えられています。そのため、支給額に応じた所得税が発生しますが、通勤手当の場合は非課税扱いとなっているため、通勤手当として支給された方が従業員にとって得になります。ただし、非課税限度額を超えてしまうと課税対象なるので注意しましょう。
それぞれの交通手段によって非課税限度額が異なるため、ここでは交通手段ごとの課税について解説していきます。
4-1. 自家用車(自転車を含む)を利用した場合
マイカー通勤している従業員の非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道分の通勤経路に沿った通勤距離に応じて限度額が定められています。
非課税となる1ヶ月当たりの限度額は以下の通りです。
- 片道55Km以上:限度額31,600円
- 片道45Km以上55Km未満:限度額は28,000円
- 片道35Km以上45Km未満:限度額は24,400円
- 片道25Km以上35Km未満:限度額は18,700円
- 片道15Km以上25Km未満:限度額は12,900円
- 片道10Km以上15Km未満:限度額は7,100円
- 片道2Km以上10Km未満:限度額は4,200円
- 通勤距離が片道2Km未満:全額課税
国税庁の規程では「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」がこの分類に該当するため、自転車通勤の場合も上記の非課税対象に当てはまります。
参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
4-2. 公共交通機関を利用した場合
公共交通機関(電車やバスなど)を利用した場合、通勤手当の1ヶ月当たりの金額が15万円を超えた際に、15万円が非課税となります。以前までは非課税の上限額は10万円でしたが、2016年の税制改正以降、通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
しかし、15万円まで非課税だからといって、好き勝手にルートを決めて良いというわけではありません。非課税限度額の適用には、合理的かつ経済的なルートで通勤することが求められます。合理的というのは「ほかの経路と比較して所要時間が短いこと」、経済的というのは「ルートの中で運賃などがもっとも低額であること」です。そのため、新幹線通勤がもっとも最短かつ経済的なのであれば、新幹線の特急料金も非課税の対象になります。
ただし、グリーン車を利用することは通勤には関係ないため、グリーン車分の費用は非課税対象外となるので注意してください。
4-3. 徒歩の場合
所得税法では「給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの」として、通勤手当に一定の非課税限度額を定めています。
このことから、交通機関の利用や交通用具を使用しない徒歩通勤については非課税となるケースはほとんどありません。
当サイトでは、所得税の課税・非課税ルールを考えるうえで重要となる、所得税の基礎知識や計算方法、注意すべき点を解説した資料を無料で配布しております。
所得税に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
5. 社会保険における通勤手当の扱い方

通勤手当は、所得税に対しては一定額までは非課税となるため、課税されることはありません。しかし、扱いは「給与(月額報酬)」なので、社会保険料に関する標準報酬月額の計算では、通勤手当も課税対象になります。
「報酬は労働の対価として支払われるもの」という考え方では、通勤するための費用である通勤手当は実費計算となので「対価ではない」といえます。所得税でも、通勤手当は会社の経費という解釈です。
しかし、社会保険料における通勤手当は、「働いて報酬を得るために必要となる手当」という解釈になるため課税対象となるので、標準報酬月額に含まれることを覚えておきましょう。
6. 従業員の通勤手段や通勤手当の計算方法は正しく把握しておこう

通勤手当は通勤にともなう福利厚生であり、新設や変更の決定権は企業の自由です。ただし、従業員の働きやすい環境づくりにも影響する重要な要素の一つとなっているので、企業側の都合による減額や廃止は望ましくありません。
その一方で、働き方の多様化にともない、通勤手当の見直しだけでなく在宅勤務手当の検討もおこなわれています。今後、通勤手当の見直しがあった場合には、それに相応する新しい手当が出てくる可能性もあるでしょう。
担当者は、手当の対象や計算方法をしっかり確認しておき、いつでも従業員に説明できるようにしておかなければなりません。そのためにも、従業員にとって身近な通勤手当について、しっかりとした知識を身につけておきましょう。
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
給与計算の関連記事
-
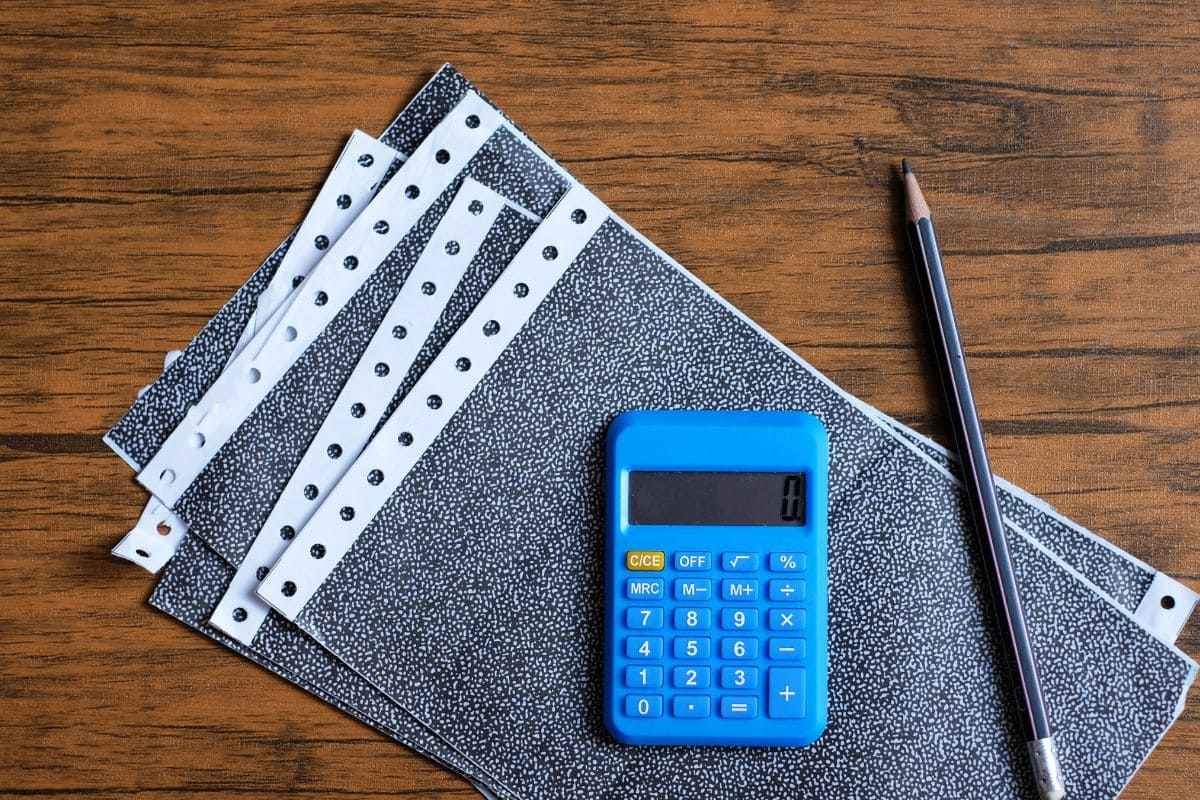
懲戒解雇した社員に退職金を支払う義務はある?不支給の条件や手続きを解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31
-


退職金の前払い制度とは?導入のメリット・デメリットやポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31
-


源泉徴収票は電子化OK!メリット・デメリットや方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31