職務給とは?職能給・基本給との違いやメリット・デメリットを解説
更新日: 2025.5.27 公開日: 2024.7.29 jinjer Blog 編集部

「職務給とほかの給与制度の違いは?」
「職務給を導入するうえでメリットとデメリットを知りたい」
「職務給をスムーズに導入する方法を知りたい」
職務給の導入を検討していくうえで、上記のような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか。職務給とは従業員が担当する業務内容を基準として、給与を決定する制度になります。
日本の会社でよく採用されている終身雇用型や年功序列型には当てはまらず、成果主義型やジョブ雇用型と近い内容です。
本記事では職務給の内容、職能給や基本給との違いについて解説しています。また、メリットやデメリットについて紹介しているため、職務給の導入を検討している経理・労務担当者の方は参考にしてください。
目次

「自社の給与計算の方法に不安がある」「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか心配」など、給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
資料では、労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れをわかりやすく解説しています。
間違えやすい給与の計算方法をおさらいしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 職務給とは


まずは職務給とはどのような制度なのか、日本でも注目され始めた新しい賃金制度の内容を知っておきましょう。
1-1. 業務内容を基準にした賃金制度
職務給は、従業員の業務内容を基準として給与を設定する賃金制度です。業務内容に焦点をあてた評価であり、従業員の能力や年齢を評価対象にしません。
キッチンで業務につく人を例にとって考えてみましょう。同じ調理という業務をしていても、年功序列や職能給の場合は長く勤めている人や、資格を有している人ほど高く評価されて賃金も高くなります。業務内容はあまり考慮されません。
職務給の場合は、新人だとしてもほかの従業員と同じ内容の業務をしていたら賃金は同じになります。お店に長く貢献してくれているから、資格を保有しているからなどの理由だけで賃金が高くなることや、反対に経験が浅いことなどの理由だけで賃金が安くなることもありません。
1-2. 職務給は日本でも普及し始めている
職務給はもともと欧米を中心に普及している賃金制度でした。
しかし、2020年に導入された同一労働同一賃金制と相性がよく、ジョブ型人事制度への関心も高まっていることから、日本でも普及し始めています。
近年は深刻な少子高齢化によって人材不足がさまざまな業種で発生しています。若手の離職率を下げ、優秀な人材を確保するためにも職務給は有効であるため、今後も増えていくと考えられます。ただし、職務給には課題もまだまだあるため、メリットだけを見て給与制度を変更すると失敗する可能性があります。
ほかの給与制度との違いや、職務給が抱える問題なども十分に理解して検討しなくてはなりません。
2. 職務給と職能給・基本給の違い


職務給と職能給は名称が似ていることもあり、混同しないように違いを十分に知っておきましょう。給与計算をするうえで知っておきたい職務給と基本給の違いと併せて解説します。
2-1. 職務給と職能給の違い
職務給と職能給の違いは以下のとおりです。
| 職務給 | 職能給 | |
| 基準 | 業務内容 | スキルや能力 |
| 評価方法 | 職務の難易度や責任範囲 | 職能評価や業績評価 |
| 賃金上昇の要因 | 職務の変更や昇格 | スキルアップや業績 |
職能給は、従業員の職務を遂行する能力を基準として給与を設定する賃金制度です。業務内容ではなく、従業員個人の能力で評価が左右されます。
日本企業の基本的な考え方であった年功序列型や終身雇用型にあう賃金制度として、長年採用されてきました。
現在は仕事に対する評価の仕方や考え方から成果主義型などへ変化しており、職務給へ移行する日本企業が増えています。
2-2. 職務給と基本給の違い
基本給は従業員の属性や所属による基礎部分であり、職務給は職務に応じて発生する追加的な給与になります。
基本給は、従業員の生活に最低限必要となる給与を基準とした賃金制度です。基本給の主な構成要素は以下のとおりです。
- 年齢
- 勤続年数
- 資格
- 基本的な職能
- 従事する職務
これらは毎月固定されているもので、月単位で変わることはありません。既定の労働時間を満たしていれば、支払われる給与だと考えるとわかりやすいかもしれません。
一方で職務給は業務内容や成果に応じて変動するため、月によって給与も変化します。同じ時間労働をしていても、前月と今月とでは給与に差が発生することもあります。
3. 職務給導入の3つのメリット


職務給には若手も評価されやすかったり、公平な評価ができたりすることなどのメリットがあります。特に大きな3つのメリットを知っておきましょう。
3-1. 若手従業員も評価されやすい
職務給では、年功序列のように年齢を基準にした評価はされません。長年勤めている人でも、新入社員でも、同じ職務をしていれば同じ給与になります。
これによって若手従業員のモチベーションを向上できるメリットがあります。若いから、経験が浅いから、などの理由に左右されず、自身の働きや成果に見合う報酬を受け取れるためです。
若手従業員でも成果をあげることで評価され、職能給では得られない給与を年齢にかかわらず得られます。
モチベーション高くして若手従業員が仕事することは、離職率を下げて会社全体の生産性の底上げになるでしょう。
3-2. 評価の公平性を確保できる
職務給では、評価の公平性を確保できるメリットがあります。業務内容に対して給与が決まり、年功序列型や終身雇用型による弊害がなくなるためです。
成果をあげた優秀な従業員に対して、年齢、勤務年数や役職を理由とした不公平な評価はありません。入社時期などにかかわらず、成果次第で正当な報酬を受けられます。
公平な評価は労使間の信頼関係を築き、従業員同士の人間関係の改善にもつながることがあります。また、評価が公平であることが伝われば、向上心を持って業務に励む従業員も増えるでしょう。
3-3. 採用におけるセールスポイントにできる
職務給を導入していることは、採用におけるセールスポイントになります。成果をあげるほど評価につながる職務給は、職能給に不満をもつ優秀な人材を集めやすいでしょう。
職能給の多い日本で、いち早く職務給を導入している企業は、成果主義を望む人材にとって魅力的です。ほかの企業と差別化でき、採用を有利に進められます。
また、「新しい制度に関心が高く、従業員の満足度を考えている企業」というイメージも持たれやすくなります。ホワイトな印象が強くなれば、新卒採用の場面でも有利に働くでしょう。
4. 職務給導入の3つのデメリット
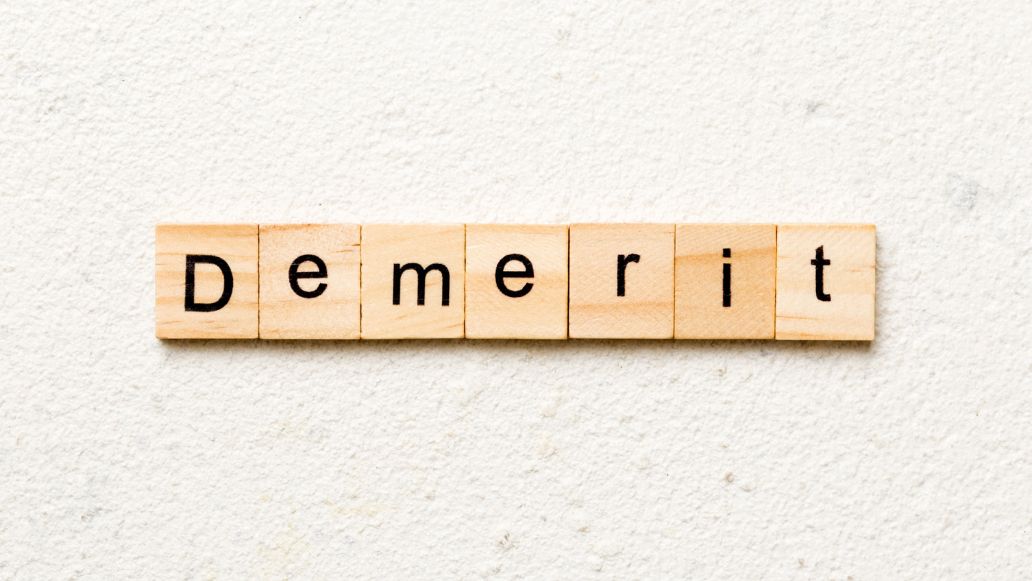
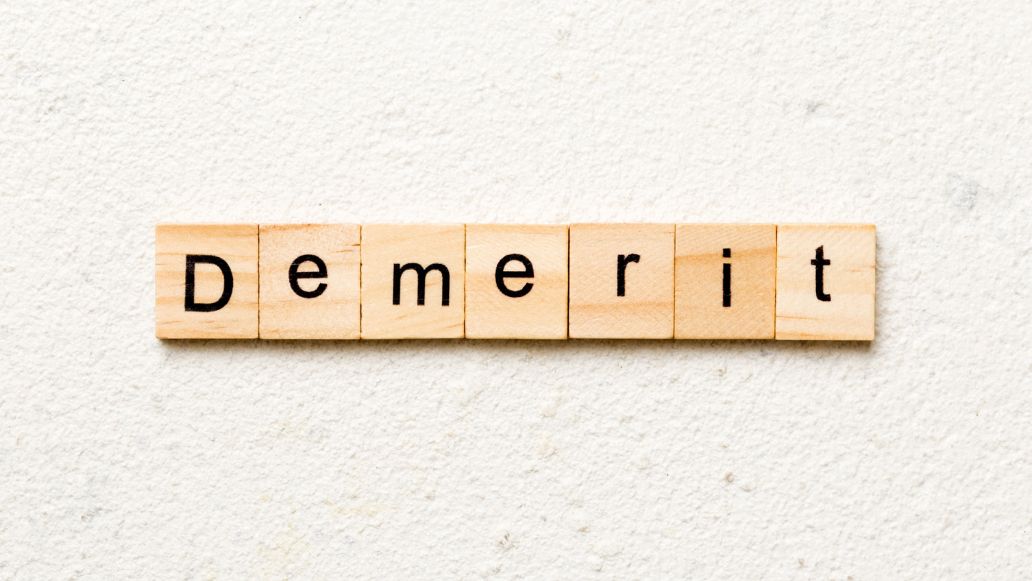
職務給にはモチベーションの向上や人材確保などのメリットがありましたが、課題も残されています。自社で対応できるものか、デメリットを減らすためにできることはあるかなど、十分に検討しましょう。
4-1. モチベーションの低下を招くことがある
職務給は若手や優秀な人材は能力が評価され、モチベーションが高くなります。その結果、さらに良い成果を出して評価を受けるというプラスの循環が生まれやすいです。
しかし、成果を挙げられない従業員は、モチベーションが下がるおそれがあります。自分なりに精一杯仕事をしているにもかかわらず、給与があがらない状況になるためです。
例えば、同時期に入社した従業員同士でも成果の有無により、徐々に差が拡がるでしょう。
上司との面談やスキルアップ支援により成果を出せる支援をおこない、仕事のモチベーションを維持する環境の提供が重要です。
4-2. 従業員から制度に対する不満が出る
従業員から職務給における賃金設定について不満が出かねません。職務給は業務内容によって給与ベースを分けて設定され、賃金設定に差が生じます。
例えば、営業職や専門職の生産部門と事務職の非生産部門で分けた場合です。非生産部門では給与ベースが低いことに加え、成果を挙げての差別化がしにくいため、高い賃金が望めません。
特に、これまでの給与形態から職務給に変更する場合は注意が必要です。職務給を導入する際に業務内容で給与ベースが異なることを説明して理解を得ましょう。
4-3. 評価や給与決定の負担が増える
職務給でおこなう評価は、手間と時間がかかります。従業員の適正な評価のために一人ひとりについて、詳細に成果内容を見て判断するためです。
例えば、営業職の従業員を評価する際は、売上の数字だけでなく、売上内容や顧客満足度結果などのさまざまな面から評価します。評価に必要なデータの収集や分析を要するため、手間と時間がかかり、会社の負担が大きくなるでしょう。
会社は職務給導入に伴い、評価の仕組み作りが必要です。データ収集を効率的におこなうため、ツールなどの導入を検討してみましょう。
5. 職務給制度への移行手順


職務給制度への移行手順は以下のとおりです。
- 給与水準を調査する
- 現行制度を見直す
- 従業員へ説明および周知活動を実施する
- 賃金規定の変更手続きをする
以下でそれぞれの移行作業を解説します。
5-1. 給与水準を調査する
まず、一般的な給与水準や競合他社の給与水準を調査します。現在の雇用情勢や賃金相場を把握し、自社の給与水準と比較するためです。
給与は地域によっても大きな開きがあります。また、これまでの給与形態から変更する場合は、従来の給与水準も無視してはなりません。
厚生労働省から公表されている賃金構造基本統計調査や、民間の研究機関などによる調査結果を参考にするとよいでしょう。
5-2. 現行制度を見直す
調査した給与水準や現在の雇用情勢を参考に、自社の給与制度の見直しをします。給与制度の課題や他社の給与水準とのギャップを把握し、職務給の導入検討をおこないましょう。
見直しした給与制度が自社にあった給与制度であるかの検証とシミュレーションをおこないます。運用後の混乱を避けるため、納得いくまで繰り返しシミュレーションを実施しましょう。
給与形態の変更は従業員から反発が出やすいです。そのため、本当に職務給制度への変更がベストな選択であるか、慎重に判断しなければなりません。
5-3. 従業員へ説明および周知活動を実施する
職務給制度を導入することが決まったら、必ず従業員へ説明および周知活動を実施します。給与は従業員の生活やモチベーションに直結する重要なことであり、詳細な説明を実施して理解させることが必要です。
説明すべき主な内容として以下が挙げられます。
- 職務制度の内容
- 移行する目的
- 今後の運用方法
- 変更点
疑問が残ったままでの制度移行は不満につながりかねません。説明会の開催や専用の問い合わせ窓口の設置が有効でしょう。
会社側が一方的に押し付けるような変更は、従業員から不信感がでてしまい離職や生産性の低下を招くことがあります。十分すぎるほどに従業員へのフォローをおこないましょう。
5-4. 賃金規程の変更手続きをする
従業員から理解を得られたら、職務給制度への変更を実際に進めていきます。新たな給与制度の運用が決まった場合は、賃金規程の変更をすることになります。社内での変更手続きと法的な変更手続きが必要です。
社内では就業規則変更の手続きをおこない、経営陣の承認と従業員代表者による了承を得ます。また、管轄の労働基準監督署へ以下2点の提出が必要です。
- 賃金規程変更届
- 就業規則変更届
いずれも労働基準監督署の窓口に持参する方法や郵送、電子申請などが利用できます。提出期限は定められていませんが、できる限り速やかに手続きをおこないましょう。
6. 職務給制度を導入する際の2つのポイント


職務給を導入することが決まった場合は、以下の3点に注意しましょう。職務給制度はまだ新しい給与形態であるため、企業側の意識の変化やミスのない手続きが求められます。
6-1. 「新卒社員は給与が低い」の認識を改める
職務給では「新卒社員は給与が低い」とは限らないため、認識を改める必要があります。
日本ではこれまで年功序列が当たり前になっていました。そのため、新卒社員はほかの従業員と比べると給与が低いというのが常識になっています。しかし、職務給制度では必ずしもそのようにはなりません。
入社して成果を挙げれば、会社は成果に見合った評価を与え、給与を支払います。職務給では、これまでの新卒社員への給与に対する考えを改めなければなりません。
6-2. 業務内容の変更による減給の可能性を伝える
職務給は業務内容の変更により、減給の可能性があることを伝えましょう。職務給の特徴である業務を基準とした賃金設定は、これまでの給与制度と大きく異なる変更点です。
例えば、営業職から事務職に異動となる場合は、業務内容が生産部門から非生産部門への変更であり、職務給制度では減給を避けられません。
従業員が導入される職務給の特徴を理解していなければ、不満につながる可能性があります。給与制度の移行前に説明することは非常に重要です。
6-3. 給与計算でミスがないように注意する
職務給では従業員一人ひとりの職務に対する評価が必要になります。
年功序列などではそのような評価は不要で、勤続年数や役職などによって給与が決定していました。時間外労働手当や休日出勤手当など以外は、毎月同じ給与が発生していたはずです。
職務給の場合は職務や成果によって毎月給与が変動することもあるため、給与計算が複雑になり負担が増えます。給与計算ソフトを導入していれば業務負担は軽減できますが、そうでない場合は正確な評価に加えて間違いのない給与計算も求められます。
給与の間違いは従業員からの不信感や不安感を高める可能性があります。給与計算が複雑になったとしても、ミスがないように十分に注意しましょう。
7. 職務給制度のメリットや課題を理解して自社に取り入れるか検討しよう


職務給は業務内容を基準とした制度であり、成果を出すことで評価され、給与が上がります。
直近の日本で注目されている同一労働同一賃金の考え方にマッチした評価方法です。成果を挙げている従業員は、成果に見合った評価を受けられるため、モチベーション高く仕事ができます。
職務給を導入する際は、必要なポイントを押さえスムーズな移行をおこない、仕事に対する従業員の向上心アップを図りましょう。



「自社の給与計算の方法に不安がある」「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか心配」など、給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
資料では、労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れをわかりやすく解説しています。
間違えやすい給与の計算方法をおさらいしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28





















