パルスサーベイは意味がない?その理由・効果を上げる方法を解説
更新日: 2024.10.3
公開日: 2022.12.4
OHSUGI

パルスサーベイとは従業員満足度に関連する意識調査の一種です。しかし、パルスサーベイは意味がないといわれてしまうこともあります。
本記事ではパルスサーベイに意味がないといわれやすい理由や、効果的な実施方法について紹介します。
従業員の定着率の低さなどが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. パルスサーベイとは


まずはパルスサーベイがどのような性質や意味を持つものなのか知っていきましょう。混同されやすいエンゲージメントサーベイとの違いも解説します。
1-1. パルスのような頻度で実施する小規模な調査のこと
パルスサーベイは、短時間で変化する脈拍信号を意味するパルスと、調査を意味するサーベイを合わせた造語です。パルスサーベイの特徴は、パルスのように小規模な調査を短いスパンで複数回おこなうことです。
従業員満足度調査や従業員意識調査をはじめとした多くの調査は、たくさんの質問項目を用意した上で行われます。調査のタイミングは年に1回や半年に1回などに設定されるのが一般的です。
パルスサーベイはこういった調査とは異なり、週次や月次といった短いスパンで調査を行います。調査項目は10問以下に設定されることが多く、1~3分程度あれば調査が完了することがほとんどです。短時間で回答できる問題を用意して短期反復型で調査をするため、従業員に負担がかかりにくいのが特徴的です。調査のスパンが短ければ状況をリアルタイムで可視化でき、柔軟なアクションを打ち出すことも可能となります。
1-2. エンゲージメントサーベイとの違い
パルスサーベイとエンゲージメントサーベイの大きな違いが、従業員の状態をリアルタイムで調査するか、長期的な視点で調査するか、にあります。
パルスサーベイはここまでに解説してきたようにパルスのような短期間・短時間で調査を実施し、「今」の従業員の状態を測れます。一方でエンゲージメントサーベイは、特定のタイミングで1年に数回程度実施されるものです。また、実施する目的も少しことなっています。パルスサーベイは従業員個人が抱えている課題や問題を把握することを目的とすることが多いです。
エンゲージメントサーベイでは、従業員全体の状態を把握して改革や新しい施策を実施するための基礎的なデータとして活用することが一般的です。このように、企業として人事データを適切に管理することはとても重要ですが、その先にある活用価値についても、正しく理解できていますか?
当サイトでは、今からでも知っておきたい、基本の「き」として人事データの必要性と活用価値を解説した資料を無料配布しています。人事データの活用で生まれる価値を今一度理解しておきたいという方はこちらから資料をダウンロードの上、ぜひ社内の活用にお役立てください。
2. 「パルスサーベイは意味ない」といわれる理由


パルスサーベイは従業員エンゲージメントの向上に役立てられる手法といわれます。その一方で、パルスサーベイを実施しても意味がない、パルスサーベイでは効果が出にくいといわれることもあります。
パルスサーベイが意味ないといわれてしまうのには、以下のような理由が考えられます。
2-1. 調査がマンネリ化しやすい
何度もパルスサーベイを実施することによって調査がマンネリ化するリスクが考えられます。
頻度の高いパルスサーベイで同じような質問に繰り返し答えさせていると、従業員は調査に飽きてしまいます。中には、質問に対して適当な回答をしてやり過ごしてしまう従業員もいるかもしれません。
こうなってしまうとせっかくパルスサーベイをしても正確な情報を得ることができなくなってしまいます。
パルスサーベイで効果を上げるためには、マンネリ化を防ぐ対策が必要です。
2-2. サイクルが短くストレスになることがある
集計や分析から活用までをスピーディーに行わなければならないのがパルスサーベイの大きな特徴です。
短時間で問題点をピックアップして効果的な対策を打ち出すのは簡単なことではありません。十分な対策ができないまま次の調査を行い、また分析に手間取るという悪循環に陥ると、パルスサーベイの効果は下がってしまいます。
サイクルが確立できないケースでは、従業員に不満が溜まったりモチベーションが低下したりするリスクも考えられます。せっかく調査に協力し問題点を伝えたのに解消されないと従業員が感じ、これがストレスになってしまう可能性があるのです。
2-3. 効果的な調査ができないことがある
パルスサーベイが単なるアンケート調査に終始してしまっては、十分な効果を上げることができません。
パルスサーベイでは、問題解決につながる質問が必ずしもできるとは限りません。せっかく従業員に対する調査の機会を得ても、問題点を洗い出せないような質問をしても意味はないのです。
ウェブサイトからパルスサーベイのツールから質問項目の例をピックアップして活用することも少なくありません。この場合には、ピックアップした設問が本当に自社の問題点を洗い出せるものなのかを十分に考えておく必要があります。
2-4. 質問が多く従業員が負担を感じてしまう
パルスサーベイは小規模な調査を何度も実施する手法です。しかし、効果を上げたいという思いから質問数が多くなってしまい、かえって効果が下がってしまう例があります。
質問が多いと回答に時間がかかり、従業員のほかの仕事に影響が出る可能性が考えられます。毎回のパルスサーベイで同じような状態が続いてしまうと、従業員は大きな負担を抱えてしまいます。
2-5. 頻繁なパルスサーベイで運用が滞ってしまう
パルスサーベイは1回ごとの質問量は少ないものの、調査を高頻度で実施する必要性が生じます。
調査時間の確保、結果の集計、データの分析、課題の抽出やフィードバックといった一連の作業にかかる時間や手間は決して少ないものではありません。何度も調査をすることは、担当者やマネージャーにとって負担となってしまうことがあります。
結果的に、業務が圧迫されて効果的なパルスサーベイができなくなり、調査そのものが意味をなさなくなってしまうケースがあります。このように、パルスサーベイしたにもかかわらず、意味をなしてないように感じるのは、目的を持った調査をおこない、調査結果の活用がうまくできていないからという可能性もあります。調査の効果を実感できていない場合、やり方を見直してみましょう。
当サイトでは、パルスサーベイのように、従業員の状態を把握する「従業員満足度調査」の調査・分析・活用方法をわかりやすく解説した資料を無料でお配りしています。資料では、パルスサーベイ以外の頻度の低い調査についても解説しているので、自社にあった調査方法を知りたい方は、こちらから「従業員満足度のハンドブック」をダウンロードして参考にしてみてください。
3. 意味のあるパルスサーベイを実施するためのポイント


パルスサーベイの意味がないといわれるのは、効果的な運用ができていないためです。パルスサーベイのデメリットを解消して意味のあるパルスサーベイをおこない、フィードバックにつなげていきましょう。
ここからは、パルスサーベイを成功させるポイントについて解説します。
3-1. 目的を明確化する
パルスサーベイを実施する際には、なぜ調査が必要なのかという目的を明確化しましょう。目的を定めることなくパルスサーベイを始めると漠然とした調査になってしまい、分析内容を活かすこともできなくなってしまいます。
パルスサーベイで何を明らかにしたいのか、問題に対してどのような対処をしたいのかが事前に明らかになっていれば、適切な対応ができるようになります。
3-2. 質問の数と項目を精査する
パルスサーベイの効果をアップさせるために、質問数と質問内容を精査しましょう。
質問数が多くなると負担が増し、効果が下がってしまいます。一方で質問数が少なすぎると十分なデータ収集ができず、分析につながらなくなります。
パルスサーベイでは、数分で答えられるいくつかの質問を用意します。業務に関することのほか、職場環境や処遇、人間関係、健康面等に関する質問などを厳選した上で調査を実施しましょう。
3-3. スピーディーにサイクルを回す
パルスサーベイの実施と集計、結果の分析、フィードバックはスピーディーに進めることが大切です。分析やフィードバックが間に合わないと、パルスサーベイの効果は大きく下がってしまいます。
パルスサーベイのスピード感を上げるためには専用ツールの活用が効果的です。
3-4. 専門チームを立ち上げる
パルスサーベイの十分な知識を持ったスタッフでプロジェクトチームを構成するのもいい方法です。
プロジェクトを立ち上げは社内へのアピールにもつながります。会社にいい影響をもたらすチームであるという印象を与え、従業員の関心を引き付けながら調査を進めていきましょう。
4. 効率的で正確なパルスサーベイを実施して企業発展につなげよう


パルスサーベイとは短いスパンで小規模な調査を繰り返す手法のことです。パルスサーベイは意味がないといわれることがありますが、これは調査の実施や分析が適切にできないケースがあるためです。
質問内容を精査したりスピーディーな分析やフィードバックを展開したりと工夫すれば、パルスサーベイの効果は高まりやすくなります。専用ツールを使うなど実施方法を工夫し、パルスサーベイの効果を高めていきましょう。
従業員の定着率の低さなどが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
サーベイの関連記事
-

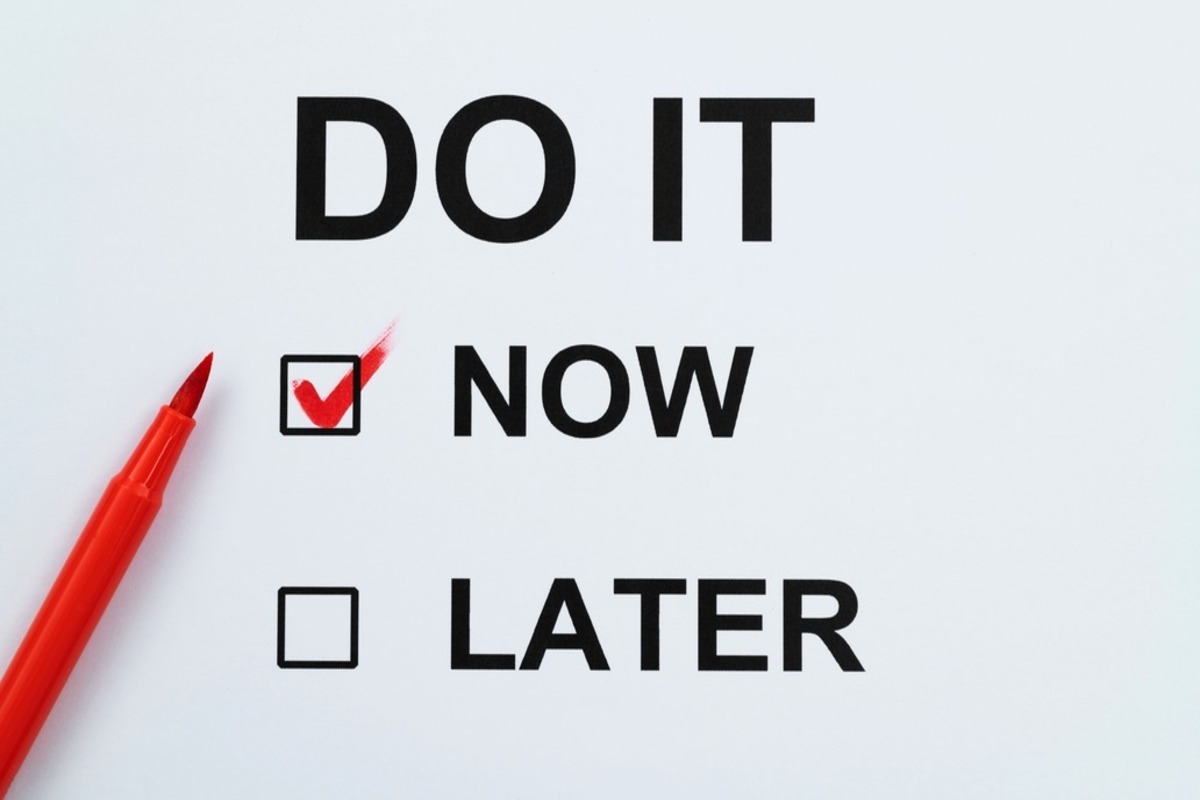
モチベーションサーベイの導入手順や実施方法を解説
人事・労務管理公開日:2023.06.17更新日:2024.01.16
-


エンゲージメントサーベイは無駄で意味がない?解決策とメリットを解説!
人事・労務管理公開日:2023.06.15更新日:2024.10.16
-


エンゲージメントシステムとは?メリットと選び方を解説
人事・労務管理公開日:2023.06.14更新日:2024.01.26






















