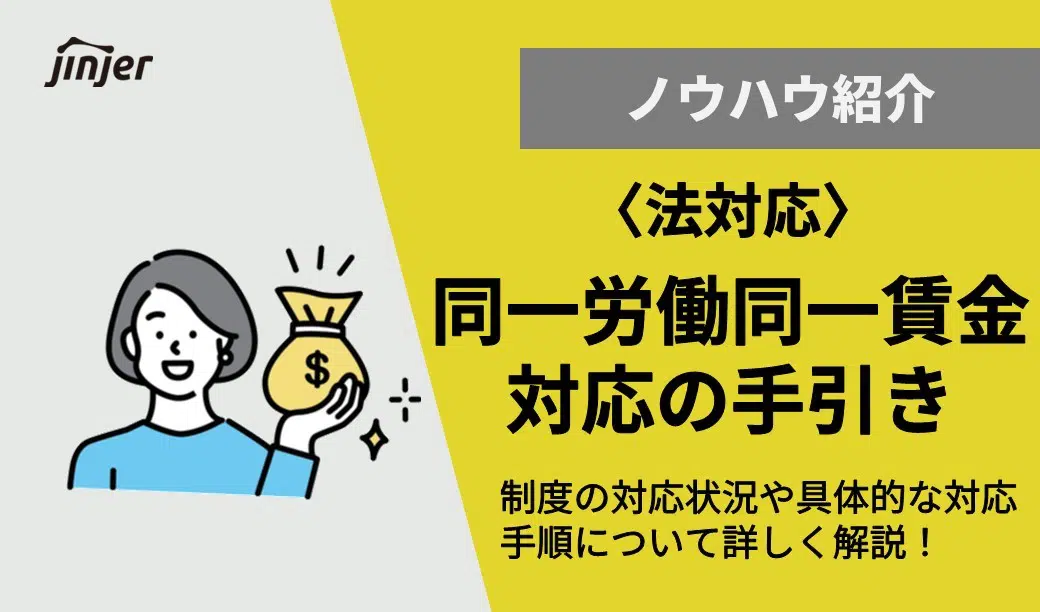同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2022.1.22
OHSUGI

働き方改革の一環として、雇用形態によらず労働者の待遇を均等・均衡化する「同一労働同一賃金」の実施がスタートしました。
同一労働同一賃金の対象には、大企業だけでなく中小企業もふくまれます。
しかし、中小企業の同一労働同一賃金の実施状況は芳しくありません。
中小企業庁の「2021年版中小企業白書」を見ると、従業員規模が少ないほど同一労働同一賃金の実施率が低くなっていることがわかります。従業員数6~20人の企業の場合、同一労働同一賃金について「十分に理解している」割合は全体の36.2%。従業員数0~5人の企業では、わずか26.5%にとどまります。
この記事では、同一労働同一賃金における中小企業の定義や、中小企業が影響を受けるポイント、同一労働同一賃金に対応しないリスクについてわかりやすく解説します。
▼そもそも「同一労働同一賃金とは?」という方はこちら
同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて
目次
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 同一労働同一賃金にいつから対応すればいい?
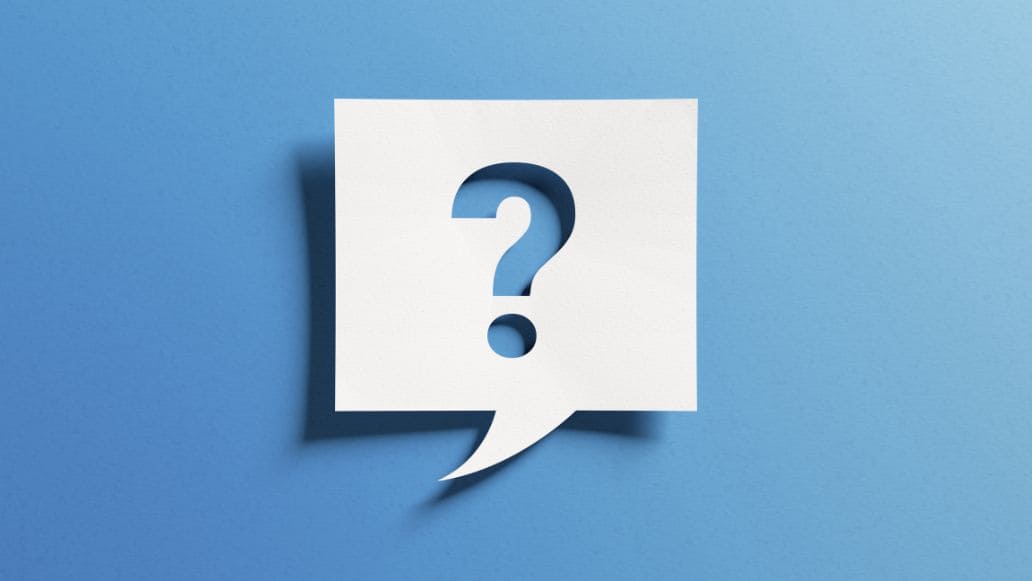
同一労働同一賃金は2020年4月1日から施行されおり、中小企業・大企業問わずに対応しなければなりません。
ただし中小企業のパートタイム・有期雇用労働者については、2021年まで「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されていませんでした。そのため、中小企業のパートタイム・有期雇用労働者に同一労働同一賃金が適用されたのは2021年4月からです。
2024年現在では、大企業・中小企業ともにすべての労働者に対して同一労働同一賃金が適用されています。中小企業だけ猶予期間が設けられている制度もあるため、混同しないように注意しましょう。
対応がまだできていない、不安がある場合などは再度チェックをおこなって問題があればできるだけ早急に対応をしましょう。
2. 同一労働同一賃金で中小企業はどう変わった?4つの影響を解説

同一労働同一賃金の導入により、中小企業のあり方は大きく変わりました。
中小企業はまず、基本給・賞与・各種手当・福利厚生や教育訓練の4点について、不合理な待遇差を是正しなければなりません。
同一労働同一賃金の中小企業への影響を詳しくみていきます。
2-1. 4つの不合理な待遇差を是正する必要がある
同一労働同一賃金の実現に向けて、まず厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を参照しましょう。
厚生労働省のガイドラインによると、企業は「基本給」「賞与」「各種手当」「福利厚生・教育訓練」の4つの不合理な待遇差をなくす必要があります。
| 基本給 | 実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなう |
| 賞与やボーナス | 同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなう |
| 各種手当 |
役職手当は同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなう その他の手当についても、支給条件が同一の場合は同一の支給をおこなう |
| 福利厚生や教育訓練 | 福利厚生や教育訓練は、雇用形態に関わらず、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施・付与をおこなう |
参考:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲|厚生労働省
関連記事:同一労働同一賃金で賞与はどうなる?就業規則や罰則についても解説
関連記事:同一労働同一賃金で各種手当はどうなる?最高裁判例や待遇差に関して
関連記事:同一労働同一賃金における福利厚生の待遇差や実現するメリットとは
2-2. 労働者の待遇差への説明責任が生じる
また、同一労働同一賃金の導入により、非正規雇用労働者は正社員との待遇差について企業に説明を求めることができるようになります。
労働者への説明責任を果たすため、「なぜ待遇差が設けられているか」「なぜ待遇差が不合理なものではないか」を整理しておきましょう。
関連記事:同一労働同一賃金の説明義務はどう強化された?注意点や説明方法も解説
2-3. 人件費が高騰する可能性がある
正社員との待遇差を解消するため、非正規雇用労働者の待遇を引き上げる場合、人件費が高騰する可能性があります。基本給・賞与・各種手当だけでなく、福利厚生や教育訓練も拡充する場合、一時的なコスト増が中小企業の課題となります。
同一労働同一賃金を実現するため、正社員の待遇を引き下げるのは望ましい対応ではありません。
厚生労働省のガイドラインでも、「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」としています。
非正規雇用労働者の正社員化や、各種手当の共通化によって待遇差を解消する場合は、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」などを活用し、コストの負担を抑えることが可能です。
参考:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲|厚生労働省
2-4. 人事制度を整備するための工数が増える
厚生労働省のガイドラインによると、総合職・エリア総合職・一般職など、複数の雇用管理区分が存在する場合も、雇用管理区分ごとに同一労働同一賃金を実現しなければなりません。
そのため、人事制度を整備するための工数が一時的に増加する可能性があります。
同一労働同一賃金の実施に向けて、どのように人事制度を構築すればよいかわからない場合は、各都道府県の「働き方改革推進支援センター」を相談先として利用できます。
3. 同一労働同一賃金の対象となる企業と従業員

すべての企業が同一労働同一賃金の対象になるとお話をしましたが、資本金や労働者数によっては会社が中小企業に分類されないことがあります。
その場合は同一労働同一賃金の対象にもならないため、自社が中小企業に該当するのか確認しておきましょう。
3-1. 同一労働同一賃金の対象になる中小企業
同一労働同一賃金の対象になる中小企業として認められるのは、以下のような条件を満たす企業です。
| 業種 | 資本金の額、または、出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | |
| その他(製造業、建築業、運送業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
このように業種によって中小企業として認められる条件が異なります。
自社の業種・資本金・労働者数を今一度確認し、中小企業に該当している場合は同一労働同一賃金に対する認識を正しくしておきましょう。
3-2. 同一労働同一賃金が適用される従業員
前述した中小企業に該当する企業に雇用されている従業員は、雇用形態を問わずに同一労働同一賃金の対象になります。
パートタイムやアルバイト、有期雇用など、雇用形態を問わず適用されます。
パートだから、アルバイトだから、という理由で同じ労働をしているのに賃金に差をつけてはいけません。違法になる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
4. 同一労働同一賃金の対応をそのままにしておく2つのリスク

同一労働同一賃金の導入により、中小企業は人件費の高騰や、人事制度の整備のための工数増加といった影響を受けます。
しかし、同一労働同一賃金の実現に時間やコストがかかるからといって、対応を先延ばしにすると思わぬ失敗をする可能性があります。
原則として、同一労働同一賃金に違反しても罰則はありません。しかし、正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差をそのままにしていると、企業は2つのリスクを抱えます。
4-1. 同一労働同一賃金に違反しても罰則はない
同一労働同一賃金に関連する法律として、2020年4月1日施行の「パートタイム・有期雇用労働法」があります。
パートタイム・有期雇用労働法には、企業が同一労働同一賃金に違反した場合の罰金や科料が明記されていません。そのため、企業が不合理な待遇差を設けたとしても、パートタイム・有期雇用労働法によって取り締まりされることはありません。
ただし、悪質な企業に対しては、行政より指導・勧告が行われる可能性があります。
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法の内容を分かりやすく解説
4-2. 同一労働同一賃金に違反した場合の2つのリスク
また、同一労働同一賃金に対応せず、そのままにしておいた場合、企業は次の2つのリスクを抱えます。
- 非正規雇用労働者の採用や定着率への悪影響
- 不合理な待遇差をきっかけとして民事訴訟に発展する可能性
正社員と非正規雇用労働者の間に不合理な待遇差がある企業は、採用や定着率に悪影響が生じるリスクがあります。また、不合理な待遇差をきっかけとして、労働者が民事訴訟を起こすリスクにも注意が必要です。
もし裁判所において不合理な待遇差があると認められた場合、正社員と非正規雇用労働者の賃金の差額の支払いや、損害賠償の支払いが発生する可能性があります。
同一労働同一賃金に違反した場合の罰則がないからといって、同一労働同一賃金に対応しないと、上記のリスクを抱えることを知っておきましょう。 当サイトでは、同一労働同一賃金におけるリスク対策として、企業が対応すべきことを図を用いて解説した資料を無料で配布しております。
自社の対応に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「同一労働同一賃金 対応の手引き」をダウンロードしてご確認ください。
5. 中小企業は同一労働同一賃金の実現を目指して早めに対応を進めよう

2021年4月より、同一労働同一賃金が中小企業にも適用されました。
中小企業は大企業同様、「基本給」「賞与」「各種手当」「福利厚生・教育訓練」の4つの観点から、不合理な待遇差を見直す必要があります。
同一労働同一賃金の根拠となる「パートタイム・有期雇用労働法」には、同一労働同一賃金に違反した場合の罰則は明記されていません。しかし、非正規雇用労働者の採用や定着率への悪影響や、民事訴訟に発展する可能性を考慮し、中小企業であっても同一労働同一賃金の考え方を深く理解することが大切です。
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法に定められた罰則の詳細を解説
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08