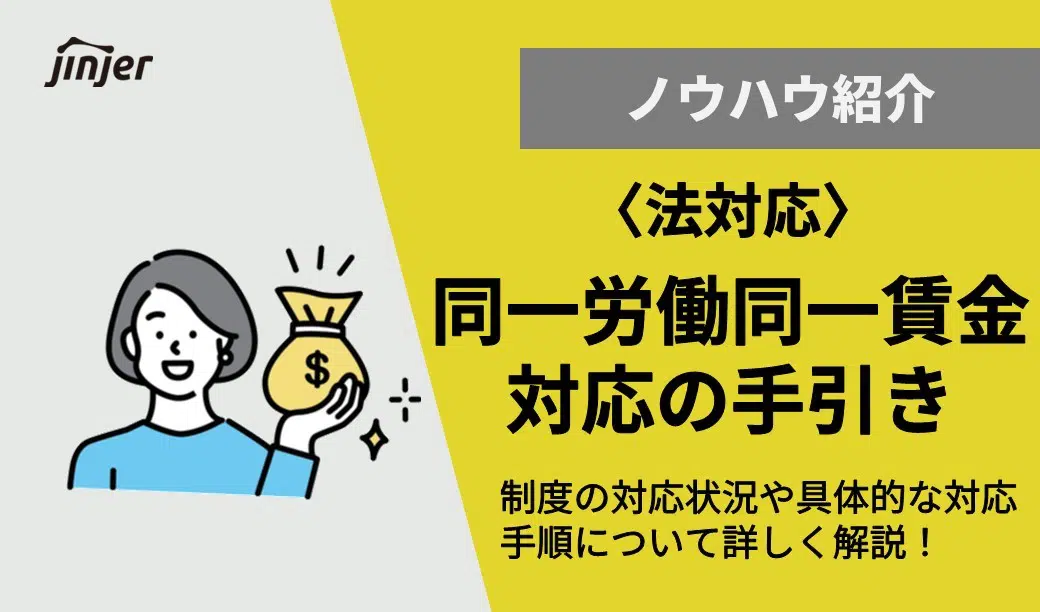同一労働同一賃金で各種手当はどうなる?最高裁判例や待遇差に関して
更新日: 2024.4.24
公開日: 2022.1.24
OHSUGI

同一労働同一賃金の導入により、大企業・中小企業を問わず、正社員と非正規雇用労働者の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されました。不合理な待遇差には、基本給や賞与だけでなく、通勤手当や精皆勤手当などの各種手当もふくまれます。
しかし、短時間労働者と正社員の両方を雇用している事業場において、まだまだ各種手当の支給状況に格差が見られるのが現状です。
厚生労働省が2016年にまとめた「パートタイム労働者総合実態調査(事業所調査)」によると、正社員の70.6%が役職手当を受け取っているのに対し、短時間労働者の受給率は7.3%。精皆勤手当についても、正社員の受給率が20.7%であるのに対し、短時間労働者の受給率は5.8%にとどまります。
この記事では、同一労働同一賃金における各種手当の考え方や、各種手当の待遇差に関する最高裁判例、待遇差の是正に向けたポイントをわかりやすく解説します。
参考:パートタイム労働者総合実態調査(事業所調査)|厚生労働省
▼そもそも「同一労働同一賃金とは?」という方はこちら
関連記事:同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて
目次
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 同一労働同一賃金の導入により、各種手当の支給はどう変わる?

同一労働同一賃金の導入により、企業は均衡待遇・均等待遇の2つの原則に基づき、正社員とそれ以外の労働者の不合理な待遇差を是正する必要があります。
| 均衡待遇 | 待遇の違いを設ける場合は、職務の内容や配置転換の有無といった事情を考慮し、不合理と認められない範囲でおこなうこと |
| 均等待遇 | 業務の内容や配置転換の有無といった事情が同一の場合は、雇用形態によって差別的取り扱いをせず、同一の待遇を設けること |
通勤手当や精皆勤手当などの各種手当についても、均衡待遇・均等待遇の考え方を前提として、支給の内容を見直す必要があります。
厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、各種手当の支給方法の具体例が説明されています。
| 役職手当 | 同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなう |
|
特殊作業手当 |
同一の支給要件を満たす場合は、同一の支給をおこなう |
各種手当の待遇差を設ける場合は、職務の内容や配置転換の有無といった事情に基づき、待遇差の理由が合理的であるかどうかを必ず確認しましょう。
また、退職手当や住宅手当、年末年始手当など具体例にはない手当に関しても、同様に合理的であるかの確認が必要です。
関連記事:同一労働同一賃金で交通費はどうなる?判例や課税について解説
2. 同一労働同一賃金に関する最高裁判例を2つ紹介

同一労働同一賃金の原則に違反し、各種手当に不合理な待遇差を設けた場合、労働者からの損害賠償請求訴訟に発展する可能性があります。実際に最高裁判例を紐解くと、各種手当の待遇差が不合理であると認められたケースもあります。
ここでは、同一労働同一賃金に関する最高裁判例を2つ紹介します。
2-1. 第2099号、第2100号・未払賃金等支払請求事件
「第2099号、第2100号・未払賃金等支払請求事件」は、運送会社で働く契約社員(有期雇用労働者)が、正社員との間の各種手当等の待遇差が不合理であるとして、未払賃金等の支払請求をおこなった事件です。
最高裁判所の判決では、原告が訴えた6つの手当のうち、5つの手当について不合理な待遇差があると認めました。
| – | 判決理由 |
| 無事故手当 | 正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、安全運転や事故防止の必要性は同等と考えられる |
| 作業手当 | 正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、作業に対する金銭的評価は同等と考えられる |
| 給食手当 | 正社員と契約社員の職務の内容が同じである限り、勤務時間中に食事をとる必要がある労働者に対し、同等の給食手当を支給すべき |
| 皆勤手当 | 正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、皆勤を奨励する度合いも同等と考えられる |
| 通勤手当 | 労働契約に期間の定めがあるかどうかによって、通勤に必要な費用が異なるわけではない |
参照:同一労働同一賃金について ~雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保~|厚生労働省
2-2. 第442号・地位確認等請求事件
「第442号・地位確認等請求事件」は、運送会社で働く嘱託乗務員(定年退職後に再雇用)が、正社員との間の不合理な待遇差を訴えた事件です。
最高裁判例では、2つの手当について不合理な待遇差があると認めました。
| – | 判決理由 |
| 精勤手当 | 職務の内容が異ならない限り、雇用形態によらず、精勤・皆勤を奨励する必要性は変わらない |
| 超勤手当 (時間外手当) |
精勤手当についての判断に従い、時間外手当の算定基礎に精勤手当を含めなければならない |
このように最高裁判例を見ると、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」で示されていない手当についても、不合理な待遇差が問題となっています。
必要に応じて労働者の意見を聴取しながら、自社の賃金体系に不合理な待遇差が存在しないかどうか個別具体的に確認していくことが大切です。
参照:同一労働同一賃金について ~雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保~|厚生労働省
関連記事:同一労働同一賃金の問題点と日本・海外との考え方の違い
3. 不合理な待遇差は対応が必須!同一労働同一賃金への3つの対応ポイント

同一労働同一賃金の原則は、2020年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」に基づきます。
パートタイム・有期雇用労働法には、同一労働同一賃金に違反した場合の罰則は明記されていません。しかし、前述の訴訟リスクを考慮すると、不合理な待遇差は早急に解消する必要があります。
ここでは、同一労働同一賃金への対応に向けた3つのポイントを解説します。
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法の内容を分かりやすく解説
関連記事:労働者派遣法とは?内容や罰則が科されるケースについて解説
3-1. 待遇差がある理由を明確化する
まずは短時間労働者や有期雇用労働者など、パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者をリストアップしましょう。
労働者の区分ごとに待遇差がある場合は、「なぜ待遇差があるのか」「職務の内容や配置転換の有無といった事情に基づき、待遇差が不合理ではないか」を明確化します。もし不合理な待遇差が存在する場合は、ただちに社内ルールを見直し、法違反の状況から早期の脱却を目指す必要があります。
なお、自社の待遇が法律に対応しているかを簡易的にチェックできるツールが、厚生労働省のホームページ上に用意されています。このようなツールも活用し、事前に点検をおこなうと良いでしょう。
3-2. 労働者に対し待遇差について説明できるようにする
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とそれ以外の労働者の待遇差について、企業が労働者に説明をおこなう義務が定められています。
たとえば、非正規雇用労働者の雇入れ時や、労働者側から求めがあった場合、待遇差についてすみやかに説明できるようにしておくことが大切です。
もし労働者の区分ごとに待遇差がある場合は、その待遇差が不合理ではないことを説明できるよう、要点を整理しておきましょう。あらかじめ待遇差の理由をまとめた説明文書を作成しておけば、労働者から説明を求められた際に便利です。
関連記事:同一労働同一賃金の説明義務はどう強化された?注意点や説明方法も解説
3-3. 厚生労働省の助成金の利用を検討する
非正規雇用労働者の手当を増額し、不合理な待遇差を解消する場合、一時的に人件費が増額する可能性があります。その場合、厚生労働省の助成金の利用を検討しましょう。
4. 同一労働同一賃金を正しく理解し、各種手当の支給方法の見直しを図ろう

同一労働同一賃金では、基本給や賞与だけでなく、各種手当の不合理な待遇差をなくすことも求められます。
実際に最高裁判例を見ると、「第2099号、第2100号・未払賃金等支払請求事件」「第442号・地位確認等請求事件」など、各種手当の待遇差をめぐる訴訟も提起されています。均衡待遇・均等待遇の2つの原則に基づき、正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消することが大切です。
同一労働同一賃金の導入により、企業は労働者に対し、待遇差が設けられた理由について説明する義務も生じました。同一労働同一賃金の考え方を正しく理解し、各種手当の支給方法の見直しをおこないましょう。
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08