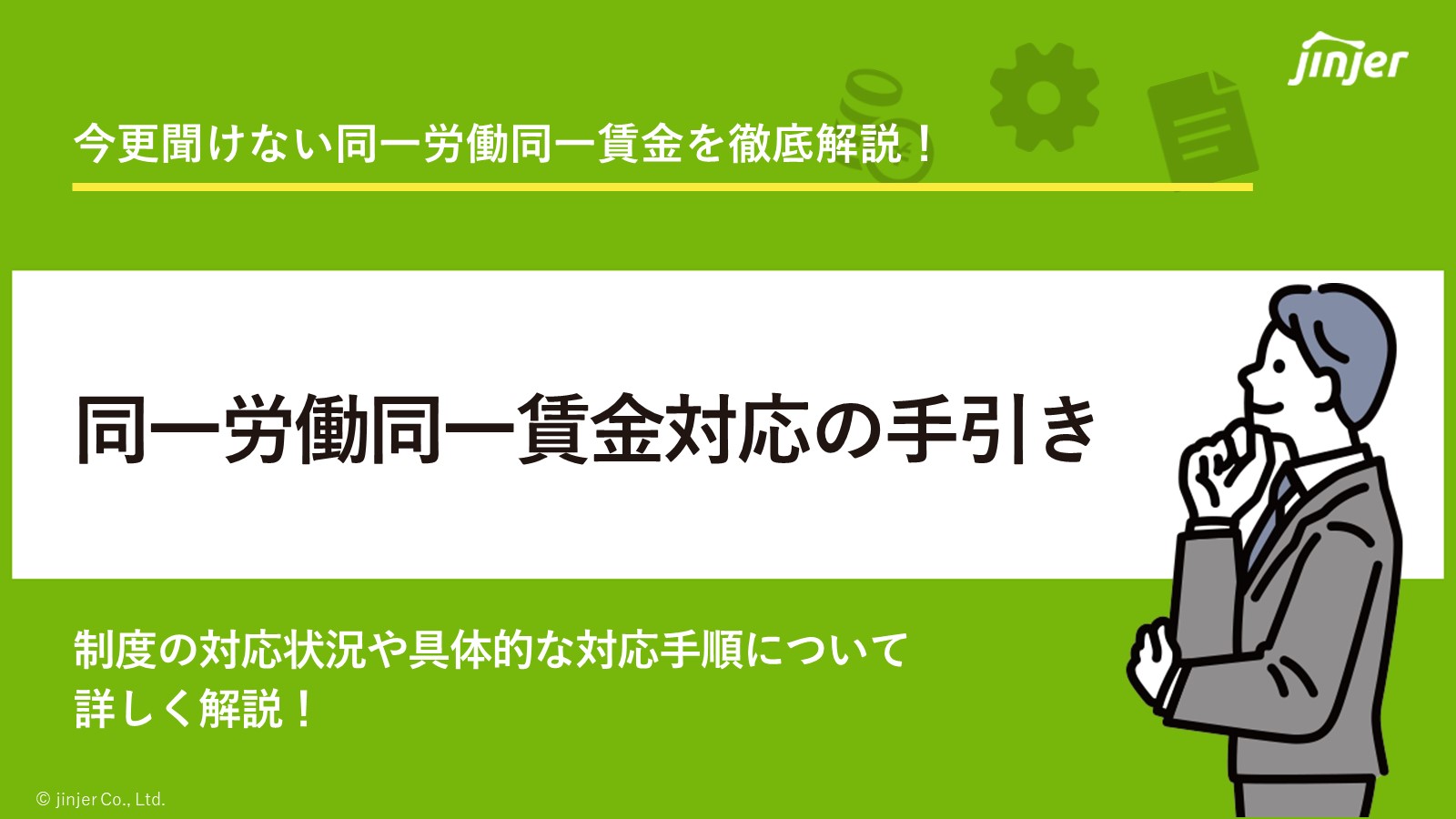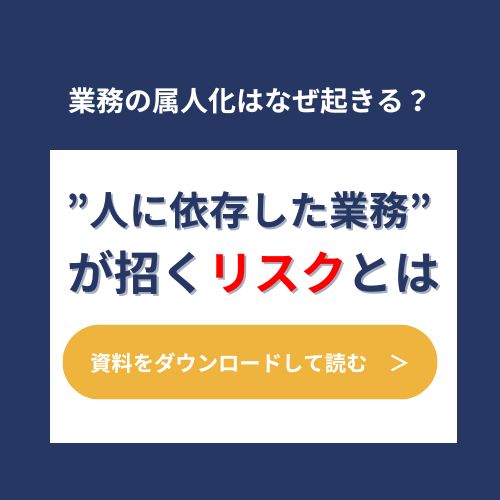労働者派遣法とは?内容や罰則が科されるケースについて解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2021.11.25
jinjer Blog 編集部

労働者派遣法を施行当時と現在のものとで比較すると、大きな変化を遂げています。
とくに最近では、派遣労働者保護のための規制強化が主な目的となっており、適切な人事をおこなうためには、労働者派遣法の改正点をしっかり抑えて対応していくことが重要です。
この記事では労働者派遣法が改正されていった歴史や経緯、改正のポイント、違反した場合にどうなるのかなどといったことについてわかりやすく説明します。
2021年4月に法改正され、すべての企業に同一労働同一賃金が適応されましたが、
「具体的にはどのような法律で、対応せずにいると、どのような罰則があるのか、実はイマイチわかっていないけど、時間の経過と共に今更聞けない…」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、そのような方のために「今更聞けない同一労働同一賃金について」わかりやすく解説したガイドブックを無料で配布しております。法律に則って同一労働同一賃金の対応をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
1. 労働者派遣法とは?


この法律が成立するまで人材派遣は禁止されていましたが、これ以降は人材派遣が認められるようになり、派遣労働という形が急速に広がっていくことになります。
施行当初は人材派遣の基盤を整備するのが、労働者派遣法の主な目的でしたが、2012年の改正以降は派遣労働者を保護する色彩が強くなってきました。労働者派遣法が改正されていった流れとしては「人材派遣解禁→規制緩和→規制強化」というものになっています。
2. 労働者派遣法の変遷・ポイント


労働者派遣法は1986年の施行以来、数々の改正を経てきました。ここでは主な改正点について説明していきます。
2-1. 1986年
まず施行時の状態について説明します。法律ができたときに人材派遣が認められた業務は13業務で、施行と同時に16業務になりました。派遣期間の上限は1年です。
2-2. 1996~2007年
1996年に対象業務が26業務へ拡大されました。これらの業務は政令26業務と呼ばれています。
そして1999年に対象業務が原則自由化され、派遣期間の上限は政令26業務が3年、それ以外のものは1年とされました。
2000年には直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」が解禁。2004年には要望の多かった製造業への派遣が解禁されました。また派遣期間の上限について、政令26業務が無期限に、1999年に解禁されたものは3年に緩和。1999年の改正と2004年の改正により人材派遣は一気に加速していきます。
2006年には一部の医療業務が解禁。翌2007年には製造業の派遣期間上限が3年に緩和されました。
2-3. 2012年
2012年は大きな改正がなされた年でした。
まず法律名が現在のものに変更され、派遣労働者の保護が強く謳われるようになりました。
それまでの緩和路線から規制路線へと流れが変わった理由は、リーマン・ショック後の派遣切りや雇い止めが社会問題化したためです。主な改正点について説明します。
離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止
直接雇用だった従業員を派遣労働者に切り替えて人件費を削減する手口が散見されました。そういったやり方を防ぐために作られた規制です。
日雇い派遣の原則禁止
30日以内の日雇い派遣が原則として禁止されました。日雇い派遣は労働条件が不安定で、ワーキングプアが急増した要因の一つと考えられたからです。
しかしソフトウェア開発や機械設計など政令で定める業務、60歳以上の人や主たる生計者でない人など一部では例外が認められています。
グループ企業に対する派遣規制
グループ内に派遣会社を作り、そこからグループ内企業へ派遣労働者を送り、正社員の代替として人件費を減らす事例が見られたことから、グループ企業への派遣は8割以下にするように規制がかけられました。
2-4. 2015年
2015年の改正では、さらなる労働者保護のための改正がおこなわれています。
届出制を廃止して許可制のみに
それまでの派遣事業者は許可制の一般労働者派遣事業と届出制の特定労働者派遣事業の2種類がありましたが、この改正で届出制は廃止されました。これは許可のいらない特定労働者派遣事業を装って、実際には一般労働者派遣事業をおこなっていた事業者が存在するなどしていたためです。
派遣期間の上限を一律3年に
2004年の改正で、政令26業務の派遣期間上限は無期限になりましたが、この上限を再び3年とすることになりました。その理由は政令26業務の判断が複雑であったことや、この制度を悪用して半永久的に派遣社員として雇い続ける事業者へ対抗する必要などがあったからです。
しかしこの改正は、政令26業務の派遣労働者が一斉に雇い止めになる可能性をはらんだ、2018年問題の要因になってしまいました。
労働契約の申込みみなし制度
労働契約の申込みみなし制度とは、違法と知りながら派遣労働者を受け入れたら、派遣会社と同一の労働条件とする契約申し込みをしたとみなすことです。つまり違法に派遣労働者を受け入れたら、派遣ではなく直接雇用義務が発生するというものです。
雇用安定措置
派遣元は労働者の雇用継続についての措置を講ずることを義務付けられました。派遣期間の終了とともに、雇い止めになるケースが多く発生したことが理由です。措置としては「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「派遣元での無期雇用」が挙げられます。
2-5.2020年
2018年に施行された「働き方改革関連法」に基づき労働者派遣法も改正されました。これまでの大きな問題だった派遣労働者と直接雇用労働者の待遇差を埋めるべく「同一労働同一賃金」が謳われています。同一賃金とは単純に賃金だけを指すのではなく、福利厚生や教育機会なども含むものです。主な改正点を2つ紹介します。
公正な待遇確保
公正な待遇を確保するための賃金決定方式として、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2つが定められました。
派遣先均等・均衡方式は派遣先の労働者と比較して待遇が均等・均衡になるようにすることです。一方の労使協定方式は派遣会社と労働者代表との労使協定で賃金が決められる方式です。この賃金は「一般労働者の平均的な賃金」以上が支払われなくてはなりません。多くの派遣事業者は労使協定方式を選んでいます。
2-6. 2021年
2021年1月の改正では派遣労働者への説明義務のほかに、次のような点が明記されました。
- 労働者派遣契約にかかわる事項の電磁的記録での作成
- 派遣先企業での派遣社員からの苦情処理
- 日雇い派遣について
なお、2021年は4月にも次のように改正されています。
- 派遣社員への希望の聴取
- 常時インターネットでの情報提供
派遣労働者への説明義務
待遇に関する情報について「派遣労働者を雇い入れた時」「派遣した時」「派遣労働者から求めがあった場合」にそれぞれ説明をする義務が課せられました。
労働者派遣契約にかかわる事項の電磁的記録での作成
法改正以前は労働派遣契約にかかわる書類は書面での交付が義務付けられていました。しかし、e-文書法が改正されたことで、電子メールをはじめとした電磁的記録での作成~交付も可能になっています。
派遣先企業での派遣社員からの苦情処理
派遣社員から出る苦情の処理は派遣会社が担当していました。しかし、法改正によって派遣社員からの苦情処理は派遣先企業側が担うことになっています。なお、派遣先企業が処理を担う苦情は派遣先が責任を負う、労働時間や休憩など労働関係法令上の義務についてです。派遣先企業は苦情処理についての責任者を設置する必要があります。
日雇い派遣について
2021年の改正では日雇い派遣についても変更が生まれています。改正によって派遣先、派遣元の都合で契約が解除になった場合、派遣元は新たに就業機会を確保する義務が生まれました。もし、新たな派遣先を確保できなかった場合、休業手当をはじめ、労働基準法に基づく責任を果たす必要があります。
派遣社員への希望の聴取
派遣元は派遣社員に対して、次のような情報をヒアリングする必要があります。
- 派遣先での直接雇用
- 別の派遣先を紹介
- 派遣元での無期雇用
- 紹介予定派遣などその他雇用を安定する措置
これらの情報をヒアリングしたら派遣元管理台帳に記載が必要です。
常時インターネットでの情報提供
派遣元の会社は情報提供の義務があります。法改正によって情報は常時インターネットで提供することが義務付けられました。そのため、派遣元は次のような情報をインターネットで提供が必要です。
- 派遣労働者の数
- 派遣先の数
- 派遣料金の平均額
- 派遣労働者の賃金の平均額
- マージン率
- 労使協定を締結しているか否かの別等
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
3. 労働者派遣法の注意点


労働者派遣法が改正されたことによって、派遣労働については次のような注意点が発生しています。
- 日雇派遣は禁止
- 二重の派遣は禁止
- 同一労働に対しては同一賃金
- 派遣契約期間には制限がある
- 特定の派遣労働者を雇うことは禁止
- 労働に関する法律の適用
- 派遣契約を解除する際も注意
- 離職から1年以内の労働者は受け入れない
3-1. 日雇派遣は禁止
労働派遣法が改正されたことで、日雇派遣は原則禁止されています。日雇派遣は1日もしくは30日以内の期間での派遣を指します。法改正によって1日だけの派遣や30日以内の派遣といったような日雇派遣を原則認められていません。そのため、派遣社員を受け入れるのであれば31日以上の受け入れが必要です。
3-2. 二重の派遣は禁止
二重の派遣とは派遣元から受け入れた派遣社員を、さらに他の企業に派遣して二重派遣先の指揮命令で勤務させることを指します。二重派遣されてしまうと、派遣社員の雇用についての責任の所在があいまいになってしまいます。そのため、給与をはじめ、派遣社員を適切に保護できなくなってしまうかもしれません。このような理由から二重派遣は違法行為とされ、禁止されています。
3-3. 同一労働に対しては同一賃金
先述のとおり、派遣労働者が正規雇用者と同じ労働をしている場合、同一の賃金を支払う義務があります。なお、同一労働同一賃金については派遣労働者だけに限りません。アルバイトやパートといった非正規雇用者であっても、同一労働同一賃金を適用しなければなりません。
3-4. 派遣契約期間には制限がある
派遣労働者を受け入れた場合、期間に制限が設けられています。派遣労働者を3年を超えて就業させることは認められていません。3年を超えて就業を希望するのであれば、労働者の過半数で組織されている過半数労働組合などへのヒアリングを実施するか、直接の雇用にするかが求められます。
3-5. 特定の派遣労働者を雇うことは禁止
派遣労働者を受け入れる際は特定の労働者を雇うことが禁止されています。例えば受け入れる前に履歴書を提出してもらう、面接を実施するといった行為は認められません。
3-6. 労働に関する法律の適用
派遣労働者も正規雇用者と同じく、労働に関する法律が適用されます。そのため、労働基準法や労働安全衛生法といった法律を遵守する必要があります。もし、長時間労働のように労働についての法律違反が発生した場合、派遣労働者を受け入れた企業が責任を負います。
3-7. 派遣契約を解除する際も注意
派遣契約を解除する際は、派遣労働者の新たな勤務先を探す必要があります。そのため、派遣労働者の受け入れ企業は人材派遣会社と協力して、新たな勤務先を探すようにしましょう。例えば関連会社で派遣労働者を受け入れるといった対策を講じる必要があります。
3-8. 離職から1年以内の労働者は受け入れない
企業は自社を退職した従業員を、1年以内に派遣労働者として受け入れることはできません。例えば退職して半年しか経過していない元従業員を派遣労働者として受け入れることは認められていません。しかし、60歳以上の定年退職者であれば派遣労働者として受け入れ可能です。
4. 労働者派遣法を違反した場合


これにより改善されれば追加の処分はありませんが、改められなければ改善命令が出されます。
口頭指導や文書指導との違いは、改善がなされるまで労働局により指導監督があることです。
重大な違反があったり、違反を繰り返したりした場合は、事業停止命令が出されることがあります。これにより新たな人材派遣ができなくなりますが、すでに派遣している労働者はそのまま労働可能です。改善命令や事業停止命令に違反するほか、許可の取消事由に当たることをしてしまうと、派遣事業許可が取り消されます。
このほかに悪質な違反は刑事告発されることもあり、この場合に立件されて有罪になると刑事罰も受けることになります。
関連記事:労働者派遣法に違反する行為とは?知っておくべき罰則規定
5. 労働者派遣法を理解して時代に対応していこう


関連記事:労働者派遣法第40条の2第4項に定められた期間制限について解説
関連記事:労働者派遣法第30条の4第1項とは?その内容や注意点を解説
関連記事:労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定とは?
関連記事:労働者派遣法26条による労働者派遣契約の内容や注意点を解説
2021年4月に法改正され、すべての企業に同一労働同一賃金が適応されましたが、
「具体的にはどのような法律で、対応せずにいると、どのような罰則があるのか、実はイマイチわかっていないけど、時間の経過と共に今更聞けない…」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、そのような方のために「今更聞けない同一労働同一賃金について」わかりやすく解説したガイドブックを無料で配布しております。法律に則って同一労働同一賃金の対応をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08