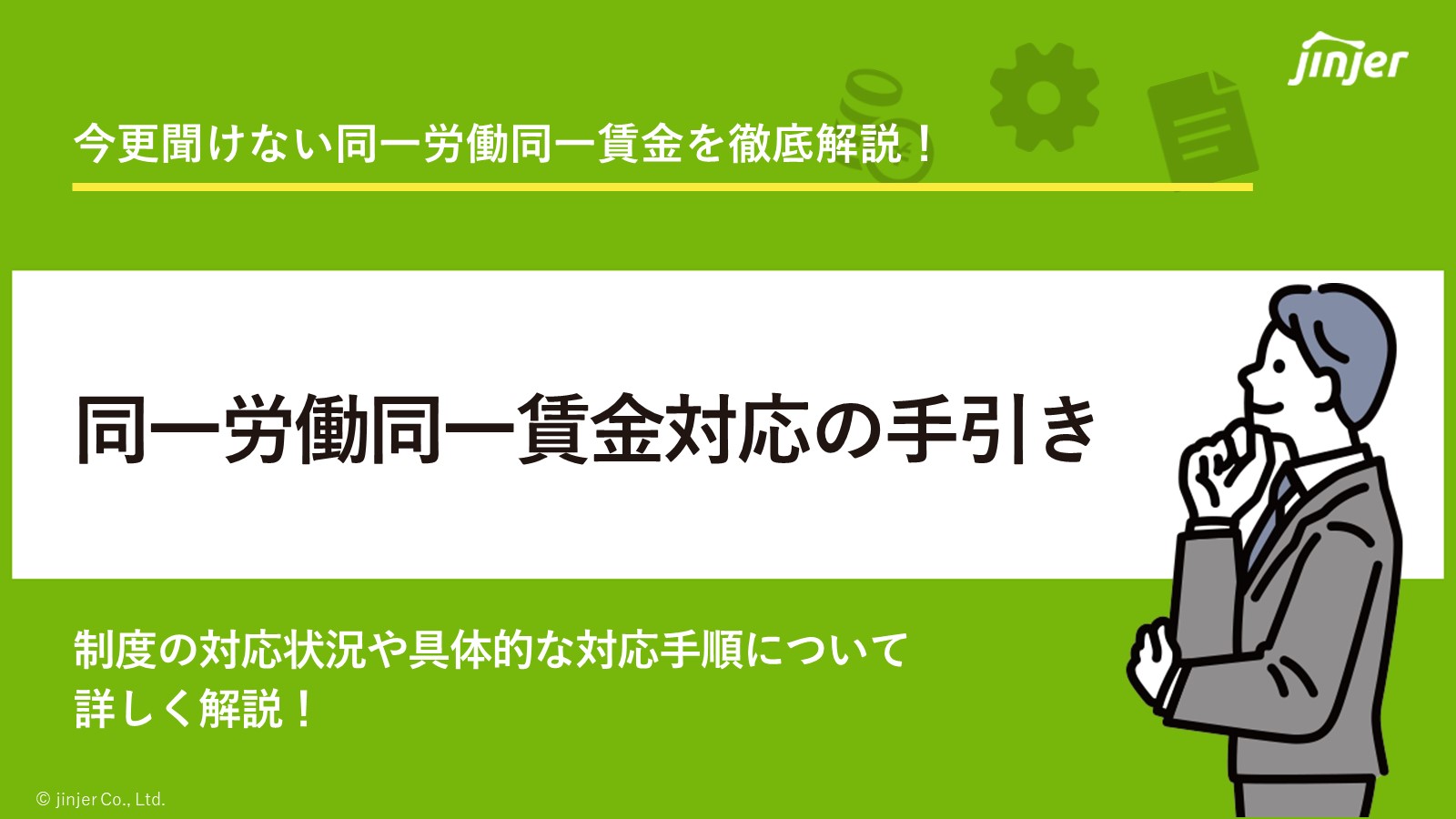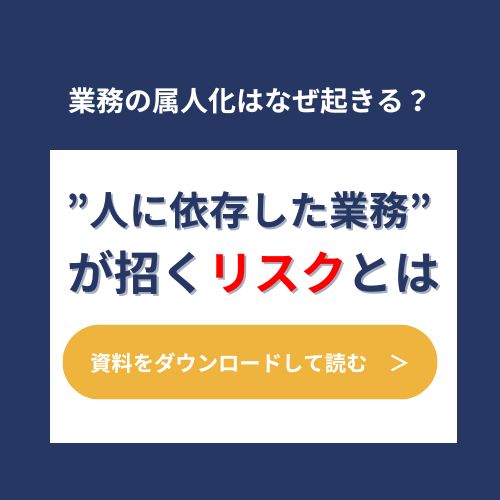労働者派遣法第30条の4第1項とは?その内容や注意点を解説
更新日: 2024.9.30
公開日: 2021.11.25
OHSUGI

2020年4月1日に改正された労働者派遣法では、第30条の4第1項が新たに追加されました。
労働者派遣法第30条の4第1項は、派遣労働者の同一労働同一賃金を目的としています。派遣労働者と一般労働者の賃金や処遇の差をなくし、働きやすい環境を整えられることがこの法律のメリットです。しかし、法律というのは専門用語が多く、担当者の方は理解しづらいかもしれません。
そこで今回は、労働者派遣法第30条の4第1項の内容について詳しく解説していきます。
▼そもそも労働者派遣法とは?という方はこちらをお読みください。
労働者派遣法とは?その内容や改正の歴史を詳しく紹介
2021年4月に法改正され、すべての企業に同一労働同一賃金が適応されましたが、
「具体的にはどのような法律で、対応せずにいると、どのような罰則があるのか、実はイマイチわかっていないけど、時間の経過と共に今更聞けない…」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、そのような方のために「今更聞けない同一労働同一賃金について」わかりやすく解説したガイドブックを無料で配布しております。法律に則って同一労働同一賃金の対応をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働者派遣法第30条の4第1項とは?


労働者派遣法第30条の4第1項とは、2020年4月1日に施行された条文です。派遣労働者の賃金や労働条件について、派遣元事業主がするべき対応の基準が記載されています。
まずは、労働者派遣法第30条の4第1項の原文を確認してみましょう。
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。
上記の条文には、協定に定めるべき項目が記載されています。大まかに挙げると、次の項目があります。
- 協定が適用される派遣労働者の範囲
- 同業の一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金額
- 派遣労働者の職務の成果や能力、意欲の向上があった場合の賃金改善
- 派遣労働者の賃金決定には職務内容や成果を公正に評価しておこなうこと
- 派遣労働者の待遇と派遣元事業主の労働者との待遇に差がないこと
- 派遣労働者に対する教育訓練の実施
つまり、協定で定めた派遣労働者に対し、同種の一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金を設定し、能力や成果に応じた賃金改善を公正な評価でおこないます。賃金だけでなく待遇面でも、派遣元労働者と同等の対応が求められるとの意味です。
2. 労働者派遣法第30条の4第1項と第30条の3との関係
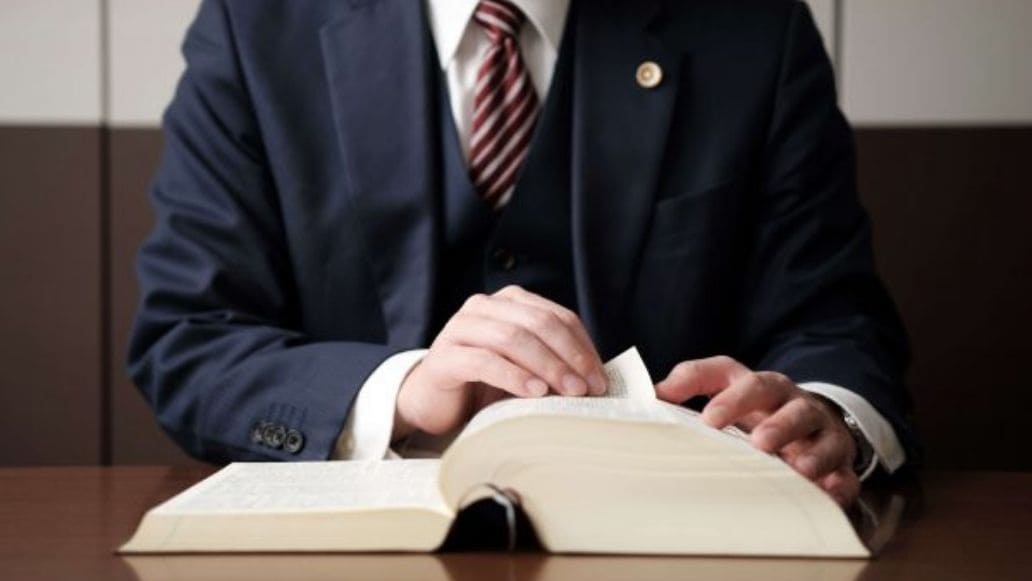
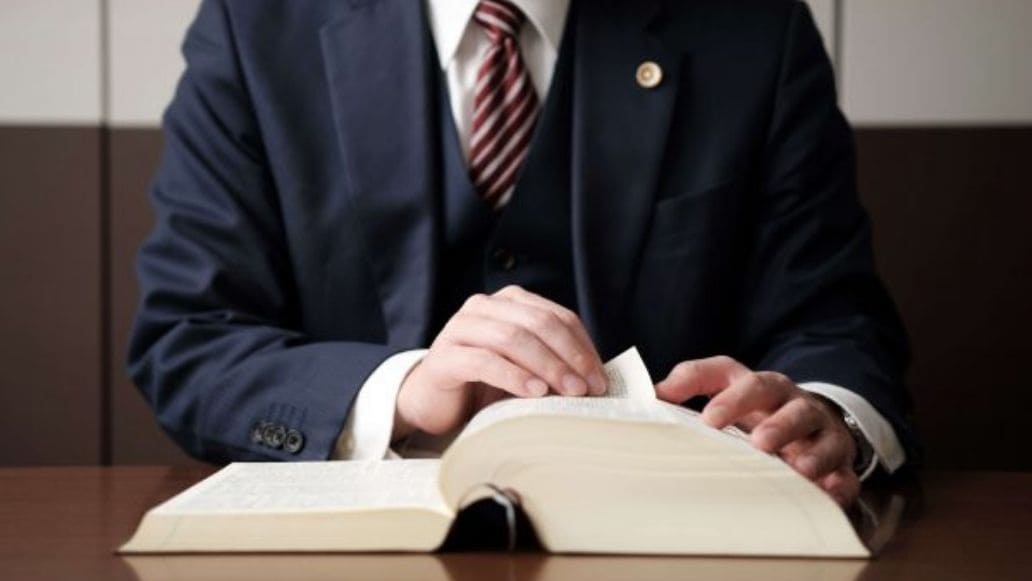
労働者派遣法第30条の4第1項は新たに制定された条文ですが、実は同法第30条の3と深く関係しています。まずはそれぞれの違いを、次の表にまとめたので見ていきましょう。
| 条文 | 第30条の4第1項 | 第30条の3 |
| 賃金決定方式 | 労使協定方式 | 派遣先均等・均衡方式 |
| 派遣先事業主の情報提供義務 | なし | あり |
| 雇い入れ時・派遣時の説明 | 労使協定方式でどのような措置を講じるか | 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講じるか |
派遣元事業主は、賃金決定方式に第30条の4の労使協定方式か、第30条3の派遣先均等・均衡方式かを選択できます。
派遣先均等・均衡を選んだ場合は、派遣先事業主から同種の一般労働者の平均賃金に関する情報提供義務が生じます。
一方、労使協定方式を選んだ場合、世間一般の同種労働者の賃金に合わせて派遣労働者の賃金を決定するため、派遣元事業主からの情報提供は必要ありません。
労働者派遣法第30条の4第1項の施行により、派遣元事業主の事務手続きの簡素化だけでなく、派遣労働者の賃金安定が実現されました。
また、2020年の労働者派遣法の改正では、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定として、派遣元事業主には雇い入れ時と派遣時に、労使協定方式あるいは派遣先均等・均衡方式を説明する義務が課せられているため注意してください。
関連記事:労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定とは?
3. 労働者派遣法第30条の4第1項のメリット


労働者派遣法第30条の4第1項は、派遣労働者の処遇を改善するだけでなく、派遣元事業主や派遣先事業主にとってもメリットがあります。
ここでは、労働者派遣法第30条の4第1項のメリットを2つ紹介します。
3-1. 書類を簡略化できる
労働者派遣法第30条の4第1項の改正は、派遣先事業者との書類のやり取りが簡略化されたことがメリットです。
労働者派遣法第30条3により、派遣先事業主は派遣先労働者の賃金情報を書面にして、派遣元事業主へ通知する必要がありました。また、均等・均衡方式では書類が多くなるため、事務手続きが煩雑になります。
しかし、第30条の4が追加されて労使協定方式を選べるようになったことで、派遣先労働者の賃金を知る必要がなくなったため手続きのフローが改善されたのです。さらに、派遣労働者の労働先が変わっても、派遣事業先の賃金情報を入手し直す必要もないので、担当者の業務負担も大幅に減るというのもメリットです。
また、労働者派遣法の改正により、派遣元企業は、労働者の過半数で組織する労働組合との労使協定を締結する必要があります。
この協定に基づく待遇の明確化は、派遣労働者の権利保護を強化し、企業としても社会的責任を果たす重要な取り組みとなります。労使協定方式を採用することで、派遣労働者の処遇が公正に扱われる環境が整うため、企業全体の信頼性や評価も向上する可能性が高まります。
これにより、派遣労働者の定着率が向上し、結果的に企業の業績にも好影響を与えるでしょう。
3-2. 派遣先によって賃金を変えなくてよい
派遣労働者の派遣先が変わっても、賃金変更はしなくてよい、ということも労働者派遣法第30条の4第1項のメリットです。
第30条の3では、派遣労働者の賃金を派遣先労働者と同等にするため、派遣先が変わるたびに賃金変更がおこなわれていました。しかし、労使協定方式では派遣先によって賃金を変える必要がなく、派遣先の要望に沿った派遣料金を設定しやすくなります。
また派遣労働者にとっても、派遣先によって賃金が変わることはデメリットでもありました。しかし、「賃金を変えなくてよい」と制定されたことで、派遣労働者も賃金が安定しやすくなるというメリットが得られます。
さらに、派遣労働者の待遇が均一化されることで、彼らが職場での不安を感じることが減少し、仕事に集中できる環境を整えることが可能です。
労使協定方式の導入により、派遣元企業が派遣労働者に適用する待遇が明確化され、雇用者との間に信頼関係が生まれることも期待されます。これにより、派遣労働者の定着率が向上し、企業全体の生産性に良い影響を与えることが可能となります。
4. 労働者派遣法第30条の4第1項に関する注意点


2020年の労働者派遣法の改正によって、新たに追加された第30条の4第1項ですが、労使協定の締結や決定事項の記載など注意すべきことがいくつかあります。
ここでは、労働者派遣法第30条の4第1項の改正で気を付けたいポイントを3つ解説します。
4-1. 過半数代表者の選出
労働者派遣法第30条の4第1項では、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結する必要があります。
過半数の代表者の条件は、次のとおりです。
- 労働基準法第41条第2項で定められる管理監督者ではない
- 労働者の中から民主的な方法で選出された者
あくまでも労働者側の立場で労使協定を結ぶ者との位置付けのため、派遣元事業主の意向で選ばれた者は不適です。
4-2. 労使協定事項の決定
労働者派遣法第30条の4第1項を実行するには、労使協定の事項を決定する必要があります。策定事項は次のとおりです。
- 労使協定の適用範囲
- 賃金の決定方法
- 賃金決定の基になる評価方法
- 賃金以外の待遇
- 教育訓練の実施方法や内容
この周知は、書面での交付やイントラネット上での常時確認が可能な方法で行わなければなりません。また、労使協定の内容は、事業所内の見やすい場所に掲示することも求められています。これにより、派遣労働者が自分の待遇について明確に理解できる環境が整えられます。労使協定のイメージは、厚生労働省で公開されているので参考にしてみましょう。
参照:労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)|厚生労働省
4-3. 行政機関への報告
派遣元事業主は毎年6月30日の期日までに、労働者派遣事業報告書に労使協定を添付し、行政機関へ届出をする必要があります。さらに、この方式の対象となる派遣労働者の人数(職種ごとに記載)や賃金の平均額を報告することも義務付けられているので、しっかり準備をしておきましょう。
また、締結した労使協定の書面は、労使協定の有効期限終了の日から3年間は保管しなければなりません。届出も保管も義務となるため、担当者は不備がないように注意してください。
5. 労使協定を締結して職場環境を整えよう


そのため、派遣元事業主は労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者との労使協定を締結し、事業報告書と一緒に提出することが義務付けられているのです。担当者の方は大変かもしれませんが、労働力を必要な時に提供してくれる派遣労働者のためにも、労使協定を締結して職場環境を整えておきましょう。
2021年4月に法改正され、すべての企業に同一労働同一賃金が適応されましたが、
「具体的にはどのような法律で、対応せずにいると、どのような罰則があるのか、実はイマイチわかっていないけど、時間の経過と共に今更聞けない…」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、そのような方のために「今更聞けない同一労働同一賃金について」わかりやすく解説したガイドブックを無料で配布しております。法律に則って同一労働同一賃金の対応をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労働者派遣法の関連記事
-


労働者派遣法第40条の条文で定められた派遣の期間制限について解説
人事・労務管理公開日:2021.11.25更新日:2024.09.26
-

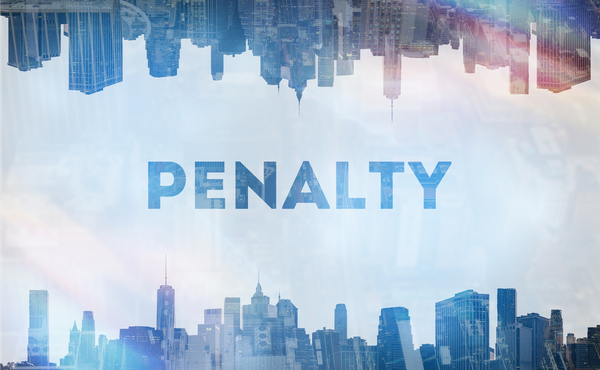
労働者派遣法に違反する行為とは?罰則規定や違反例を解説
人事・労務管理公開日:2021.11.25更新日:2024.09.19
-


労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定とは?
人事・労務管理公開日:2021.11.25更新日:2024.08.23