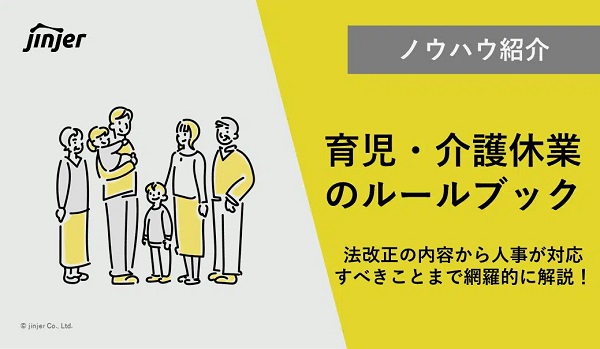労働者派遣法第40条の条文で定められた派遣の期間制限について解説

労働者派遣法第40条の2によると、派遣労働者は原則3年を超えて同一派遣先へ派遣できません。ただし、上記の派遣可能期間の制限には例外もあります。派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者や、60歳以上の派遣労働者が例外にあたります。厚生労働省の定める休業を取得した派遣労働者の代替派遣に関して、派遣可能期間が記載されているのは「労働者派遣法第40条の2第4項」です。
今回は、労働者派遣法第40条の2第4項に定められた派遣可能期間の制限や派遣可能期間に関する注意事項を解説します。
▼そもそも労働者派遣法とは?という方はこちらをお読みください。
労働者派遣法とは?その内容や改正の歴史を詳しく紹介
目次
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 労働者派遣法第40条の2第4項の条文とは?

まずは確認のため、労働者派遣法第40条の2第4項の条文を以下に示します。
第40条の2第4項
当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
労働者派遣法第40条の2は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間を定めた法律です。派遣可能期間は、派遣労働者が派遣された日から概算して算出します。派遣先事業主は、法律で定められた派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れてはいけない、というのが原則です。
労働者派遣法第40条の2第4項は、この原則の例外を示しています。労働者派遣法第40条の2第4項では、休業・育児休業・介護休業などを取った派遣労働者の派遣可能期間に関して記されています。第40条の2第4項によると、上記のケースに当てはまる派遣労働者は、派遣可能期間を超えた派遣が可能です。
2. 労働者派遣法第40条で定められた期間制限

労働者派遣法第40条の2で定められている派遣可能期間は3年です。
第40条の2第5項の2
前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
原則として、3年を超えて同じ派遣労働者を同一の派遣先部署へ派遣することはできません。
ただし、派遣可能期間の制限には、以下の例外があります。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務に就く派遣労働者
・1カ月の勤務日数が10日以下の日数限定業務に就く派遣労働者
・産前産後休業・育児休業・介護休業等の厚生労働省令で定められた休業を取得した派遣労働者
労働者派遣法第40条の2第4項では、産前産後休業・育児休業・介護休業等の厚生労働省令で定められた休業を取得した派遣労働者は、「労働者派遣法第40条の2第4項」において「派遣可能期間を超えても受け入れて良い」となっています。そのため、派遣可能期間3年の期間制限はかかりません。
3. 労働者派遣法第40条で定められた休業の種類

労働者派遣法第40条の2第4項では、以下の休業を取得した派遣労働者に代わり、同一業務を行う別の派遣労働者に対する派遣可能期間の制限はない、ということも定めています。
| 休業の種類 | 対象者 | 期間期間 |
| 産前休業 | 妊娠中の労働者 | 原則出産予定日の6週間前 |
| 産後休業 | 出産後の労働者 | 出産日の翌日から8週間 |
| 育児休業 | 1歳未満の子を養育する男女労働者 | 原則、子が1歳まで(最長2歳まで) |
| 介護休業 | 要介護状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母を介護する男女労働者 | 対象者家族1人につき3回、通算93日まで |
参照:あなたも取れる!産休&育休|厚生労働省
参照:育児休業制度 |厚生労働省
参照:介護休業制度|厚生労働省
育児休業の対象者には、次の要件があります。
- 子が1歳6カ月に達する日まで労働契約の期間が満了しないこと
また、介護休業の対象者は、以下の要件にあてはまらなければいけません。
- 介護休業の取得予定日から起算して93日を経過する日から6カ月間に、労働契約の期間が満了しないこと
これらの要件を満たしていないと対象者にはならないため、派遣期間を超える受け入れはできないので注意しましょう。
4. 労働者派遣法第40条の2第4項に関する注意点

労働者派遣法第40条の2第4項の対象となる派遣労働者は、派遣可能期間3年の制限は受けません。ただし、派遣可能期間に関与する条文には、いくつか注意なければならないポイントもあります。
ここでは、労働者派遣法第40条の2第4項に関与する注意点を解説します。
4-1. 事業所単位・個人単位の派遣期間制限
派遣可能期間には、事務所単位と個人単位の制限があります。それぞれの違いは、次のとおりです。
| 派遣期間制限 | 特徴 | 派遣可能期間 |
| 事業所単位 | 派遣先の同一事業所に派遣労働者を派遣できる |
最大3年 *期間制限日を迎える1ヶ月前までに、過半数労働組合(過半数代表者)の合意があれば最大で3年ずつ延長可能 |
| 個人単位 | 同一の派遣労働者を派遣先の同一部署に派遣できる | 最大3年*延長不可 |
事業所単位・個人単位どちらも派遣可能期間は3年です。ただし、事業所単位の派遣期間制限は、過半数労働組合に意見聴取をして合意が得られれば延長できる、というのが個人単位との大きな違いとなります。
4-2. 3年を超えた派遣継続は労働組合の意見聴取が必要
事務所単位の派遣期間制限には例外があり、労働者派遣法第40条の2第4項に規定される派遣労働者を派遣する場合でなくても、派遣可能期間の延長ができます。
ただし、次の者からの意見聴取が必要です。
- 派遣先事業所の過半数の労働者で構成される労働組合
- 労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者から意見聴取しないと、3年を超えての派遣はできないので注意してください。
4-3. 抵触日の通知義務
派遣先事業主は、派遣元事業主への抵触日の通知義務があります。
抵触日とは、事務所単位あるいは個人単位の派遣可能期間を超えた日です。つまり、期間の延長がなければ、派遣期間制限3年が切れた翌日が抵触日となります。
抵触日はあらかじめ、派遣先事業主から派遣元事業主へ通知する必要があります。また、派遣元事業主から派遣労働者への通知することが求められます。
ただし、労働者派遣法第40条の2第4項の対象となる派遣労働者は、派遣可能期間の制限がないため、抵触日の設定もありません。
5. 労働者派遣法第40条を正しく理解しよう

労働者派遣法では、原則として派遣期間は3年という期限を定めています。しかし、この期限はすべての派遣労働者に適用されるものではありません。労働者派遣法第40条の2第4項では、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した派遣労働者に代わって、別の派遣労働者を派遣する場合の派遣可能期間が定められています。
つまり、労働者派遣法第40条の2第4項に当てはまる代替派遣労働者には、派遣期間制限は適用されないのです。これを正しく理解していないと、新たな派遣労働者を探して契約をするという余分な業務が増えるので、対象となる派遣労働者の管理を徹底しましょう。
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08