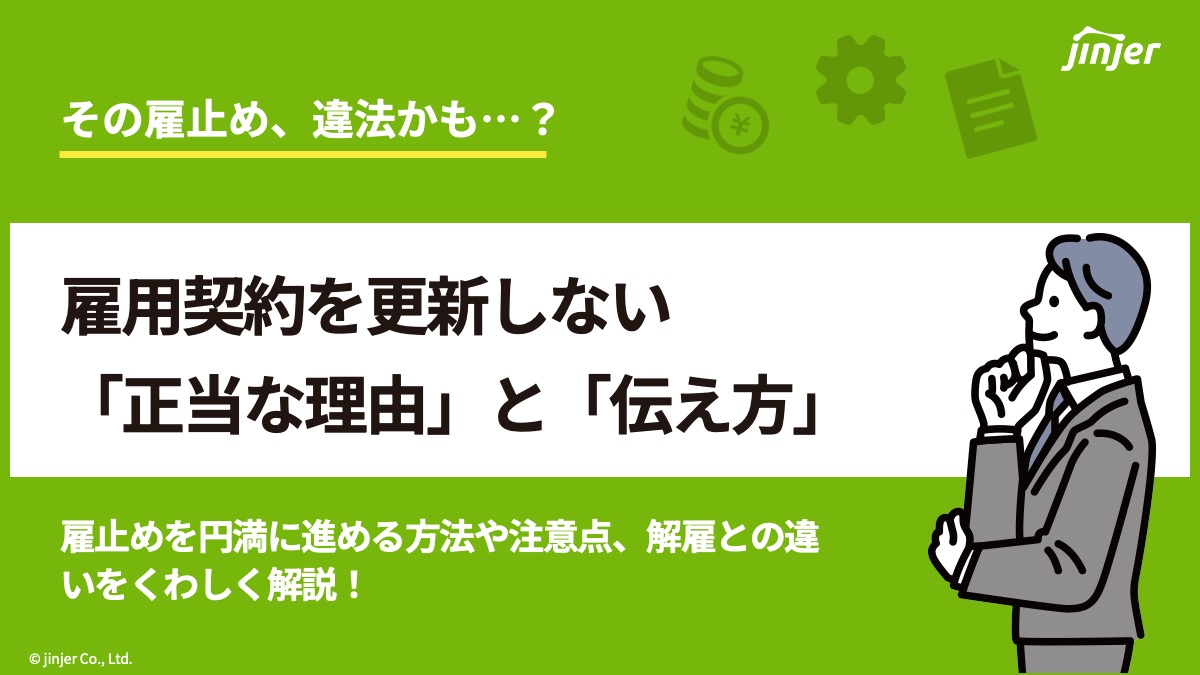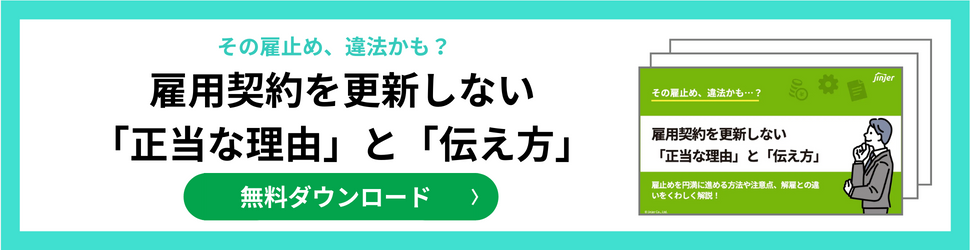雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

契約社員など有期雇用の労働者は、契約期間を過ぎれば雇用契約も終了するのが原則です。
しかし、雇用期間の定めが曖昧、雇用契約書に更新の有無や判断基準ついて記載がない、雇用の継続について労働者に期待をさせるような状況の場合、労働契約法第19条により、雇い止めが認められないケースもあります。
今回は、雇用契約を更新せず雇用契約を終了する際、雇い止めが認められるケースと認められないケースほか、雇い止めの従業員への伝え方についてご紹介いたします。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
目次
円満に雇用契約を終了させる方法を詳しく解説
契約更新の可否は雇用主となる企業側が判断することが多く、「一方的に決めても良い」と考えてしまう企業も少なくないでしょう。
しかし実際には、「雇用者から見て、契約更新が期待できる状況だった」と判断される場合の雇止めは認められないことがほとんどです。
また、雇止めできる条件が揃っていたとしても、従業員にとっては職と収入源を失うことであり、すぐに納得できることではありません。
裁判やトラブルを避けるためには、雇止めとなる正当な理由と伝え方に注意する必要があります。
「雇止めをしたいが、法的に問題ないか確認したい」
「契約更新しない旨をどう伝えたら良いかわからない」
「雇止めできる正当な理由にどういったものがあるのか知りたい」
という方におすすめの資料を用意しておりますので、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用契約を更新しない正当な理由

有期雇用契約においては、引き続き雇用関係を更新しない限り、契約期間満了とともに雇用契約も終了します。
契約更新をしないことについて、労働者からその理由について証明書を請求された場合は、使用者(雇用主)は速やかに証明書を交付しなければなりません。証明書に記載する「雇い止めの理由」には、契約期間満了以外の理由を明示する必要があります。
雇用契約を更新しない理由の例としては、次のようなものがあります。
- 本契約を更新しないことについて、前回契約更新時に合意されていたため
- 本契約が、契約締結の際に設けられた更新回数の上限にかかわるため
- 担当業務が終了・中止したため
- 事業縮小のため
- 業務を遂行する能力が不足していると立証されたため
- 職務命令に対する違反行為、無断欠勤などの勤務不良がみられるため
1-1. 雇い止めの効力が認められるかどうかは契約関係の状況に左右される
契約期間満了による雇用契約の終了について、原則通り雇い止めが有効かどうかは、労使間の契約関係の状況が重要なポイントです。
過去の有期雇用契約の雇い止め判例によると、次のような「純粋有期契約タイプ」であれば、雇い止め理由が正当かどうかにかかわらず、雇い止めの効力が認められます。
- 業務内容が臨時的な事案である。または契約上の地位が臨時的・一時的なものである
- 労使間において、期間満了によって契約関係が終了することに明確な認識がある
- 更新の手続きが明示された判断基準によって厳格に行われている
- 更新回数が少なく、通算契約期間が短い
- 同じような地位の労働者について、過去に雇止めの事例がある
反対に、当てはまらない場合には、雇い止めをおこなうのが難しいといえるでしょう。 改正労働契約法によって、有期雇用契約の雇い止めや解雇が厳しく制限されるようになったためです。
2. 契約を更新しない場合に会社がおこなう手続き


契約を更新しない場合、会社は更新しない理由などを伝達しなければなりません。
ここでは、どのような内容を従業員に伝達しなければならないのかを詳細に解説します。
2-1. 契約締結時の明示事項
『契約締結時の明示事項』は、更新の有無や判断基準を雇用契約書に記載することです。会社は労働者を雇い入れる際に、更新について労働者に下記の項目を明確化しなければなりません。
①更新の有無の明示
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容は、以下の3つが挙げられます。
⑴ 自動的に更新する
⑵ 更新する場合があり得る
⑶ 契約の更新はしない
②判断の基準の明示
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容は、以下の5つが挙げられます。
⑴ 契約期間満了時の業務量により判断する
⑵ 労働者の勤務成績、態度により判断する
⑶ 労働者の能力により判断する
⑷ 会社の経営状況により判断する
⑸ 従事している業務の進捗状況により判断する
③その他留意すべき事項
トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面で明示することが重要になります。これはアルバイトやパートの立場であっても同様です。
アルバイトやパート採用であっても、労働法を遵守した雇用契約書をできるだけ取り交わしましょう。
関連記事:アルバイト採用でも雇用契約書は必要?書き方の基本や注意点
関連記事:雇用契約を更新する手順|従業員に対して実施すべき具体的対応を解説
2-2. 雇止めの予告・明示理由
1年以上継続雇用されている、または、3回以上更新されて働いている労働者には、『雇い止めの予告(解雇予告)』が必要です。雇い止め予告は、契約を解除する30日前までに労働者に伝えなければなりません。
また雇止めをする場合は、『契約締結時の明示事項』は、更新の有無や判断基準を雇用契約書に記載することです。
会社は労働者を雇い入れる際に、更新について労働者にきちんと説明しなければなりません。
2-3. 契約期間についての配慮
有期労働契約は、契約期間が終了したからといって、簡単に契約を打ち切ることはできません。
厚生労働省が公開している「有期労働契約の締結、及び雇止めに関する基準について」には、下記のように記載されています。
「使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。」
企業は、1年を超えるような契約については契約期間等に配慮する義務があります。
3. 雇用契約を更新しないことを認められないケース

有期雇用契約であっても、次のようなケースの場合、労働契約法 第19条の適用により、客観的・合理的な理由に欠け、社会通念上の相当性が認めらないと判断され、雇い止めができません。
雇い止めが認められない場合は、以前と同じ労働条件のもと、有期雇用契約を更新することになります。
3-1. 実質的に無期契約と変わらない状態である場合
該当労働者の勤務実態が、次のような場合は、実質無期契約となっていたと判断されます。
- 業務内容や地位、職責が、正社員とほぼ変わらない場合
- 更新回数が非常に多く、契約期間の通算が長い場合
雇い止めが認められるには、正社員と同等、またはそれに近い正当性が求められることが多いケースです。使用者が主張する雇い止めの理由が次のようなものであれば、雇い止めは無効となる可能性が高いでしょう。
- 契約期間満了以外の理由が明示されない
- 勤務不良を理由にしているが、勤務不良の内容や程度の基準があいまい。客観性・合理性に欠けるうえ、これまでに警告を一度も行っていない
- 契約更新をしない理由が経営不振であるが、「整理解雇の4要件」を全て満たしていない
3-2. 雇用継続への期待が合理的である場合
通常、雇用契約の更新は、期間満了時に改めて契約を締結します。更新するかどうかは、使用者と労働者、双方の合意のもとで決定するものです。
しかし、有期雇用契約であっても、更新手続きが完全に形骸化し、反復更新によって長期雇用されているケースがあります。また、継続雇用制度によって定年後に再雇用社員を雇用している場合もあるでしょう。
このような場合は、以下のような判断基準のもと、雇い止めが無効となる可能性があります。
- 業務内容や種類が臨時的・季節的でなく、恒常的なものである
- 契約上の地位が正社員とほぼ変わらない
- 反復更新の有無や回数、通算の勤続年数
- 契約更新手続が厳格に行われていたか
- 使用者から雇用継続の期待を持たせる言動があったか
- 同様の職責・地位の労働者について、雇い止めの事例があるか
- 勤続年数や年齢に上限設定があるか
また、有期雇用契約が繰り返し更新され、契約期間の通算が5年を超えた場合、労働者は期間の定めのない無期雇用契約への転換を申し込むことができます。
過去に、無期雇用への申込権を獲得する直前の4年目でおこなわれた雇止めが無効と判断された判例も存在するなど、労働者を守るための法律であるため、雇用契約を更新しないことは認められづらくなっています。
なお、使用者は労働者に対し、無期雇用への転換の権利が発生したことを告知する義務があり、労働者は転換権について認識している状態にしておかなければなりません。
4. 雇用契約を更新しないことの伝え方とポイント

ここでは、雇用契約を更新しないことを伝える際のポイントを解説します。
4-1. 雇止めの予告期間を認識しておく
契約更新を3回以上、または雇用期間の通算が1年を超える有期雇用契約者に関しては、契約期間満了日の30日前に雇止め予告をしなければなりません。
雇用契約を更新しないことを従業員へ伝える際には、本人と個別面談を行なうべきでしょう。従業員の今後の生活や転職活動を考慮し、面談はできる限り設定するようにしておきましょう。
また、従業員に請求された場合に雇用期間満了通知書の交付が必要となります。速やかに交付できるよう、予め作成しておくことをおすすめします。
なお、会社側の意向にかかわらず、面談の結果、従業員自身が契約更新を希望していない場合は、退職届または契約更新を希望しないことを明示した文書を提出してもらいます。
4-2. 契約解除通知書にサインをもらう
契約終了後のトラブルを防止するためにも、契約終了が確定したら、契約解除通知書に本人のサインをもらうようにしましょう。書式に指定はありませんが、自社に必要な事項は全て明記しておく必要があります。
最低限、「解除する契約」「解除の理由、解除する旨」「解除するまでの猶予期間」などが記載されているとよいでしょう。
過去に、無期雇用への申込権を獲得する直前の4年目でおこなわれた雇止めが無効と判断された判例も存在するなど、労働者を守るための法律であるため、雇用契約を更新しないことは認められづらくなっています。
このように、雇止めするためには、適切な理由と従業員が納得することの2点を押さえる必要があります。とはいえ、今後の生活への不安や自信の仕事ぶりが評価されていなかったのでは、という悔しさから、すぐに納得してもらうことは難しいでしょう。当サイトでは、トラブルになりにくい伝え方についてより詳しく解説した資料も用意しています。「どう伝えたら良いんだろう…」とお悩みの方はこちらからダウンロードしてご覧ください。
5. 解雇(途中解約)をおこなう際の注意点


改めて説明をおこなうと、雇止めとは、契約期間が満了した状態で契約を解除することを指します。
一方、解雇とは、契約期間中であるのにもかかわらず、契約を解除することを指します。
ここでは、解雇(途中解約)をおこなう際の注意点について解説します。
5-1. 有効となる解雇理由を準備しておく
労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。そのため、雇用契約の途中に解約する理由には妥当性がなくてはなりません。
なお、解雇には以下の通り、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇という3つの種類が存在します。
・普通解雇
健康状態による労働能力の低下、能力不足、勤怠不良、不正行為など、労働者の債務不履行を理由とした解雇のこと。
・懲戒解雇
労働者にとって最も重い罰で、悪質な違法行為や重大な規律違反など、大きく会社の秩序を乱した場合におこなわれる解雇のこと。
・整理解雇
会社の経営不振などによる人員削減を目的とした解雇のこと。
それぞれの条件に当てはまる場合には、解雇の種類に応じて、妥当性のある解雇理由を準備しておきましょう。
反対に当てはまらない場合、解雇するのは難しいといえるでしょう。
5-2. 30日以上前に解雇予告をおこなう
雇止めと同様、解雇をおこなう場合には、少なくとも30日前に解雇予告をおこなう必要があります。
正当な解雇理由があった場合でも、解雇予告は必ずおこなわなければならないので注意しておきましょう。
5-3. 解雇予告手当を支払う
上述したように、30日以上前に解雇予告をおこなわなかった場合、労働者に対して日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。計算方法は以下の通りです。
「1日の平均賃金」×「30日に満たなかった日数」=「解雇予告手当」
6. 契約時に契約更新・雇い止めに関する判断基準を明示しておくことが重要

有期雇用契約は契約期間満了とともに契約が終了するため、契約不更新による雇止めは違法ではありません。
しかし、一定期間雇用を継続した労働者に対し、契約期間満了を理由に雇止めを行うことは、労使間でのトラブルに発展する可能性があったり、認められないこともあります。
雇い止めをめぐるトラブルを防ぐためには、雇用契約書を取り交わす際、更新の有無や判断基準について、きちんと明示しておくことが重要です。
▼雇用契約のカテゴリで人気の記事
雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
円満に雇用契約を終了させる方法を詳しく解説
契約更新の可否は雇用主となる企業側が判断することが多く、「一方的に決めても良い」と考えてしまう企業も少なくないでしょう。
しかし実際には、「雇用者から見て、契約更新が期待できる状況だった」と判断される場合の雇止めは認められないことがほとんどです。
また、雇止めできる条件が揃っていたとしても、従業員にとっては職と収入源を失うことであり、すぐに納得できることではありません。
裁判やトラブルを避けるためには、雇止めとなる正当な理由と伝え方に注意する必要があります。
「雇止めをしたいが、法的に問題ないか確認したい」
「契約更新しない旨をどう伝えたら良いかわからない」
「雇止めできる正当な理由にどういったものがあるのか知りたい」
という方におすすめの資料を用意しておりますので、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08