法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
更新日: 2024.6.12
公開日: 2022.4.14
YOSHIDA

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。この社会保険制度の改正による影響で、2022年(令和4年)10月から段階的に社会保険の適用範囲を拡大することが決定し、雇用主である企業は適切な対応が求められています。
この記事では、今回の改正における社会保険適用拡大の該当要件や企業側の対応ポイントについて解説します。多くの中小企業が対応を求められることになるため、企業の担当者は制度の概要をしっかりと確認しておきましょう。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
「パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらい」
「従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」
「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」 など、社会保険の加入に関して正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。さらに2024年10月には法改正により適用条件が変更されます。
当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。
社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。
さらによくある細かい質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。
適切に社会保険の加入を案内したい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
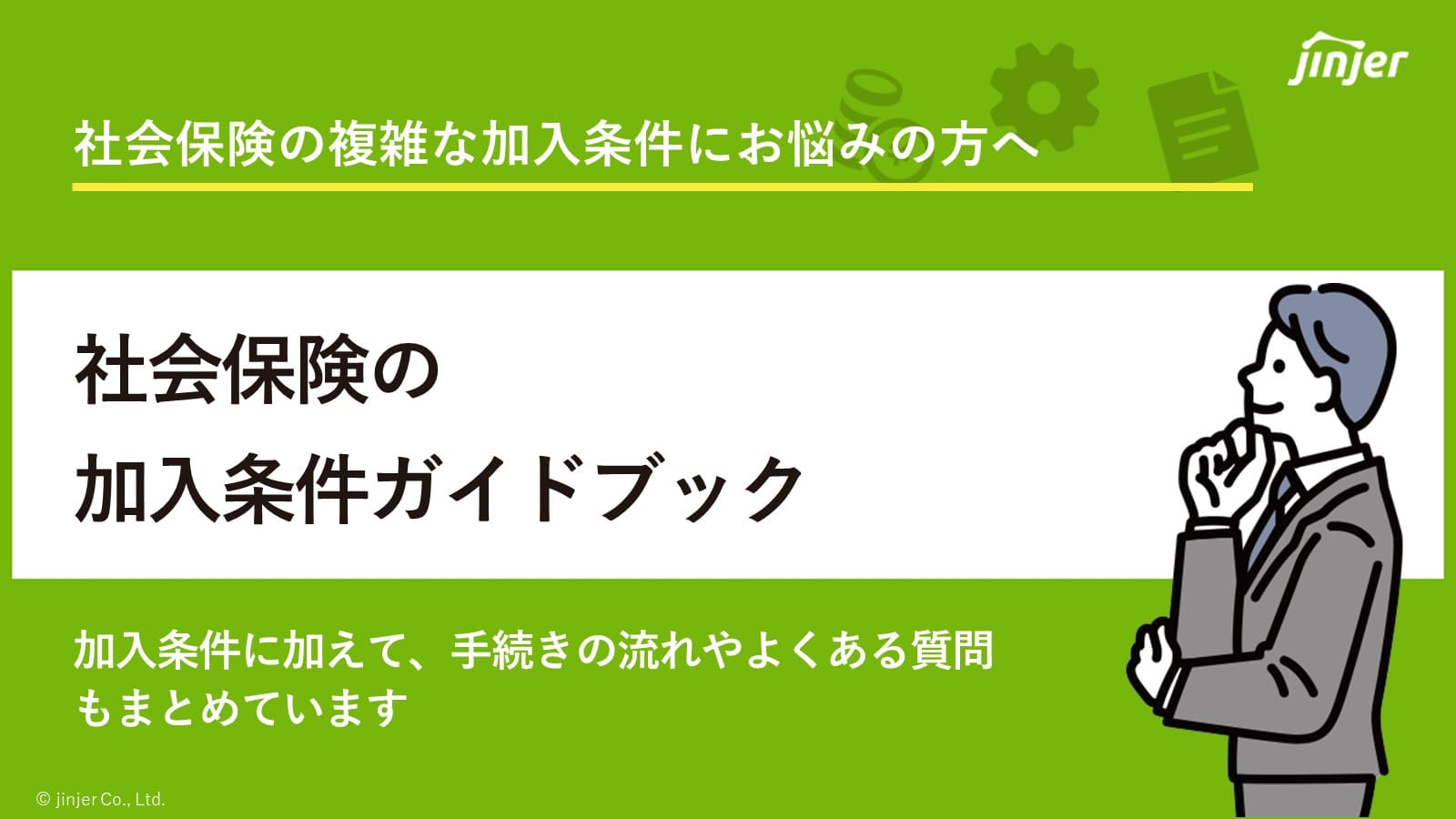
1. 2022年の社会保険適用拡大で変わること

社会保険の適用拡大は、少子高齢化やワークスタイルが多様化する現代の日本の状況に合わせ、適切な社会保険の提供を目的として実施されている取り組みです。
2022年10月の社会保険適用拡大により、これまで従業員数が501名以上の企業に所属する短時間労働者を対象としていた社会保険加入が従業員数500名以下の企業へと段階的に引き下げられます。これにより、500名以下の小規模な企業で働くパートやアルバイトといった短時間労働者も、要件を満たした場合は社会保険に加入しなくてはならなくなります。
社会保険に加入すると、医療保険が充実しパートやアルバイトでも傷病手当や出産手当などが受け取れるようになったり、厚生年金に加入することで年金が国民年金と2階建てになり、受けられる保障内容が広がるといった変化が生じます。今まで十分な保障が受けられなかった短時間労働者にとっては、メリットが多い法改正だといえるでしょう。
この社会保険適用拡大は、実は2016年に一度実施されています。その際は、以下の事業所で労働しており、要件を満たした短時間労働者に対してのみ社会保険に加入させることを義務付けていました。[注1]
- 被保険者が常時501人以上の「特定適用事業所」
- 被保険者が501人に満たない場合であっても、労使の合意があって届け出をした「任意特定適用事業所」
今回の社会保険適用拡大では、上記の要件を満たさない500人未満の企業に対しても、一定の要件を満たすパートやアルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務化されます。
[注1]令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
2. 2022年の社会保険制度改正で社会保険適用を拡大する要件

社会保険適用拡大は、事業所側と従業員側のどちらにも適用される条件があります。
条件に当てはまった場合、短時間労働者を社会保険に加入させる義務が発生するため、内容をしっかりと把握しておくことが肝心です。
ここでは、2022年10月の社会保険制度改正により、社会保険適用拡大の対象となる企業や従業員の要件について紹介します。
2-1. 社会保険適用拡大の対象となる企業の要件
社会保険適用拡大は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上500人以下の企業を対象として段階的に行われています。
現行の制度と今後適用拡大となる企業の要件は、以下のとおりです。[注2]
- 2016年10月~:常時501人以上
- 2022年10月~:常時101人以上【現行】
- 2024年10月~:常時51人以上
なお、上記の従業員数の数え方は、フルタイムの従業員数と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数の合計になっています。
今後はより多くの中小企業が社会保険適用拡大の対象となるため、規模が小さい企業であっても法改正への対応が求められるようになります。
自社には無関係だと思わず、しっかりと最新の情報を把握しておきましょう。
[注2]厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化|厚生労働省・日本年金機構
2-2. 社会保険適用拡大の対象となる短時間労働者の要件
次に、社会保険適用拡大の対象となる短時間労働者の要件について見ていきましょう。
社会保険適用拡大の対象となる要件は、2022年10月より一点だけ変更になります。[注1]
| ~2022年9月 | 2022年10月~ | 2024年10月~ | |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
| 賃金 | 月額8.8万円以上 | 変更なし | 変更なし |
| 勤務期間 | 1年を超える雇用の見込みがある | 2か月を超える雇用の見込みがある | 2か月を超える雇用の見込みがある |
| 適用除外 | 学生ではない(休学中や夜間学生を除く) | 変更なし | 変更なし |
大幅な変更はありませんが、勤務期間の要件が1年から2か月に短縮された点に注意しましょう。
上記の要件をすべて満たしているパートやアルバイトの従業員は、必ず社会保険に加入させる必要があります。
なお労働時間は契約上の時間であり、残業などといった臨時的な労働時間は要件に含まれません。
また、賃金に関しても残業手当や通勤手当などは含まれないため、判断の際は注意してください。
もし社会保険の加入要件を満たす従業員が社内にいる場合は、入社時の処理と同様に届け出を行う必要があり、届け出を忘れてしまうと罰則になる可能性もあるため、担当者は忘れずに手続きを行わなければなりません。
当サイトでは、本記事で解説している法改正の内容や担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の内容で不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
3. 社会保険の適用拡大にあてはまった場合の対応

社会保険の適用拡大にあてはまった企業は、社会保険の適用拡大があることを従業員に周知したうえで、対象となる従業員とコミュニケーションをとり、必要な手続きをする必要があります。
ここでは、社会保険の適用拡大に対応する方法と手順を解説します。
3-1. 対象従業員の確認と周知
まずは、事業所でどの従業員が対象となるかを確認しましょう。対象となる従業員の条件は、先ほど解説した通りです。
どの程度の人数で対応が必要かを把握すれば、対応にどの程度の工数がかかるかの見積もりを算出したり、企業内でどの程度社会保険料の支払いが増えるかを算出したりすることができるでしょう。
そのうえで、従業員へ社会保険の適用拡大により社会保険の加入や社会保険料の支払いが発生する場合があることを周知しましょう。
3-2. 対象従業員への通知
対象の従業員へ社会保険の加入対象になることを伝え、本人の意思を確認しましょう。
その際は社会保険とはどのようなもので、加入することでどのような保障が受けられるか、月々の支払い(控除額)はいくらになるかなどを丁寧に説明します。
社会保険へ加入することへ難色を示された場合は、保障が手厚くなるなどのメリットを伝える、これまでよりも労働時間を減らして社会保険の加入条件にあてはまらないようにするなど、従業員と相談しながら加入を決めることをおすすめします。
従業員への説明なしに加入させ、保険料を徴収するとトラブルにつながりかねないため、必ず事前に通知しましょう。
3-3. 社会保険の資格取得に関する書類作成
社会保険へ加入する従業員について、社会保険被保険者資格取得届を作成して管轄の年金事務所へ提出します。
社会保険被保険者資格取得届は、適用条件に当てはまるという事実が発生してから5日以内に届出が必要なため、前もって対象者の確認と書類の準備をしておく必要があります。
届出に必要な書類は基本的に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」のみですが、届出へマイナンバー(基礎年金番号)の記入が必要なため、従業員からマイナンバーカードや年金手帳のコピーを提出してもらいましょう。この際、本人確認も忘れずに行います。
届出を作成し終えたら、管轄の年金事務所へ提出します。届出用紙を窓口で提出する、もしくは郵送するか、e-Govによる電子申請、CDまたはDVDによる電子媒体での申請も可能です。
参考:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
4. 特定適用事業所となるために必要な手続き

今回の法改正に伴い、特定適用事業所の要件も変更となります。もし今まで該当していなかった企業が特定適用事業所の要件を満たした場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
ここからは、特定適用事業所の要件や手続きの流れについて紹介します。
4-1. 特定適用事業所とは
特定適用事業所とは、事業主が同一である適用事業所で、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える(501人以上)事業所のことです。
事業主が同一である適用事業所とは、具体的に以下の場合を指します。
- 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)かつ法人番号が同一の適用事業所
- 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
2022年10月からはこの要件が変更となり、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える(101人以上)の事業所も含まれるようになります。2024年からは、ここに短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)事業所も加わります。
なお特定適用事業所以外で、労使合意に基づいて短時間労働者を社会保険の適用対象とする申し出をした事業所を「任意特定適用事業所」と呼びます。
特定適用事業所に該当しない場合でも、所定の手続きをして任意特定適用事業所になれば、短時間労働者の要件を満たす従業員を社会保険に加入させることが可能です。
4-2. 特定適用事業所に該当するタイミング
自社が特定適用事業所に該当しているかどうかについて、どのように判断すればいいのか迷ってしまう企業も多いでしょう。とくに従業員の変動が多い会社では従業員数をカウントするタイミングが難しく、月によって要件を満たしたり満たさなかったりすることもあるかもしれません。
特定適用事業所に該当しているかどうか判断するタイミングやカウント方法は、以下の原則に従いましょう。
- タイミング:直近12ヶ月のうち6か月基準を上回った場合
- カウント方法:常時使用する労働者ではなく、社会保険の被保険者数のみ
この際、適用対象となったあとに従業員数が基準を下回っても引き続き適用され続ける点、同一の法人番号ごとにカウントする点に注意してください。
4-3. 特定適用事業所に必要な手続き
自社が適用事業所に該当したときは、その事実が派生した日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を日本年金機構又は健康保険組合に提出する必要があります。[注2]
この届出を行わなかった場合でも、年金機構において判定を行い、要件を満たしていると判断された場合は「特定適用事業所該当通知」が送付されます。この場合も、要件を満たした短時間労働者を社会保険に加入させることが義務付けられるため注意しましょう。
5. 社会保険適用拡大の概要を押さえて適切な加入を

社会保険制度の改正により、2022年10月より社会保険適用拡大が行われます。
この改正により、今まで特定適用事業所に該当しなかった企業や、短時間労働者の要件を満たしていなかった従業員に大きな影響が出ることは間違いありません。企業は変更点や必要な手続きをしっかりと理解し、要件を満たす従業員を適切に社会保険へ加入させる必要があります。
また、企業側のみが制度を理解するのではなく、従業員にも何が変わるのかを知ってもらうことも大切です。
変更点や従業員に与える影響をしっかりと周知し、質問があったときに答えられるよう準備しておきましょう。
関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!
「パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらい」
「従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」
「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」 など、社会保険の加入に関して正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。さらに2024年10月には法改正により適用条件が変更されます。
当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。
社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。
さらによくある細かい質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。
適切に社会保険の加入を案内したい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
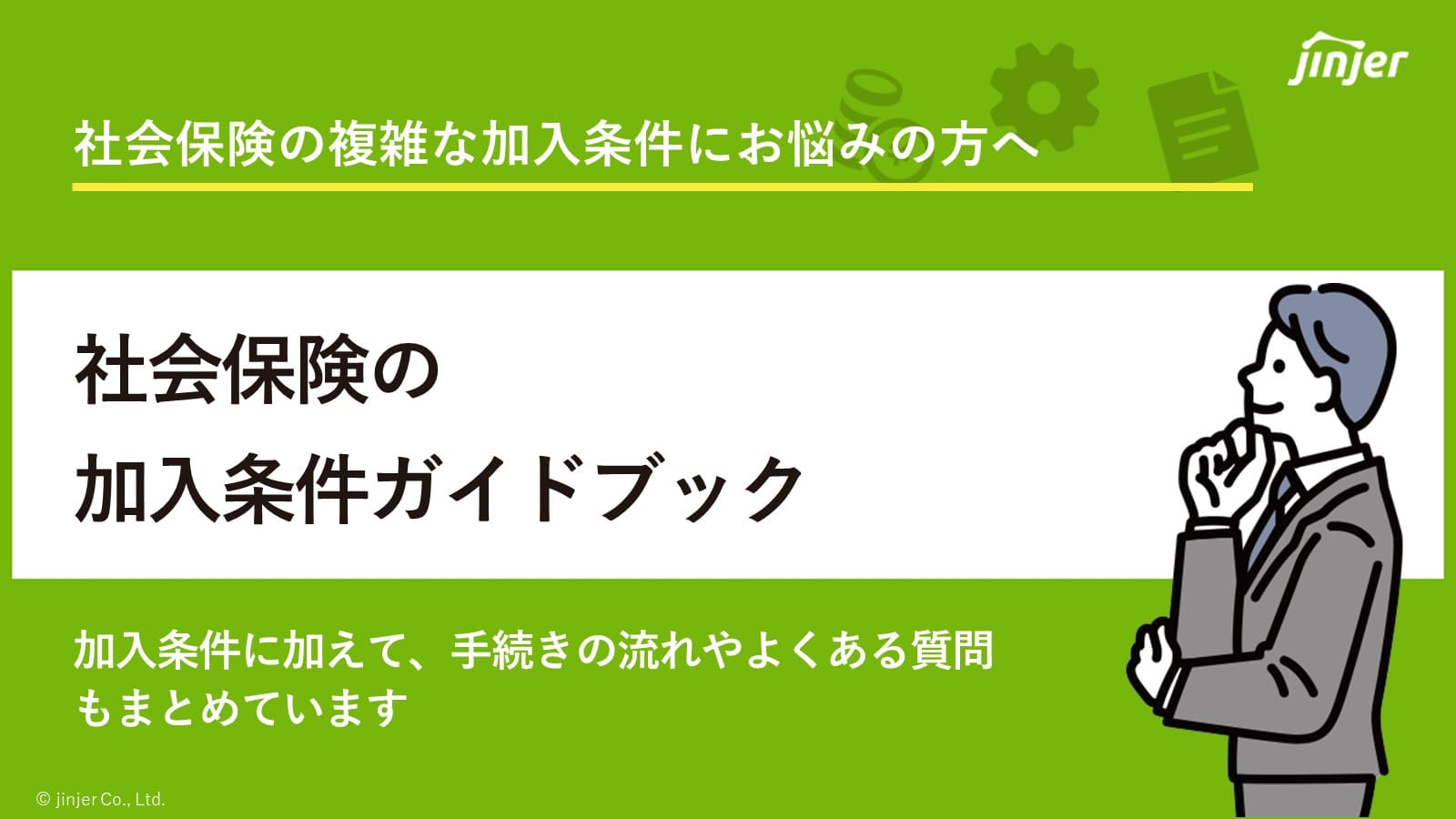
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08


























