社会保険とは?国民健康保険との違いや加入・扶養の条件、2024年10月からの適用拡大について
 社会保険と雇用保険は、保障内容や加入条件に違いがあります。
社会保険と雇用保険は、保障内容や加入条件に違いがあります。
また、社会保険と一言でいっても、広義の意味と狭義の意味があるため、どちらを指しているかの理解がなければ、現行だけでなく法改正後の法律を正しく理解することはできないでしょう。
この記事では、上述した社会保険の基礎となる概要や雇用保険・国民健康保険との違い、加入条件や法改正の内容などを解説します。
関連記事:労務とは?人事との違いや業務内容、労務に向いている人などを解説
目次
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 社会保険とは


社会保険とは、国民が何らかの理由(病気・ケガ・失業・加齢など)により生活に困窮した際、一定の給付により救済を計ることを目的に作られた保険制度です。一般的には強制加入となります。
また、社会保険は相互扶助(社会全体での助け合い)の考えが基本です。
そのため、多くの国民が加入することで財源を確保し、万が一に備える仕組みとなっています。
1-1. 広義の意味での社会保険
また、社会保険と一言でいっても、「広義の意味」と「狭義の意味」があるため、実務の際は注意しましょう。
広義の意味の社会保険には、下記の5種類の制度が含まれます。
- 健康保険
- 厚生年金保険(年金保険)
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
ここではそれぞれの概要を解説します。
① 健康保険
健康保険制度の目的は、病気やケガ、出産や死亡の際に、医療給付や手当金などを支給することにより、国民の生活安定を計る制度です。
会社員か自営業者かなど、職域により加入する保険先の保険者は異なるものの、日本では全ての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が取られています。
そのため、国民は医療機関を自由に選べるだけでなく、高度な医療も現役世代は3割、それ以外は2~1割の自己負担額で受けられます。
さらに高額療養費制度なども導入し、安心・安全に医療を受けられる仕組みが整っています。
加入できる制度は、職業や年齢などにより、下記のように分かれます。
- 健康保険
健康保険の適用事業所で働く会社員が加入できる。保険者(運用主体)は全国健康保険協会や各健康保険組合。 - 船員保険
船員として船舶所有者に雇われる人が加入できる。保険者は全国健康保険協会。 - 共済保険
国家公務員、地方公務員、私学の教職員が加入できる。保険者は各種共済組合。 - 国民健康保険
上記1.2.3.の保険制度に加入していない自営業者や一般住民などが加入。保険者は居住地の市区町村。 - 後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者などが加入。保険者は後期高齢者医療広域連合。
会社の場合、全国健康保険組合(協会けんぽ)か各健康保険組合、どちらに加入しているかによって事務手続きが異なります。保険者は、全国健康保険組合、各健康保険組合、市区町村と加入制度により異なります。
② 厚生年金(年金保険)
厚生年金は公的年金保険制度の一つです。
公的年金保険制度では、基本的に20歳から60歳の人が年金制度に加入します。
全員が保険料を納めることで、高齢者や障害をもつ人、会社員に扶養されていた遺族などに給付することで、支える仕組みとなっています。保険者は厚生労働省、事務処理は日本年金機構が行っています。
年金制度も、全国民が加入する「国民皆年金」である点が特徴です。
また、実際に加入する制度は、下記の被保険者区分により異なります。
第一号被保険者
自営業者や学生など第二号、第三号以外の被保険者が加入。
加入制度は国民年金保険。基礎年金を受給できる。
第二号被保険者
会社員や公務員などが加入。なお、保険料の半分は会社が負担する。
加入制度は国民年金保険と厚生年金保険。基礎年金、厚生年金を受給できる。
第三号被保険者
会社員などに扶養されている者が加入できる。保険料の自己負担はなく、会社を含む第二号被保険者全体で負担する。加入制度は国民年金。基礎年金を受給できる。
また、第二号被保険者は上記のように国民年金と厚生年金の両方に加入できるため、2階建て構造の年金制度となっています。
さらに、企業によっては3階建て部分に相当する「企業年金」を導入しているケースもありますが、こちらは国が運用している制度とは異なります。
厚生年金は加入の下限年齢が定められていないため、学生でない20歳以下の従業員は加入する必要があり、原則70歳未満の従業員まで加入対象となります。また、保険料は従業員の給与に応じて異なります。
③ 介護保険制度
介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、2000年に設立された制度です。自己負担1~2割程度で必要な介護サービスを受けられます。なお、保険者は市区町村や広域連合です。
40歳以降の加入が義務付けられており、制度の内容は、下記の2種類の被保険者区分により違いがあります。
第1号被保険者
40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者が対象で、医療保険料と一緒に徴収される。
老化に起因する特定疾病により、要介護(要支援)状態となった場合のみ給付を受けられる。
第2号被保険者
65歳以上が対象。なお、第1号被保険者は所定の年齢に達すると、自動的に第2号被保険者に切り替わる。市区町村が徴収し、原則は年金からの天引き。要介護状態、要支援状態に認定されることで給付を受けられる。
実際に介護を受ける際は市区町村の職員や主治医などにより要介護認定の調査を行い、下記の分類により要介護度を判定します。
- 要支援(1~2):予防給付として、一部の介護サービスが受けられる
- 要介護(1~5):介護給付として、介護サービスが受けられる
実際に受けられるサービスは下記の通りになります。
- 訪問サービス:訪問介護、訪問入浴介護などを自宅で受けられる
- 通所サービス:デイサービス、デイケアなどを施設で受けられる
- 短期入所サービス:看護師の常駐する施設で短期間生活を送れる
④ 労働者災害補償保険制度
労働者の業務上、または通勤などによるケガや病気に対し保険給付を行い、社会復帰の促進を行う保険事業です。
療養給付、休業給付、障害給付、介護給付などが受けられます。
保険料は、原則会社が全額負担し、労働者が支払うものではありません。保険者は厚生労働省や各都道府県の労働基準監督署です。
会社は一人でも労働者を雇用する際は、必ず労災保険に加入しなければいけません。ここでいう労働者とは、正社員・パート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態を問わないため、注意しましょう。
また、会社自体の加入手続きは、労働基準監督署で行います。
⑤ 雇用保険
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定を目的としています。具体的には、失業時や教育訓練を受ける際に給付金を支給し、生活の支援と職業復帰を図るシステムです。この制度により、失業者には「失業等給付」が提供され、生活の困窮を防ぐとともに、再就職活動をサポートします。
また、雇用保険には「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二つの事業が含まれており、これにより失業の予防や雇用機会の増大、労働者のスキルアップが実現されます。
1-2. 狭義の意味での社会保険
このうち、厚生労働省などが「社会保険」と呼称するものは狭義の意味であり、
- 健康保険
- 厚生年金保険(年金保険)
- 介護保険
1.2.3のみを指しています。そのため、2022年、2024年の法改正で短時間労働者の適用範囲が拡大されるのは社会保険とは、健康保険と厚生年金(年齢によっては介護保険)となります。雇用保険や労災保険は労働者の安全や生活を守ることを目的とした「労働保険」です。「介護保険」は介護が必要な人を社会で支えることを目的としていることから、それぞれ運用目的が異なります。
社会保険と雇用保険の違い
狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)も雇用保険も、強制加入の保険制度であり、国が主体となって運用していることに変わりはありません。
しかし、両者はその目的や保障内容、加入条件などに違いがあるため、詳しく解説します。
①加入できる条件が違う
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険は、加入できる条件が異なります。社会保険の加入条件は後ほど詳細を説明しますが、加入条件のハードルは、社会保険の方が高く、雇用保険の方が低くなります。
②目的や保障内容が違う
社会保険と雇用保険は下記のとおり、保障の目的が異なります。
| 社会保険 | 労働保険(雇用保険) |
| 年金保障や医療費保障で、国民の生活を支える役割がある。 会社員は厚生年金保険と健康保険組合や協会けんぽの健康保険、自営業者などは国民年金保険と国民健康保険など、全ての国民が何らかの制度に加入する必要がある。 |
失業・休業・労働災害など、働くうえで困難が起こった際に、労働者を保障する役割がある。そのため、条件を満たす会社員は強制的に加入するが、会社員以外(自営業者や専業主婦(主夫)など)は加入できない。 |
以上のように、社会保険と雇用保険は保障する対象が異なるため、誰が加入できるかも異なります。
そのため、従業員を雇用する際は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)も、労働保険(雇用保険)も、どちらにも加入が必要です。
③以前は管轄する省庁も異なっていた
社会保険と労働保険(雇用保険)は、2001年1月6日以降、どちらも厚生労働省が管轄し、保険事業を運営しています。しかし、以前は下記のとおり、保険を管轄する省庁に違いがありました。
- 社会保険:厚生省
- 労働保険:労働省
このように、運用の歴史から見ても、上記2つの保険制度には違いがあります。
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
2. 社会保険と国民健康保険の違い
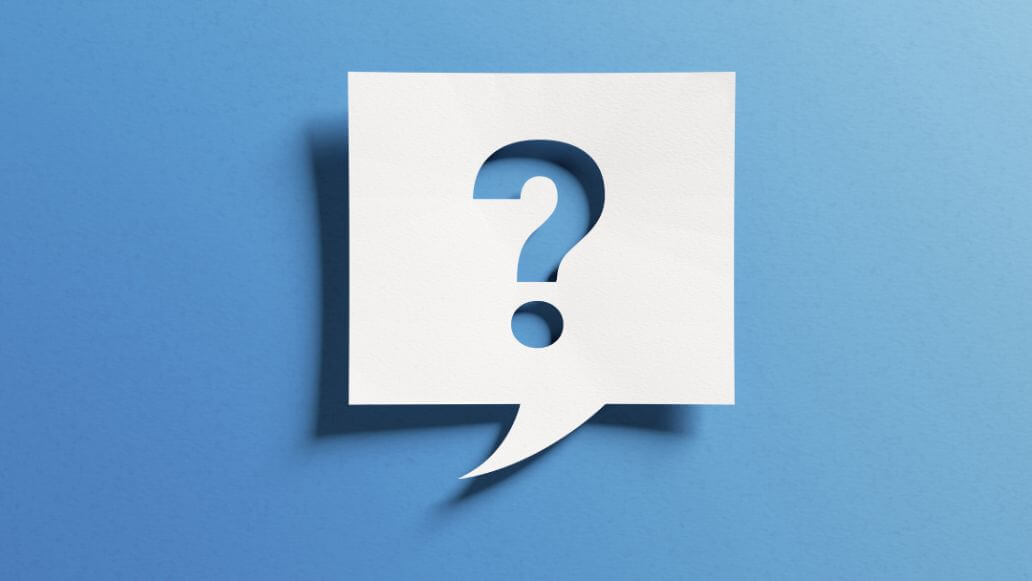
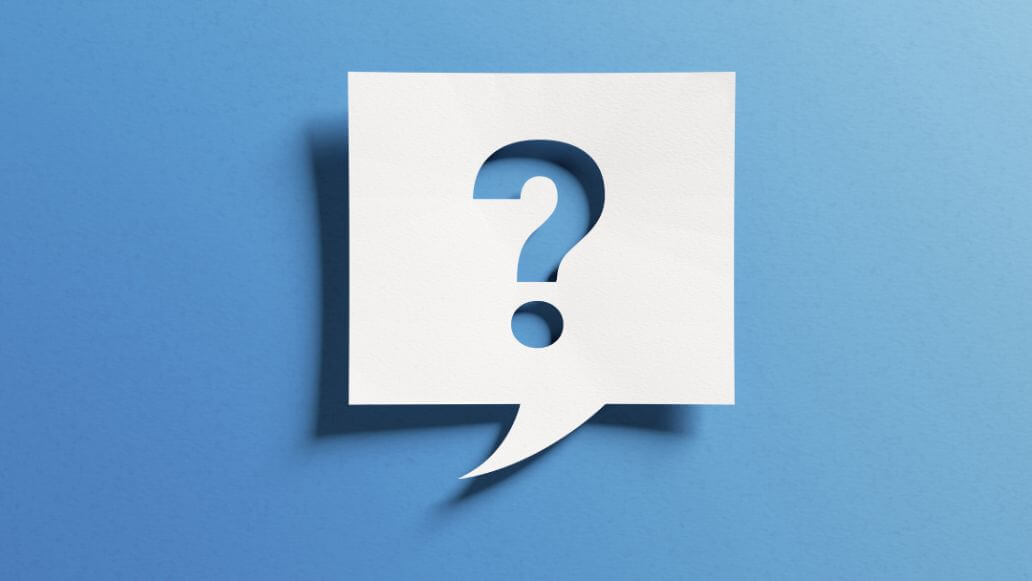
社会保険と似た制度に国民健康保険がありますが、これら二つは似て非なるものになります。違いを見ていきましょう。
2-1. 国民皆保険制度とは
国民皆保険制度とは、日本国内に住む全ての人が何らかの形で公的医療保険に加入し、医療費を分担する制度のことです。
これには「社会保険(健康保険)」や「国民健康保険」、「医療保険」が含まれ、全ての日本国民が対象となります。ただし、生活保護受給者や一部の外国人は適用外となります。この制度によって、医療費の自己負担が軽減されるため、誰もが必要な時に医療サービスを受けやすくなります。
2-2. 国民健康保険とは
国民健康保険とは、市区町村が運営する健康保険のことを指し、自営業である方や無職の方、年金受給者などの社会保険の加入対象外の方が加入する健康保険になります。もし自社の従業員が独立する場合は、社会保険から国民健康保険に切り替える必要があることを覚えておきましょう。また、従業員に違いを聞かれることもあると思いますので、正しく答えられるようにしましょう。
関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!
2-3. 加入条件の違い
社会保険と国民健康保険では、加入条件が大きく異なります。社会保険(健康保険)に加入するためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、第1に1週間の所定労働時間が20時間以上であること。次に、月額の賃金が8.8万円を超えていることです。また、2ヶ月を超える雇用の見込みがあり、学生でないこと(夜間学生や通信制は例外)も必要です。さらに、従業員101人以上の事業所、2024年10月からは従業員数51人以上の事業所で働くことが条件となります。
一方、国民健康保険は会社に属していないフリーランスや自営業、無職、年金受給者などが対象です。基本的には、社会保険や他の医療保険制度に加入していない国民がこの保険に加入します。これにより、全ての国民が医療保険の恩恵を受けられるような構成になっています。
このように、社会保険と国民健康保険は加入条件に大きな違いがあり、それぞれの働き方や生活状況に応じた適切な医療保険を選ぶことが必要です。最新の法改正情報にも注意を払いながら、最適な選択を企業として行うことが不可欠です。
2-4. 保険料計算方法の違い
社会保険(健康保険)と国民健康保険では、保険料の計算方法に明確な違いがあります。まず、社会保険(健康保険)の保険料は、被保険者の年齢や4月から6月に支払われた報酬の平均額に基づき「標準報酬月額」を決定し、それをもとに算出します。また、加入する保険組合や都道府県によっても保険料率が異なり、満40歳になると介護保険料も加算されます。この保険料は全額を個人で負担するのではなく、勤務先の会社と折半するという特徴があります。
一方、国民健康保険料は、世帯主が世帯全員分を負担し、被保険者の人数や収入、年齢をもとに計算されます。運営は市区町村が行っており、居住地によって保険料が異なります。さらに、一定期間の所得が基準を下回る世帯に対しては保険料が減額される制度がありますが、減額の基準も市区町村によって異なります。減額制度の詳細や自分の保険料率については、居住する市区町村のホームページから確認できます。
2-5. 扶養に対する考え方と対応の違い
社会保険(健康保険)と国民健康保険の扶養に対する考え方と対応には明確な違いがあります。まず、社会保険では被保険者が自分の配偶者、両親、親族を扶養者として入れることができ、被扶養者が増えてもその分、保険料が増加することはありません。たとえば、被扶養者には被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、兄弟姉妹が含まれ、主として被保険者によって生計を維持されていることが条件となります。また、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であることや、同居・別居の条件に応じた収入基準も適用されます。
一方で、国民健康保険には扶養の概念が存在しません。すべての家族がそれぞれ独立した被保険者として扱われ、例えば同居する配偶者や子どもも個別に保険料を支払います。国民健康保険の保険料は各個人の所得に基づいて計算されるため、家族の人数や収入によって大きく異なることが特徴です。このように、扶養に対する考え方と対応の違いは、企業の人事担当者や経営者にとっても重要な事項となるでしょう。
3. 社会保険の加入条件
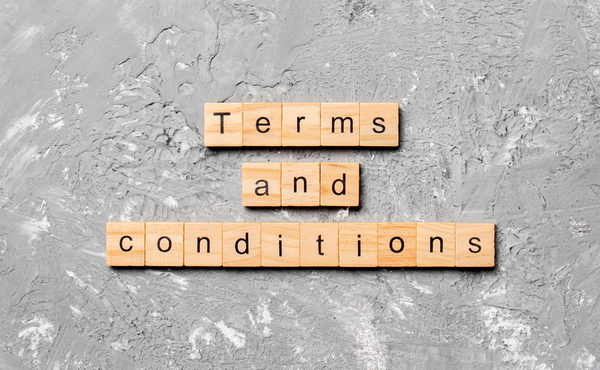
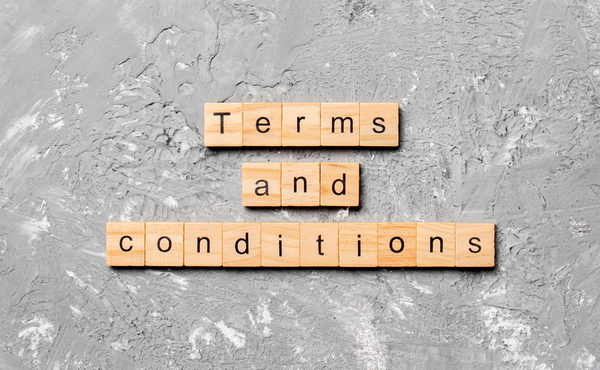
次に、厚生年金保険と健康保険に加入できる従業員の条件を解説します。
適用事業所で勤務している従業員は原則としては1週間および1ヶ月の所定労働時間が一般社員の4分の3以上の場合には社会保険に加入します。
ただし特定適用事業所等(厚生年金被保険者が101人以上の企業等)の場合には以下全てに該当する場合には社会保険に加入します。
- 1週の所定労働時間が20時間以上である
- 1カ月あたりの所定賃金が88,000円以上である
- 学生ではないこと
(100人以下の場合は、社会保険の加入について労使で合意がなされていること)
以上が現行の加入条件であり、上記に該当する従業員は加入が義務付けられています。
関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!
3-1. 社会保険の適用事業所とは
適用事業所とは、社会保険の適用を受ける事業所のことを指しており、法律によって加入が義務付けられている強制適用事業所と、任意で加入を選択できる任意適用事業所の2種類があります。
①強制適用事業所
強制適用事業所になるのは、以下のどちらかの条件に当てはまる必要があります。
①株式会社などの法人の事業所(事業主のみの会社である場合を含む)
②農林漁業やサービス業などの場合を除いた、従業員が常時5人以上いる事業所
②任意適用事業所
任意適用事業所は、強制適用事業所とならない事業所において、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、厚生労働大臣の認可を受けることができた事業所が該当します。
関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説
3-2. 社会保険制度に関する法改正
2016年以降から社会保険の重要性が見直され、短時間労働者の適用範囲が拡大されてきました。
現在の加入条件は先述した通りですが、2022年10月と2024年10月に法改正が2度行われる予定で、現行のものよりも社会保険の適用範囲が拡大されます。
2022年10月の法改正の内容
2022年の法改正では、④の勤務期間と⑤の従業員数の条件が緩和されます。法改正後の加入条件は以下の通りです。
- 1週の所定労働時間が20時間以上である
- 1カ月あたりの所定賃金が88,000円以上である
- 学生ではないこと
- 雇用期間が2か月を超えると見込まれること
- 従業員数が101人以上の会社の従業員であること
2024年10月の法改正の内容
さらに、2024年10月の法改正では、従業員が51人以上の会社に務める従業員で上記と同じ条件の者は社会保険への加入が必要となります。なお変更後の加入条件は以下の通りです。
- 1週の所定労働時間が20時間以上である
- 1カ月あたりの所定賃金が88,000円以上である
- 学生ではないこと
- 雇用期間が2か月を超えると見込まれること
- 従業員数が51人以上の会社の従業員であること
法改正の年が近くなりましたら、早めに従業員へ説明や面談を講じるようにしましょう。
この法改正では、従業員が51人以上の会社に務める従業員で上記と同じ条件の者は社会保険への加入が必要となるので、早めのうちに従業員へ説明や面談を講じる必要があります。当サイトでは、このような最新の法改正に対応した社会保険手続きに関する資料を無料で配布しております。 法改正の内容や社会保険に関する正しい手続きの方法を確認しておきたい方は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。
参考:厚生労働省「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
関連記事:法改正による社会保険適用拡大で企業側が対応すべきポイントとは
4. 社会保険の加入・資格喪失手続きと必要になる書類


社会保険関連の手続きは、必要書類の種類が多いにもかかわらず、手続きの期限が5日以内や10日以内と非常にタイトなスケジュールで行われます。
そのため、社会保険手続きの全体像を把握していないと、書類の漏れや記入ミスが発生した際に、期限に間に合わないリスクがあるので注意が必要です。
本章では入退社手続きや名義変更手続きなどを網羅的に解説しているため、スムーズな手続を行うためにも流れを把握しておきましょう。
4-1. 入社時の加入手続き・必要書類
社会保険の中でも狭義の意味合いで用いる健康保険・厚生年金保険の加入手続き方法をご紹介します。
①健康保険・厚生年金保険の加入手続き・必要書類
社会保険への加入手続きの概要は以下になります。
- 手続きを行う期限:加入義務が発生した日から5日以内
- 提出先:事業所の所在地を管轄している年金事務所
- 提出方法:電子申請・郵送・窓口持参
- 必要書類:申請書類・会社が用意する添付書類・従業員が用意する添付書類
社会保険への加入手続きは、加入義務の事実が発生してから5日以内に社会保険被保険者資格取得届を提出しなければいけないため、非常にタイトなスケジュールになります。
加入手続きを行う担当の方は入社前から必要書類の回収などの準備を進めましょう。また、加入手続きや必要書類について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。
関連記事:社会保険の加入手続き方法や必要書類を詳しく紹介
関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説
関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?必要になる事業所や手続きについて
関連記事:社会保険資格取得届とは?提出が必要な事業所や手続きの流れについて
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
②雇用保険の加入手続き・必要書類
続いて、雇用保険の加入手続きの概要は以下の通りです。
- 手続きを行う期限:加入義務が発生した日から10日以内 ※(資格取得届は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)
- 提出先:事業所の所在地を管轄しているハローワーク
- 提出方法:電子申請・郵送・窓口持参
- 必要書類:保険関係成立届・雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険も社会保険と同様に、加入義務が発生し、翌月10日以内に手続きを完了させないといけないため、あらかじめ書類の準備を行うようにしましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の加入要件や記入時の注意点について
③70歳以上の労働者を雇用する場合の手続き
70歳を迎える従業員がいる場合や雇用する場合には注意が必要です。
70歳を迎える誕生日の前日に厚生年金の資格を喪失してしまうので、70歳を迎えた日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被雇用者該当届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
70歳以上、もしくは70歳を超えそうな従業員がいる企業の担当の方で、より詳しく対応を知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。
関連記事:社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点
4-2. 退職時の手続き・必要書類
入社時と同様に、従業員が退職する際も社会保険の脱退手続きが必要になります。手続きの期限も入社時と同様に短いため、本章を通して流れを把握しましょう。
関連記事:従業員が退職する際の社会保険の手続きや退職者に渡す書類について
①健康保険・厚生年金保険の脱退手続き・必要書類
従業員が退職・転勤・死亡したときに提出しなければならないのは、「社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格喪失届」になります。提出期限は、原則として事実発生(退職や転勤日などの翌日)から5日以内と、非常にタイトな事務手続きが必要になるため注意が必要です。
手続の手順は以下の通りです。
①被保険者資格喪失届を書く
②健康保険被保険者証を返却してもらう
③被保険者資格喪失届を提出する
また、そのほかの必要書類に関しても知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースとは
関連記事:社会保険喪失証明書の発行までの流れや国民健康保険への切り替え方法
関連記事:社会保険喪失届が必要なケースや提出が義務付けられた書類とは
②雇用保険の脱退手続き・必要書類
雇用保険の脱退手続も健康保険・厚生年金保険と同様の手続きを踏む必要がありますが、提出期限が異なるため正しく覚えておきましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、事実発生の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄しているハローワークに届け出る必要があります。詳しくは以下の関連記事で解説しているためご覧ください。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説
③健康保険被保険証の返納手続き
従業員が退職により健康保険の被保険者資格を喪失する場合、該当従業員から、交付していた健康保険被保険者証を返納してもらう必要があります。事業主が提出する「被保険者資格喪失届」に添付する箇所があるため、資格喪失届の提出に間に合うように従業員から回収し、日本年金機構へ忘れずに提出しましょう。
4-3. そのほかの手続き
社会保険関連の手続きは、入退社時の一般的なものだけでなく、結婚した場合などのイレギュラーな手続や国民健康保険への切り替えなどが生じる場合があります。
本章で解説する手続きを行うケースは少ないですが、いつでも対応できるように流れを覚えてきましょう。
国民健康保険から社会保険へ切り替える際の手続き
国民健康保険から社会保険への切り替え手続きが発生するケースとしては、フリーランスなどの自営業を行っていた方が入社するケースが考えられます。
まず雇用主側は、社会保険加入手続きを5日以内に行えば問題ありません。
次に従業員側は、年金手帳とマイナンバーが記載されている書面の写しとともに「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。国民健康保険の資格喪失手続きも従業員は必要になるため、入社前に対応済みかどうか確認するようにしましょう。
また以下の関連記事に、社会保険から国民健康保険に切り替える際の手続きに関しても記載しているため、気になる方はご覧ください。
関連記事:社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険の特徴について
関連記事:社会保険で名義が変更になった時にやるべき手続きとは?
5. 社会保険に加入するメリットとデメリット
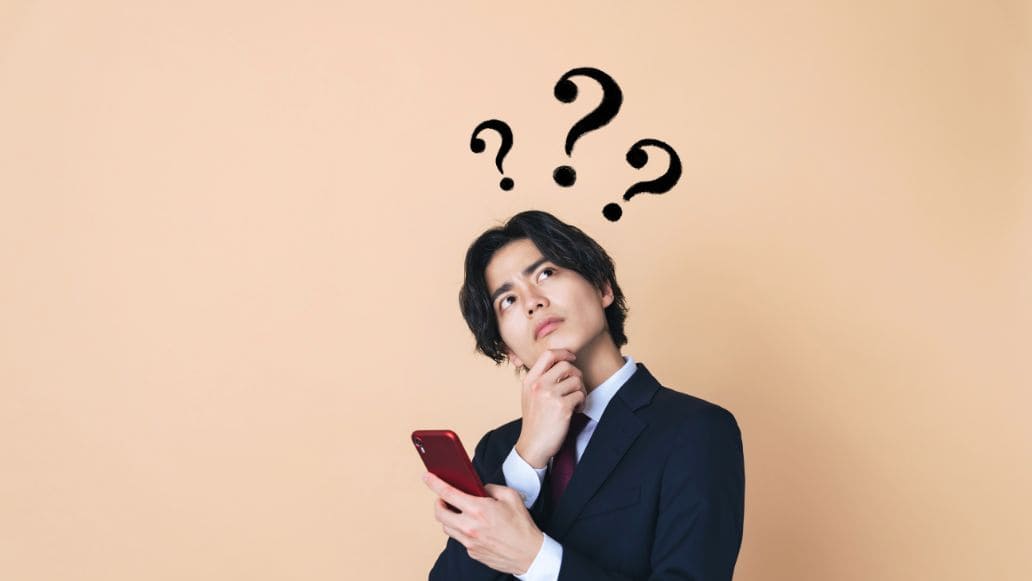
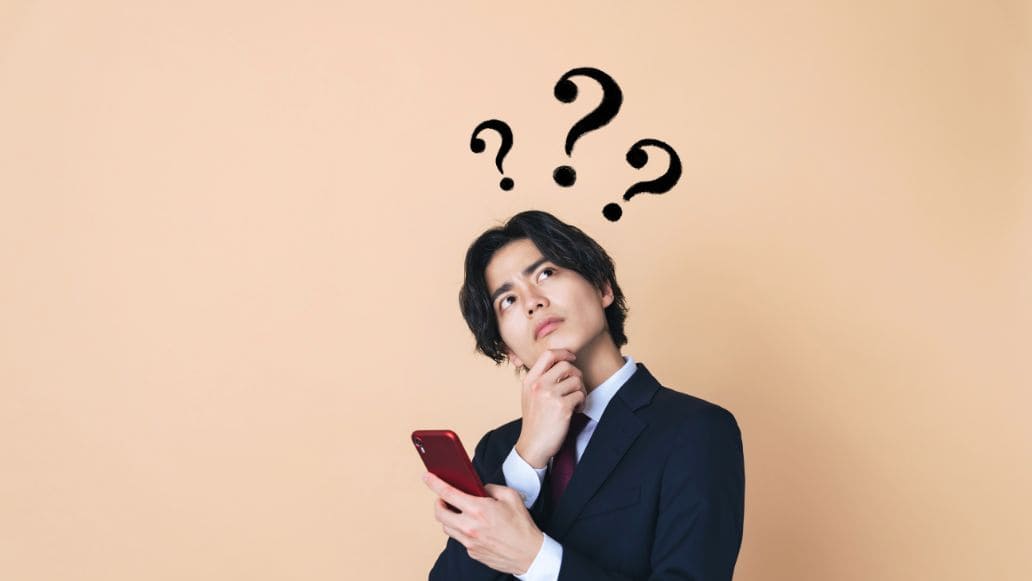
社会保険に加入すると、従業員側と企業側にとってそれぞれメリットとデメリットがあります。具体的に紹介します。
5-1. 従業員側から見るメリット・デメリット
社会保険に加入する従業員側のメリットとして、まず「第2号被保険者」として国民年金のみならず厚生年金を上乗せして受け取れるという点があります。
このため、将来の年金受給額が増えることが期待されます。また、健康保険料が会社と折半されるため、従来の国民健康保険よりも個々の負担が軽くなります。さらに、扶養基準の130万円を意識せず働くことができるため、収入を増やしやすくなる利点もあります。病気やけが、出産時には傷病手当金や出産手当金が支給され、生活の安定が図れます。万が一死亡した場合でも、家族に遺族厚生年金が支給されるという保障があります。
一方、デメリットとしては、配偶者の扶養範囲内で働いていた人が社会保険に加入すると、毎月の保険料が給与から天引きされることで、勤務時間によっては手取り額が減少する可能性があります。このため、特にパートタイムで働いている従業員にとっては注意が必要です。
5-2. 会社側から見るメリットデメリット
まず、企業側から見たメリットとして、「社会保険完備」の会社は求人時に非常に魅力的とされ、優秀な人材を集めやすくなります。さらに、生産性向上を目的とした国からの補助金を優先的に受け取れるケースがあり、結果的には企業の競争力を強化することが可能です。
一方でデメリットについても考慮が必要です。具体的には、従業員の健康保険料を企業側が従業員と折半することになり、その分の支出が増えるため、従業員1人あたりの雇用コストが高くなります。このため、一度に多くの従業員を雇う際には予算に対する負担が増えることが懸念されます。
企業の人事担当者や経営者は、これらのメリットとデメリットをよく検討し、自社の経営戦略と人事方針に合った社会保険の運用を考えることが重要です。最新の法改正情報にも留意し、柔軟に対応する姿勢が求められます。
6. 社会保険の扶養の条件とは


社会保険手続きを行う中で、従業員から扶養に関する相談を受けることも少なくないかなと思います。
社会保険の扶養の条件は以下の2つ存在します。
①被扶養者の範囲
②収入条件
まず①の被扶養者の範囲に関しては、被保険者との同居の必要性の有無で2種類の条件があります。
被保険者との同居が必要ないケースにおいては、配偶者や子、孫及び兄弟姉妹、直系尊属である人が扶養条件を満たします。また、甥っ子や姪っ子、ひ孫、祖父母などの「3親等以内の親族」は、同居していれば扶養条件を満たすことになります。
続いて②の収入条件に関しては、「年間130万円未満」であることが条件になります。ただし、60歳以上または障害者の場合は、「年収180万円未満」まで引き上げられます。
より詳しく確認したい方は以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、扶養のメリットを解説!
6-1. 社会保険の扶養を外れる際の手続き・必要書類
もし社会保険の扶養を外れる必要がある場合は手続きをしなければなりません。
必要な手続きは大まかに3種類に分けることが可能で、「雇い入れ側がすべき手続き」「扶養を外れる従業員がすべき手続き」「被扶養者が勤める会社がすべき対応」に分かれます。
詳しくは以下の記事に詳しくまとめてありますので、気になる方はご確認ください。
関連記事:社会保険の扶養が外れる条件とは?外れることによる影響や必要な手続きを解説
関連記事:健康保険被扶養者届を提出すべきケースや手続きの流れについて解説
7. 社会保険を考える上での注意点


ここまで社会保険の概要や加入条件、必要な手続などを解説してきましたが、そのほかにも退職時や社会保険未加入時などに注意すべき点があるので、本章ではその注意点を4点ピックアップして解説します。
7-1. 社会保険未加入の場合に罰則が生じる
社会保険に加入しなければならない事業所が未加入、もしくは従業員を加入させなかった場合、複数の罰則が生じてしまうので注意が必要です。罰則は、以下の4種類になります。
①6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
②未加入であった過去2年間に遡り加入をし、保険料を徴収
③延滞金の発生
④ハローワークに求人が合出せない
未加入の場合、罰則はもちろん痛手になりますが、本来加入すべきであるのにもかかわらず未加入であるという不信感を従業員に抱かせてしまうことによる人材の放出のリスクもあるので、未加入は必ずしないようにしましょう。
また、未加入時の罰則に関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。
関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説
関連記事:社会保険の遡り加入をすべきケースや支払い方法について
7-2. 70歳以上の従業員の社会保険の取り扱いに関して
2021年4月に雇用保険法等改正が施行され、70歳までの雇用確保努力義務が各企業に課せられるようになりました。
また、70歳以上の労働者を雇用する場合、健康保険や厚生年金保険の再度加入手続きが必要になるため、注意が必要です。
また、75歳を迎えるもしくは75歳以上の労働者を雇用する場合は、健康保険被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。返納期限が、「資格失った日(75歳の誕生日の前日)から5日以内」となるため、忘れずに対応しましょう。
7-3. 社会保険の2重加入に該当する従業員がいる場合
働き方改革の後押しの元、副業や複業が許可される企業が増えつつあります。
基本的には本業の会社で社会保険に加入していると思いますが、副業の場合でも1週間で30時間以上の労働時間があると、社会保険に加入しなくてはなりません。これが、社会保険の二重加入という状態になります。
社会保険の二重加入を行う場合は、別途手続きが必要になります。自社でダブルワークの従業員がいる場合は、社会保険の二重加入の対象であるか事前に確認しておきましょう。
なお、雇用保険は1つの会社のみで加入となり、基本的には本業の会社での加入になるので、頭の片隅で覚えておきましょう。
7-4. 退職する従業員に社会保険の任意継続を必ず案内する
健康保険の任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度になります。
退職後は、国民健康保険に加入することが一般的と考える労働者の方が多いため、この任意継続の条件を満たす場合に案内をしないと労使間トラブルに発展する恐れがあります。
こちらは、労働者に対する権利でもあるため、退職前に任意継続するか否かを必ず確認するようにしましょう。
8. 社会保険の手続きはシステムを用いてラクに


社会保険は5つの保険から成り立っており、それぞれ目的や加入条件が異なります。各社会保険の加入手続きや脱退手続は、5日以内の提出や10日以内の提出など、かなりタイトなスケジュールで進むため注意が必要です。
コロナ過においてリモートワークが進み電子申請が可能になっており、電子申請に適応した人事・労務管理システムを行うことで業務の手間を減らすことが可能です。
従業員の出入りが多いなどで社会保険手続きにお困りのご担当者様は、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08





















