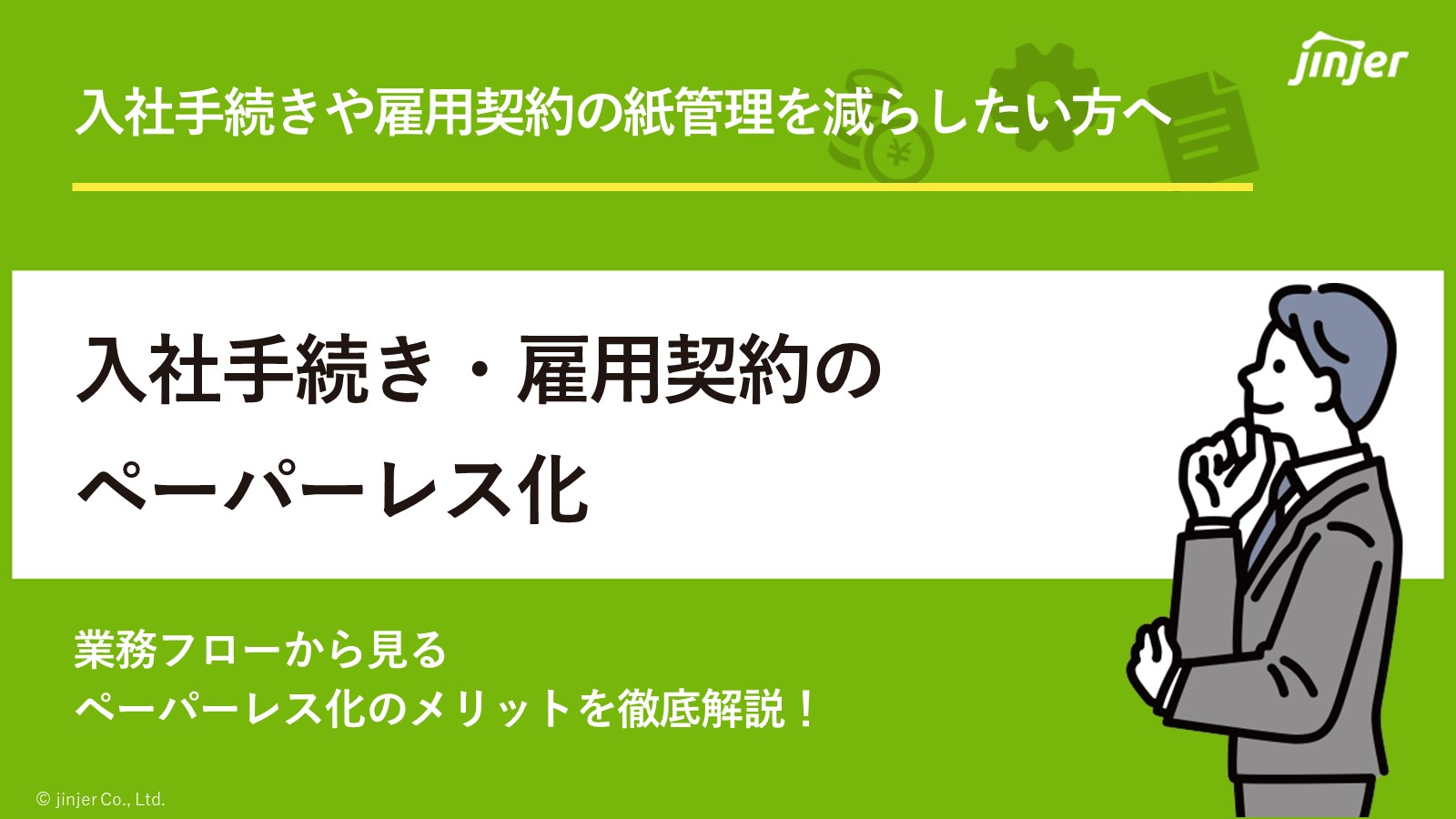労務とは?人事との違いや仕事内容、労務に向いている人や資格について解説
更新日: 2024.7.24
公開日: 2023.6.1
OHSUGI
 従業員の勤務状況や会社のルール策定などを担っているのが労務担当者です。企業において重要な資産と言われている、ヒト・モノ・カネ・情報のひとつである「ヒト(従業員)」を管理する労務は、企業にとって大切な業務です。この記事では労務の具体的な業務内容や労務の業務が向いている人材の特徴、労務の仕事を効率化するコツを紹介します。
従業員の勤務状況や会社のルール策定などを担っているのが労務担当者です。企業において重要な資産と言われている、ヒト・モノ・カネ・情報のひとつである「ヒト(従業員)」を管理する労務は、企業にとって大切な業務です。この記事では労務の具体的な業務内容や労務の業務が向いている人材の特徴、労務の仕事を効率化するコツを紹介します。
目次
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
1. そもそも労務とは?


また、労務には従業員の勤怠管理や労働契約の管理なども含まれ、組織と従業員の関係性を円滑に維持するための重要な業務です。さらに、労務は法令や労働基準に従った業務遂行が求められるため、法的な知識も必要となってきます。
組織の運営において労務は欠かせない要素であり、適切な労務管理を通じて従業員の満足度向上や効率的な業務遂行が実現されることになります。
関連記事:労務管理の基礎知識!目的や仕事内容、勤怠管理・人事管理との違いを徹底解説
2. 労務と「人事」はじめ似た言葉との違い


- 労務:福利厚生や労働安全衛生管理など労働環境を整える業務
- 人事:採用や育成、評価、昇格など企業の中の人材管理が主な業務
具体的には、労務は福利厚生の提供や労働時間管理、労働安全衛生対策、労働条件の遵守など、従業員の働く環境や条件を整える業務に関わります。これによって従業員の健康や働きやすさを確保し、労働環境の改善に寄与します。
一方で、人事は組織の目標や戦略に合った人材の配置や育成を行います。採用活動や研修計画の策定、従業員のパフォーマンス評価、キャリア開発のサポートなどが人事業務に含まれます。組織の成果を最大化するために、適切な人材を確保し、成長を促進する役割を果たします。
一般的には、労務はより組織全体の運営や従業員の生活面に焦点を当てた業務であり、人事は人材の選抜・育成・評価に関する戦略的な業務といえます。しかし、企業によって人事のなかに労務が含まれているケースや人事担当者が労務業務を兼ねていることもあるでしょう。そのため、企業や人によって労務と人事の認識に差があるかもしれません。
関連記事:人事と労務は何が違う?業務内容と適性、キャリアアップにつながる勉強を解説
関連記事:「人事管理」と「労務管理」の違いとは?具体例でわかりやすく解説
2-1. 労務と役務の違い
「労務」は、労働に関連する事務処理や管理業務を指します。労働環境の整備や労働条件の管理、従業員の健康や安全を守るための業務を含みます。労務は、労働にまつわる法的な規定や規則を遵守しながら、従業員の働く環境をより良くすることを目指す業務です。
一方、「役務」は、広い意味での「役割」や「業務」という概念を指します。ある人や組織が他の人や組織に提供する特定の働きやサービスを指します。具体的な活動や提供されるサービスによって異なる意味を持つことがあります。
簡潔に言うと、労務は主に労働に関連する事務や管理、従業員の働く環境に関わる業務を指し、役務は広範な「役割」や「業務」を指していると言えます。
2-2. 労務と総務の違い
「労務」と「総務」は、組織内で異なる業務領域を指す用語です。
「労務」は、従業員の労働に関連する事務処理や管理業務を指すのに対し、「総務」は、組織内の広範な一般的な管理業務を指します。
具体的には、オフィスの設備や備品の管理、施設の運用、法的な手続きや契約管理、資産管理、庶務などが総務業務に含まれます。組織全体の円滑な運営や効率的なリソースの利用を支える役割を果たします。
3. 労務の主な仕事内容


3-1. 就業規則はじめ規程の管理
労務担当者にとって、社内の規則や規定の管理も業務のひとつです。たとえば企業のルールとなる就業規則は、労働基準法に基づいて作成して届け出ることが義務付けられています。[注2]
一方、就業規則以外にも社内規定として賃金や育児、介護休業について作成します。
[注2]厚生労働省 北海道労働局|就業規則を作成・届出、周知しましょう
関連記事:労使協定の基礎知識や届出が必要なケース・違反になるケースを解説
関連記事:労働基準法第89条で定められた就業規則の作成と届出の義務
3-2. 社会保険の手続き
労務の主な仕事内容として社会保険の手続きがあります。傷病時に必要な健康保険や、将来の備えとなる厚生年金、退職後の生活を保障するための雇用保険など、各種社会保険の手続きを社員に代わって行います。それぞれの手続きは、必要書類の提出期限が設けられているため、入社後にスピーディーな手続きが進められるよう、入社前の適切なガイダンスも必要です。
3-3. 勤怠管理(有給)の管理
勤怠管理では従業員の出勤状況、遅刻や早退などの情報を勤怠管理として管理する必要があります。勤怠の管理は人事評価とつながり、給与と関係してくるため労務担当者は正しく管理するようにしましょう。
また、2019年4月より働き方改革によって年次有給休暇の取得が義務化されました。[注1]
有給休暇はもともと従業員の心身を回復させることが目的です。そのため、義務化という理由だけでなく、従業員のストレスを緩和させるためにも、正しく有給休暇を管理しましょう。
[注1]厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
関連記事:勤怠管理は何をチェックするべき?用意すべき法定三帳簿とは?
関連記事:勤怠とは?管理方法や管理項目など人事が知っておきたい基礎知識を解説!
3-4. 給与計算
従業員の勤怠管理を行う労務担当者は、同様に給与の計算も行います。給与は従業員のモチベーションと関係しています。そのため、給与の計算を誤ってしまうと、従業員のモチベーションが低下しかねません。従業員のモチベーションを低下させないためにも、給与計算はミスしないように心がけましょう。たとえば給与計算を処理するシステムや、税理士や社労士といった専門家への給与計算代行の検討がおすすめです。
3-5. 福利厚生の整備
労務の主な仕事内容として福利厚生の整備が挙げられます。福利厚生とは、企業が従業員に対して提供する給付やサービスのことです。制度を整備し、従業員の働きやすさを向上させることが、労務の重要な役割となります。
法定福利と法定外福利との2種類がある
福利厚生には法定福利と法定外福利の2種類があります。具体的には次のとおりです。
| 福利厚生の種類 | 具体例 |
| 法定福利 |
など |
| 法定外福利 |
など |
関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容について解説
関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
関連記事:育児休業とは?対象者や必要な手続きについて徹底解説
3-6. 「法定三帳簿」の管理
労務の業務と共に把握しておきたいのが「法定三帳簿」です。
「法定三帳簿」とは「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを指します。この3つの帳簿は、労働基準法上で作成が義務付けられており、帳簿の中に記載する項目や保存期間がそれぞれ定められています。
| 記載する項目 | 保存期間 | |
| 労働者名簿 |
|
5年(当分の間は3年) |
| 賃金台帳 |
|
5年(当分の間は3年) |
| 出勤簿 |
|
5年(当分の間は3年) |
関連記事:労働基準法第109条規定の労働者名簿の正しい取り扱い方
関連記事:賃金台帳とは?基本的な作成方法と知っておきたい法的ルール
関連記事:出勤簿の役割とは?効率的に管理する方法を詳しく紹介
3-7. 労働安全衛生として従業員のメンタルヘルスを管理
労働安全衛生法では従業員へのストレスチェック実施が義務付けられました。[注3]
ストレスチェックを実施することで、従業員の心のバランスを確認して不調を未然に防ぐ、ストレスの原因となる職場の環境を改善できるといったメリットにつながります。従業員のストレスが溜まってメンタルヘルスに不調をきたすと、後々離職につながってしまうかもしれません。
[注3]厚生労働省 滋賀労働局|2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました
4. 労務担当者の一般的な年間スケジュール
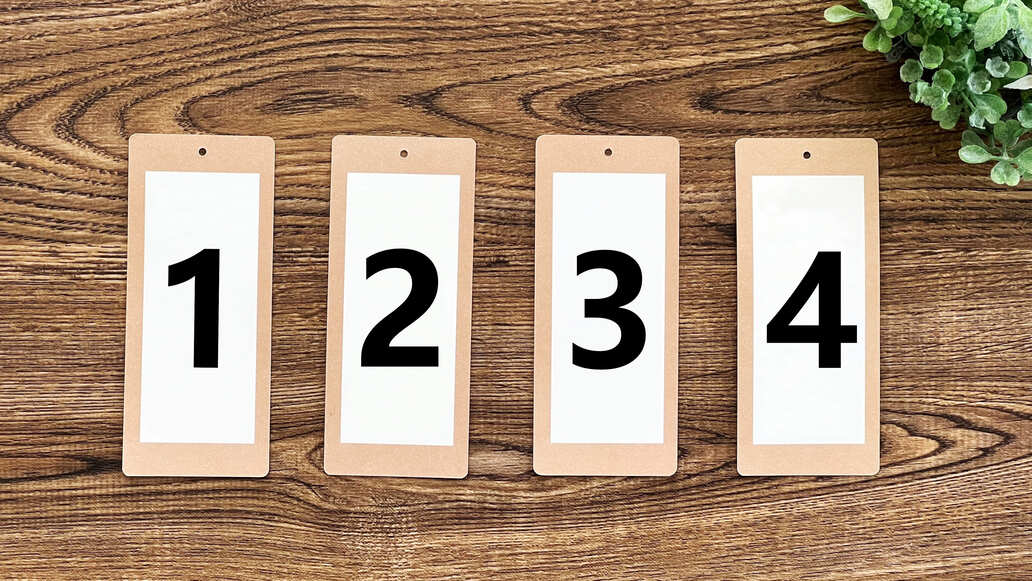
労務業務の年間スケジュールは、組織や業界によって異なる場合がありますが、一般的な目安を以下に示します。
1月~3月
年末調整の実施と提出:前年の給与支払いに関する年末調整を行い、必要な書類を提出します。
年次有給休暇の付与:新年度に向けて従業員に対する年次有給休暇の付与やリセットを行います。
労働契約の更新:期限切れとなる労働契約を更新または再契約する手続きを行います。
4月~6月
労働基準法改正の対応:新たな法改正に合わせて労働条件や手続きを見直し、必要な対応を行います。
年次健康診断の実施:従業員の健康状態を把握するための年次健康診断を実施します。
7月~9月
ボーナス支給:夏季ボーナスなどの支給に関連する手続きや計算を行います。
労災保険の更新:労働災害保険の契約を更新する手続きを行います。
10月~12月
年末調整の準備:次年度のための給与データや税金関連の情報を整理し、年末調整の準備を行います。
給与改定や昇進の対応:新年度に向けての給与改定や昇進に関する手続きを行います。
終業処理:年度末に向けて終了する業務や手続きに関する処理を行います。
5. 労務の仕事をおこなう上での注意点


5-1. 法令遵守
労務業務を遂行する際には、労働基準法や雇用関連の法律・規制に厳密に従うことが重要です。法令に違反することは組織にとって大きなリスクとなり、法的なトラブルや罰金の可能性があります。労働契約の適切な記載、給与計算、勤務時間の管理などの業務は、法令に基づいて正確に実施する必要があります。法改正や法規制の変更にも迅速に対応し、法的コンプライアンスを確保しましょう。
5-2. プライバシーとセキュリティ
労務関連のデータは個人情報を含むことが多いため、プライバシーやデータセキュリティに留意して取り扱う必要があります。
Excelなどのドキュメントで個人情報を管理する場合には、閲覧、編集のパスワードを設定する、社外への持ち出しを禁止するなど、ルールを厳格に設け、データの保護と機密情報の適切な管理を徹底しましょう。
厚生労働省は雇用管理に関する個人情報の適切な取り扱いについてまとめた指針も提示しています。
参照:雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説|厚生労働省
5-3. 従業員とのコミュニケーション
従業員との円滑なコミュニケーションは信頼関係を築くために重要です。労務業務に関する情報を適切に伝え、従業員からの質問や懸念に真摯に対応することが求められます。透明性を保ち、労務の方針や手続きについて理解を促進することで、従業員の満足度や信頼を高めることができます。また、従業員からのフィードバックを受け入れ、業務の改善につなげる姿勢を持つことも大切です。
6. 労務の仕事を効率化するコツ


- 業務を定型業務と非定型業務に分ける
- スケジュールを策定する
- 資料のペーパーレス化をすすめる
- 労務管理専用のツールを導入する
それぞれ、以下に詳細を解説します。
6-1. 業務を定型業務と非定型業務に分ける
業務には定型業務と非定型業務があり、それぞれの違いは次のとおりです。
- 定型業務:勤怠管理や給与計算など決まった手順で行なう業務
- 非定型業務:ハラスメント対策や就業規則の改定といったケースによって対応が異なる業務
両者のうち、定型業務は自動化、標準化しやすいため労務管理システムを活用してみましょう。一方、非定型業務は自動化、標準化が難しいため、適切な担当者を配置するようにしましょう。
6-2. スケジュールを策定する
労務業務の種類は多岐にわたるため、年間のスケジュールを策定して進めていきます。年間のスケジュールを策定することで、優先順位をつけられるため期限も把握しやすくなるでしょう。また、年間スケジュールを策定することで、定期的に実施される業務を一元管理可能です。さらに重複している業務や無駄な業務を省くことも可能です。
6-3. 資料のペーパーレス化をすすめる
デジタル化によるペーパーレス化も労務業務の効率化につながります。従来のように紙資料で管理していると、書類の発行や検索などに時間がかかってしまい、業務効率の低下につながりかねません。一方、デジタル化によってペーパーレス化することで、書類の発行、検索、保管がしやすくなります。
また、ペーパーレス化は業務の精度向上が期待できるでしょう。たとえば紙の場合は記入漏れをはじめとしたミスが発生しやすいです。一方、ペーパーレス化すれば記入漏れやほかのミス防止につながります。
関連記事:タイムカードでの打刻を電子化!ペーパーレス化のメリットや導入方法を解説
関連記事:年末調整のペーパーレス化とは?その背景や課題を詳しく解説
関連記事:給与明細の電子化(ペーパーレス化)!導入手順やメリット、注意点を徹底解説
関連記事:契約書をペーパーレス化する方法とは?メリットや注意点もあわせて解説
関連記事:ワークフローをペーパーレス化するには?効果や方法を徹底解説
6-4. 労務管理専用のツールを導入する
労務管理を効率化するためには、専用のツールを導入することもおすすめです。専用のツールを導入することで、定型業務を自動化可能です。また、ミスや手間の軽減にもなるでしょう。また、労働管理専用のツールのなかには、リアルタイムで従業員の動向を把握できるものもあります。
関連記事:労務管理ソフトを導入するときの注意点や選び方を紹介
関連記事:労務管理・人事管理のペーパーレス化とは?メリット・デメリット解説や具体例紹介
7. 労務のやりがいから考える向いている人


労務の仕事を説明してきましたが、その業務を担う上でのどんなやりがいがあるのでしょうか。業務を通して得られるやりがいは仕事を続けていく意味にもつながります。やりがいを感じながら業務に従事していくためにも、どんな人が労務の担当者に向いているのかを解説していきます。
7-1. 労務のやりがいとは
労務のやりがいとは、日々労働に関する法律のアップデートや制度への対応を担うため、情報収集能力が身に付き、その知識や能力は日常生活でも応用できるという点があげられるでしょう。習得した法律知識や社会保険の知識がそのまま実務で役立つ点が魅力です。また、労務という分野を通じて仕事や生活に役立つ多方面の知識が自然に身につきます。さらに労務の仕事において、従業員のライフステージの変更に伴って手続きを行うため、従業とより近い距離でコミュニケーションをとり、サポートできるという点もやりがいです。従業員の給与計算や社会保険の手続きを担当することで、直接的な感謝の言葉を受けることも多いようです。このように労務の業務には、単調な業務に見えがちですが、日々の業務を通じてやりがいを実感できる機会はたくさんあり、労働環境の改善に役立つことが、自身のモチベーション向上にも繋がります。
7-2. 労務に向いている人
労務業務には、正確性と細心の注意を持ち、細部に気を配り、ミスを最小限に抑えることが求められます。順をおって細かく作業をするのが好きな人に向いていると言えます。
日々従業員から質問を受けることも多くあり、コミュニケーションを円滑に行い、疑問や懸念に対応できるスキルも欠かせません。さらに、労務業務には従業員のプライバシー情報を含むため、倫理的な配慮が必要であり、情報を適切に保護し機密性を守る姿勢が求められます。
8. 労務の業務に求められる能力・スキル


求められるスキルや持っておくとより良いスキルとしては、以下があげられます。
- 労働基準法や雇用関連法規などの法的知識
- 表計算などのデジタルツールや人事・給与管理システムの操作をすることが多いため、基本的なコンピュータの操作スキル・ITリテラシー
- 労務業務にはさまざまな課題や問題が発生するため、複雑な状況に対して適切な問題解決策を見つける問題解決能力
- 法令遵守やプライバシー保護、データセキュリティに対する意識
詳しく解説します。
関連記事:人事労務管理のDXを成功させるには?よくある失敗事例をもとに解説
8-1. 労働環境に関わる法律知識
労務の担当者は日々会社を運営する上で関連してくる法律に触れながら業務を行います。
例えば労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法など関連してくる法律は多岐にわたります。そのため、労務担当者に求められる能力としては、労働環境に関わる法律知識の深さであるといえます。
8-2. ITリテラシーの高さ
労務管理の場面では、業務を効果化するために、勤怠管理システムや給与計算ソフト、社会保険手続きのためのオンラインツールなど専用のツールを導入することがあります。目的としては業務をペーパーレス化することで、手作業によるミスを減少させ、業務の正確性を高め業務工数を大幅に効率化することがですが、これらのツールは自動計算機能を使うための設定やデータ分析機能を活用するための設定を行う必要があり、パソコンの操作やITリテラシーが必要になる場面が多くあります。そのため、ツールやシステムを積極的に活用するため、ITリテラシーは必要なスキルです。
8-3. 個人情報保護における知識
労務担当者は従業員個人の情報に関わることが多いため、情報を保護するための知識やスキルも求められます。
例えば個人情報としてマイナンバーや家族の情報を預かることも多くありますが、このような情報が万が一にも漏えいしてしまった場合、担当者レベルの責任ではなく会社としての信用を失う危険性があります。そのため、労務担当者としては、個人情報の保護における正しい意識と知識が求められるのです。
9. 持っておくと労務の仕事に役に立つ資格


9-1. 社会保険労務士
労働基準法や社会保険に関する法律に基づく労働条件や社会保険制度に関するアドバイスや指導ができる国家資格です。労働者の保険や年金、雇用契約など幅広い領域に関する知識が求められます。
9-2. 労務管理士
人事管理や労務管理に関する知識を評価する民間資格です。従業員の雇用、労働契約、給与計算、評価制度などに関する専門的な知識やスキルを持つ資格です。
9-3. 衛生管理者
この資格は労働安全衛生法で定められた国家資格で、常時50人以上の労働者が勤務する事業所に1人以上必要になります。具体的には、従業員の健康や労働災害を防ぐために管理者として設けられる役割です。資格として取得していると会社側から手当が付与されるケースも多くあります。
9-4. 経営労務コンサルタント
労働関連のアドバイスやコンサルティング業務を行う際に活用される民間資格です。法的知識や労働条件に関する専門知識だけでなく、企業のニーズに合わせた労働問題の解決策を提供するスキルが求められます。
9-5. 給与計算士
給与計算や社会保険、税金に関する知識を評価する民間資格です。従業員の給与計算や賞与計算、税金の取り扱いなどに関する専門的なスキルが求められます。
10. 会社における労務の役割を理解して正しい組織運営を!


関連記事:勤怠管理をペーパーレス化するには?電子化のメリット・デメリットも解説
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08