労働基準法第109条規定の労働者名簿の正しい取り扱い方

労働基準法の第107条と109条には、労働者名簿に関する詳しい取り決めがあります。
労働者名簿とは、労働者の氏名や住所、採用した日や業務内容など、労働者に関する情報を書き記した書類のことをいいます。労働基準監督署が労働者名簿の有無をチェックすることもあるので、正しい方法で用意しておきましょう。
この記事では、労働基準法第107条と109条に規定される労働者名簿の扱い方について解説いたします。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 労働基準法に規定されている労働者名簿とは?
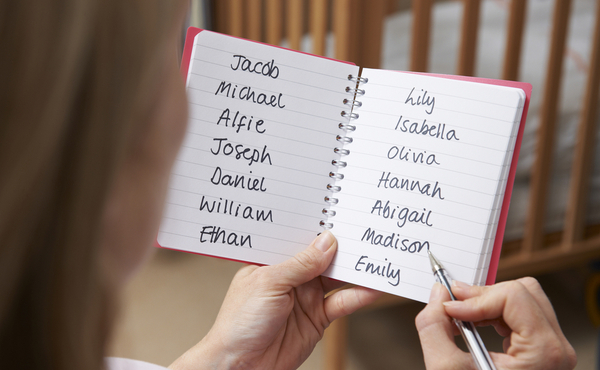
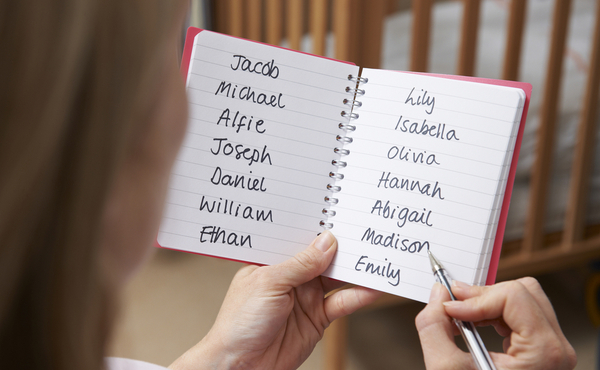
労働基準法第109条は、労働者名簿をはじめとする労働関連の書類の保存について規定している法律です。労働者を雇っている会社は必ず労働者名簿を作成し、必要な年数保管しなくてはいけません。
法律に従って正しく保管するためにも、労働基準法第109条に加えて、第107条と第108条の労働者名簿の取り決めについても、ここで合わせて押さえておきましょう。
1-1. 労働基準法第107条の内容とは
労働基準法第107条は、労働者名簿の作成を使用者に義務付けている法律です。労働者名簿に記入する項目については、以下のとおり定めています。
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない
引用:労働基準法|eーGov法令検索
また、労働基準法の施行規則第53条には、労働基準法第107条の労働者名簿に追加で記載すべき内容を以下のように明記しています。
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由
- 死亡の年月日及びその原因
つまり、労働者名簿には社内の人員の業務内容や役割などを詳しく記載する必要があるのです。さらに、従業員の退職または死亡の時期と理由についても記載しておきましょう。
ただし、従業員数が常時30人未満となるのであれば、従事する業務の種類の記入は必須とはなりません。
1-2. 労働基準法第108条の内容とは
労働基準法第108条では、次のとおり賃金台帳に関する取り決めを定めています。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
引用:労働基準法|eーGov法令検索
なお、労働基準法の定めに従って企業が作成する以下の3つの重要書類は、法定3帳簿と呼ばれます。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
労働者名簿には労働者の氏名や採用日など、労働者に関する情報を記載していきます。賃金台帳には労働者に対する給与の支払状況を、出勤簿には労働者の始業時刻や終業時刻など労働時間を詳しく記載しておきましょう。
これら3つの帳簿は労働基準監督署の立ち入り調査で確認されることが多いので、必ず作成し保管しておくことが大切です。
関連記事:賃金台帳とは?基本的な作成方法と知っておきたい法的ルール
関連記事:出勤簿の役割とは?効率的に管理する方法を詳しく紹介
1-3. 労働基準法第109条の内容とは
労働基準法第109条では、労働者名簿や労働関連の書類の保管について、次のとおり定めています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない
引用:労働基準法|eーGov法令検索
なお、労働基準法施行規則の第56条では、労働基準法第109条の規定に関して、起算日を設定しています。
これによると、労働者名簿は労働者の退職または解雇の日、労働者が業務上の事故で亡くなった場合には死亡日を起算日とすることになっています。労働者名簿はこの日から起算して5年間保管しておく必要があります。
2020年の民法改正によって労働基準法の内容も改正されました。元々は、3年間の保管で良いとされていましたが、法改正を機に5年間に延長されたのです。
ただし、当面の間は経過措置として3年間の保管期間も認められています。経過措置がいつまで有効かは明確ではないため、今後の法改正に目を光らせておく必要があるでしょう。
労働者名簿をはじめとする労働関連の書類は、労働者との間にトラブルが生じた際、紛争解決するための重要な証拠となり得ます。法改正への対応やトラブルを防止する上でも、5年間保管しておくのが望ましいと言えます。
2. 労働基準法による労働者名簿の作成が必要なケースとは


労働者を1人以上雇っている会社であれば、労働者名簿の作成義務が生じます。
企業の規模が小さいからといって労働者名簿の作成が不要となるわけではありません。また、個人事業主の場合でも労働者を雇っているのであれば労働者名簿を作成しておきましょう。
労働者名簿は企業全体で作成するのではなく、それぞれの事業所で作成する必要があります。つまり、支社や営業所、工場、お店といったそれぞれの組織で1つずつ労働者名簿を作成しなければならないのです。
また、労働者名簿の保管も事業所ごとにおこないます。企業本社の人事部や総務部でまとめて保管するのではなく、それぞれの事業所の責任において労働者名簿を保管しておきましょう。
労働者名簿には正社員だけでなくアルバイトやパートなど、雇用しているすべての労働者について記載します。ただし、一時的な日雇い労働者に関しては労働者名簿への記載の義務はありません。
労働基準法第107条第2項には、労働者名簿の更新について「遅延なく」と記載されています。労働者の異動や退職など入れ替わりや変更があったときには、すぐに労働者名簿の更新をしておきましょう。
3. 労働基準法による労働者名簿の作成方法


労働基準法における労働者名簿の作成方法に明確な決まりはありません。労働基準法第107条の規定にある労働者の氏名や性別、住所、履歴、雇用の年月日などが正しく記載されていれば、どのような書式で作成しても問題はないのです。
とはいえ、労働者名簿の作成方法に迷う方もいるでしょう。厚生労働省では、労働者名簿のテンプレートを配布しています。
労働者名簿を作成するときには、厚生労働省や各労働局のウェブサイトからテンプレートをダウンロードしたり形式の参考にしたりと工夫してみましょう。
3-1. 労働者名簿は電子データで作成・保管もできる
労働者名簿は手書きで作成するほか、電子媒体での作成や保管も許可されています。
電子データであれば、更新が必要となったときにすぐに情報を書き換えることができ便利です。IT環境が整っているのであれば、パソコンのシステムやクラウドツールを使用して労働者名簿を作成するのもよいでしょう。
ただし、電子媒体による労働者名簿の作成は、事業所内にコピー機があるなどすぐに印刷できることが条件となっています。
なお、労働者名簿には労働者の個人情報を記載することになります。労働者から個人情報を得るときには、各個人に必ず同意を取るようにしましょう。
個人情報の漏えいは企業にとって大きな打撃となります。リスクを避けるためにも、個人情報を記載した労働者名簿は適切に保管しましょう。
参照:主要様式ダウンロードコーナー(労働者名簿)|厚生労働省
4. 労働基準法における労働者名簿を正しく作成・保管しよう


労働基準法の107条には労働者名簿の作成に関する取り決めが、さらに109条には労働者名簿をはじめとした重要書類の保管方法に関する取り決めが記載されています。
労働者を雇うときには必ず労働者名簿の作成が必要となります。労働者名簿は労働者の実態を把握するための重要な書類となります。労働基準法の定めに応じて必要な情報を適切に記載し、保管しておきましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08






















