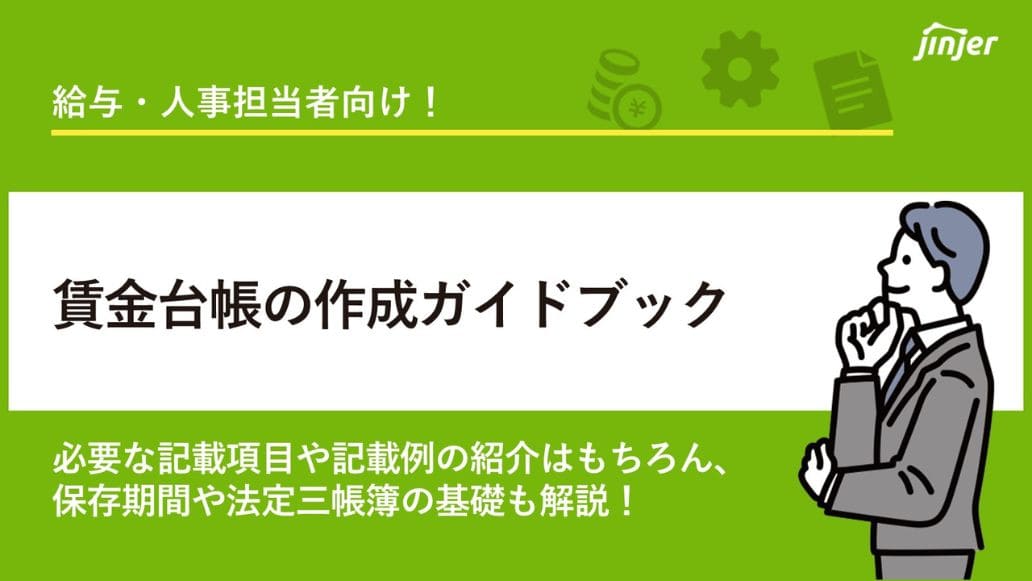賃金台帳とは?基本的な作成方法と知っておきたい法的ルール
更新日: 2024.4.15
公開日: 2021.11.12
OHSUGI
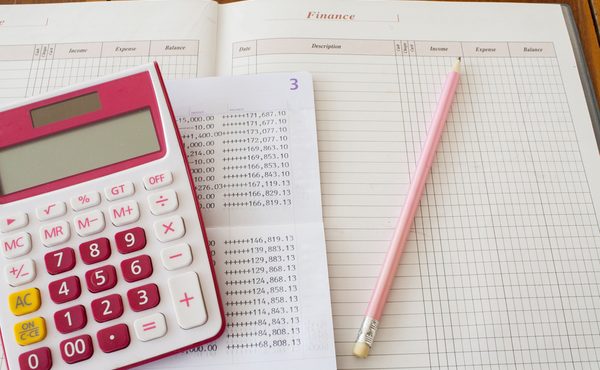
従業員を雇い入れている企業は、賃金台帳を作成して保存することが義務づけられています。この台帳は労働基準監督署や年金事務所などの調査の際に必要なもので、作成を怠ると罰則が科されることもあるため注意が必要です。
この記事では、賃金台帳の作成方法と法的ルールについて説明します。正しい作成方法と保存方法を押さえて、従業員への支払いを適切に管理しましょう。
「賃金台帳の作成方法や保管期間などがあっているか不安」
「賃金台帳を作成していない場合のリスクを知りたい」
など賃金台帳の取り扱いに関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、『賃金台帳の作成ガイドブック』を無料で配布しております。記載する際に必要な項目や具体的な記入例をまじえながら、作成手順を詳細に解説しています。
適切な保管期間や賃金台帳の基礎ついても詳しく紹介していますので、「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「賃金台帳の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、大変参考になる内容となっています。
ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
1. 賃金台帳とは?


1-1. 賃金台帳の役割
賃金台帳は、従業員への給与の支払情報を記録するもので、労働者の権利や労働条件を保護するための措置の一環として作られます。
給与の労働時間に対する支払い情報や、休暇、控除などの情報を正確かつ透明に記録し、法的要件を遵守するための根拠となります。
また、給与支払いのトラブルがあった際の情報源や、経営における支出管理のデータとしても活用出来ます。
1-2. 賃金台帳と給与明細の違い
賃金台帳と似た書類として、「給与明細」という書類があります。どちらも従業員に支払った給与について記載した書類ですが、記載事項が異なります。給与明細には賃金台帳の要件である法定項目が記載されていません。
1-2-1. 給与明細は賃金台帳の代わりになるのか?
給与明細は、賃金台帳の代わりになることはありません。給与明細と賃金台帳は、異なる目的と役割を持つ文書だからです。
賃金台帳は雇用主が保持する帳簿であり、労働者の給与や労働条件に関する情報を記録します。賃金台帳は法的な保存義務があり、国や地域の労働法や税法に基づき一定期間保存する必要があります。賃金台帳には従業員の個人情報や給与支払いの履歴が記載されます。
一方、給与明細は、従業員が受け取った給与や手当、控除などの詳細な情報を示す文書です。通常、従業員に対して給与支払いと同時に提供され、給与明細には支払い日や支払い内容、源泉徴収税額などが記載されます。給与明細は従業員に対して給与の明確な説明を提供する役割を果たしますが、法的な保存義務を負う文書ではありません。
以下に賃金台帳と給与明細の違いをまとめていますので、ここでしっかりと区別しておきましょう。
| – | 賃金台帳 | 給与明細 |
| 記載事項 | 労働基準法により法定項目が定められている | 給与の金額や出勤日数など、当月の勤怠情報を記載する |
| 保存義務 | 労働基準法により5年間(当面の間は3年)の保存が義務づけられている | 給与支払いの際に発行するが、企業の保存義務はない |
| 作成の目的 | 従業員への給与支払を管理するため | 従業員に給与を通知するため |
関連記事:給与明細とは?発行の必要性や記載する項目を詳しく紹介
1-3. 賃金台帳に記載対象となる人
賃金台帳を作成した際に記載対象となる人は、事業所で労働するすべての従業員です。
正社員や管理監督者はもちろんのこと、パートタイマーやアルバイト、日雇い労働者も対象となります。個人事業主の場合でも、従業員が1人でもいる場合は賃金台帳の作成が必要になります。
1-4. 賃金台帳は1社につき1冊つくるのか?
同じ会社でも部門や事業内容が異なる場合、事業場ごとに作成して保存する必要があります。労働基準法108条で記されており、例えば東京に本社があり大阪に支社があるような場合は、東京と大阪で1冊ずつ、1企業として2冊の賃金台帳を作成・管理しなければなりません。
各事業場とは「労働者が使用者の指揮命令に従って労働をおこなう場所または施設」を指します。
当サイトでは「賃金台帳の作成ガイドブック」という資料を無料配布しており、本資料ではそもそも賃金台帳の基礎はもちろん、賃金台帳の作成方法や作成しなかった場合のリスク、また保存期間なども解説しております。本資料ひとつで賃金台帳に関しては網羅的に理解できる資料となっており、大変参考になるので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
2. 賃金台帳に記載する項目


賃金台帳に記載する事項は、労働基準法施行規則の第54条で以下のように定められています。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外・休日・深夜労働時間数
- 基本給や手当の種類およびその額
- 控除内容とその額
関連記事:賃金台帳に必要な記載事項とは?それぞれの意味を詳しく解説
3. 賃金台帳の作り方
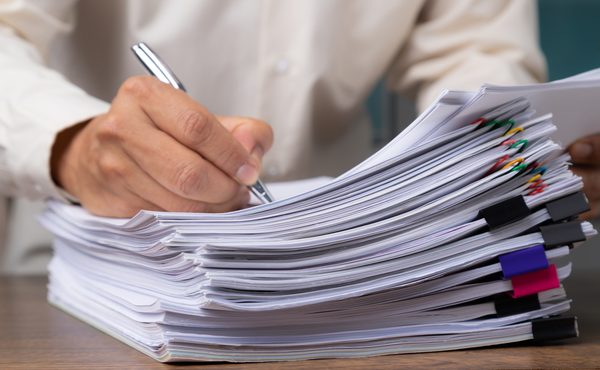
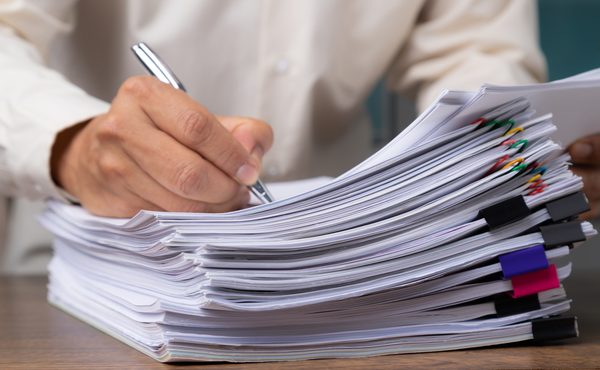
3-1. 作成方法・フォーマットを選ぶ
賃金台帳には記載すべき項目が定められていますが、書式についてはとくに定められていません。そのため法定項目さえ満たしていれば、どのような書式でも正式な賃金台帳として認められるのです。
一般的な作成方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- エクセルで作成する
- 会計ソフトを使う
- 厚生労働省が配布しているテンプレートを使う
賃金台帳は、上記の方法で企業が自ら作成することも可能ですし、社労士に依頼して作成してもらうことも可能です。従業員数によって費用は異なりますが、社労士に依頼すれば1か月あたり3~5万円程度で作成してもらうことができます。
作成をアウトソースすることには費用がかかりますが、従業員が多い場合は、自社で作成するよりも外注化したほうが時間的・人的コストの削減につながるケースもあります。まずは、自社に合った作成方法を選びましょう。
3-1-1. エクセルで作成する
賃金台帳は決められたテンプレートはありません。そのため、エクセルを使用すれば自社で独自に作成可能です。自社で作成する時間がないが社労士へのアウトソースも難しいという場合はインターネット上に公開されているエクセルフォーマットの活用がおすすめです。
インターネット上に公開されているエクセルフォーマットには、さまざまな種類があります。自社の状況に応じたフォーマットを選択しましょう。公開されているエクセルフォーマットを使用する際は、見本の記入例に沿って各項目へ記入していきます。また、プリントアウトすれば手書きでも記入可能です。
3-1-2. 会計ソフトを使う
賃金台帳は会計ソフトを使っても作成可能です。会計ソフトの賃金台帳であれば、PDFファイルまたはCSVファイルなどさまざまな形式で出力可能です。また、会計ソフトで賃金台帳を作成すれば、経理業務や労務までまとめて管理ができるため、事務の効率化が期待できます。
3-1-3. 厚生労働省が配布しているテンプレートを使う
厚生労働省は賃金台帳のテンプレートを用意しています。厚生労働省のテンプレートであれば法定項目を踏まえたうえでの賃金台帳の運用が可能でしょう。なお、厚生労働省のホームページからは賃金台帳以外にもさまざまなテンプレートを入手可能です。賃金台帳のテンプレート入手に合わせて、給与計算や労務管理に必要なテンプレートをダウンロードするのもおすすめです。
3-2. 法定項目を踏まえて記載する
作成方法が決まったら、あとは法定項目を踏まえて記載していくのみです。それぞれの項目のポイントをまとめたので、作成時はしっかりと押さえておきましょう。
氏名・性別
従業員が特定できるよう、氏名だけではなく性別も記載しておきます。氏名の隣など、わかりやすい場所に性別を記載する欄を作成しておきましょう。
賃金計算期間
支払った給与がいつからいつの分までなのか分かるように記載します。例えば「2023年1月11日~2月10日」などと書いておくことで、いつからいつまでの分の給与かを確認できるようにしておきます。
この項目は正社員でもアルバイトでも記載する必要がありますが、例外として1か月未満の日雇い労働者の場合は記載が不要です。
労働日数・労働時間数
その期間中に労働した日数と時間数についても記載しておきます。タイムカードを見ながら記載すると、ミスが防げます。
時間外・休日・深夜労働時間数
時間外労働や休日労働、深夜労働時間数は、残業代や休日手当、深夜労働手当などを計算するときに必要な情報です。それぞれで割増率が異なるため、個別に時間を計算して記載に残しておかなければいけません。
管理監督者や管理職の人は、時間外手当や休日手当に関しては支払いが不要であるため、記載が不要です。ただし、深夜労働手当は支払いが必要なので、記載しておきましょう。
基本給や手当の種類およびその額
基本給だけではなく、通勤手当や扶養手当などの手当をすべて項目別に金額を記載します。通貨以外で支払われる給与がある場合は、その部分についても記載する必要があります。
- 控除内容とその額
給与から差し引く健康保険や雇用保険などについて、その内容と金額を残しておきます。会社が独自で控除している旅行積立金や社宅費、財形貯蓄などについても記載する義務があります。
関連記事:賃金台帳はアルバイトでも必要なの?項目と書き方を解説
4. 賃金台帳の保管ルールと法的罰則について
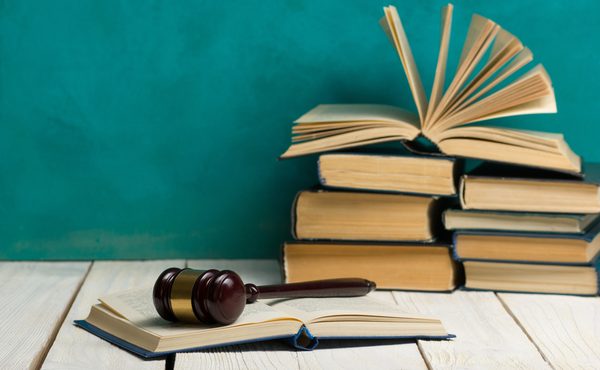
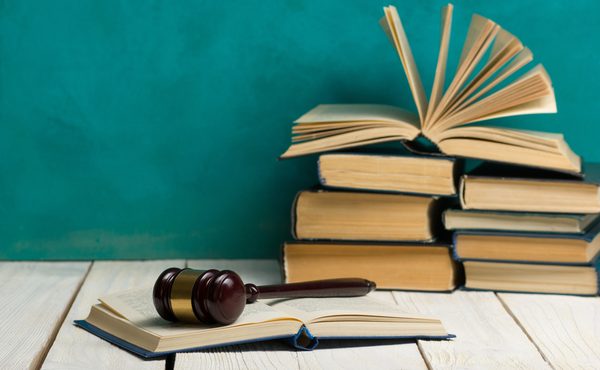
法的ルールに則って管理・保存しなければなりません。
前述のとおり、帳簿に記載する項目が指定されていることに加え、保管期間にもルールが設けられています。具体的なルールや不備があった際にどのような罰則があるのか解説していきます。
4-1. 賃金台帳は5年間(当面の間は3年)保存しなければならない
この台帳は、先述したように法定項目の記載が義務づけられているほか、同法109条および労働基準法施行規則の第56条により、最後に書き入れた日から起算して、5年間(当面の間は3年)保存することが法的ルールとして規定されています。なお、保存の方法は紙媒体でも電子媒体でも問題ありません。
4-2. 賃金台帳の保管方法
賃金台帳は支社や事業所ごとの保存が必要です。賃金台帳の具体的な保管方法に定めはありません。紙での保管、データでの保管どちらの場合であっても、いつでも提出できるようにしておきましょう。
賃金台帳は労働基準監督署から提出を求められることがあります。賃金台帳の提出を求められた際にすぐに用意できるようにしておく必要があります。データで保管している場合はすぐに準備できるでしょう。紙で保管している場合は年単位でまとめておけば、すぐに提出の求めに応じられます。
4-2-1. 賃金台帳を電子保存する際の要件
賃金台帳は電子保存が認められています。賃金台帳を電子保存するには、次のような要件を満たす必要があります。
(1)法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
(2)労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
(3)誤って消去されないこと。
(4)長期にわたって保存できること。
上記のような要件に加えて、不正アクセスへの対策も求められるでしょう。
4-3. 賃金台帳に不備があった場合の罰則
上記の法的ルールを遵守せずに法定項目の基準を満たしていない場合や、台帳を保存していない場合は労働基準法違反となるため注意しましょう。労働基準監督署から是正監督書が交付されるほか、悪質な場合は同法120条に記載のあるとおり30万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。
なお、労働基準法で作成・保存が義務づけられた帳簿はほかにもあり、同法107条に規定されている労働者名簿や、108条に規定されている出勤簿などが挙げられます。これらの帳簿は総称して「法定三帳簿」と呼ばれ、従業員を雇い入れる企業は必ず備えつけておかなければいけません。
関連記事:賃金台帳の保存期間や違反した際の罰則・保存方法を解説
4-4. 提出義務はあるのか
賃金台帳については、一般的には法的な提出義務はありません。労働基準法などの労働関連法令では、賃金台帳の作成と保存が義務付けられていますが、その提出に関しては明確な要件はありません。
ただし、労働監督官庁や税務当局など、特定の機関からの要請や監査に対しては、賃金台帳の提出が求められる場合があります。これは、労働条件や給与に関する情報の確認や評価を目的としたものです。
また、労働組合や労働者本人からの要求に応じて、賃金台帳の開示や提供が求められることもあります。労働者の権利保護や労働条件の適切な管理に関わる情報提供として、賃金台帳の開示がおこなわれる場合があります。
5. ルールを押さえて正しく賃金台帳を作成・保存しよう


指定されたフォーマットはありませんが、法定項目を押さえて作成し、最後に書き入れた日から5年間(当面の間は3年)保存することがルールで定められています。正しい取り扱い方を押さえて、適切に管理することを心がけてください。
関連記事:賃金台帳の提出方法を解説!賃金台帳がない場合の対応も紹介
関連記事:賃金台帳の写しが必要な場面や作成時の注意点を解説
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25