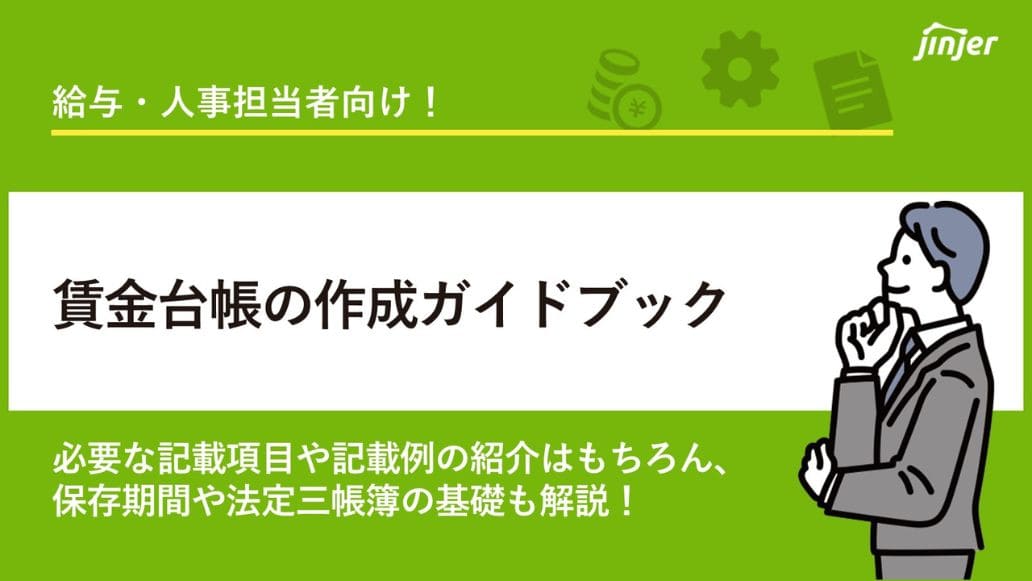賃金台帳の書き方やおすすめの書式・注意点から保管期間まで解説

賃金台帳とは、従業員に支払う給与を計算するために必要となる項目や賃金の額などを記録する帳簿のことです。従業員を1人でも雇い入れている企業および個人事業主は、事業所ごとに賃金台帳を備え付けることが法律で義務づけられています。
賃金台帳は作成すれば良い、というものではなく、記載しなければならない項目が定められているので、きちんと確認をしておきましょう。本記事では、賃金台帳の書き方や記入対象者、注意点などを解説していきます。
▼賃金台帳とは?という方はまずはこちら
賃金台帳とは?基本的な作成方法と知っておきたい法的ルール
「賃金台帳の作成方法や保管期間などがあっているか不安」
「賃金台帳を作成していない場合のリスクを知りたい」
など賃金台帳の取り扱いに関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、『賃金台帳の作成ガイドブック』を無料で配布しております。記載する際に必要な項目や具体的な記入例をまじえながら、作成手順を詳細に解説しています。
適切な保管期間や賃金台帳の基礎ついても詳しく紹介していますので、「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「賃金台帳の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、大変参考になる内容となっています。ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 賃金台帳とは


賃金台帳とは、労働基準法によって定められている「法定三帳簿」の1つで、従業員に支払う賃金の詳細や支払い状況、勤務時間を記載した帳簿のことです。記載する内容や記載しなければならない従業員の範囲、保管期限などが法律で定められているので、記載項目を正確に把握して記載しなければなりません。
記載項目は給与明細と一部共通しているものがありますが、原則として賃金台帳として代用することができません。賃金台帳は後述しますが、記載すべき事項が決められています。市販の明細書などでは必要な項目が抜けている場合がありますので、別々に作成するようにしましょう。
2. 賃金台帳の書き方


賃金台帳に記載が必要な項目は、以下のとおりです。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外・休日・深夜労働時間数
- 基本給や手当の種類およびその額
- 控除内容とその額
上記の法定項目を踏まえ、まずは労働基準法の要件を満たせる賃金台帳の書き方について説明します。
関連記事:賃金台帳に必要な記載事項とは?それぞれの意味を詳しく解説
参考:労働基準法施行規則|e-GOV
2-1. 氏名・性別
賃金台帳の対象となる人物を特定するために、氏名と性別を明記しておきましょう。企業の中には、管理のための労働者番号を振っているところもあります。
また、賃金台帳には従業員ごとの給与情報や労働状況を記載する必要がありますが、特に氏名や性別を記入することで、どの従業員に関する情報かをより明確にすることができます。
こうした情報は、後の確認作業やトラブル防止にも繋がるため重要です。さらに、従業員の賃金計算期間や労働日数を正確に記載することで、労務管理の透明性が高まり、信頼性のある帳簿として機能します。
2-2. 賃金計算期間
賃金計算期間とは、給与の計算対象となる期間のことです。「2021年1月1日~2021年1月31日」などと記載します。賃金支払期間ごとに計算期間を並べて記載しておくことで、支払った給料が何か月分のものか確認できるようになります。
期間についての記載は雇用形態にかかわらず必要ですが、1か月未満の日雇い労働者に関しては記載する必要はありません。
この賃金計算期間は、給与台帳や賃金台帳の重要な構成要素として、従業員に対する支払いの透明性を確保する役割も果たします。さらに、賃金計算期間を明確にすることで、企業は支払義務を果たしているかの確認にもつながり、労務管理の一環として重要な記録となります。正確な賃金計算期間の設定は、労働契約や就業規則にも基づくため、適切に管理することが求められます。
2-3. 労働日数・労働時間数
賃金計算期間中に労働した日数や労働時間は、給与計算に欠かせない情報です。そのため、賃金台帳にしっかりと記載しておきましょう。記載ミスがないよう、タイムカードを見ながら正確に記入するようにしてください。
有給休暇や特別休暇がある場合は、労働したものとみなします。休暇の日数や時間を該当欄に記入のうえ、有給休暇や特別休暇であるとわかるようにしておきましょう。
また、欠勤した分の賃金を差し引く欠勤控除がある場合は、欠勤があった月の「総支給額合計額」より欠勤控除を差し引く必要があります。欠勤控除は非課税となるため、控除額を差し引いた額を「課税合計額」として計算してください。そして、控除項目の欄に「欠勤控除 ▲18,000円」などと記載しておきます。
さらに、労働日数や労働時間の正確な記録は、後々の賃金台帳への反映だけでなく、税務署や監査機関からの確認においても重要な役割を果たします。したがって、タイムカードや出勤簿との整合性を保ち、適時にチェックを行うことで、より信頼性の高い賃金台帳を作成することができます。
関連記事:労働時間とは?法律上の定義や上限、必要な休憩時間数についても解説
2-4. 時間外・深夜・休日労働時間数
従業員に時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合は、割増賃金が発生します。それぞれで割増率が異なるため、個別に把握して記録に残しておきましょう。
管理監督者や管理職の場合、時間外手当や休日手当は不要であるため記載も不要です。ただし、深夜手当のみは支払う必要があるため、記録に残しておいてください。
また、賃金台帳にはこれらの労働時間だけでなく、実際の労働日数や賃金計算期間を明確に記載することが重要です。記載した労働時間が正確であるか確認するためには、タイムカードや他の出勤記録との照合が役立ちます。
このように、労働時間を適切に管理することで、企業は法令遵守を徹底し、従業員に対して正当な賃金を支払うことができます。
関連記事:時間外労働の定義とは?知っておきたい4つのルール
関連記事:所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説
2-5. 基本給や手当の種類およびその額
賃金台帳には、給与の総額ではなく基本給と各手当を分けて記載しておかなければいけません。基本給や「時給×労働時間」で算出した割増率のない額と、通勤手当や扶養手当などを別で記録に残しておきます。なお、通貨以外で支払われる給与がある場合は、その評価額についても記載する必要があります。
また、給与台帳の作成にあたり、各手当についての詳細な情報を記載することも重要です。たとえば、育児手当や住宅手当など、各従業員に適用される具体的な手当の名称と金額を明確に示すことで、透明性を高め、後の税務調査や労働基準監督署の確認にもスムーズに対応できるようになります。これにより、会社の財務状況を正確に把握し、労務管理を適切に行う一助となるでしょう。
2-6. 控除内容とその額
最後に、健康保険料や雇用保険料などといった、給与から控除される項目について、その内容と金額を記載します。企業が独自で控除している親睦会費や旅行積立金などがある場合は、それについても書いておいてください。報奨金や社宅家賃などといった課税対象費用を現金で負担した場合も、しっかりと記載しておきます。ただし、社宅費は半額以上を企業が負担すると課税対象となるため、記載時は注意しましょう。
また、控除項目を記載する際は、各項目ごとに詳細を明示することが重要です。例えば、健康保険料や厚生年金保険料については、その種類や金額だけでなく、どの年金制度に基づいているかも明確にすることで、透明性を保つことができます。
これにより、従業員自身が納得できる形で情報を把握できるとともに、万が一の監査時にもスムーズに対応できる環境を整えることができます。控除のルールは年々変わる可能性があるため、最新の法令を確認し、必要に応じて適切な情報を更新しておくことが求められます。
2-7. 厚生労働省の「賃金台帳テンプレート」
賃金台帳のテンプレートは、厚生労働省のホームページからダウンロードできるので、法定項目を確実に記載したい場合は活用してみましょう。
厚生労働省のテンプレートには、「常時使用される労働者に対するもの(様式第20号)」と「日日雇い入れられる者に対するもの(様式第21号)」があるので、記入対象者の雇用形態に合ったものを使ってください。
記入例も公開されているので、初めて賃金台帳を記入する際には参考にしてみると良いでしょう。
当サイトでは「賃金台帳の作成ガイドブック」という資料を無料配布しています。本資料では、賃金台帳の作成方法を記載例をもちいてわかりやすく解説しています。また賃金台帳の保存期間や、賃金台帳の作成を怠った際のリスクなど法定三帳簿の基礎となる内容まで網羅的に解説しており、担当者の方にとっては大変参考になる内容となっております。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
テンプレート:「常時使用される労働者に対するもの(様式第20号)」
テンプレート:「日日雇い入れられる者に対するもの(様式第21号)」
賃金台帳の記入例:様式第 20 号(常用)
3. 賃金台帳の記入対象者とは?


賃金台帳は法定帳簿なので、法定項目すべてを記入するだけでなく記入対象者も把握しておかなければなりません。「アルバイトやパートの分はいらないだろう」など自己判断で作成すると、記入が必要となっている従業員の給与を正しく管理できなくなってしまいます。ここでは、記入対象者について解説するのでチェックしておきましょう。
3-1. すべての従業員が対象
賃金台帳の記入対象者は、雇用しているすべての従業員です。「すべて」なので、アルバイト・パートはもちろん非正規社員も記入の対象となります。例え一定期間の契約や短期間の契約であっても、雇用関係がある場合は賃金台帳を作成しなければなりません。
これは日雇い労働者にも当てはまるので、「日雇いなら不要だ」と勘違いしないようにしましょう。ただし、雇用期間が1ヵ月未満や日雇い労働者の場合、「賃金計算期間」は記載しなくても大丈夫です。
3-2. 役員でも対象になることがある
役員は従業員ではないので、基本的には賃金台帳の記入対象者ではありません。ただし、管理職など従業員と役員を兼務している場合は雇用関係が成り立つので、兼務役員は記入対象となるため間違えないようにしてください。
また、役員報酬を支払っている場合は、「健康保険や厚生年金保険の被保険者となる」という位置づけなので、保険料の控除額を記録しておくことが求められます。そのため、強制ではなく法的な義務もありませんが、役員でも賃金台帳を作成することをおすすめします。
4. 賃金台帳の書き方で注意すること


4-1. 書式や作成方法に決まりはない
賃金台帳には記載が必須の法定項目がありますが、その要件さえ満たしていれば書式や作成方法に決まりはありません。企業が管理しやすい方法で作成が可能なので、ぜひ自社に合った作り方を見つけてみてください。
書式は自分で作成してもいいですし、インターネットでダウンロードできるものを使っても問題ありません。ExcelやWord、PDFや会計ソフト、紙媒体など、どのような方法で作成・保管しても大丈夫です。
また、従業員数が多くて自社で作成することが難しい場合は、社労士に依頼して作成してもらうことも可能です。従業員の人数によって異なりますが、1か月あたり3~5万円で作成してもらえます。コストは掛かりますが、人的・時間的コストを大幅に削減することができます。
4-2. 書いた内容を修正するときは翌月に調整する
記載と処理が終わった賃金台帳を修正したい場合は、翌月の給与で調整をおこなうのが一般的です。その際、給与を調整したことがわかるよう、誤って処理した給与の金額や修正後の控除額を明記しておくようにしましょう。
給与計算のミスは企業の信頼失墜につながるため、原因をしっかりと究明し、従業員に対して丁寧に説明してから控除をおこなうようにしてください。
5. 賃金台帳の保管期間は5年間(当分の間は3年間)


賃金台帳は作成して終わりではなく、一定期間保存しておくことが義務づけられています。
労働基準法の第109条によると、作成した賃金台帳は最後に書き入れた日から起算して5年間(当分の間は3年間)保存することが求められているため、誤って処分しないように注意しましょう。
5-1. 賃金台帳の保管が必要な理由
法定項目を満たしていなかったり台帳の保存を怠ったりした場合は労働基準法違反となり、是正勧告や罰金の対象となるため、賃金台帳は適切に管理してください。賃金台帳の保存が必要な理由としては、従業員の給与や勤務状況が適切に記録され、労務管理において透明性を保つことができる点が挙げられます。
また、社員の権利を守る手段としても機能し、信頼関係の構築にも寄与します。特に、監査や税務調査に備えるためにも、賃金台帳は正確かつ整然と保存されていることが重要です。
保存方法については、紙媒体だけでなく、電子データとしての保存も検討できますが、データのセキュリティ対策を施すことが必須です。従って、保存場所や管理方法を明確にし、定期的に内容を見直すことが求められます。
関連記事:賃金台帳の保存期間や違反した際の罰則・保存方法を解説
6. 賃金台帳の書き方を押さえて適切に給与を管理しよう


賃金台帳を作成するときは、無料配布されているテンプレートをダウンロードして活用すると便利です。ただし、テンプレートの中には法廷項目が抜けている場合もあるので、必ず項目を確認して、担当者の方が使いやすいものを見つけてみてください。
「賃金台帳の作成方法や保管期間などがあっているか不安」
「賃金台帳を作成していない場合のリスクを知りたい」
など賃金台帳の取り扱いに関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、『賃金台帳の作成ガイドブック』を無料で配布しております。記載する際に必要な項目や具体的な記入例をまじえながら、作成手順を詳細に解説しています。
適切な保管期間や賃金台帳の基礎ついても詳しく紹介していますので、「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「賃金台帳の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、大変参考になる内容となっています。ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
書き方の関連記事
-


報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説
人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24
-


顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介
人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24
-


回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26
賃金台帳の関連記事
-


賃金台帳はアルバイトでも必要なの?項目と書き方を解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.08.29
-


賃金台帳の書き方やおすすめの書式・注意点から保管期間まで解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.10.22
-


賃金台帳の保存期間や違反した際の罰則・保存方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.09.17