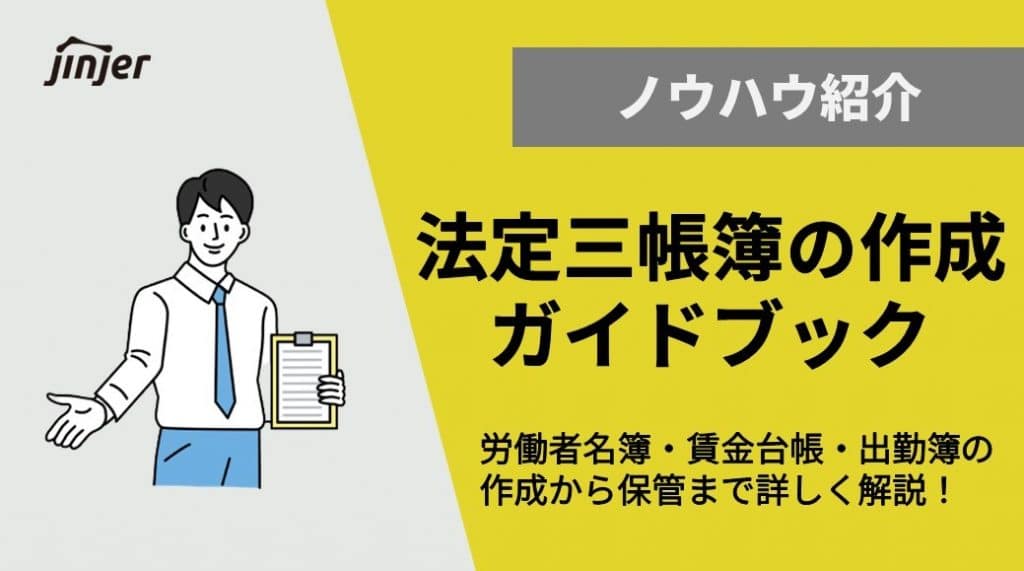出勤簿とは?役割や必要項目、自作する際の注意点を解説
更新日: 2024.4.12
公開日: 2021.11.12
YOSHIDA

出勤簿は従業員の労働時間や出勤日数などを管理するために必要なもので、これをもとに毎月の賃金の計算などをおこないます。出勤簿はすべての企業が必ず作成しなければならないものなので、今一度出勤簿の役割についてきちんと学んでおきましょう。本記事では、出勤簿の概要から効率的に管理する方法などを紹介します。
「法定三帳簿の作成ガイドブック」を無料配布中!
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3種類の帳簿のことです。
いずれも、雇用形態に限らず、従業員を雇用する際には必要となるうえ、労働基準法で保存期間や記載事項などが決められているため、適切に調製しなければなりません。
当サイトでは、『法定三帳簿の作成ガイドブック』を無料で配布しており、作成から保管の方法まで法定三帳簿の基本について詳しく紹介していますので、
「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「法定三帳簿の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1.出勤簿の役割とは?
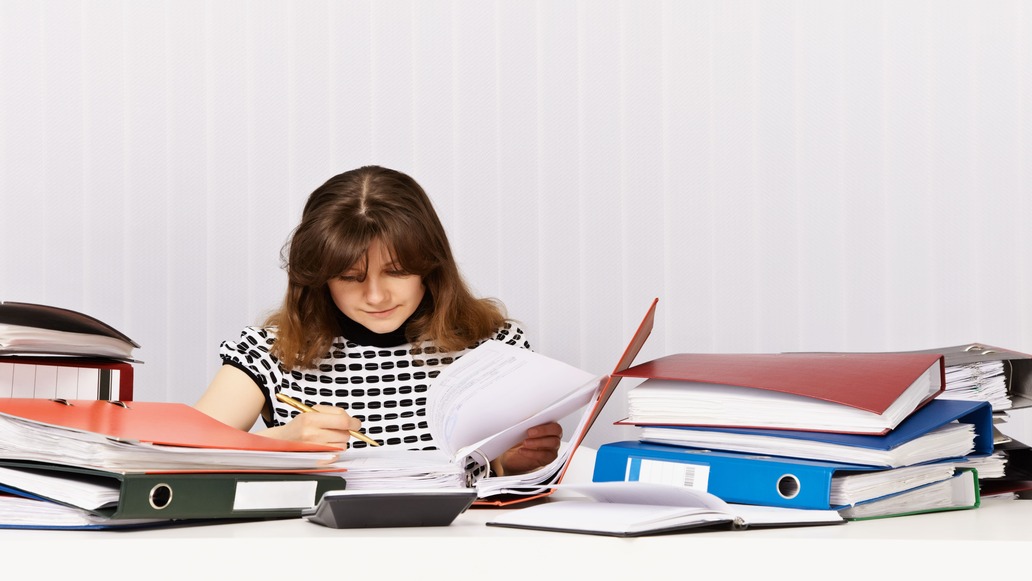
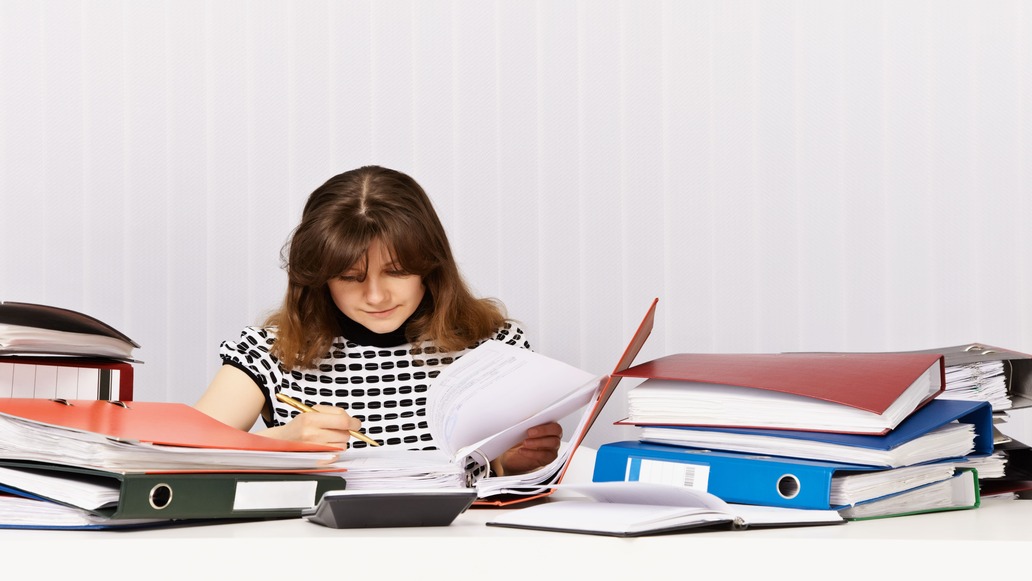
ここでは、企業が作成を義務付けられている出勤簿の役割について解説します。
きちんと給与を支払うために、従業員の健康や良好な関係を守るためにも、正しく出勤簿を作成しましょう。
1-1. 出勤簿とは
出勤簿とは、従業員の労働時間を正しく把握するための帳簿のことです。法定三帳簿のひとつで、作成と保管が企業に義務付けられています。決められたフォーマットはないため、ガイドラインに則って作成しましょう。
ガイドラインでは、労働時間の適正に把握するために講じるべき措置として、ただ出退勤の記録をするだけでなく、従業員が自ら確認できることや客観的記録をもとに確認すること、従業員に圧力をかけて適正な自己申告を阻害しないことなどが盛り込まれています。
参照:労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
1-1-1. 雇用形態に関係なく従業員全員が対象
出勤簿は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた全従業員分を作成しなければなりません。
派遣社員の場合は、派遣先企業ではなく派遣元企業が作成した出勤簿に従業員が記入し、派遣先の社員に確認してもらうのが一般的です。
1-1-2. タイムカードとの違い
タイムカードも、出勤簿と同様に労働時間を管理するための書類として利用できます。
ただし、タイムカードは一般的に出退勤の時間のみが記録されるため、休日出勤や時間外労働の割増賃金は別で計算しなければなりません。また、残業許可証や日報など、労働時間を証明する書類が別で必要になる可能性もあるため、注意しましょう。
1-2. 出勤簿の目的
出勤簿の目的は、労働者の労働時間を適切に管理することです。
労働基準法により、従業員が働ける時間や日数には制限が設けられています。もし労働基準法や就業規則に反した働かせ方をした場合、企業に罰則が科されるため適切に管理しなければならないのです。また、長時間の残業や深夜労働などには割増賃金が発生します。深夜に残業した場合には、時間外労働と深夜労働の両方で割増賃金を支払わなければなりません。そのため、どこからが残業時間に当たるのかを適切に把握する必要があります。
1-2-1. 従業員の労働時間や労働日数の把握
出勤簿には、従業員の労働時間や労働日数を記入しなければなりません。これによって、各従業員が「いつ」「どれくらい」働いたのかが明確になります。
「〇月〇日〇時間」といった記入では、何時間時間外労働をしたか、何時間休憩を取ったか、またその日が休日出勤であったかなどがわからないため、それらをきちんと記入する欄も設けなければなりません。なかには残業代を支払わないためにこれらの時間をごまかそうとする企業もありますが、法改正によりそれも難しくなってきています。
1-2-2. 時間外労働時間などの給与計算
出勤簿をもとに従業員の月々の給与を計算します。
労働基準法では基本的に1日8時間、または週40時間までと労働時間が定められていますが、これを超えている場合はその時間に対する割増賃金を支払う義務もあります。
割増賃金には様々な種類があり、時間外労働だけでなく、休日労働や深夜労働も割増率が違います。休日労働で時間外労働が発生する、時間外労働の延長で深夜労働に入るなどの場合はさらに給与計算が複雑になります。
出勤簿で出勤時間や出勤日数を適切に管理していればこれらの計算もすぐにでき、煩わしい給与計算の時間を短縮できます。
2. 出勤簿には何を記載すべき?項目と自作するときの注意点を解説
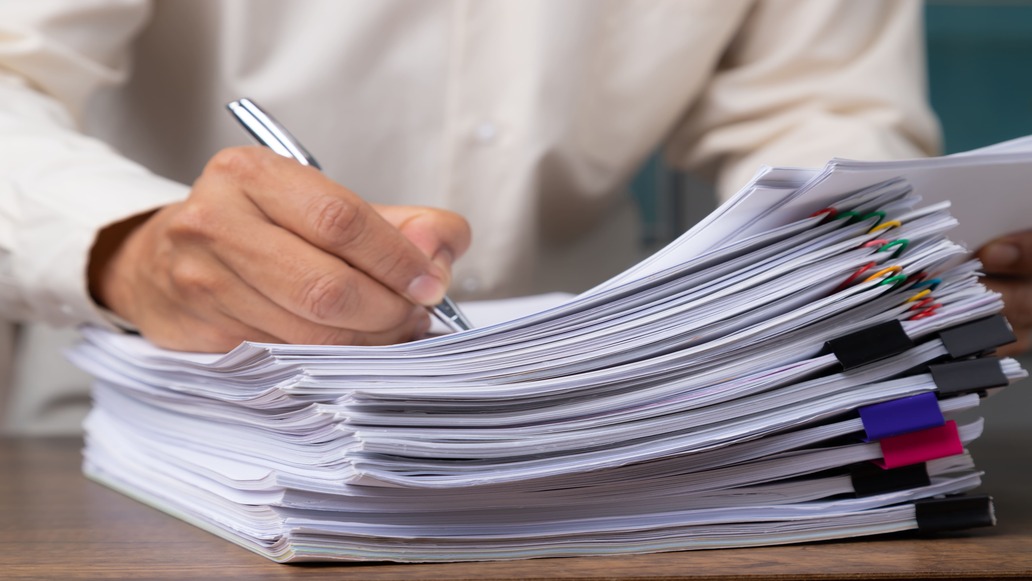
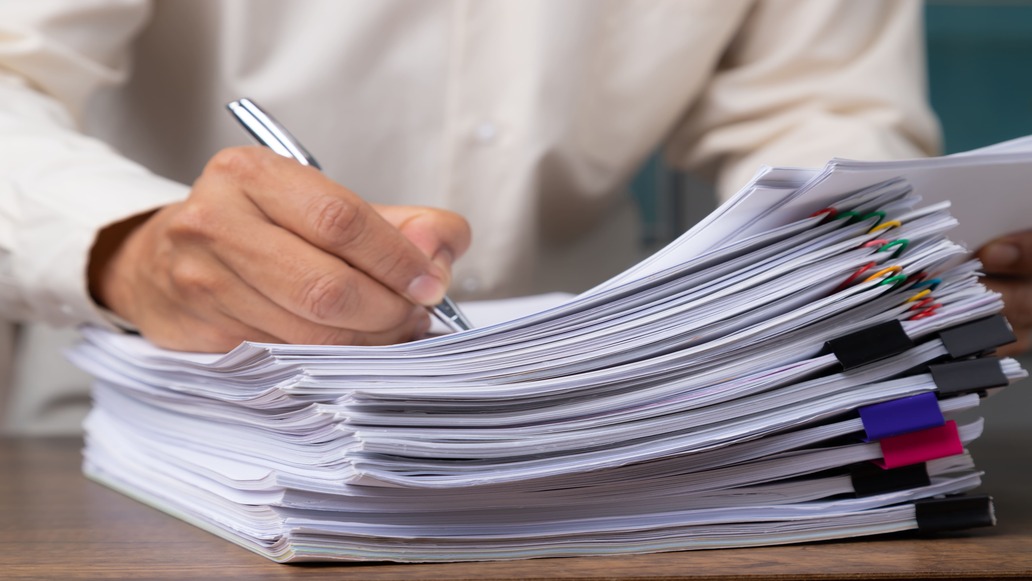
出勤簿には何を記載すべきでしょうか。本章では、記載すべき項目と自作する場合の注意点を解説します。
2-1. 出勤簿に記載すべき項目
出勤簿には、決められたフォーマットはありません。ただし、従業員の労働時間を正確に把握するために、以下の項目を入れる必要があるでしょう。
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 時間外労働時間
- 休日労働時間
- 深夜労働時間
このほかにも、オフィスへの入退室記録やPCの稼働時間の記録などがあれば、サービス残業の有無を証明できます。合わせて管理しておくと良いでしょう。
始業・終業時刻
業務を始めた時間と、その日の業務を終えた時間を記録します。雇用契約書で定められた勤務時間よりも長く働いている場合、残業にあたるため、後述する時間外労働時間にも記録しなければなりません。
休憩時間
労働基準法では、1日の間で6時間以上働く場合は休憩時間を与えるように義務付けています。
休憩時間の決まりは以下のとおりです。
| 6時間超8時間以内 | 45分 |
| 8時間超 | 1時間 |
また、休憩時間は労働時間の間で取得する必要があるため、出社してすぐに休憩に入ることなどはできません。
時間外労働時間
基本的には1日8時間、または1週間で40時間を超えて働いた場合の時間が該当します。
ただし、変則労働時間制で雇用契約を結んでいる場合はこの限りではありません。各々の契約内容と定時の時間を確認して算出するようにしましょう。
休日労働時間
労働基準法では「休日は1週間に1日以上与えなければならない」とされています。これを法定休日と言います。急なトラブルなどで、法定休日に労働した場合は35%の割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、会社が定めている所定休日に労働した場合は、本来休みの予定であっても休日労働にはあたりません。
深夜労働時間
22時から翌5時までの時間に働いた場合、深夜労働時間として割増賃金が発生します。22時以降が所定労働時間であっても同様です。
また、22時以降の残業は深夜労働の割増率と時間外労働の割増率の2つがかかるため、それぞれで記載しなければなりません。
2-2. 出勤簿を自作する場合の注意点
先述のとおり、出勤簿には法的に定められたフォーマットやテンプレートはありません。そのため、手書きやエクセルなどの表計算ソフトを用いて自作することも可能です。ですが、手書きで管理している場合、翌月の集計時に「時間外労働時間が上限を超えていた」「有給が年間で5日消化されていない」などの問題に気づく可能性があります。表計算ソフトで作成した場合も、「特定の条件でセルの色を変える」「該当する従業員の情報だけ自動で抜き出す」など、通知機能を持たせなければ同様です。
当サイトでは出勤簿を含む、労働者名簿や賃金台帳などの法定三帳簿の基礎知識から作成方法まで網羅的にまとめた「法定三帳簿の作成ガイドブック」という資料を無料配布しております。法定三帳簿の作成を行っている方にとっては大変参考になる内容になっているので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3.出勤簿を管理する際の注意点


出勤簿は法律でさまざまな決まりが作られています。保管方法や明記する項目など、管理時の注意点について確認しておきましょう。
3-1. 5年間の保管義務がある
出勤簿は原則として5年間(当分の間は3年間)の保存が義務付けられてます。
従業員が働き始めた日から5年間ではなく、最後に出勤した日から5年間です。
退職後残業代などに問題があった可能性がある場合、この出勤簿を提出して正しい給与を計算しなければなりません。
問題が発覚した際にこの出勤簿を提出できない場合は罰金が科せられますので注意しましょう。
従業員が多い企業では、数百名、数千名もの出勤簿を5年間保管しておくのは大変です。
その場合はパソコンでデータとして保存する方法もあります。その際は法律で定められた条件がきちんと表示されているか、すぐに提出できるようになっているか、消去・あとからの書き換えがすぐにわかるようになっているかなどの条件があります。
出勤簿や勤怠管理情報のペーパーレス化や適切な保管方法について、詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてお読みください。
関連記事:勤怠管理をペーパーレス化するには?電子化のメリット・デメリットも解説
関連記事:タイムカードの保管期間は5年!タイムカードの保管について徹底解説!
3-2. 労働時間の切り捨ては違法
労働基準法の第24条に「賃金の全額を支払わなければならない」とあります。
そのため、労働時間の切り捨ては違法です。始業時間が9:00であっても、タイムカードを8:50に切って業務を開始した場合は、8:50からの賃金を支払う必要があります。しかし、タイムカードやシステムによっては、15分や30分の端数を自動で切り捨てていることもあるかもしれません。この場合、労働基準監督署から指摘が入ったり、給与の未払いとして重大な問題に発展したりする可能性があるため、注意しましょう。
4. 出勤簿の効率的な管理方法


これまでは勤務時間のみを記入する出勤簿を使っていた、従業員の押印のみの出勤簿を使っていたという場合、いきなり細かい記入が必要な出勤簿に変更するのは大変です。
どのようにすれば効率的に出勤簿を管理できるのかをきちんと把握しておきましょう。
法改正に伴い、より効率的に出勤簿を管理できるシステムなども充実してきています。
4-1. 勤怠管理システムが便利
出勤簿を効率的に管理するもっとも簡単な方法としては勤怠管理システムの導入です。
勤怠管理システムを使えば、従業員がパソコンやスマホから出勤時間、退勤時間を打刻できます。
また、GPS機能によって不正な残業をしていないかを確認できるシステムもあります。
勤怠管理システムにあらかじめ所定の休日や労働時間を記入していれば、時間外労働や休日労働、深夜労働なども一目瞭然です。
▼(人気記事)GPS機能付きの勤怠管理システムに関する詳しい記事はこちら
タイムカードはもう不要?GPSで打刻できる勤怠管理システムとは
▼(お得な資料)残業時間に関する法改正を確認したい、残業管理の手間を削減したい方はこちら
【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド
さらに自動で月々の給与の計算をおこなってくれるシステムもあるため、これまでのように給料日前に計算に追われる、計算ミスから給与の未払いが発生するなどのトラブルを回避できるようになります。
勤怠管理システムはさまざまな種類が登場しており、内容や料金にも大きな違いがあります。企業に合う勤怠管理システムを探してみましょう。
4-2. 場合によっては手書きの方が便利
出勤簿は勤怠管理システムを利用することで効率的に管理できますが、場合によっては手書きの方が便利なこともあります。
毎日、毎週の労働時間が決まっている企業ならシステムを使った方が便利ですが、シフト制や日々の出勤時間、退勤時間が違う仕事もたくさんあります。
その場合は手書きで管理した方が、毎回システムを書き換えるよりも簡単に管理をおこなえます。
また、従業員が少ない企業の場合もシステムを導入する工数と手書でおこなう工数を比較すると手書きの方が早い場合もあります。勤怠管理システムを導入する費用がかかるため、会社の規模によっては導入メリットが見合わないかもしれません。
従業員が少なく、正社員とパート、アルバイトなどの住み分けができているのであれば、手書きのままでも問題ないでしょう。
しかし、手書きは当然ミスも増えやすくなりますので、これまで以上に慎重に記入をおこなうようにしてください。
手書きで出勤簿を作成する際の注意点は以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:タイムカード・出勤簿の手書きは違法?勤怠管理の必要性を理解しよう
5. 出勤簿の役割を確認して正しく利用しよう


出勤簿の基本的な情報から効率的な管理方法について解説しました。
出勤簿は給与計算だけでなく、従業員の健康の維持やトラブル回避のためにも重要な役割を担っています。
従来通り押印のみの出勤簿や、出勤時間と退勤時間しかわからないような出勤簿を使い続けている場合はいざトラブルになった際に不利になる可能性もあります。
勤怠管理システムの導入なども検討し、より正しく従業員の労働時間、支払うべき賃金を把握できるようにしましょう。
関連記事:出勤簿は印鑑の押印だけでも大丈夫?法律的な問題点を解説
「法定三帳簿の作成ガイドブック」を無料配布中!
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3種類の帳簿のことです。
いずれも、雇用形態に限らず、従業員を雇用する際には必要となるうえ、労働基準法で保存期間や記載事項などが決められているため、適切に調製しなければなりません。
当サイトでは、『法定三帳簿の作成ガイドブック』を無料で配布しており、作成から保管の方法まで法定三帳簿の基本について詳しく紹介していますので、
「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「法定三帳簿の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25