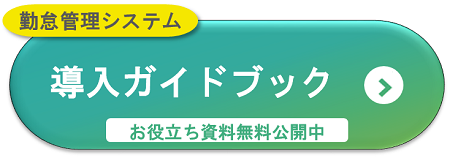タイムカードや出勤簿の保管期間は5年?7年?正しい保管期間を徹底解説!
更新日: 2024.7.4
公開日: 2020.1.28
OHSUGI

多くの勤怠管理の担当者は、月末になると、タイムカードや出勤簿を集計しているでしょう。しかし、タイムカード・出勤簿は集計して終わりではありません。実は、タイムカードの原本や出勤簿は一定期間保管しなければいけないことが労働基準法にて定められています。
「保管期間は5年と7年どっちが正しいのか?」「雑に保管していると、どういう困ったことが起きるのか?」「どのように保管すればいいのか?紙?それともExcel?」といった疑問を持っていませんか?
今回は、タイムカード・出勤簿に定められた保管期間について、徹底解説します。
関連記事:最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
目次
タイムカードのような勤怠にかかわる情報は5年間の保管が法律で義務付けられています。一方で、紙の保管には場所や整理の手間がかかったり、探し出すのに時間がかかったりするため、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような方におすすめなのが、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」です!
ジンジャー勤怠では、入社してからの勤怠情報をシステム内で管理することができます。
場所や整理不要で、データの検索もできるため、人事担当者さまの業務が楽になります!
ジンジャー勤怠に関して、もっと知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
1. タイムカード・出勤簿の正しい保管期間は5年(ただし当分の間は3年)

労働基準法第109条にて、タイムカードおよび出勤簿の保管期間は5年と定められています。
【労働基準法第109条】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
引用:e-Gov|労働基準法
1-1. 従来の保存期間は「3年」と定められていた
これまでタイムカードや出勤簿などの勤怠データに関する書類は3年の保存期間となっていましたが、2020年4月1日の労働基準法改正により3年から5年に延長されています。経過措置により、当面の間は3年間で良いとされていますが、いずれ正式に延長される可能性もあるため、覚えておきましょう。
1-2. 保管期間が7年になる帳票とは
なお保管期間が7年となるのは、源泉徴収簿と兼用している場合の賃金台帳になります。解釈によっては、賃金台帳をつくるために必要な書類としてタイムカードや出勤簿が含まれるため、7年保管すべきと判断される場合もあるため、社労士や税理士などの専門家に確認のうえ、保管期間を定めるのが安心です。
2. なぜタイムカード・出勤簿を保管する必要があるのか?

そもそも、なぜタイムカードの原本や出勤簿を保管する必要があるのでしょうか。
大きく分けると、「労働基準法にて保管義務が定められているため」「労働基準監督署に提出する資料に必要なため」「従業員とのトラブルを防ぐため」の3つです。詳しく、解説していきます。
2-1. 労働基準法にて保管義務が定められている
労働基準法においてタイムカードや出勤簿などの勤怠データは保管する義務があることが定められています。
無期限に保管する必要はなく、保管期間が定められています。詳細は後述しますが、基本的な保管期間は5年(当分の間は3年)です。
もし、定められた保管期間を守れなかった場合は罰則があり、労働基準法違反により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
引用:e-Gov|労働基準法
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
引用:e-Gov|労働基準法
2-2. 労働基準監督署の調査で必要な書類の一つである
労働基準監督署は、労働基準法に抵触していないか、調査が入るケースがあります。そのときに調査されるのが、下記の3つです。
【労働基準監督署が調査する内容】
- 長時間労働や未払い賃金などに関わる労働時間の管理が適正か
- 労働条件の不利益変更や不当解雇がおこなわれていないか
- 健康診断などの安全衛生がおこなわれているか
この中の①の情報を提示するときに、タイムカードないし出勤簿が必要です。タイムカード・出勤簿がない場合、労働基準監督署から指導を受けます。
また、働き方改革関連法でも、労働時間の客観的把握が求められているので、その観点からもタイムカード・出勤簿の保管は必要です。
なお、企業として保管しておくべき勤怠にかかる書類や情報はタイムカード・出勤簿だけではないため、不安な方は今一度必要な記録がすべて保管されているか確認しておきましょう。
【関連記事】タイムカードの原本における保管期間・保存方法とは
2-3. タイムカード・出勤簿の保管で、従業員とのトラブルを防ぐことができる
タイムカード・出勤簿は、従業員の労働時間を客観的に証明することができる一つの手段です。そのため、従業員から、残業代や未払い賃金の請求があったときに、タイムカード・出勤簿を公開することで、客観的な対応が可能です。
もし、タイムカード・出勤簿がなければ、お互いの主張が異なり、どちらが正しいか確認する術がありません。
実際にタイムカード・出勤簿の保管をめぐって起きた事例があります。今回は、平成22年7月15日にあった医療法人大生会事件の大阪地裁の判決をご紹介します。
判例
【事案の概要】
Y社は、病院の経営を業とする医療法人である。Xは、Y社と期間の定めのない雇用契約を締結し、総務事務部門で勤務していた(月額基本給18万円)。
Xは、上司から総務管理への配置換えを命じられ、同時に基本給15万円とすることを通知された。
平成21年3月9日午後9時頃、Xが退勤したところ、上司から午後10時ないし11時頃に電話があり、すぐ戻るよう指示を受けた。
しかしXは「帰りの電車がないので行けません」と述べて指示を拒んだところ、翌日Xのタイムカードが撤去され、15日まで打刻できない状態にされたうえ、同月14日に、4月14日をもって解雇する旨通告された。
Xは、Y社に対し、未払い基本給の一部や時間外割増賃金、解雇等に対する慰謝料等を請求した。
【裁判所の判断】
未払い基本給に年14.6%の利率を付した支払を命じた。慰謝料として合計40万円の支払いを命じた。
この慰謝料の40万円の中で、10万円はタイムカードを打刻させなかったり、タイムカードの開示を求められたのに、とタイムカード等の開示を拒絶したことによる慰謝料です。
このようなことにならないためにも、企業はタイムカードを保管・開示できる状態にしておく必要があります。出勤簿も同様です。また、タイムカード・出勤簿を保管していたとしても、途中で紛失してしまうと労働時間の記録が無くなってしまうことになるため、保管中の管理も怠らないようにしましょう。当サイトでは、「そもそもどのような情報や書類を残しておくべきなのか正確に把握できていない」という方に向けて、法律に沿った勤怠管理の方法や保管すべき情報・書類を詳しく解説しているため、法律に則った勤怠管理をおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
3. アルバイトや派遣もタイムカード・出勤簿の保管対象になるの?

タイムカード・出勤簿の保管は、全従業員分が対象かといわれると、そうではありません。ここでは、タイムカード・出勤簿の保管の対象者について、説明します。
3-1. アルバイトや派遣社員は、タイムカード・出勤簿の保管対象
アルバイトや派遣社員などの雇用形態に関係なく、タイムカード・出勤簿は保管する必要があります。
また、派遣社員に関しては、派遣元も派遣先もタイムカード・出勤簿を保管・管理する必要があります。
【関連記事】派遣社員の勤怠管理にも必要!タイムカードの保管期間とは?
3-2. 「高度プロフェッショナル制度対象労働者」の従業員は、タイムカード・出勤簿の保管対象外
2019年に労働安全衛生法が改正され、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く裁量労働制の適用者や管理監督者を含む全ての労働者が、客観的な記録を用いて労働時間の把握をすることが義務化されました。
よって、高度プロフェッショナル制度対象労働者のみタイムカード・出勤簿の保管義務対象外となります。
しかし、高度プロフェッショナル制度対象労働者であっても、企業側には勤怠の管理義務があります。そのため、労働基準法ではタイムカード・出勤簿の保管が義務付けられていませんが、一定期間は破棄せずに保管しておくことが推奨されます。
関連情報:出雲労働基準監督署|客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました
4. タイムカード・出勤簿の保管期間は、いつから数えたらいいのか?

タイムカード・出勤簿の保管期間は5年ですが、いつのタイミングから5年と数えるのでしょうか。ここでは、タイムカード・出勤簿の保管期間の起算日について説明します。
4-1. 基本的には、最後に記録した日から起算する
タイムカード・出勤簿の保管期間の起算日は、完結日と決められています。完結日とは、最後に記録した日のことを指します。
つまり、タイムカード・出勤簿に関しては、最後に記録した日を起算日とみなします。
4-2. 派遣社員の場合は起算日に注意
派遣社員の起算日は、最後に打刻した日ではなく、派遣契約終了日です。
派遣社員の勤怠は、派遣元が作成した「派遣元管理台帳」で管理されます。派遣元管理台帳に、最後に記録されるのは、派遣契約が終了した日です。そのため、派遣社員のタイムカード・出勤簿の起算日は、派遣契約終了日と同日とされます。
ほかの雇用形態と同じように考えていると、起算日が異なるので、注意が必要です。
【関連記事】派遣社員の勤怠管理にも必要!タイムカードの保管期間とは?
5. 期間内のタイムカードの保管方法とは
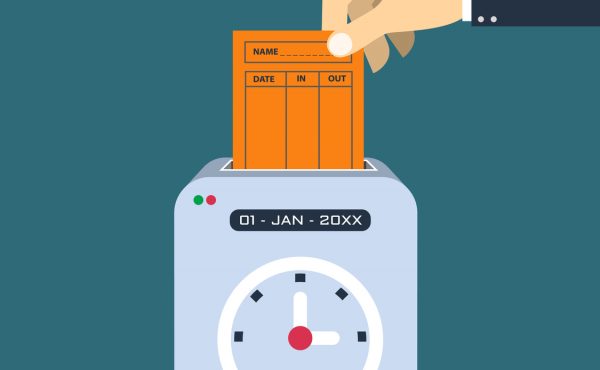
今まで、タイムカード・出勤簿の保管期間について説明してきましたが、保管期間を把握した上で、実際にどのような方法でタイムカードを保管するべきなのでしょうか。保管方法を解説します。
5-1. 紙のタイムカード
紙のタイムカードは、湿気や紫外線から守るために適切な環境で保管する必要があります。
また、全従業員のタイムカードを紙媒体で保管する場合、保管場所を確保することが重要です。倉庫に山積みにすると、間違って破棄する恐れがあります。
そのため、わかりやすく管理することが求められます。具体的には、従業員ごとではなく、年月ごとにダンボールやケースに入れて保管する方法を推奨します。
これにより、必要な時にすぐに取り出せるようになります。また、定期的な点検と整理を行い、保管状況を常に最新の状態に保つことも重要です。
5-2. データ上のタイムカード
データ上のタイムカードは定期的にバックアップし、安全なサーバーやクラウドに保存することが重要です。
この方法はデータの紛失や盗難のリスクを最小限に抑えます。法定保管期間中のタイムカード管理は課題となりがちです。データ上での管理には以下のようなメリットがあります。
1. 場所を取らない
紙媒体の保存は多くのスペースが必要ですが、データ保存ならその必要がなく、保存場所にかかる経費も削減できます。さらに、データは劣化しないため長期保管に適しています。
2. 管理や情報のアクセスが簡単
データで保管すると、探す手間が省け、迅速に必要な情報にアクセスできます。これにより、労働基準監督署から求められた際も即座にデータを提供でき、業務効率が向上します。
3. セキュリティの向上
データはクラウドやサーバーに安全に保存され、紛失や盗難のリスクを軽減できます。自然災害や人為的ミスによるデータ削除からも復元できるため、情報管理が強化されます。
これらのメリットを踏まえ、データ上でのタイムカード管理は働き方改革の一環として有効であり、紙媒体の管理に比べて多くの利点があります。このように実際に働き方改革をきっかけに、勤怠管理システムを導入し、タイムカードの保管などを考えずに済むようになった事例をご紹介します。
システム導入事例
2019年4月に施行された働き方改革関連法によって、残業時間を正確に管理する必要がありました。そのタイミングで、前から考えていた勤怠管理システムを導入することに決めました。
導入前に想定していなかった効果の1つは、タイムカードの保管を考える必要がなくなったことです。
正直、そのときはタイムカードをとりあえず保管しておいて、期間が3年過ぎたと気づいたタイミングで破棄していました。ちょうど会社の拡大機であったため、保管するタイムカードが増え、管理スペースが足りなくなっていました。
しかし、勤怠管理システムを導入したことで、勤怠データはサーバーに保管されるため、物理的な保管スペースは必要なくなりました。
想定していなかった効果でしたが、勤怠管理システムを導入してよかったです。
(インターネット関連サービス/150名/3拠点)
6. タイムカードを保管する際の注意点

タイムカードを保管するためには次のような点に注意しましょう。
- 退職者タイムカードも保管する
- タイムカードは期間ごとにまとめる
6-1. 退職者のタイムカードも保管する
タイムカードの保管対象はその時点で雇用している従業員だけではありません。退職者のタイムカードも保管する必要があります。
退職した従業員であっても、もし未払いの賃金があった場合は賃金請求権によって請求が可能です。このような際に適切に対応できるように備えるためにも、退職者のタイムカードも保管しておきましょう。
6-2. タイムカードは期間ごとにまとめる
タイムカードを保管する際は期間ごとにまとめるのがおすすめです。一般的に労働基準監督署からタイムカードの提出を求められた場合、期間ごとに提出します。
期間ごとにまとめていないと、いざという時に慌てて整理してタイムカードの一部を紛失してしまうかもしれません。
このようなリスクを回避して、万が一の際にスムーズに提出できるように、タイムカードは期間ごとにまとめておきましょう。
7. タイムカード保管のルールを正しく把握しておこう

タイムカード・出勤簿で勤怠を管理している企業は、5年間タイムカード・出勤簿を保管しておく必要があります。
基本的には、最後に記録した日が起算日ですが、派遣社員に関しては、派遣契約終了日が起算日となるので、注意が必要です。
タイムカード・出勤簿の保管が面倒だと感じる方は、勤怠管理システムを考えてみてはいかがでしょうか。
▼この記事をご覧の方にオススメの記事はこちら
タイムカードで計算する簡単な方法は?電卓で集計する計算式も紹介
\ タイムカードの5年間の保管方法にお悩みの方 /
タイムカードのような勤怠にかかわる情報は5年間の保管が法律で義務付けられています。一方で、紙の保管には場所や整理の手間がかかったり、探し出すのに時間がかかったりするため、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような方におすすめなのが、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」です!
ジンジャー勤怠では、入社してからの勤怠情報をシステム内で管理することができます。
場所や整理不要で、データの検索もできるため、人事担当者さまの業務が楽になります!
ジンジャー勤怠に関して、もっと知りたい方は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25