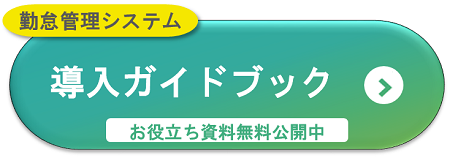タイムカード・出勤簿の手書きは違法?勤怠管理の必要性を理解しよう

近年、テレワークなどさまざまな働き方に対応するために、クラウドを利用した勤怠管理システムを導入する企業が増加傾向にあります。しかし、小規模の企業や個人経営の企業などは、タイムカードを手書きで管理しているケースも少なくありません。
本記事では、手書きで勤怠管理をおこなう際に注意するポイントについて解説します。
目次
手書きの出勤簿やタイムカードでは、客観的な記録による労働時間の把握ができておらず、
書き換えなどができるため勤怠情報の改ざんリスクがあります。
また、手書きの出勤簿などを使っている場合、従業員一人ひとりの労働時間の計算も
手計算やExcelへ転記して計算する必要があり、
労働時間の集計にも手間と時間がかかっているのではないでしょうか?
そのような課題がある場合、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を検討してみませんか?
ジンジャー勤怠でできること
従業員が出退勤の打刻をすることで、打刻データをもとに労働時間を自動集計
打刻データの修正に管理者の承認が必要な設定
→勤怠情報の改ざんを防ぐ仕組みづくりを可能に!
他にもジンジャー勤怠では有給休暇の自動付与など、人事の方を楽にする機能を取り揃えております!
勤怠管理システムについて、もっと詳しく知りたい方はこちらからお気軽にお問い合わせください。
1. 手書きのタイムカードや出勤簿は違法?

手書きの勤怠管理は、厚生労働省が労働時間を把握するための方法として定めている「客観的な記録」には該当しません。
手書きの記録は従業員自身で改ざんし、労務担当者が正確な実労働時間を把握できない可能性があるため「自己申告制」に該当します。
ただし、出勤簿に手書きで出退勤の時間を記入する勤怠管理がすべて違法となるわけではありません。外回りの営業など労働時間を客観的に把握する手段がない場合に限り、自己申告制による勤怠管理が認められています。その場合は以下の措置を講じることが求められており、このルールを守れば手書きによる出勤簿の勤怠管理は違法ではありません。
(2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明をおこなうこと
② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的におこなわれていないか確認すること
とはいえ、客観的に労働時間を把握する手段があるにもかかわらず、手書きの出勤簿による勤怠管理をすることは違法となるため、注意しましょう。
なお、デジタル打刻であれば、従業員自身が後からの改ざんができないため、客観的な出勤簿となります。
具体例としては、ICカードへの打刻や入退室履歴、PCやタブレットを使用して打刻する勤怠管理システムを利用したものを指します。
関連記事:勤怠管理において客観的記録をつけるための方法やポイントとは
1-1. 適切な方法で勤怠管理をする必要性
適切な方法で勤怠管理をおこなうことで、労働時間の正確な把握による給与計算や、労働基準法などの法律順守にも繋がります。また、みなし残業として残業代を出さない、または低く見積もって計算してしまう不正を回避し、適切な勤怠状況を確保することも可能です。
さらに、実際のトラブルを防止するだけでなく、勤怠管理をおこなうことで健全な経営管理を推進しているアピールにもなります。
しかし、従業員一人ひとりの勤怠管理をおこなうのは業務負担が大きく、人員不足になる場合は勤怠システムの導入を検討してみましょう。勤怠システムでは勤怠状況を一括で管理できるので、人件費や時間を削減しながら、的確な勤怠管理が可能です。
2. タイムカードへの時間の書き方

タイムカードを手書きで管理する場合、従業員数が少ない企業であれば、毎月発生する集計業務がそこまで負担にならない可能性があります。ただし、従業員ごとに記載する項目がばらばらでは、正確な勤怠管理ができないので書き方を統一することが重要です。
勤怠管理をするには、下記の項目について記録する必要がありますが、タイムカードには労働日ごとに出退勤の時間、休憩時間、総労働時間などを最低限記載してもらうようにするとよいでしょう。
| ・出勤日 ・労働日数 ・出勤、退勤の時刻 ・日別の労働時間数 ・時間外労働をおこなった日付・時刻・時間数 ・休日労働をおこなった日付・時刻・時間数 ・深夜労働をおこなった日付・時刻・時間数 |
3. 手書きで記入する場合の注意点

勤怠管理を手書きでおこなうことは、少人数であれば管理がしやすい反面、シフトと実績の照合作業や、打刻漏れの際に従業員へ確認の連絡など、タイムカードの管理にお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本項目では、勤怠管理をタイムカードに手書きでおこなう際、注意するポイントについて解説します。
3-1. 勤怠管理に必要な情報
企業は、従業員の労働時間を正確に把握する必要があります。
勤怠管理では出退勤の時間、欠勤、遅刻、休憩時間、休日の取得、有給取得などすべてを把握しなくてはいけません。
その理由は、労働基準法第32条に法定労働時間の記載があり「1日8時間、週40時間」という決まりがあります。この法律を企業が守れているのか、それに基づいた報酬を支払えているのかが勤怠管理になります。
また労働時間を正確に把握することは、正しい給与計算に必要不可欠です。給与や残業代も、日々の労働時間の記載があるからこそ計算することができます。さらに、勤怠管理を通して従業員が働き過ぎていないか、体の不調は訴えていないかなど、企業内の労働環境の見直しにもつながっていくでしょう。
従業員の勤怠管理を正しくおこなうことは、企業の健全な体質を維持していくことになります。
出勤簿に必要な項目の詳細は以下の記事で解説しています。
関連記事:出勤簿とは?役割や必要項目、自作する際の注意点を解説
36協定とは
36協定とは、企業が従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日出勤を命じる際に、労働組合などと書面による協定を結び、管轄地区の労働基準監督署に届け出る必要があることをいいます。以前は労使間の合意があれば労働時間を無制限に延長することができましたが、大幅に法改正がおこなわれた結果、時間外労働の上限が設けられました。
関連記事:36協定は全ての企業に義務が?対応する勤怠管理システムの選び方とは
3-2. タイムカード記入に鉛筆を使わない
厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の把握を、「原則として使用者による現認やタイムカードやパソコンの使用時間記録等の客観的な記録によっておこなう」と推奨されています。
この部分だけ切り取ると「労働者が自分でタイムカードを記入することは客観的記録と捉えられない」と解釈することも可能ですが、労働者の自己申告による労働時間の管理自体が否定されてるわけではありません。
ガイドラインでは、やむを得ず自己申告制により始業・終業時刻を把握する場合には、使用者が労働者に対して適正に自己申告をおこなうよう十分な説明をしたり、報告が適正におこなわれているか確認したりするなど、一定の措置をとるよう示しています。
しかし、自分で出退勤時刻を書き込む管理方法では、労働者が実際の労働時間よりも多く申告したり、逆に、使用者によって労働者が実際の労働時間よりも少なく申告させられる可能性があります。そのため、鉛筆書きでの自己申告は「労働時間の客観的な把握・管理の方法」として適切ではありません。情報の改ざんができないよう、ボールペンなどの使用を従業員に促していきましょう。
3-3. 間違えてしまった時の対処法
まずは打刻ミスをした本人に話を聞いて、事実なのかどうかすぐに確認しましょう。すぐに確認しなければ、月末の給与計算でミスが発生します。そのようなことを起こさないためにも、早めに確認するのがおすすめです。確認する際には、ミスをしてしまった理由や実際の勤務状況などについて聞きましょう。
また、ミスをしてしまった従業員には、始末書を出してもらいます。始末書を出してもらうという行為には、打刻ミス防止やルールの再確認などの効果があるだけではなく、労基署の監査で勤務実績を修正した時のエビデンスにもなります。
4. 勤怠管理のポイント

企業が従業員の勤怠管理をする際には、注意する2つのポイントがあるのでチェックしておきましょう。
4-1. 自社の勤務形態に合わせた勤怠管理をおこなう
雇用形態は、正社員だけではなく契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、また最近では自宅に居ながら仕事ができるテレワークという働き方も徐々に浸透しつつあります。このように、柔軟な働き方が社会に浸透していく一方で、「正しい勤怠管理ができるか」ということが課題となっている企業も少なくありません。
雇用形態が異なるだけであっても給与計算が煩雑になり、人数が多ければ集計にも時間と工数がかかります。また、パートやアルバイトの場合はシフトで勤務している場合が多く、希望日を聞いて人員配置をする作業は、かなり面倒で煩雑な内容になります。
したがって、それぞれの勤務形態の労働状況をどのように正確にデータを吸い上げて、ミスなく給与計算につなげられるかが、勤怠管理の重要なポイントになってくるでしょう。
4-2. 勤怠状況を正確に把握する
従業員の勤怠の状態を正確に把握することは、コスト削減につながっていきます。その理由は、給与計算が正しくおこなわれるからです。給与計算が正しく処理されていないと、残業代や保険料、税金などの計算を間違えてしまい、多く支払ってしまうかもしれません。
また、日頃から勤怠管理をしっかりとおこない、それに基づいて勤務時間などの情報を正しく吸い上げることで、余計な時間や工数を使わなくて済みます。
より正確な勤怠管理をするとなると業務が増えるイメージがありますが、最終的にはコスト削減となるので、勤怠管理システムなどの導入して、効率よく把握できるようにするのもポイントになります。
5. タイムカードを手書きするメリット・デメリット

勤怠管理は企業にとって重要な業務の1つです。勤怠を管理する方法は、手書きからシステムまで形態はさまざまです。しかし、今後はさらに働き方が多様化されることが考えられるため、労働時間や給与計算などの業務が煩雑になり管理が難しくなるでしょう。
これらの管理をシステム化して、業務負担を軽減してくれるのが勤怠管理システムです。ここでは、勤怠管理システムのメリット・デメリットを紹介するので、導入検討の参考にしてみてください。
システムを導入してペーパーレス化を進める方法については下記の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:勤怠管理をペーパーレス化するには?電子化のメリット・デメリットも解説
5-1. タイムカードを手書きするメリット
まずは、タイムカードを手書きするメリットを紹介します。
コストがかからない
手書きのタイムカードは従業員の少ない企業にとって、安価なコストで勤怠管理を円滑にする利点があります。
導入費用やランニングコストが抑えられるため、会社全体の従業員数が少ない企業や、今期・来季以降の予算を抑えたいと考えている企業にとってはメリットとなるでしょう。
フォーマットを自由にカスタマイズできる
手書きのタイムカードであれば、フォーマットを自由にカスタマイズできるというメリットもあります。
フォーマットに個々の従業員の労働時間や残業時間、休日出勤や休日労働などの項目を入れることもできるので、部署ごとの勤怠管理が容易になります。
5-2. タイムカードを手書きするデメリット
手書きのタイムカードは、コストがかからず自由にフォーマットを作れるというメリットがあります。しかし、デメリットもあり、こちらの方が担当者の業務負担につながるので確認しておきましょう。
勤怠情報改ざんのリスク
タイムカードを手書きで管理するデメリットとして、勤怠情報の改ざんが挙げられます。例えば、遅刻をした従業員が、本人はオフィスに到着していない場合であっても、タイムカードへの代筆を同僚に頼むことができます。
すると、本人は遅刻をした場合であっても、タイムカード上の記録では定時前に出社していることになるため、遅刻と扱われないという事象が発生します。他にも、休日出勤をしていないのにしていることになったり、残業時間を多く記載したりするなどの不正も考えられます。
勤怠情報の改ざんのリスクがあるというのは、企業にとって大きなデメリットです。
関連記事:勤怠の改ざんが発覚!不正予防と対処法について徹底解説
保管する手間がかかる
労働基準法では、タイムカード等の書類につき、5年間の保管義務が定められています。 しかし5年間(当分の間は3年間)ものタイムカードを保管するのは場所を取るうえ、管理が大変です。 また火災や紛失などによって、記録を失ってしまうリスクもあります。
関連記事:タイムカードの保管期間は5年!タイムカードの保管について徹底解説!
勤怠管理が正確にできない可能性がある
前述していますが、手書きのタイムカードの場合は、遅刻しても定時の出社時間を記載する、残業を水増しして申告するなど従業員による不正のリスクがあります。また、残業代の削減や長時間労働の隠蔽のために、企業側が勤怠情報を改ざんする可能性もあります。
勤怠管理を正確にすることは、正しい給与計算に直結します。しかし、手書きのタイムカードの場合は信頼関係がなりたっていないと、双方にとって「正確な給与が支給されない・できない」という大きな問題につながるデメリットがあります。
ヒューマンエラーが起こりやすい
手書きのタイムカードは、人によっては雑に記入したり癖のある文字で書いたりするため、集計時に読み間違いをしてしまう可能性があります。さらに、すべての従業員の出退勤時間を確認し、集計するという作業はヒューマンエラーが起こりやすいというデメリットもあります。
また、記入漏れや書き間違いなどがあれば、従業員への確認作業も必要になるため、業務効率が悪くなるというのもデメリットです。
6. まとめ

勤怠管理において、手書きでの運用は違法ではありません。手書きであろうと他の手法であろうと、勤怠管理を正しくおこなっていればコンプライアンスを遵守していることになります。
しかし、手書きのタイムカードなどは「客観的な記録」ではないので、外周りの営業職など特殊な勤務形態以外の従業員は、電子機器などで勤怠管理をすることが求められます。また、手書きによる労働状況の把握はデメリットも多いので、正確な勤怠管理ができるシステムの導入などを検討してみることをおすすめします。
\ 手書きの出勤簿から勤怠管理システムへの乗り換えを検討中の方 /
手書きの出勤簿やタイムカードでは、客観的な記録による労働時間の把握ができておらず、
書き換えなどができるため勤怠情報の改ざんリスクがあります。
また、手書きの出勤簿などを使っている場合、従業員一人ひとりの労働時間の計算も
手計算やExcelへ転記して計算する必要があり、
労働時間の集計にも手間と時間がかかっているのではないでしょうか?
そのような課題がある場合、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を検討してみませんか?
ジンジャー勤怠でできること
- 従業員が出退勤の打刻をすることで、打刻データをもとに労働時間を自動集計
- 打刻データの修正に管理者の承認が必要な設定
→勤怠情報の改ざんを防ぐ仕組みづくりを可能に!
他にもジンジャー勤怠では有給休暇の自動付与など、人事の方を楽にする機能を取り揃えております!
勤怠管理システムについて、もっと詳しく知りたい方は以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25