勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!
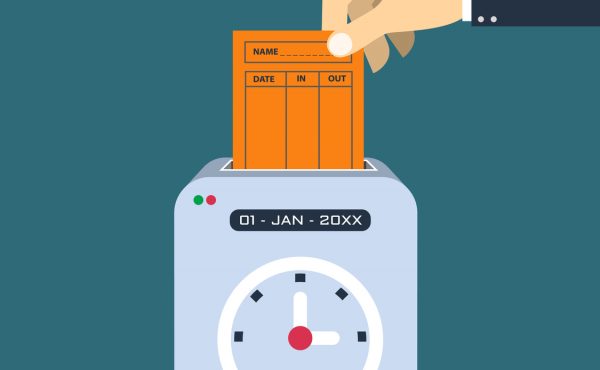
毎月決まった日におこなわれる勤怠を締める業務。なんとなく作業としておこないがちな業務ではありますが、実は勤怠管理を的確におこなうことにはきちんとした理由があるのです。本記事では勤怠管理を正しい方法でおこなわなければならない理由や、大切な勤怠管理を抜け漏れのないようにおこなっていくための方法を紹介します。
目次
勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」では、勤怠や人事周りの業務効率化ができます!
直感的に操作しやすい画面で、人事・給与のような周辺業務にもデータを簡単につなげられるのが特徴です。
紙管理からジンジャー勤怠に変更したことで、月末の集計業務が楽になった!
ジンジャー給与と一緒に使って、勤怠情報を用いた給与計算ができるようになった!
給与明細発行までの工数が削減できた!
といったお声をいただいております。ジンジャー勤怠や勤怠管理システムについてもっと知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
1. 勤怠管理とは

そもそも勤怠管理とは、従業員の出退勤の時間や欠勤、遅刻早退などの勤務状況を記録し、労働時間を管理することです。勤怠管理の方法について検討する際は、勤怠管理の基本をしっかりと理解できていることを確認しましょう。
1-1. 勤怠管理で把握すべき項目
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、勤怠管理では使用者は労働日ごとに労働者の始業と終業の時間を確認・記録しなくてはならないとしています。
労働日ごとに始業・終業の時間を記録することによって、単純な労働時間だけでなく、「時間外労働」「深夜労働」「休日出勤」があった時間を把握することが可能になります。
また、労働基準法第108条、単に従業員が労働した時間だけを賃金台帳に記入するのではなく、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間など賃金計算の基礎となる項目ごとに分けて賃金台帳へ記入しなくてはならないとしています。
また、上記の時間に加え「休憩時間」や「欠勤日」、「有給休暇の取得日数と残日数」「代休・振休の日数」も記録し管理する必要があります。
関連記事:勤怠管理における遅刻早退の控除の取り扱いや処理の方法について
関連記事:勤怠控除とは?計算方法と注意するべきポイントを紹介
1-2. 労働時間と休憩時間の定義
勤怠管理を正確に行うには、正しい労働時間の定義を把握しておく必要があります。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間です。したがって、業務内容に含まれていなかったとしても、着用が義務付けられている制服への着替え時間や強制参加になっている社内研修も「労働時間」とみなされます。
また、休憩時間とは、労働時間の途中に、労働者が労働から離れ自由に過ごす事を保障された時間です。この時間は使用者の指揮命令下にないことが前提とされているため、例えば昼休憩の際に電話番をさせることは休憩時間を与えたことにはなりません。
関連記事:勤怠管理における休憩時間の取り扱いとは?労働基準法の基礎知識を解説
関連記事:勤怠管理において業務時間内の中抜けをどう扱うべき?
1-3. 勤怠管理の対象者と行うべき事業場
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、労働時間把握の義務が課されているのは、労働基準法第4章が適用される全ての事業場です。
労働基準法第4章は労働時間と休憩時間、休日休暇について定められている章であるため、基本的に従業員を雇用する場合は必ず勤怠管理が必要であると考えましょう。
また、対象者についても高度プロフェッショナル制度の労働者を除くすべての労働者となります。
これまで「労働基準法第41条に定める者(管理監督者)」と「みなし労働時間が適用される労働者」は労働時間把握の例外とされていましたが、2019年の労働安全衛生法の改正により、対象となったため注意しましょう。
したがって、パート・アルバイトや派遣など雇用形態の違いにも関わりなく、勤怠管理は正確におこなわなければなりません。
関連記事:役員の勤怠管理は必要?従業員との違いや各種保険について解説
2. 勤怠管理をおこなう目的・必要性

勤怠管理をおこなう大きな目的は、労働条件や労働基準法を守りつつ「正確な給与計算をするため」と「従業員の健康を守るため」です。
基本的な事柄ではありますが、トラブルを避けるためにも、いまいちど勤怠管理の目的を確認しておきましょう。
2-1. 労働基準法などの法律と労働条件遵守のため
労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間、週40時間まで」と定めています。この法定労働時間を超えて働かせる場合に労使間で締結する36協定にも罰則付きで残業時間に上限規制が設けられています。
したがって、労働時間の上限を超えて働かせてしまい、法律違反になってしまうリスクを勤怠管理を厳密に行うことで避けることができます。
また、労働基準法第108条と第109条では、従業員ごとに労働時間などをまとめた賃金台帳を調製することと、タイムカードなど労働時間の記録に関するものは全て5年間(当分の間は3年間)の保存することを定めているため、勤怠管理により従業員の出退勤の時間を記録・保存しておく必要があります。
関連記事:法律改正で変わる勤怠管理 | 2019年4月より改正された労働基準法を徹底解説
2-2. 従業員に支払う給与を正確におこなうため
勤怠管理を的確におこなわなければならない2つ目の理由は、従業員に支払う給与を正確に行うためです。従業員に支払う給与は従業員が労働した時間全てに対して支払わなければなりません。
勤怠管理で従業員が働いた時間を正確に記録できていなければ、正確な給与を従業員に支払えなくなってしまうため、従業員とのトラブルになってしまう可能性があるのです。
従業員とのトラブルを予防しながら働きやすい環境づくりをするためには、厳密に勤怠管理をおこなう必要があります。
2-3. 従業員の健康維持と過労死の防止
「過労死」は「karoushi」と日本語がそのまま英語になるほど、日本特有の深刻な社会問題です。過度な長時間労働による過労死を防止し、従業員の心身の健康を守ることは、使用者に課された重要な責務です。
使用者は勤怠管理によって常に従業員が働きすぎていないかをチェックし、過度な長時間労働を行っている従業員がいる場合は、業務量を調節するなど対策を講じなければなりません。
また、労働安全衛生法では深夜労働や時間外労働を規定の時間以上行っている労働者に対し、使用者は必要に応じて健康診断や医師との面談を受けさせなければならないと定めているため、その対象者を把握するためにも勤怠管理は必要になります。
3. 勤怠管理をしていないリスク

勤怠管理は企業に求められる業務です。それにもかかわらず勤怠管理をしていなかった場合、次のようなリスクが考えられます。
- 法令に違反する
- 未払い残業代を請求される
- 社会的信用が落ちる
3-1. 法令に違反する
企業が勤怠管理をしなかった場合、法令に違反してしまいます。例えば、企業は従業員の労働日数や労働時間などを賃金台帳に記載する義務があります。賃金台帳に従業員の労働時間ほかを記載するには、勤怠管理が必要です。つまり、勤怠管理を怠っていると賃金台帳を用意できないため、法令に違反するといえるでしょう。
また、企業は従業員の労働時間や勤務状況がわかる出勤簿やタイムカードなどを5年間(当分の間は3年間)保管する義務があります。勤怠管理をしていない場合、従業員の出勤時間やタイムカードを保管できません。
従業員の時間外労働には上限が設けられています。上限を超えて時間外労働させた場合、法令違反と扱われます。勤怠管理を怠ると時間外労働を適切に管理できないため、法令に抵触しかねません。
3-2. 未払い残業代を請求される
企業が従業員の勤怠管理をおこなう目的は、従業員に支払う給与を正確に算出するためです。そのため、勤怠管理をおこなわった場合、残業代や給与を請求される可能性があります。特に残業代は請求される可能性があるでしょう。勤怠管理をおこなっていても、残業代計算のミスが発生しかねません。勤怠管理をおこなっていない場合、残業代は未払いになることがなおさらでしょう。
未払いの残業代を請求されたにも関わらず、放置を続けていると遅延損害金が発生してしまいます。さらに、従業員から労働審判や裁判をおこされる可能性があります。裁判で会社に悪質性が認められると、付加金の支払いが命じられるかもしれません。このようなリスクを避けるために、適切に勤怠管理をおこない、残業代をきちんと支払いましょう。
3-3. 社会的信用が落ちる
勤怠管理をおこなっていない場合、企業の社会的信用低下につながります。勤怠管理をおこなわないことが法令に抵触する恐れがあります。また、未払い残業代の発生リスクもあるでしょう。これらは企業の社会的信用を低下させる要因です。
企業の社会的信用が低下してしまうと、取引の停止や従業員の離職につながりかねません。昨今は転職サイトなどに口コミが掲載されるケースがあります。このようなサイトに口コミとして勤怠管理をおこなっていないことを掲載されてしまうと、新たに従業員を採用するのが難しくなってしまうでしょう。取引先からの取引停止、従業員の離職と採用難によって事業が立ち行かなくなってしまうかもしれません。
4. 勤怠管理の方法とメリット・デメリット

最初に、従業員の労働時間を記録するための原則的な方法を確認しておきましょう。その次に、具体的にどのようなツールを用いて勤怠管理するのか、また、それぞれの方法にはどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説していきます。
4-1. 勤怠管理の方法
勤怠管理で必ず行わなくてはならないことは、従業員の出退勤の時間を記録・保存することと、賃金台帳を作成することです。
厚生労働省が発表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、勤怠管理の方法は、①使用者が自ら労働者の始業と終業の時間を確認・記録すること②タイムカードやICカードなど客観的な記録をもとに始業と終業の時間を確認・記録することと定めており、自己申告制による勤怠管理は原則認めていません。
もしやむを得ず自己申告制による勤怠管理をおこなう場合は、ガイドラインで規定されている5つの措置をとる必要があります。
| ①従業員に自己申告による勤怠管理の方法を説明すること ②勤怠管理対象者に、当該ガイドラインの説明をすること ③自己申告のあった時間と実際の労働時間に乖離がないか、必要に応じて調査し、乖離があった場合は適切な時間に補正すること ④自己申告している時間が適切であるか確認すること。特に、従業員が労働時間でないと考えていても、実際は労働時間にあたる場合がある。 ⑤従業員による適切な労働時間の報告を妨げるような制度を設けないこと。また、実際は残業時間が超過しているにもかかわらず、記録上は超過していないように申告する慣習がないか確認すること。 |
勤怠管理によって記録された従業員の労働時間に関する資料は、タイムカードのみならず残業申請書なども含めて5年間(当分の間は3年間)保存する必要があります。
また、従業員ごとに作成する賃金台帳は従業員ごとに労働日数、労働日数や労働時間、残業時間など給与計算に必要な項目ごとに分けて記載しなくてはなりません。
関連記事:勤怠管理において客観的記録をつけるための方法やポイントとは
関連記事:勤怠管理をおこなう上で理解しておくべきルールを徹底解説
4-2. 出勤簿で勤怠管理をする方法
ここからは、勤怠管理を行う具体的な方法を確認していきましょう。まず1つ目の方法は、出勤簿で勤怠管理をする方法です。
出勤簿は、勤務表に従業員が出退勤の時間を記入していく方法で、締め日に回収してから各従業員の労働時間を手作業で集計していきます。
出勤簿のフォーマットさえ作成してしまえば、あとは紙代しかかからず、比較的手軽に始められる勤怠管理の方法です。
しかし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、そもそも労働者の自己申告制による勤怠管理を原則認めておらず、自己申告制の場合は特別な措置を必要としています。また、記入漏れが発生しやすい、労働時間の集計に時間がかかる、書類の保管にスペースをとり、紛失のリスクもあるというデメリットが存在します。
関連記事:タイムカード・出勤簿の手書きは違法?勤怠管理の必要性を理解しよう
4-3. タイムカードで勤怠管理をする方法
2つ目の方法はタイムカードを使用することです。タイムカードは専用の機械(タイムレコーダー)にカードを通すだけで出勤・退勤といった勤務状況を自動的に記載することができます。
タイムレコーダーによってはPCに接続して労働時間を自動で集計していくれるものありますが、基本的には出勤簿と同じくタイムカードを従業員や各拠点から集めたあとは手作業での集計になります。
手書きのような手間をかけることなく勤怠管理ができるので、時間的なコストを削減して手軽に打刻ができるというメリットがあります。
一方、出勤簿と同じく打刻漏れが発生しやすい・集計に時間がかかる・保管に場所をとるというデメリットがあります。また、飲食店など店舗や支店が複数ある企業では、タイムカードを各拠点から集めることにも時間や工数がかかってしまいます。
4-4. エクセルで勤怠管理をする方法
3つ目の方法は、エクセルを活用して勤怠管理をする方法です。エクセルを利用すれば、入力された勤務時間や勤務日数を自動的に集計できるので、従業員の勤務状況の把握や給与計算の業務負担を大幅に軽減できます。
一方で、エクセルによる勤怠管理であっても従業員の自己申告によって出退勤の時間が入力されているため、国が推奨している方法ではありません。また、ミスなく集計してくれる関数やマクロを作成するのに知識や時間が一定必要になることも考えなくてはなりません。
4-5. 自作のシステムを使用する方法
4つ目の方法は、自作のシステムを使用する方法です。自社に合わせてシステムを構築しているため、就業規則や慣習に沿った管理をしやすいことが大きなメリットです。
一方で、就業規則の変更や法改正があった際に、都度システムの改修をしなくてはならないことがデメリットとなります。さらに、もし社内の従業員が作成したシステムであった場合、その従業員が退職してしまうと誰もシステムを改修できなくなってしまうという問題も発生するため、注意が必要です。
4-6. 勤怠管理システムを導入する方法
5つ目の方法は、勤怠管理システムを導入する方法です。勤怠管理システムを導入することによるメリットは、従業員の正確な勤務時間を把握できるということです。多くの勤怠管理システムでは、スマホ打刻、PC打刻、ICカード打刻などさまざまな打刻方法を搭載しています。そのため、従業員の不正打刻を防止できることが期待できることに加えて、管理者側は毎月の締め作業の工数が削減されるといったメリットがあげられます。
また、勤怠管理システムの製品によっては、自動集計された従業員の勤怠情報と他の給与管理システムなどと連携することができるため、従業員情報を一元管理することにつながります。
一方で、導入するには他の方法と比べて高いコストが発生することと、設定や従業員への使い方説明など運用が軌道に乗るまでにある程度時間がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。
関連記事:勤怠管理のペーパーレス化とは?電子化のメリット・デメリットも解説
5. 勤怠管理で起こりやすいトラブルとは

勤怠管理を厳密に行わないことによって起こりやすいトラブルとして、残業代の未払い問題や長時間労働によって従業員の心身の健康を害してしまうことなどが挙げられます。
残業代未払いの問題では、残業申請の制度が形骸化していたり、打刻漏れや打刻修正によって実際の労働時間と記録上の労働時間に乖離が生まれてしまうことなどが原因として挙げられます。
また、勤怠管理が厳密に行われておらず長時間労働していることに気が付いていなかったり、長時間労働していると把握していながら、労働環境の改善を行わなかった場合も、勤怠管理がなされているとは言えないでしょう。
特に、2019年4月に行われた働き方改革による法改正で、勤怠管理はより厳密に行わなくてはならなくなっています。法改正で必要になった勤怠管理や、法改正に対応する方法が不安な方に向け、当サイトでは法改正の内容とその対応方法をまとめた資料「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」を無料で配布しております。勤怠管理の法律違反を避けたい方は、こちらからダウンロードページをご覧ください。
関連記事:勤怠管理をしていない企業が抱える問題点と対処法とは
6. 働き方に合わせた勤怠管理をおこなうポイント

多様な働き方や雇用形態の社員がいる企業の場合、勤怠管理をする上で注意したいポイントが異なってきます。ここでは、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員、在宅勤務に分けて勤怠管理をする際の注意点をご紹介します。
6-1. 扶養内で働きたいパート・アルバイトの勤怠管理
パート・アルバイトの雇用形態で働く従業員の多くは、学生か主婦・主夫で、「扶養控除内」での就労を希望していることがほとんどでしょう。
この場合、扶養控除内でおさまるようにシフトを組む必要があります。繁忙期でどうしても勤務日数や勤務時間が多くなってしまう場合は、他の月で労働時間を減らして調節する必要があり、年単位での管理が必要になってきます。
扶養控除から外れる条件は所得税の課税が発生する103万円、社会保険加入が必要な106万円もしくは130万円、配偶者特別控除から外れる150万円の4つがありますが、従業員がどの扶養控除内を希望しているのかを確認しておきましょう。
関連記事:パート・アルバイトの勤怠管理はシステムで効率化できる理由とは?
6-2. 契約社員の勤怠管理
契約社員は労働契約の期間に定めがある以外は基本的に正社員と同じかそれに近い待遇であることが多いため、特別に異なる勤怠管理を行う必要はありません。時間外労働や深夜労働、休日出勤の時間をしっかりと記録・管理し、休憩時間や有給休暇の付与を行いましょう。
6-3. 派遣社員の勤怠管理
派遣社員の勤怠管理は派遣元と派遣先の企業が分けて行っているため、煩雑になりやすいものです。
出退勤の時間や労働時間、休憩時間の管理は派遣先が行う一方、給与計算や有給休暇の付与は派遣元が行うため、派遣先の企業は正確な労働時間を派遣元に報告する必要があります。
したがって、打刻漏れや承認漏れが起きにくい勤怠管理を徹底するのはもちろんのこと、労働時間をスムーズに共有できる方法で勤怠管理を行うことがポイントです。
関連記事:勤怠管理システムの導入が派遣スタッフの管理におすすめな理由を解説
6-4. テレワーク・在宅勤務における勤怠管理
タイムカードやICカードによる打刻を行っていた場合、テレワーク・在宅勤務において「打刻できない」という問題が発生します。
この場合、PCの使用履歴やチャットツールのログイン時間などで勤怠管理をするという方法もありますが、どうしても自己申告による勤怠管理にならざるを得ないことも多いでしょう。その場合は、従業員へ自己申告による勤怠管理の方法を説明し理解を得ることや、申告した時間と実態にズレが起きていないかを必要に応じて確認するようにしましょう。
また、ガイドラインでは自己申告による勤怠管理を行う場合、従業員が正しい労働時間を申告することを制限するような制度を設けてはならないとしています。(例:残業時間数の報告に上限を定め、これ以上は承認しないなど)
関連記事:テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめな方法3選
7. 正確に勤怠管理するなら勤怠管理システムの導入がおすすめ

正確な労働時間の管理や、法改正に基づいた勤怠管理を行うなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
システムであれば労働時間の集計をミスなく自動で行ってくれるため、タイムカードを集めたり、打刻漏れの確認をする工数も含め労働時間の集計にかかる工数を大幅に削減することが可能です。
さらに、PCやスマートフォン、ICカードなどを用いた打刻で客観的な記録がとれるため、厚生労働省が発表しているガイドラインにも適しています。
勤怠管理システムには「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つがあるため、検討する際は違いを把握しておきましょう。それぞれの違いは次のとおりです。
| オンプレミス型の勤怠管理システム |
|
| クラウド型の勤怠管理システム | サーバーは全利用企業で共有しているため、インターネットに接続するだけでシステムが使える 法改正に対応した内容は自動でアップデートされるため、対応不要 導入費用が比較的安い 細かいカスタマイズはおこなえないことも |
オンプレミス型、クラウド型の違い以外にも、勤怠管理システムを選ぶ際のポイントはいくつもあります。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
7-1. 機能・使いやすさ
勤怠管理システムを導入する際は、システムの機能に着目しましょう。勤怠管理システムに備わっている機能はシステムによって異なります。そのため、自社にはどのような機能が必要なのかを洗い出して、それに応じたシステムを選ぶのが大切です。
また、勤怠管理システム導入にあたっては使いやすさも重要なポイントです。勤怠管理システムは導入して完了ではありません。導入後、システムを使用し続けて業務を効率化、適切に勤怠管理することが目的です。使いづらいシステムの場合、せっかく導入しても定着しない恐れがあります。勤怠管理システム導入後も運用していくためには、使いやすいシステムを選ぶようにしましょう。なかには、無料の使用期間を設けているシステムもあります。このようなシステムであれば無料の期間に使いやすさを確認して、導入を決定することができます。
7-2. セキュリティ体制が整っている
勤怠管理システムを導入する際はシステムのセキュリティ体制が整っているか確認しましょう。セキュリティ体制に不備がある場合、ウイルスやマルウエアによってシステムが使用できなくなる、不正なアクセスによって情報が漏えいするなどのリスクが考えられます。
勤怠管理システムのセキュリティを把握するためには、プライバシーマークを取得しているかどうか、情報セキュリティマネジメントシステム認証であるISMS認証を取得しているかどうかなどを確認しましょう。プライバシーマークやISMS認証を取得している場合、一定のセキュリティ対策が講じられていると考えられます。
7-3. サポート体制が整っている
勤怠管理システムの使用を定着させるには、システムのサポート体制が整っていることが大切です。勤怠管理をおこなう担当者がシステムについて疑問を抱いた場合、サポート体制が整っていれば質問できます。勤怠管理システム導入はさまざまなトラブルや疑問点が発生するでしょう。そのため、都度サポートしてもらえるシステムを選ぶのがポイントです。勤怠管理システムについての初期設定だけでなく、運用までもサポートしてくれるかどうかをポイントにシステムを選んでみましょう。なかには運用方法や管理までも提案してくれるケースがあり、このようなケースであれば手扱いサポートを受けられます。
8. 自社にあった方法で適切に勤怠管理をおこなおう

ここでは勤怠管理をどうして的確におこなう必要があるのかということだけでなく、勤怠管理をおこなう従業員の種類、実際に勤怠管理をおこなう上で取り入れておいた方が良い施策について説明しました。
事業所ごとに最適な勤怠管理の方法は違ってきますが、より正確性の高い勤怠管理を実現したい場合は勤怠管理システムを取り入れるのがおすすめです。
\ 勤怠管理にはジンジャー勤怠がおすすめ! /
勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」では、勤怠や人事周りの業務効率化ができます!
直感的に操作しやすい画面で、人事・給与のような周辺業務にもデータを簡単につなげられるのが特徴です。
- 紙管理からジンジャー勤怠に変更したことで、月末の集計業務が楽になった!
- ジンジャー給与と一緒に使って、勤怠情報を用いた給与計算ができるようになった!
- 給与明細発行までの工数が削減できた!
といったお声をいただいております。ジンジャー勤怠や勤怠管理システムについてもっと知りたい方は、まずは以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25




















