勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ

特に大所帯の企業は、手書きで正確な勤怠管理をおこなうのが難しい状況です。また、近頃は労働者の権利が重視され、残業代の未払いや過剰な連続出勤など、いわゆる「ブラック企業対策」を積極的におこなう企業も多くなりました。その対策の一つとして有効なものが「勤怠管理システム」です。
今回は、勤怠管理システムがどれほど便利な機能なのか、またその選び方についてご紹介します。
関連記事:勤怠とは?管理方法や管理項目など人事が知っておきたい基礎知識を解説!
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
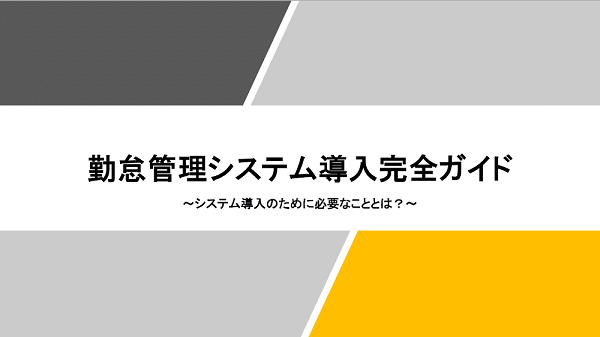
働き方改革が始まり、「勤怠管理システムの導入を考えているけど、何から着手したらいいかわからない・・。とりあえず、システム比較からかな?」とお困りの勤怠管理の担当者様も多いでしょう。
そのような方のために、当サイトでは勤怠管理システムのメリットや導入までの手順をまとめたガイドブックを無料で配布しております。
これ一冊でシステム検討から導入までに必要な情報がまとまっておりますので、社内で検討する際に役立てたい、上司に説明する際の資料が欲しいという方はぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をダウンロードしてご覧ください。



目次
1. 勤怠管理システムとは

勤怠管理システムとは文字通り、シフト作成、打刻から労働時間の集計、残業申請など勤怠管理に必要な業務を一括でおこなうことができるシステムです。
どの業種でも人手不足が目立つ今、現場の仕事も手いっぱいなのに、勤怠管理を手作業をおこなっていてはいくら時間があっても足りません。業務に支障が出てしまう前に、ぜひ勤怠管理システムの利便性を取り入れましょう。
1-1. なぜ勤怠管理システムが必要なのか?導入する目的
勤怠管理システムを導入をおすすめする理由は大きく分けて2つあります。「私の会社もこの問題が目立つ」という方は、解決の糸口に繋がるかもしれないので、ぜひご参考にしてください。
1-1-1. 会社と社員との給与トラブルを防ぐ
1つ目は「会社と社員の給与トラブルを防ぐ」についてです。給与トラブルを防ぐためには、打刻時間を正確にとらえ、月の総勤務時間や残業時間から給与を算出することが重要です。
人間の手作業でおこなうわけではないので、ヒューマンエラーが起こりにくいので、「タイムカードの勤務時間と実際の給与が違う」などといったトラブルを未然に防ぐことができます。
1-1-2. 業務の効率化
2つ目は「業務の効率化」。勤怠管理システムは勤怠実績からシフト管理などの勤怠に関連する業務ををひとまとめに出来る大変優れたシステムです。人事や総務など、管理者の大きな味方になります。
関連記事:勤怠管理システムを導入する目的とは?メリット・デメリットも確認
2. 勤怠管理システムのメリット


勤怠管理システムのメリットとして以下が挙げられます。
- 従業員の労働時間を正確に把握できる
- 割増賃金を的確に計算できる
- 法改正に対応できる
- 不正の打刻を防止できる
- 勤怠管理かかるコストを削減できる
- モバイル対応であれば営業先でも打刻できる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
関連記事:勤怠管理システムを導入する5つのメリットは?デメリットも解説!
2-1. 従業員の労働時間を正確に把握できる
勤怠管理システムを導入することで従業員の労働時間を正確に把握できます。企業は従業員の労働時間を客観的に把握しておく必要があります。特に時間外労働については上限が規制されているため、的確な把握が求められます。
勤怠管理システムであれば、従業員がどれくらい時間外労働しているかを把握して、上限に達しないようなマネジメントが可能です。
2-2. 割増賃金を的確に計算できる
時間外労働が発生した場合、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金は時間外労働の長さがどれくらいか、休日労働かどうか、深夜労働になるかなど状況によって異なります。勤怠管理システムを給与システムと連携できるため、複雑な割増賃金を的確に計算可能です。
2-3. 法改正に対応できる
勤怠についての法律は改正される可能性があります。タイムカードやExcelなどで勤怠管理している場合、自社で新たな法律に対応しなければなりません。しかし、自社で法改正に対応するとなると時間がかかるだけでなく、理解不足によるミスにつながりかねません。
一方、法改正に対応した勤怠管理システムであれば自社で対応せずとも、システムの提供元が適切に対応してくれます。
2-4. 不正の打刻を防止できる
タイムカードや自己申告で勤怠管理している場合、打刻の不正が発生しかねません。例えば従業員が自身の打刻を不正してしまう、管理者が従業員の打刻を不正してしまうなどが発生する可能性があります。対して、勤怠管理システムであれば打刻を不正されることがありません。
2-5. 勤怠管理かかるコストを削減できる
勤怠管理にはさまざまなコストが発生します。例えば、タイムカードやExcelなどで勤怠を管理している場合、集計に多くの時間を費やしてしまいます。しかし、勤怠管理システムであれば従業員の勤務時間が自動で集計されます。そのため、勤怠の集計にかかるコストを削減可能です。
関連記事:勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説
2-6. モバイル対応であれば営業先でも打刻できる
勤怠管理システムのなかには、スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末に対応しているシステムがあります。このようなシステムであれば営業先や外出先からであっても打刻が可能です。さらに、打刻場所を選ばないため、テレワークにも対応できます。
関連記事:勤怠管理システムはタブレットに対応可能!メリットや選び方を解説
3. 勤怠管理システムのデメリット


便利な勤怠管理システムですが、当然デメリットもあります。勤怠管理システム導入のデメリットは次のとおりです。
- 導入にコストがかかる
- 社内で運用ルールを周知する必要がある
3-1. 導入にコストがかかる
勤怠管理システム導入による一番のメリットはコスト面です。システムは購入当初は無料のものもありますが、システム運用費や打刻機器などの機材購入費がかさばるでしょう。システム運用費は、1人あたり数百円ほどと少額ですが、大所帯になるとその金額も大変な額になります。
次に配慮すべき点は「システムの規模」です。システムに備わっている機能を持て余してしまう、もしくは規模が足りていないなどの問題になる前に、システムの内容を確認して購入しましょう。
例えばオンプレミス型は、一度システムを構築してしまえば使い勝手は良いのですが、管理は従業員がおこなわなければならず手間もコストもかかるので大企業向けです。
クラウド型は、システム構築する必要がなく、サポート体制が備わっているので管理も楽ですが、既存のシステムに合わせて扱わなければならないので従業員数が少ない会社向けになっています。
3-2. 社内で運用ルールを周知する必要がある
勤怠管理システムの導入にあたっては、社内で運用ルールを周知する必要があります。運用ルールが周知されていないと勤怠管理システムを導入しても、適切に運用できずシステムが定着しないかもしれません。そのため、勤怠管理システムを導入するには社内で運用ルールを策定、周知するようにしましょう。
4. 勤怠管理システムは何を基準に選べばよいのか

せっかくコストをかけてシステムを導入するのですから、失敗したくはないですよね。ここでは、導入する勤怠管理システムを決める際に基準にすべき項目を3つご紹介します。
4-1. 自社の就業規則や労働形態に対応できるか
自社の就業規則にそって打刻や労働時間の集計、有給休暇の付与ができなければ元も子もありません。まずは、自社の就業規則に合った設定ができるかを確認しましょう。
また、あわせて自社の労働形態に対応できるかもチェックポイントです。例えば、営業職なら直帰の打刻ができるのか、人によって所定労働時間を変えられるのか、現在使っている打刻方法に対応しているかなどは、必ず確認しておきましょう。
関連記事:勤怠管理システムにおける休憩時間の打刻方法をご紹介
関連記事:勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務効率をアップしよう
4-2. サポート体制が充実しているか
サポート体制とは、システム導入後に勤務体系に合わせた設定方法や、操作に関する細かい手助けをしてくれるサービスです。購入後は電話サポートを受け付けており、時には自社まで足を運んでくれるサービスもあります。
複雑な勤怠管理システムは、一から自分だけで使いこなすのは困難です。「どこまでが無料で、どこから有料なのか」「対応できる日時はいつか」「店舗まで足を運んでくれるのか」など、サポート体制の充実度を始めに確認してください。
4-3. 無料で試せるトライアルがあるか
「システムで本当に勤怠管理ができるのか不安」「使い勝手を購入前に確認したい」という方には、無料で試せるトライアルができるかどうかをチェックするのもおすすめです。
特に、クラウド型の勤怠管理システムには無料トライアルがあることがほとんどです。設定方法や使用感を確認した上で安心して導入できるシステムを見つけましょう。
ここまで、導入する勤怠管理システムを決定する際の基準をご紹介してきましたが、この他にも「勤怠管理システムを導入するまでにはどんなステップがあって、何をすればいいの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。そのような方に向け、当サイトでは勤怠管理システムを導入するまでのガイドを無料で配布しております。ご興味のある方は、こちらより「勤怠管理システム導入完全ガイド」の資料ダウンロードページをご覧ください。
どのようなシステムが自社に合うかわからない場合は、会員登録不要、質問に答えるだけでぴったりの勤怠管理システムを無料診断できるFitGapを活用してみるのもよいでしょう。
4-4. 外部システムと連携できるか
勤怠管理システムのなかには、外部システムと連携できるものがあります。勤怠管理システムを導入するには、外部システムと連携できるシステムを選びましょう。例えば給与計算システムと勤怠管理システムとを連携させることで、給与計算がスムーズにおこなえます。また、人事評価システムと勤怠管理システムとを連携させることで、従業員へフィードバックしやすくなるでしょう。
5. 勤怠管理システムを活用して勤怠管理をスムーズにおこなおう


「働く人が少ない」昨今の日本は多くの会社が人手不足に悩んでいると言われます。従業員数が少ないと、管理者の仕事量も増え、結果として勤怠管理の負担が増えてしまいます。
「勤怠管理システム」を上手く使いこなせば、勤怠管理にかかる労力削減に繋げることができるかもしれません。
しかし、費用面などから手軽に導入できるものではないので、クラウド型のトライアルを実施し、まずはその手ごたえを体験してみてはいかがでしょうか。
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
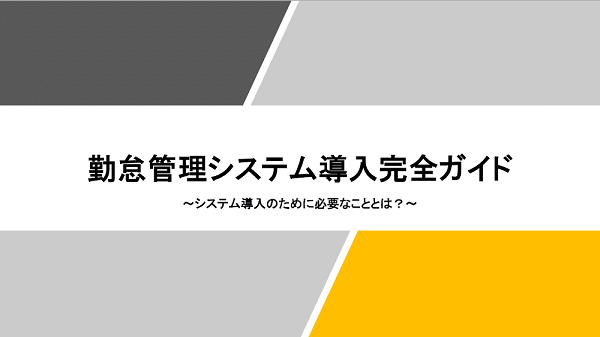
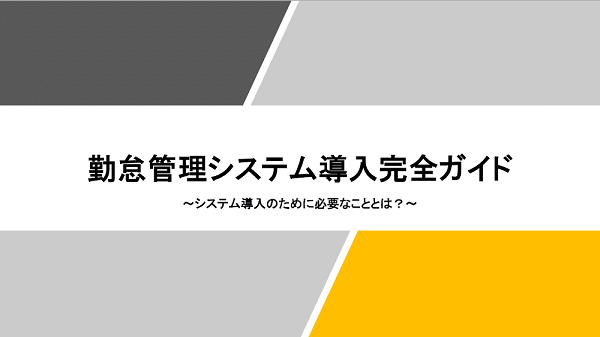
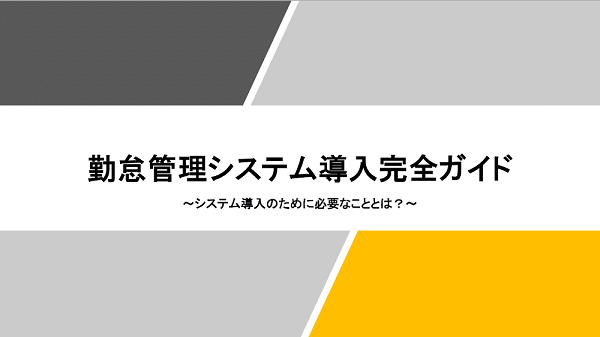
働き方改革が始まり、「勤怠管理システムの導入を考えているけど、何から着手したらいいかわからない・・。とりあえず、システム比較からかな?」とお困りの勤怠管理の担当者様も多いでしょう。
そのような方のために、当サイトでは勤怠管理システムのメリットや導入までの手順をまとめたガイドブックを無料で配布しております。
これ一冊でシステム検討から導入までに必要な情報がまとまっておりますので、社内で検討する際に役立てたい、上司に説明する際の資料が欲しいという方はぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をダウンロードしてご覧ください。



関連記事:大企業が導入すべき勤怠管理システムを選ぶ際のポイント4つ
関連記事:中小企業向け勤怠管理システム|導入前の課題、導入後の効果とは
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25



















