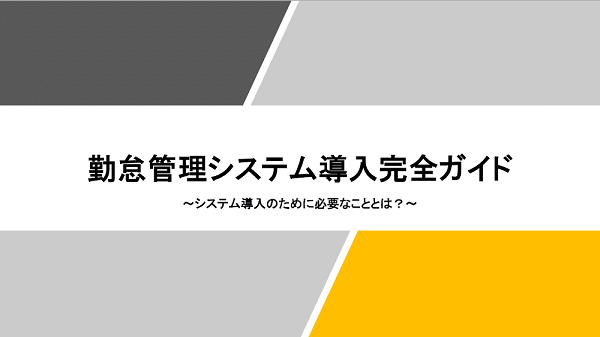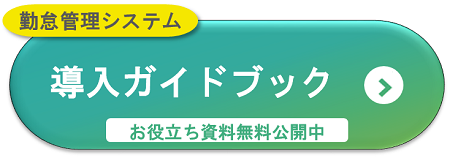勤怠管理システムのメリット7つを徹底解説!デメリットはある?

2019年4月から施行されている『働き方改革関連法案』。これによって従業員の正確な勤怠情報を把握することが義務化され、人事担当者がおこなう勤怠管理業務は煩雑化しています。本記事では、企業が勤怠管理システムを導入するメリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
働き方改革が始まり、「勤怠管理システムの導入を考えているけど、何から着手したらいいかわからない・・。とりあえず、システム比較からかな?」とお困りの勤怠管理の担当者様も多いでしょう。
そのような方のために、当サイトでは勤怠管理システムのメリットや導入までの手順をまとめたガイドブックを無料で配布しております。
これ一冊でシステム検討から導入までに必要な情報がまとまっておりますので、社内で検討する際に役立てたい、上司に説明する際の資料が欲しいという方は
ぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 勤怠管理システムとは?
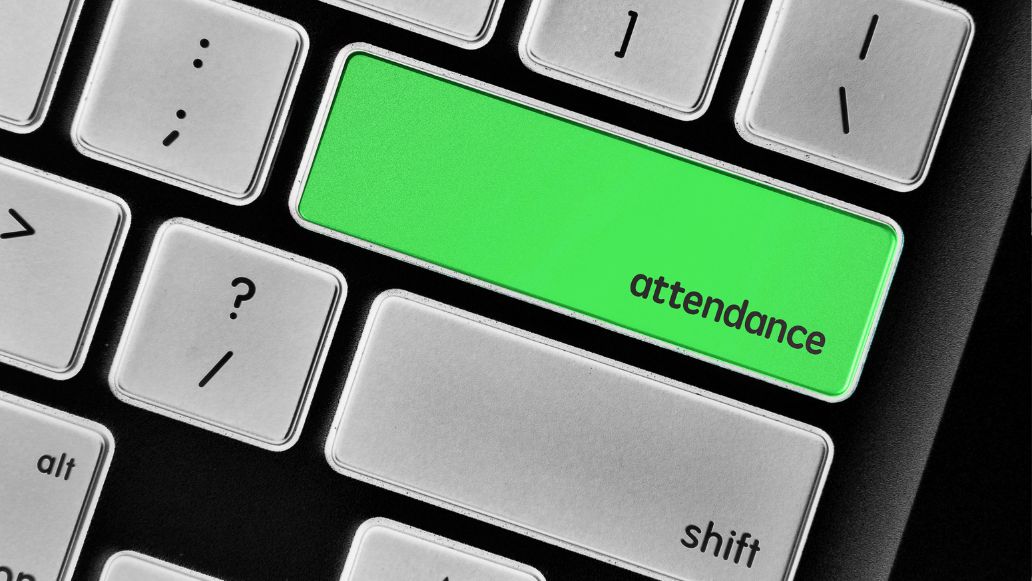
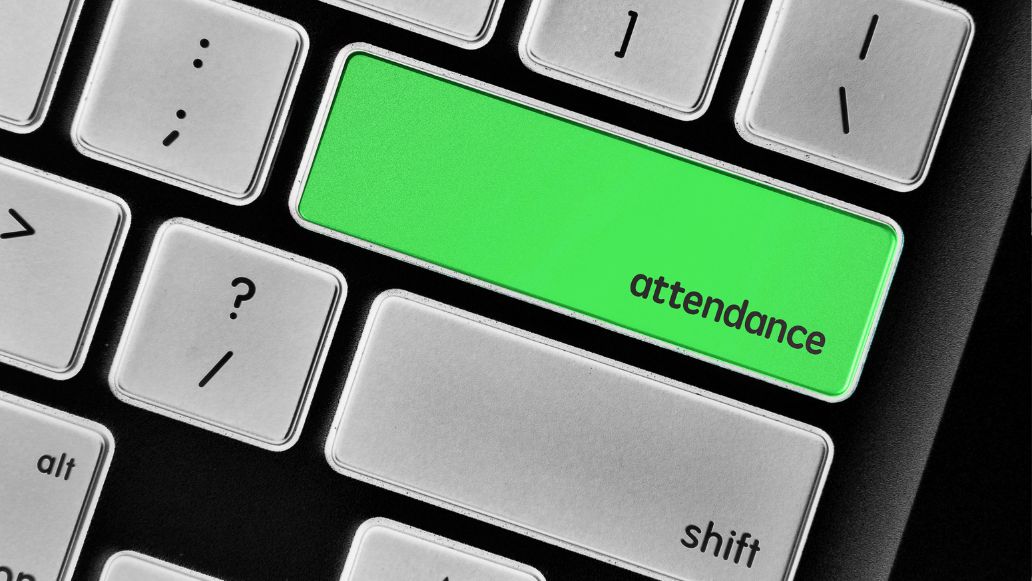
勤怠管理システムとは、タイムカードやExcelなどでおこなっていた従業員の勤務時間管理を自動で管理できるシステムです。従業員の出勤時間や退勤時間の打刻、休暇取得日数などの労働状況はもちろん、シフトの作成や休暇の取得申請、労働時間の集計など勤怠管理で必要なデータを1つのシステムでおこなうことが可能です。
給与計算システムをはじめとした他のサービスと連携することで、労務業務全体の工数削減を実現します。搭載されている機能はシステムによって異なりますが、給与計算システムなど他のサービスと連携したり、労働基準法に関連する法改正の際には管理方法をしたりできるので、人事や労務の業務負担削減をすることも可能です。
1-1. 勤怠管理システムの機能
勤怠管理システムは管理者も従業員も使用するため、それぞれに向けた機能が搭載されています。従業員向けの主な機能は、打刻機能やワークフロー、残業時間の上限を超過した場合のアラーム機能などが挙げられます。
管理者向けの主な機能は、勤怠情報集計機能やシフト・スケジュール管理機能、各種システムとの連携、帳票出力(CSV・PDF形式)機能が搭載されているのが一般的です。
勤怠管理システムにはたくさんの種類がありますが、これらの機能で差別化が図られているので、自社に必要な機能を検討して選びましょう。機能が多ければその分業務負担が減る、というイメージがあるかもしれません。しかし、やみくもに多機能なシステムを導入してしまうと、使いこなせなかったり、費用対効果が得られなかったりすることもあります。
特に管理者用の機能は、「確実に業務負担を減らせる機能」「使いこなせる機能」などをしっかり絞ってから導入を検討することをおすすめします。
1-2. 勤怠管理システムの必要性
勤怠管理システムを運用するにはコストがかかるため、導入を迷うことがあるかもしれません。しかし、法改正に沿った勤怠管理をおこなうには、勤怠管理システムが必要です。法改正では、以下の手法による客観的な労働時間の把握を義務づけています。
- タイムカードによる記録
- パソコンなど電子計算機の使用時間の記録
- 把握した労働時間状況の記録は3年間保存する
自己申告制の勤怠管理では、タイムカードの打刻ミスが起こるリスクがあり、正確な労働時間を把握できないかもしれません。労働時間の記録も、紙ベースでは保管の負担が大きく、担当者への引き継ぎも大変です。
勤怠管理システムを使えば、労働安全衛生法に則った正確な労働時間の把握が可能なので、業種や職種に関わらず必要なシステムといえるのです。
2. 勤怠管理システムを導入する7つのメリット
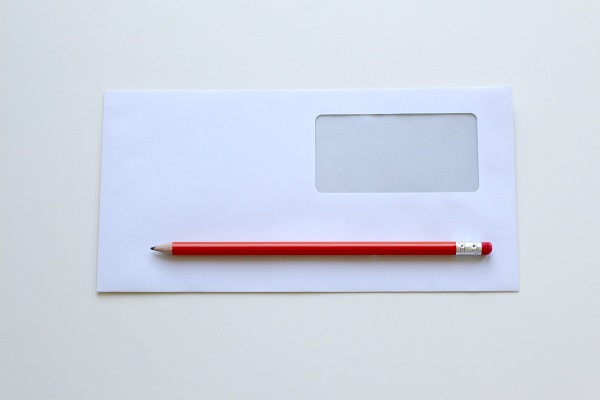
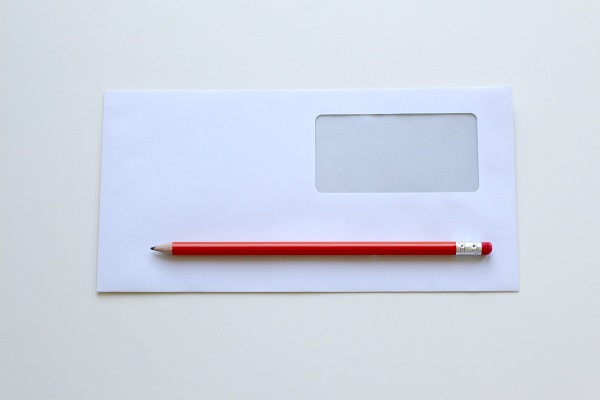
勤怠管理システムを導入することで得られるメリットは、主に5つ挙げられます。では、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
2-1. 正確な勤怠状況をリアルタイムで把握できる
勤怠管理システムを導入することによるメリットとして、従業員の正確な勤怠情報をリアルタイムで把握することができることが挙げられます。
多くの勤怠管理システムでは、インターネットに接続されているスマートフォン・PC・タブレットで打刻ができるようになるため、打刻漏れを防ぐ効果が期待できます。
管理者は時間と場所を問わず、従業員の勤怠情報や各種申請を承認可能になるため、月末の締め作業の工数を大幅に削減することができます。
働き方改革関連法案によって、従業員の勤怠情報を把握することが義務化された中で、勤怠管理システムを用いて正確な情報を効率的に管理することは『ブラック企業対策』としても有効です。
2-2. 集計が自動化され人的コストが削減される
勤怠管理システムには、自動で勤怠データを集計する機能が備わっており、これによって手作業での集計作業が不要となり、労務担当者の負担を大幅に軽減できます。
特に、エクセルやタイムカードで勤怠管理をおこなっている担当者の場合、集計やチェック、分析、毎月の締め作業に加えて給与計算や報告書の作成など、日々の膨大な手作業が自動化されるため、勤怠管理業務にかかる時間を大幅に削減できます。
さらに、フレックスタイム制や変形労働時間制といった複雑な雇用形態も、システム内で個別に設定することで簡単に集計できます。
加えて多くの勤怠管理システムは、給与計算ソフトと自動連携することができるため、少ない工数で従業員情報の一元管理が実現できます。そのため、法改正などで業務負担が増えたとしても、担当者を増やす必要はなく、人的コストを削減することが可能です。
さらに、休日取得状況を管理する機能や勤怠に関わる申請機能が備わっており、スピーディーに手続きを完了させ、その結果を勤怠データに自動的に集約することが可能です。この結果、担当者が手作業で処理する必要はなくなります。勤怠管理システムを導入することで、これまで必要とされていた手間と時間を大幅に削減でき、労務担当者は他の重要な業務に専念できます。
2-3. 労働基準法違反を防ぐことができる
勤怠管理システムの導入により、労働基準法違反を防ぐメリットは大きいです。システムには労働基準法に基づいたアラート機能が搭載されており、残業時間や休憩時間などの法的要件を守ることが可能です。このアラート機能により、労働時間が法定上限に達しそうな場合や、超過した場合にタイムリーに警告が出るため、違反のリスクを低減できます。
さらに、労働基準法では2019年4月から時間外労働の上限規制が導入されています。これに対応するためにも、勤怠管理システムは不可欠です。このアラートがきっかけとなり、従業員の労働時間に対する意識も高まり、結果的により健全な労働環境を維持することができます。
以上のように、勤怠管理システムを導入することにより、企業は法令順守と従業員の健康管理を同時に達成できるのです。
2-4. 法改正に柔軟に対応できる
人事労務関係の法律が改正された場合、担当者はそれに対応した管理方法に変更する必要があります。
勤怠管理システムの多くは、こうした法改正の内容を自動アップデートされるため、人事労務担当者が毎回対応に追われることはありません。
2-5. 不正打刻を防止できる
タイムカードやエクセルを用いた勤怠管理の場合、遅刻や残業申請をおこなう際に書き換えることが可能です。そのため、本当に記録された出退勤時刻か信憑性に欠けてしまいます。
勤怠管理システムでは、自社のセキュリティーカードや定期券といったICカードによる打刻や、インターネットに接続されているスマートフォンやタブレットを利用した打刻など、勤怠管理システムには多くの打刻手法があります。
そのため、従業員の勤務スタイルに合わせた打刻手法を選ぶことができるため、不正打刻を防止する効果が期待できます。
2-6. 従業員の働きやすさを促進できる
勤怠管理システムによって、従業員の勤怠情報をリアルタイムで把握できるようになれば、長時間労働が続いている従業員に管理者側からアプローチをすることが可能です。長時間労働が続くと作業効率が悪くなるだけではなく、最悪の場合離職をしてしまうリスクがあります。
リアルタイムで集計される従業員の勤怠データを利用すれば、1on1面談の実施など迅速に対応できます。労働環境の改善は、従業員の働きやすさの促進はもちろん、従業員の離職を防ぐことにもつながるでしょう。
2-7. 従業員の生産性が向上する
また勤怠管理システムはパソコンやスマートフォン、タブレット等の端末で打刻ができるようになるため、従業員は手元の機器で簡単に打刻を記録することができ、業務の効率化に期待ができます。さらに打刻ミスがあった際には、自身で修正の申請ができるワークフローシステムが搭載されているケースもあるため、管理側と勤怠における連携がよりスムーズにできるようになるのも大きなメリットです。
関連記事:勤怠管理のクラウド化とは?メリット・デメリットや注意点・選び方を詳しく解説
3. 勤怠管理システムを導入するデメリットはある?


勤怠管理システムを導入することには多くのメリットがありますが、その一方でデメリットがあることも事実です。本項目では、勤怠管理システムの導入により生じる可能性があるデメリットについてご紹介します。
3-1. 自社の「働き方」がシステムに合わない場合がある
勤怠管理システムは、多くの企業が導入しやすい機能を設けていますが、企業によって勤務形態が異なるため、一部の企業ではシステムが合わない可能性があります。
無料トライアルを設けているシステムが多いため、導入前にお試しされることをおすすめします。
3-2. システム導入費用が負担になる場合がある
一部の勤怠管理システムには、導入時に初期費用が発生する場合があります。システムの必要性や機能を理解していれば問題ありませんが、ただ他社が導入しているからという流れで導入してしまうと、うまく使いこなせずに費用が負担になってしまうかもしれません。
そのため、従来の勤怠管理を続けていくことと、新たに勤怠管理システムを導入することのどちらが長期的に見てコストパフォーマンスが良いのか、ということを考えてからシステムを導入する必要があります。
3-3. 導入時の業務負担の増加
勤怠管理システムは、導入してから運用できるようになるまでの作業工程が多いため、担当者の業務負担が増加するというデメリットがあります。
導入したばかりの勤怠管理システムは初期化の状態なので、就業規則や業務形態に合わせて担当者が項目ごとに設定しなければなりません。また、従業員にも導入の意図や使い方などの周知を徹底し、正しく運用できる土台を整える必要があります。
ただし、運用までにある程度の手間や時間がかかるのは、どのシステムでも同じです。勤怠管理システムは、運用が始まってから導入効果が出はじめるので、それまでのデメリットだと割り切ることも大切です。
3-4. システムトラブル・不具合で打刻が正しくできない
システムトラブルや不具合が発生すると、正確な勤怠データが取得できない可能性があります。具体的には、タイムレコーダーの故障やパソコンでページが正しく表示されない問題が考えられます。これにより、正しい出退勤時刻を打刻できないケースが発生します。その原因には、打刻機の故障、推奨環境を満たしていない、ネットワーク回線の問題などが挙げられます。復旧するまでの間、システムが使えない時間が発生することも想定しなければなりません。
こうしたイレギュラーに対して即座に対応できる機能やサービスがなければ、勤怠データの正確な管理は困難になります。クラウド型でもオンプレミス型でも、システムである以上、トラブルの可能性は否定できません。万が一のシステムエラーの場合、トラブルシューティングの方法や勤怠管理への影響をどう回避するかについて、事前に確認し、検討しておくことが重要です。
3-5. クラウド化により情報セキュリティが心配される
クラウドベースの勤怠管理システムを導入する際には、情報セキュリティのリスクが気になります。昨今のサイバー攻撃の激化により、不正アクセスや情報漏洩の危険性が高まっているため、人事担当者や経営者には高いセキュリティ意識が求められます。しかし、注目されているクラウド型の勤怠管理システムの多くは、セキュリティ対策に多額の投資を行い、一般企業よりも強固なセキュリティ環境を提供しています。そのため、導入前にはシステムのデータ取り扱い方法やセキュリティ対策の詳細、自社での取り組み方をしっかり確認・検討することが不可欠です。これにより、情報漏洩リスクを最小限に抑え、安心してクラウド型勤怠管理システムを運用することができます。
4. 勤怠管理システムの導入手順
勤怠管理システムは、ただ導入するだけではメリットが得られないことがあります。せっかくコストをかけて導入するのですから、メリットをしっかり得られるようにしましょう。ここでは、勤怠管理システムの導入手順を紹介します。
4-1. 導入目的を明確にする
勤怠管理システムは、自社にとっての導入目的を明確にすることが重要です。
従業員の労働時間を正確に把握するためであれば、パソコンやスマホ、ICカードなどで管理できるシステムが必要です。法改正に対応するためであれば、管理内容を自動でアップデートするシステムを選ぶ必要があります。
導入目的があいまいだと必要な機能の選定ができず、システム導入が無駄になってしまう可能性があるので「なぜシステムを導入したいのか」を明確にしておきましょう。
4-2. 勤怠管理システムの選定
導入目的を明確化したら、必要な機能を搭載した勤怠管理システムを選定しましょう。
勤怠管理システムにはいろいろな種類があり、初期費用やランニングコスト、特徴や運用方法、サポート体制などが異なるので、比較検討して自社に適したシステムを選んでください。
4-3. 勤怠管理システムの導入を従業員に周知する
勤怠管理システムは全社員が使うものなので、管理者だけでなく従業員にも導入を周知しましょう。IT系システムというのは、人によっては使い方が難しいので丁寧なサポートが必要です。
基本的には社内説明会やマニュアルで対応できますが、マンツーマンで説明をすることも想定して導入スケジュールを組むことをおすすめします。
4-4. 勤怠管理システムの試運用
全部署でいっせいに勤怠管理システムを導入してしまうと、トラブルや不具合が起きたときの対応が間に合わないかもしれません。トラブルのせいで業務がストップしてしまうと、余計な負担がかかってしまうことになります。
そのため、導入初期は一部の部署だけするなど、一定の期間は試運用で始めてみましょう。
4-5. トラブルがなければ全部署で運用を始める
試運用をおこなってみて、労働時間や休暇・残業が正確に反映されているか、操作に不具合がないかなどをチェックして問題がなければ、全部署にシステム導入をしましょう。
全部署に導入する際には、事前にスケジュールを決めて、現場が混乱しないようにすることも大切です。システムにトラブルがなくても、現場で対応できなければ運用を始められないので、導入スケジュールを周知しておくことも重要です。
5. 勤怠管理システムのメリットを理解して自社にあった運用を


勤怠管理システムの導入に成功することで、多くのメリットを享受できるため、メリットはもちろんデメリットをしっかりと把握した上で導入を検討されることをおすすめします。
関連記事:勤怠管理システムを導入する目的とは?メリット・デメリットも確認
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
勤怠管理の関連記事
-


勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック
勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.10.18
-

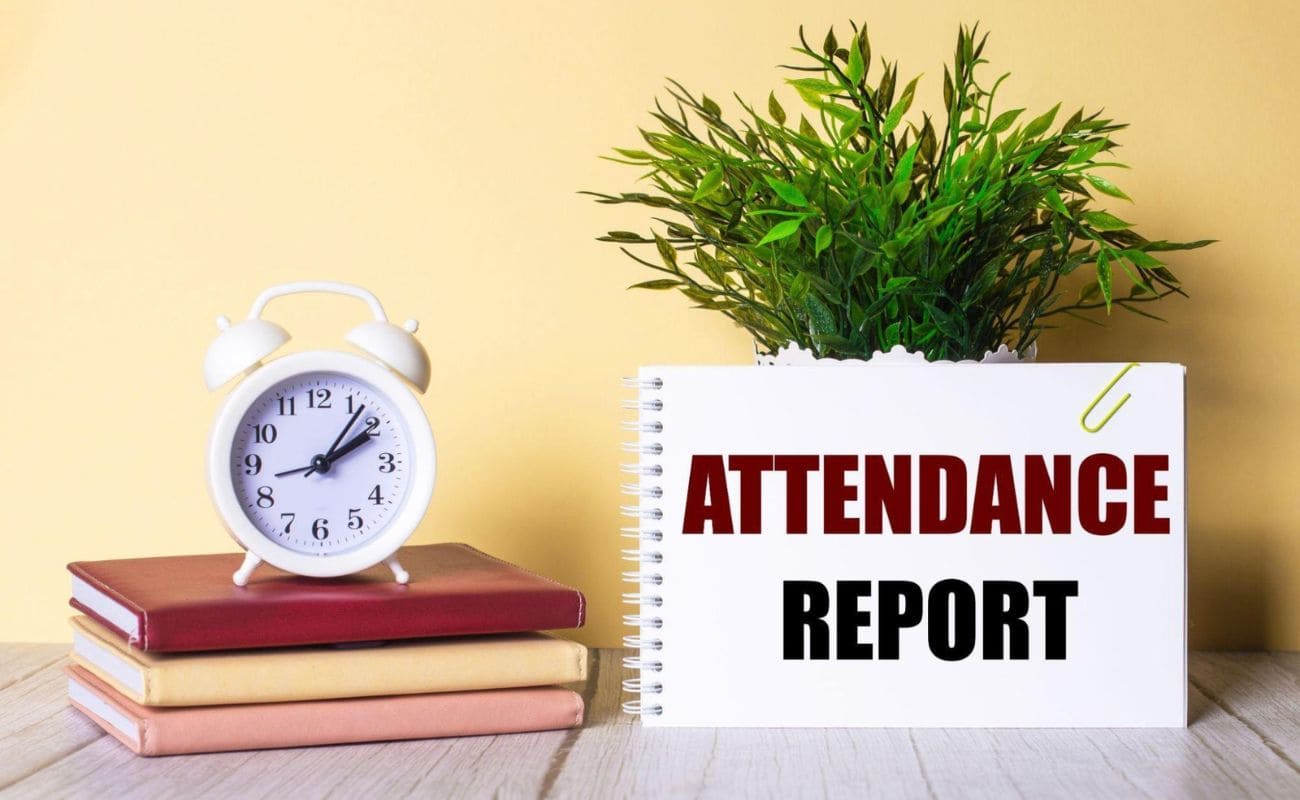
勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.07.04
-


タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.08.02