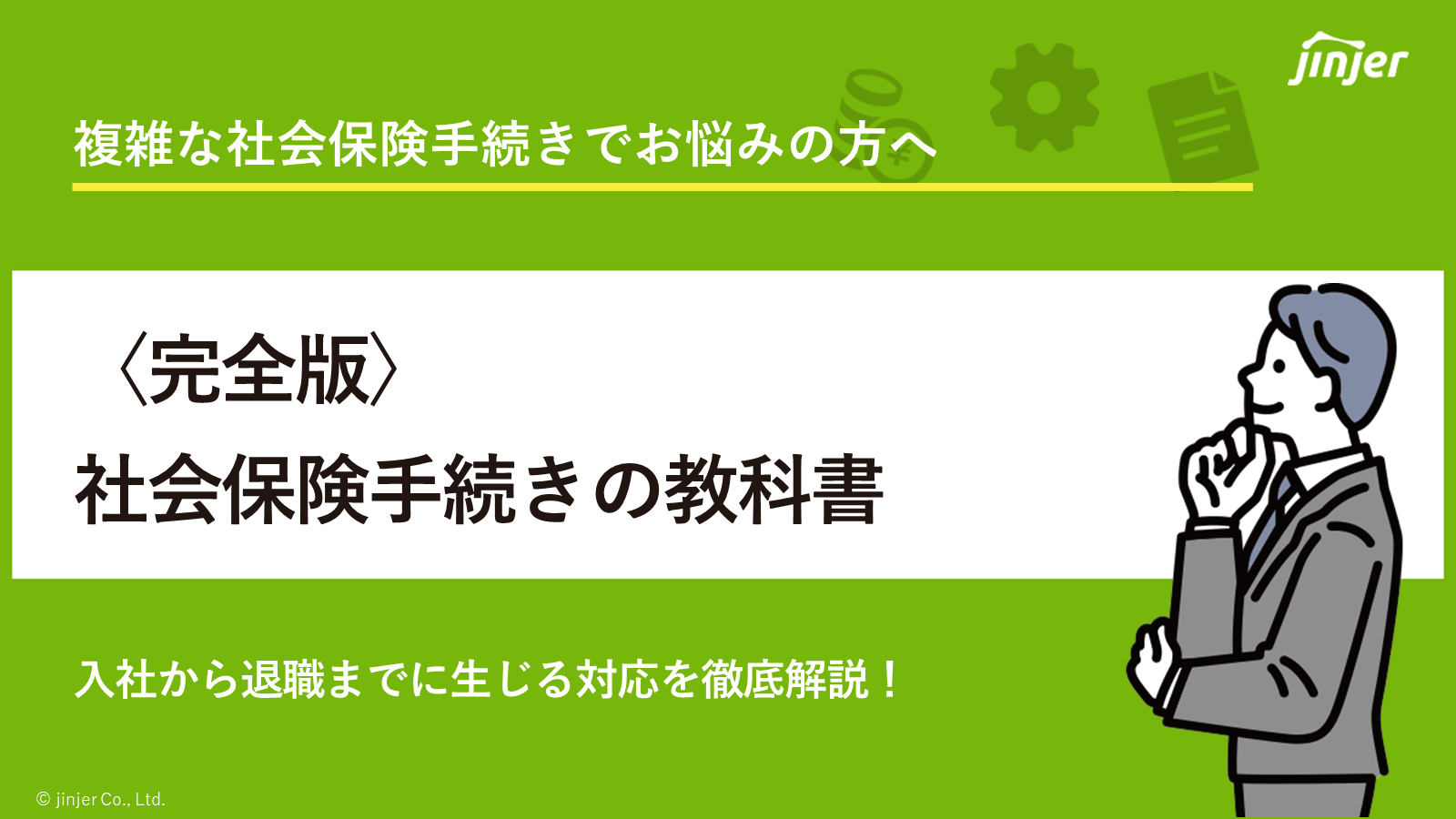社会保険の扶養が外れる条件とは?外れるタイミングや年収への影響・必要な手続きを解説

給与収入が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまいます。従って、扶養者がいる場合や、扶養から外れずに働きたい場合は注意が必要です。今回は、社会保険の扶養が外れる条件を解説します。また、扶養を外れた際のメリット・デメリットもご紹介。
外れた際の手続き方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険における扶養とは?

社会保険の扶養制度とは、主に家族の中で自分では生計を立てることが難しい人を経済的に支援するための仕組みです。これにより、扶養される側(被扶養者)は社会保険料の支払いを免除され、扶養する側(被保険者)は扶養控除などを受けられ、税負担の軽減が図られます。
1-1. 税制法上(所得税)の扶養との違い
税制法上の扶養は、所得税法に基づいて扶養控除を受けるための扶養であり、社会保険制度上の扶養とは異なります。
税制法上の扶養控除を受けるためには、扶養親族の合計所得金額が48万円以下であること、納税者と生計を一にしていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、税制法上の扶養控除には以下の要件があります。
扶養親族の合計所得金額が48万円未満であること、納税者と生計を一にしていること、配偶者以外の親族であること(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことなどです。
これらの要件をすべて満たした場合、扶養控除が適用され、納税者の所得税負担が軽減されます。一方で、社会保険制度上の扶養は、被扶養者が一定の年収以下であることが主な条件となり、社会保険料の支払い免除や医療費の補助などが受けられます。このように、扶養には税制法上と社会保険制度上の二種類があり、それぞれの要件やメリットが異なる点を理解しておくことが重要です。
2. 社会保険の扶養が外れる条件

アルバイトやパートタイム従業員として働いていると、扶養を外れないようにと注意する方が多くいます。12月に、給与所得が103万円超えてしまうからシフトを調整したいと言われたことがあるのではないでしょうか?なかには、「130万円超えないように調整したいです」という言葉もちらほらあるかもしれません。
この130万円を年間の給与所得で超えてしまうと、社会保険の扶養から外れなければならないというわけです。
それでは、103万円を超えてしまうとどのようなことが起きてしまうのでしょうか。また、150万円の壁というのもあるので、従業員に違いを聞かれたときに答えられるように解説します。
2-1. 扶養が外れるタイミングはいつ?
社会保険の扶養が外れるタイミングは、年収見込みが130万円を超えると判断された時点です。
具体的には、月収が10万8,333円以上となる場合です。ただし、一時的な超過ではなく、継続的に超えているかどうかが重要です。さらに、年収が106万円以上で特定の条件に当てはまる場合も扶養から外れることがあります。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
2-2. 103万円
103万円の壁とは、年収が103万円を超えると所得税が課される境界線を指します。この金額は基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を合計したもので、年収が103万円以下であれば控除により課税所得が0となり、所得税が免除されます。これを超えると、扶養控除対象から外れ、所得税が発生します。
2-3. 106万
106万円の壁とは、従業員数が101人以上の企業で週20時間以上働くパートやアルバイトが年収106万円を超えると健康保険と厚生年金保険に加入する義務が発生する条件です。この義務は2024年10月から従業員数51人以上の企業にまで拡大される予定です。学生は除外されます。
2-4. 130万円
130万円の壁とは、年収が130万円を超えると、健康保険と厚生年金の扶養から外れることを指します。この場合、個人で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料や税負担が増えます。従業員数や勤務状況によっては、106万円の壁が適用される場合もあります。
2-5. 150万円
150万円の壁とは、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得上限を示すものです。年収が150万円以下であれば配偶者特別控除を全額受けられますが、これを超えると控除額は段階的に減少します。納税者本人の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されません。
2-6. その他の条件
扶養が外れるその他の条件には、被保険者の年収の1/2を超える場合があります。年収が130万円未満でも、被保険者の年収の1/2を超えると扶養から外れます。また、1月から6月に65万円以上の収入がある場合も注意が必要です。
関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続き方法や扶養になるメリットについて
3. 2024年10月より法改正により社会保険の適応範囲が拡大

ここまで社会保険の扶養が外れる条件について説明してきましたが、もう一点抑えておくべき要素として、 2024年10月より施行される社会保険の適応範囲が拡大があります。以下にこれまでの法改正の流れと今回の法改正の内容を表にしました。
|
2016年10月 |
2022年10月 | 2024年10月 | |
| 社員数 | 500人以上 | 100人以上 | 50人以上 |
| 1週間の所定労働時間 | 20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
| 雇用期間 | 1年以上の想定 | 2ヵ月以上の想定 | 変更なし |
| 毎月の賃金 | 8.8万円以上 | 変更なし | 変更なし |
| 適用除外 | 学生ではない | 変更なし | 変更なし |
| その他 |
上記に該当しない場合でも一週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合には加入 |
変更なし | 変更なし |
これにより、今後従業員数が51人以上の企業でも、年収130万円未満でも健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。施行は2024年10月からで、大企業だけでなく中小企業にも影響が出ることが予想されますので、扶養が外れるタイミングと併せて正しく把握しておくことが重要です。
4. 従業員が扶養から外れる際に必要な手続き

万が一扶養から外れる場合には、手続きが必要です。
扶養から外れる場合というのは、主に以下の例が挙げられます。
- 被扶養者が就職した
- 被扶養者が別の扶養に入った
- 被扶養者が75歳以上で後期高齢者の保険証がある
- 年間収入が130万円を超えた
- 雇用保険を受給が始まった
- 被扶養者が死亡した
これらのように外れるタイミングで必要な手続きは、雇い入れ側がすべきことと、被扶養者だった人がすべきことがあるので、それぞれ解説します。
4-1. 社会保険に加入する場合の手続き
従業員が社会保険に加入する際には、「被扶養者届」や「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。加入手続きを速やかに行わないと、過去の保険診療費の返金が求められる場合がありますので注意しましょう。
雇い入れ側がすべき手続き
被保険者の子供や配偶者が扶養から外れると連絡を受けた際に、被保険者から、該当の被扶養者の保険証と健康保険被扶養者異動届に記載してもらい、書類を預かります。こちらの異動届は、就職などに収入が130万円以上見込まれる事由が発生してから5日以内に提出しなければなりません。
上記の切り替えの手続きを怠った状態で通院などをしてしまうと、後日健保が負担した医療費およびその他給付金を返還する必要が生じ、労使間でのトラブルにつながりやすいです。
また、扶養削除日に関しても、事由が発生した当日、もしくは翌日に削除しなければいけないので、事前に被保険者から必要書類を集められるように準備しましょう。
被扶養者が勤める会社が対応すべき手続き
扶養から外れることを考えている被扶養者がいる場合は、社会保険の加入条件について相談をしてくると考えられます。その際に、該当する従業員が社会保険の加入条件を確認しなければなりません。
もし、社会保険の加入条件を満たした上で、社会保険に加入するとのことであれば、社会保険被保険者資格取得届の準備を進めなければなりません。厚生年金保険にも加入することになるため、従業員に年金手帳もしくはマイナンバーを準備するように伝えましょう。
扶養削除日から5日以内に提出しなければならないため、注意が必要です。
関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?必要になる事業所や手続きについて
▼社会保険の加入条件を確認したい方はこちらをご覧ください
社会保険の加入条件とは?2022年の法改定の内容や手続きなどを解説
4-2. 国民健康保険に加入する場合の手続き
扶養から外れ、社会保険からも脱退することになりますが、再度健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入する場合、扶養の概念がないため、家族全員が個別に保険料を支払い、それぞれ加入手続きを行う必要があります。この点で、社会保険の扶養制度と大きく異なります。
扶養を外れる従業員がすべき手続き
国民健康保険に加入する際は、社会保険の扶養を外れることが決まったタイミングですぐに準備をするようにしましょう。
国民健康保険に加入する際には社会保険の資格を喪失した証明を求められることがあるため、証明を用意しておきましょう。
関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!
5. 扶養が外れることによる年収への影響

ここまでで、扶養を外れてしまうと社会保険に加入しなおさなければならなかったり、従業員自身で保険料や税金の支払いを行わないといけないなど、手間が増えることをお伝えしてきました。
本章では、従業員に「扶養を外れることで何が変わるの?」と聞かれた際に正しく答えられるように解説します。
5-1. 支出が増え世帯年収が減る
税法上では、年収103万円を超えると所得税の支払いが必要となり、社会保険上では、年収130万円を超えると社会保険料の支払いが必要となります。
扶養に入っている間は払う必要のなかった所得税や社会保険料も、扶養を外れたら上記のように支払い義務が生じるため、世帯支出が増えてしまうというわけです。
家計の足しにするために働き始めたとしても、かえって負担額を増やしてしまう可能性もあるため、扶養を外れるか慎重に検討してもらいましょう。
5-2. 健康保険料を負担し加入しなければならない
年収が130万円を超えて扶養を外れてしまった場合、勤務先の社会保険(健康保険)か国民健康保険のどちらかに加入しなければなりません。
勤務先の社会保険に加入する場合は、毎月の給与から天引きされるため手取り自体は減ってしまいますが、コンビニなどで保険料の納付する手間はかかりません。
国民健康保険に加入する場合は、手取り額は変わりませんが、後日まとめて保険料を納付しないといけなくなるので手間が増えてしまうという特徴があります。
扶養から外れることにより、金銭面でも時間面でも負担が増えるということを理解し、扶養を外れないようにするのか従業員に寄り添えるようにしましょう。
5-3. 投資などの配当金も収入とされる場合がある
また社会保険の扶養が外れることによる年収への影響として投資収益が継続して入る場合、収入としてカウントされる可能性があります。特に株式の配当金など、定期的に収入が発生するものは要注意です。NISA口座での取引は一時収入と見なされますが、毎年の配当金は対象外です。
5-4. 遡って扶養が外れ返金額を支払う可能性もある
収入が基準額を超えた場合、さかのぼって扶養が外れたことが判明すると、過去の医療費の返金を求められる可能性があります。扶養が外れることで世帯年収にも関係し、さらに返金額を支払うことになれば大きな支出です。そのため収入の変動がある場合は速やかに報告し、適切な手続きを行うことが重要です。
6. 社会保険の扶養から外れるメリット

社会保険の扶養から外れることは一定のデメリットもありますが、もちろんメリットもあります。詳しくみていきましょう。
6-1. 独自の保障が受けられる
独自の保障として、被扶養者から外れ自分が被保険者となると、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられます。これにより、病気やけがに対する経済的な心配が軽減されるメリットもあります。
6-2. 年金額の増加が見込まれる
社会保険料を自ら負担することにより、自らの年金が積み立てられます。これにより、将来的に受け取る年金額が増加し、老後の生活基盤が安定します。納付年数が長いほど受取額も増えるため、長期的なメリットがあります。
6-3. 収入額が増加する
扶養から外れることは、収入の増加を意味します。自立した経済生活を送ることができ、自己実現の手段となります。収入が増えることで、生活の質が向上し、さらなるキャリアアップのチャンスが広がります。
7. 扶養が外れる条件やタイミングを理解して正しい手続きを

社会保険の扶養は1月から12月までの年間収入が130万円を超えると外れてしまいます。社会保険の扶養から外れた場合には、世帯主が勤める企業に扶養者が減ることを伝える申請を行い、被扶養者だった方は区役所で保険加入の手続きが必要です。
年収が130万円を超えた場合は、まずは会社に扶養者が減ることを申請しましょう。それから14日以内に区役所での手続きが必要です。加入するのは、社会保険か国民健康保険のどちらかで、勤めている会社が条件に適合していれば社会保険に加入できます。
また、社会保険の扶養から外れると保険料を納めなければならない、年収が低くなるなどのデメリットばかりが目につきますが、将来受け取る年金の総額が増えたり、万が一の時に受け取れる手当が増えたり、メリットもあります。
年収が130万円を超えそうな場合は十分に注意し、扶養を外れた時点で直ちに手続きを行いましょう。
関連記事:【2023年】パート主婦が扶養内で働くなら月いくらまで?扶養範囲内について解説!|転勤妻のおしごと事情
関連サイト:期間工は、若者に人気のある短期雇用の仕事で、寮費無料や手厚い福利厚生を提供し、年収は約450万円程度になることが多いです。
特殊な労働環境であっても社会保険への加入が必須条件となっています。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08