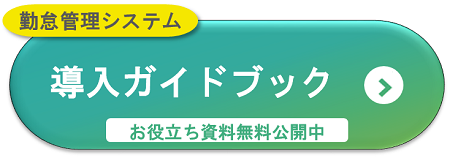勤怠管理システムにおける休憩時間の打刻方法をご紹介

普段皆さんの企業では、休憩の管理をどのようにしているでしょうか?タイムレコーダーや手書き記録などで管理している企業もあるかもしれません。しかし、勤怠管理システムでこれを管理すると、企業にとってのメリットが多数あります。
今回は、勤怠管理システムで休憩時間を記録する方法と休憩の原則、休憩時間の分割について紹介します。
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
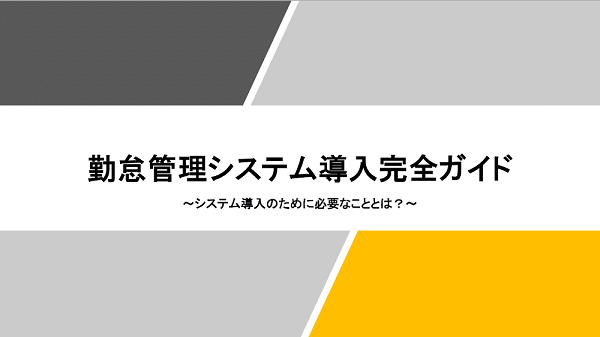
働き方改革が始まり、「勤怠管理システムの導入を考えているけど、何から着手したらいいかわからない・・。とりあえず、システム比較からかな?」とお困りの勤怠管理の担当者様も多いでしょう。
そのような方のために、当サイトでは勤怠管理システムのメリットや導入までの手順をまとめたガイドブックを無料で配布しております。
これ一冊でシステム検討から導入までに必要な情報がまとまっておりますので、社内で検討する際に役立てたい、上司に説明する際の資料が欲しいという方はぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をダウンロードしてご覧ください。



1. 勤怠管理システムで休憩時間を打破する方法とは

勤怠管理システムで打刻する方法を2つご紹介します。勤怠管理システムによって用意されている打刻方法が異なるため、実際にシステムを選ぶ際は、打刻方法が自社に適しているか確認する必要があります。複数の会社のシステムを見て、無料トライアルを利用して管理者側だけではなく、現場の従業員にも協力を促して検討しましょう。
1-1. 手動で勤怠管理システムに打刻する
まずは手動で勤怠管理システムに打刻する方法です。従業員が自分で打刻していきます。方法としては、パソコン・スマートフォンで管理システムの画面を開き、休憩開始時間と休憩終了時間を記録する方法や、ICカード・指紋認証などワンタッチで打刻する方法などさまざまです。
メリットとしては、簡単に打刻ができることと従業員が休憩時間を確保しやすいという点です。デメリットとしてはヒューマンエラーが起きる可能性があること。打刻忘れで記録が取れないこともあるので注意が必要です。
1-2. 自動で勤怠管理システムに打刻する
勤怠管理システムに休憩時間が自動で打刻されるタイプのシステムもあります。
時間帯で設定する方法では、あらかじめ○時~○時までというように時間を決めておきます。すると、システム内で自動集計されるため、従来のように、『休憩時間の集計ミスを間違えた』ということを防ぐことができます。
1-3. 休憩時間の打刻方法はシステムによって異なる
勤怠管理システムによって用意されている打刻方法が異なるため、実際にシステムを選ぶ際は、打刻方法が自社に適しているか確認する必要があります。複数の会社のシステムを見て、無料トライアルを利用して管理者側だけではなく、現場の従業員にも協力を促して検討しましょう。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
2. 休憩時間の3原則とは


中休みは、ただ取らせればいいものではありません。実際に付与するのにも決まりがあります。労働基準法にも記載されている内容なので、理解して中休み時間を管理するようにしてください。理解していないと従業員から訴えられてしまう可能性も生じるので気をつけましょう。
2-1. 【3原則】労働時間中に休憩を取らせなければならない
中休みは必ず勤務時間内に付与しなければなりません。労働基準法第34条1項では、以下の通りに記載されています。
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
8時間勤務という決まりであっても、『3時間働いて1時間の中休み、その後5時間働く』というように中休みを付与します。『8時間勤務して1時間の中休みを付与』としても労働基準法違反になる恐れがあるため、自社に休憩時間を設定する場合は気をつける必要があります。
2-2. 【3原則】休憩中は労働から離れさせなければいけない
中休み時間中には労働から離れさせなければいけないという決まりです。企業は従業員の行動を制限してはいけません。労働基準法第34条3項では以下の通りに記載されています。
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
しかし、仕事によっては電話対応をしなければならなかったり、来客の対応をしなければならないケースもでてきます。対応が日常化しているときには労働基準法違反とみなされてしまう可能性もあります。
そのような場合には、労働基準監督署に相談して正しい対処法を教えてもらいましょう。問題が起きる前に早めに手を打つことが大切です。
2-3. 【3原則】休憩は従業員に一斉に与えることが基本
中休みは、一斉に与えるのが基本の原則です。労働基準法第34条第2項には、休憩は労働者に一斉に与えなければならないと規定されています。労働基準法第34条2項では以下の通りに記載されています。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
2-4. 【3原則の例外】業種によっては一斉取得の必要がない
休憩は従業員に一斉に与えるとう3原則は、すべての企業に当てはまるわけではありません。業種によっては一斉に取る必要はありません。
労使協定の締結が不要な業種は以下の通りです。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接待娯楽業、官公署
接客業や医療業界では業務の特性上、一斉に休憩を取ることが難しい場合があります。運輸交通業、通信業、商業、保険衛生業、金融広告業、接客娯楽業、映画・演劇業、官公署などの業種については、労使協定を締結しなくても休憩の一斉付与から除外されます。この場合、個別に休憩を取る形でも問題ありません。
さらに、上記の業種に該当しない場合でも、労使協定を結ぶことで一斉に休憩を付与しないことが認められます。ただし、労使協定を結ぶ際には、一斉に休憩を付与しない理由、新設される休憩の時間、対象者の範囲などを具体的に明確に定める必要があります。これにより、全体の稼働率を考慮しつつ、労働者にとって公平で適正な休憩時間を確保することが求められます。
3. 休憩時間の分割は可能?


よくある疑問に「中休みをまとめて付与する必要はあるのか?」ということがあります。結論から述べると、中休みをまとめて付与する必要はありません。業務の関係上分割して与えたとしても罪には問われません。
しかし、従業員が満足して中休みできる時間は確保しましょう。自由が与えられないと中休みと呼ぶことはできません。最低でも10分以上は与える必要があります。
休憩時間に関する人気の記事はこちら
▼労働時間に休憩は含む?含まない?気になるルールと計算方法
4. 休憩時間に関するルールを正しく理解して勤怠システムを導入しよう

今回は、勤怠管理システムの休憩時間の打刻方法について紹介しました。打刻の方法が手動か自動かによって、その管理の方法にも違いが生じます。自分の企業にあった方法を選択しましょう。
また、休憩時間には原則が存在し、これは法律上でも決まっていることです。これを守らないと従業員に訴えられる可能性もあるので注意しましょう。この記事を参考にして、勤怠管理システムで休憩の管理をしてみてください。
関連記事:勤怠管理システムを導入する目的とは?メリット・デメリットも確認
「勤怠管理システム導入完全ガイド」
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25