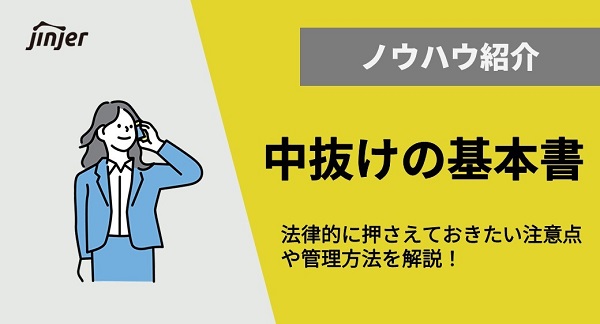勤怠管理における中抜けの意味とは?扱い方や就業規則についても解説
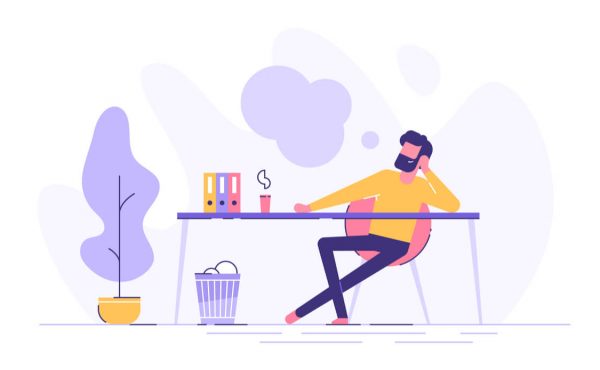
業種、業態により勤務時間や業務形態はさまざまです。状況によっては、途中で1時間や3~4時間など中抜けすることもあるでしょう。
中抜けすること自体は会社が認めれば問題ありませんが、勤怠管理において中抜けする場合は、どのように処理・管理するべきなのでしょうか。
今回は、中抜けの定義から管理方法について解説します。
関連記事:勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!
中抜けは、適切に扱わなければ労働時間集計や残業代の計算に誤りが発生するため、正しい管理方法を把握しておかなくてはなりません。
当サイトでは、中抜けの扱い方や法律的におさえておきたいポイントなど本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
中抜けを適切に管理したい方は、こちらから「中抜けの基本書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 中抜けとは?意味をおさらい

中抜けとは、どのような状況のことを指すのでしょうか。例を紹介しながら解説します。
1-1. 勤務時間内に一時的に仕事から離れること
中抜けとは、勤務時間中に仕事から一時離席することを指します。特に飲食業界や旅館業界、医療業界ではよくみられる事象です。忙しく人手が必要な時間帯が朝方や夕方のみなどと一日の中で決まっているため、その時間帯を勤務時間とし、間の時間を中抜けという扱いにすることがあります。
また、近年、海外の会社のように休憩時間を2時間、3時間取得をすることが可能な企業が増えつつあります。
休憩時間が長くなることで休憩回数が増えたり、就業時間が長くなるので、会社としては管理が煩雑化することは認識する必要があります。
1-2. 私用による一時外出も含む
中抜けは、会社の都合だけとは限りません。プライベートが理由で一時的に中抜けが必要になる場合があります。
休暇や半休のほかに、短時間離席したい場合や、仕事が忙しいためすぐに戻ってきたい場合などは、中抜けが最適でしょう。
お子さんがいる従業員なら、学校行事や、避難訓練のお迎え、面談など1時間、2時間抜けて対応しなくてはいけないイベントも多いでしょう。
2. 勤怠管理で中抜けはどのように扱うのか

ここまで中抜けの意味や、一般的に用いられているケースについて解説しました。
ここからは実際に中抜けが発生する場合における、勤怠管理の扱いについて確認していきましょう。
2-1. 中抜け時間を休憩時間として扱う
プライベートな理由などで中抜けする場合の管理方法として多いのが、中抜けしている時間を休憩時間として扱うことです。
つまり、中抜けしている時間も会社が拘束している時間帯です。何時から何時まで休憩したか(中抜け)したかを管理する必要があります。
休憩時間となる場合は、労働時間としては変わらないため、その分終業時間がその日は遅くなる場合があるという点も認識しておく必要があります。
関連記事:勤怠管理における休憩時間の取り扱いとは?労働基準法の基礎知識を解説
2-2. 中抜けを半休・時間単位の有休として扱う
中抜けを時間単位の有給休暇取得や半休として扱うことも可能です。この方法であれば、終業時間を後ろ倒しする必要はないため、わかりやすい運用です。
ただし、そもそも時間単位の年次有給休暇を制度として利用できるようにするには、労使協定の締結が必須であると法律で定められているため、注意が必要です。
加えて、半休を制度化するのに労使協定は必要ありませんが、会社から一方的に半休を取らせることはできないため、中抜けを半休として扱う際には必ず従業員の意思を確認してからにしましょう。
2-3. 1日2回の就業として扱う
朝と夜の出勤などは、日中を休憩として扱わず1日2回の出勤として扱う方法があります。2回の出勤にする際の注意点としては、休憩時間の取得についてです。
労働基準法34条により労働時間6時間を超える場合は、45分の休憩を与える必要があります。
参考:e-Gov|労働基準法
2-4. テレワーク時の外出などによる中抜けのとり扱い
新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり、多くの企業が取り入れるようになったテレワークや在宅勤務は、自宅で業務を行うため中抜けが発生しやすい勤務形態です。
テレワーク中に発生した中抜けは、「休憩時間として扱い、終業時間を繰り下げる」「時間単位の年次有給休暇とする」扱いが可能になります。
ただし、始業・終業の時間に変更がある場合は就業規則への規定、時間単位の有給を取得を認めるには労使協定の締結が必要になるため、注意しましょう。
当サイトでは「中抜けの基本書」という資料を無料配布しております。本資料では中抜けの取り扱いや法的観点、中抜け管理の効率化する方法などを解説しており、中抜けに関してこの一冊で理解できるような内容となっており大変参考になる資料です。中抜けの管理に不安のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
参考:テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン|厚生労働省
2-5. 健康診断における中抜けの扱い
一般的な定期健康診断を受診するために、中抜けが生じるケースも多いでしょう。
結論として、定期健康診断を所定労働時間内に実施する義務はありません。ただし従業員の利便性の観点から、所定労働時間内におこなわせるほうが望ましいとされています。
定期健康診断による中抜け時の賃金の扱いは、労使間で定めるべきものとされています。健康診断による中抜けに対して賃金を支払うことは、法律上は義務付けられていません。
とはいえ、受診の円滑化には中抜け分の賃金も支払うことが望ましいとされています。
参考:Q7.健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか?|厚生労働省
参考:健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?|厚生労働省
3. 中抜けの勤怠管理における、就業規則への記載方法・例


ここからは、中抜けの勤怠管理における就業規則への記載ポイントを解説します。
新たに中抜けの制度を導入するには、就業規則を変更しなければなりません。中抜けは遅刻、早退、および欠勤に関する項目として追加することが望ましいでしょう。
中抜け制度を就業規則に記載する例は、以下の通りです。
【中抜け制度】
勤務時間内に私的な用件で一定時間業務から離れる場合は、事前に所属長に許可を申し出て、承認を得る必要がある。
始業時間:平日午前9時 / 土曜日午前10時
終業時間:平日午後6時 / 土曜日午後5時
休憩時間:午前12時から午後1時(1時間)
ただし、業務の都合上やむを得ず、上記の勤務時間の繰上げ又は繰下げをする場合、従業員に対して前日までに連絡する。
中抜けとして時間単位の年次有給休暇を扱えるようにしたい場合には、別途時間単位年休について労使協定を締結し、就業規則へ記載する必要があります。
時間単位の有給休暇の導入方法については、以下の記事をご参照ください。
4. 勤怠管理システムで中抜けを管理しよう

勤怠管理の効率化が期待できる勤怠管理システムには、さまざまな機能が備わっています。
ここからは中抜けの管理に的を絞って、勤怠管理システムにはどのような機能があるのか確認してみましょう。
4-1. 複雑な勤務体系の管理ができる
中抜けの管理方法として「休憩時間として扱う」「2回の出勤として扱う」などと解説したように、中抜け制度にはイレギュラーな勤怠の扱いが生じます。
勤怠管理システムは、一般的な勤務体系とは異なる特殊な勤怠管理にも対応が可能です。
また、店舗や営業所などが複数ある場合は、状況をリアルタイムで確認できる点も便利です。同じ会社でも「職場によって雇用形態、勤務体系が異なる」、「シフトによっては日をまたぐことがある」など、多様な勤怠管理がおこなわれることもあるでしょう。
勤怠管理システムを検討する際には、「自社の勤怠体系が問題なく対応・管理できるか」という観点をクリアした製品を選ぶようにしましょう。
4-2. 自社にあった打刻方法を選択する
中抜けをする場合、仕事から抜けた時刻と戻ってきた時刻を把握する必要があります。この管理漏れや不正を防止するためにも、打刻方法は重要となります。
勤怠管理システムでは、スマホやPC、タブレットなどから手軽に打刻が可能です。システムによっては、GPS機能が搭載されており、従業員が打刻した場所を確認できるものも存在します。リアルタイムで反映されるため、管理がしやすく不正打刻防止にも効果的でしょう。
ほかにも、各勤怠管理システムによってさまざまな打刻方法が用意されているため、自社の勤務体系にあった打刻方法を確認するとよいでしょう。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
5. まとめ

本記事では、業務時間中の中抜けの扱いについて解説しました。ホテル業など計画的に朝と夜などと時間帯が分かれる場合は、2回の就業としての扱いでもいいでしょう。
中抜けの扱い方としては、「休憩時間で調整」「2回の就業」どちらの方法にしても管理が煩雑であり、手間がかかることは確かです。
勤怠管理システムを導入していない企業は、これを機に勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
自社の勤務形態などが対応されている勤怠管理システムの場合、導入する前よりも業務効率化されることが期待できるでしょう。
中抜けは、適切に扱わなければ労働時間集計や残業代の計算に誤りが発生するため、正しい管理方法を把握しておかなくてはなりません。
当サイトでは、中抜けの扱い方や法律的におさえておきたいポイントなど本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
中抜けを適切に管理したい方は、こちらから「中抜けの基本書」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25