勤怠管理していない会社は違法?リスクや問題点から対処法を解説
更新日: 2024.7.4
公開日: 2020.1.29
OHSUGI

勤怠管理は企業が必ずおこなう必要がある業務の一つです。しかし、一部の企業では従業員の勤怠情報をきちんと管理していない場合や、そもそも勤怠管理をおこなっていない場合があります。
もし、勤怠管理をおこなっていない場合、どのようにして社内整備をする必要があるのでしょうか。本記事では、勤怠管理をおこなっていない企業のリスク、勤怠管理を実施する上での対策についてご紹介します。
関連記事:勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!
法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。資料では2019年に改正された労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、
自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
目次
1. 勤怠管理に関する法律・ガイドラインの基礎知識


勤怠管理は、労働基準法と労働安全衛生法にて義務付けられています。そのため、勤怠管理していない会社においては、法律違反になります。まずは勤怠管理について理解するために、労働基準法と労働安全衛生法を詳しく解説します。
1-1. 勤怠管理に関連する法律「労働基準法」
労働基準法は、全ての企業が従うべき基本的な労働規範を定めており、特に勤怠管理に関して重要な法律です。第108条では、各事業場で賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等について賃金支払の都度遅滞なく記入する義務があります。賃金台帳には、労働日数や労働時間数、時間外労働の時間数等を記載する必要があります。これにより、従業員の労働時間を正確に把握することが求められます。
また、第109条には、労働者名簿や賃金台帳を含む重要な労働関係書類を最低5年間(当分の間は3年間)保存する義務があります。ここには出勤簿やタイムカードも含まれます。このため、記録するだけでなく、そのデータを長期間にわたって管理する体制も必要です。企業の管理職や経営者、労務担当者がこれらの法律を遵守し、適切に勤怠管理を行うことは、リスクの軽減や労働環境の改善に繋がります。
労働基準法に違反した場合の罰則
従業員の勤怠を適切に管理することは会社に求められる責務であるため、従業員の勤怠を管理していない場合、法令違反を問われるかねません。労働基準法には、違反した内容によって、罰金や懲役などの罰則が設けられています。
1-2. 勤怠管理に関連する法律「労働安全衛生法」
労働安全衛生法は、従業員の安全と健康を守るための重要な法律であり、具体的には労働時間の管理や労働環境の整備を求めています。労働安全衛生法第66条8の3では、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないと定められています。これには管理監督者も含まれ、従業員の労働時間の把握が義務付けられています。
具体的な方法として、労働安全衛生規則第52条の7の3では、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録、その他の適切な方法が挙げられています。適切な方法で労働時間を把握し、36協定で定められた時間外労働の上限規制に違反しないようにすることが企業に求められます。
労働安全衛生法に違反した場合の罰則
労働安全衛生法に違反した場合、内容によって罰金や懲役を課されることがあります。また、違反の度合いに応じて業務停止命令が発令されることもありますんで注意が必要です。
1-3. 厚生労働省が発表した勤怠管理のガイドライン
また厚生労働省が発表したガイドラインでは企業が勤怠管理をおこなうことが明記されています。
1.労働日ごとに始業・終業時刻を記録すること。
2.使用者の現認あるいは適切な手段(タイムカードなど)により記録すること。
3.上記の手段について従業員に十分な説明をし、実態調査を実施すること。また、適正な記録を妨げる措置(労働時間数の上限設定など)を行わないこと。
4.労働基準法第109条に基づいて記録を保存すること。
5.勤怠管理の担当者は、労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、管理上の問題の把握・解決を図ること。
6.必要に応じての労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状把握・問題解決を行うこと。
参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
勤怠時間を管理することは企業の義務!
この他にも、働き方改革による法改正で義務化された有給休暇の年5日取得や残業の上限規制などは、勤怠管理を行っていなければ対応することができません。
以上のことから、これまで以上に企業が従業員の勤怠情報を詳細まで把握することが求められているのです。
「法改正の内容をきちんと理解できていないので、確認したい」という方にむけ、当サイトでは法改正の内容と対応方法をまとめた資料「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」を無料で配布しておりますので、法律に則った勤怠管理をしたい方はこちらより資料ダウンロードページをご覧ください。
2. 勤怠管理していない会社のリスクと問題点

2019年4月1日から、『働き方改革関連法』が施行されました。この法律が施行されたことによって、企業に対して従業員の労働時間の把握が義務化されました。
勤怠管理をおこなっていない企業の多くで、長時間労働・残業代の未払い・みなし残業に加えて、パワーハラスメントなどが発生しており、労働環境があまり良いとはいえないことが多いです。本項目では、勤怠管理をおこなっていない企業へのリスクについて解説します。
2-1. 従業員の長時間労働を把握できない
勤怠管理をおこなっていない場合、従業員の長時間労働を把握できません。長時間労働の労働は従業員に支払う給与がかさんでしまうだけではありません。長時間労働によって従業員のモチベーションが低下して離職や心身の疲弊につながる可能性があります。
2-2. 残業代の未払いが発生する
勤怠管理を正確に行わないと、労働時間を適切に把握できず、残業代の未払いが発生するリスクが高まります。労働時間を正確に記録しないと、社員の実際の労働時間に基づいた時間外労働の管理が困難となり、未払いが発生する可能性があります。未払い残業代の問題は労働争議や社内トラブルの原因となるため注意が必要です。
厚生労働省のデータによれば、平成31年度および令和元年度には未払い残業代が発生した企業が1,611社に上り、そのうち161社は1,000万円以上の未払い残業代を支払う事態に陥りました。このような高額な支払いは企業経営に大きな影響を与えるだけでなく、社会的信用を損なうリスクもあります。
参考:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)|厚生労働省
2-3. 社会からの評価が落ちる可能性がある
勤怠管理をおこなっていない企業では、長時間労働が慢性化するなど、労働環境そのものがあまり良くない傾向があります。
そのため、『勤怠管理をおこなっていない』という事実が社外に知られてしまうと、場合によっては『ブラック企業』の扱いを受け、社会からの評価が落ちてしまう可能性があります。
また、転職を考えている人や就職活動をしている学生は、『ブラック企業』と呼ばれる企業を就職候補先として考えないでしょう。すると、社内では人員不足になり、長時間労働が慢性化するという負の連鎖が続いてしまうことが考えられます。
2-4. 労基法違反による訴訟問題に発展する可能性がある
きちんと勤怠管理をおこなっていない場合、訴訟問題に発展する可能性があります。勤怠管理は、従業員の給与を支払う上で非常に重要になります。そのため、勤怠管理をおこなっていないということは、従業員の労働への対価として正当な給与を支払うことができていないということになります。
訴訟問題に発展すると、前項で述べたように社会からも評価が落ちてしまうだけではなく、全従業員が自社に対して不信感を持つことになるでしょう。
関連記事:タイムカードのない会社は違法?正しい勤怠管理について解説
3. 手書きの勤怠管理は改ざんのリスクがある


勤怠管理をおこなう方法はさまざまです。そのなかでも手書きで勤怠管理をしているケースがあるでしょう。しかし、手書きの勤怠管理は改ざんされてしまうリスクがあります。
3-1. 従業員の不正に気づくことができない
適切な勤怠管理が行われていないと、従業員による勤怠データの改ざんや不正行為に気づくことが困難になります。従業員の自己申告のみで勤怠状況を管理している場合、遅刻や欠勤が申告されず、残業時間が水増しされるといった問題も発生しやすくなります。本来支払う必要のない賃金を従業員に支払うことになり、人件費が無駄に増えるリスクがあります。
また従業員自身による改ざんだけでなく、管理者による従業員の労働時間の改ざんもありえるでしょう。このような改ざんリスクを防ぐためには手書き以外の勤怠管理方法を検討しておきましょう。
4. 勤怠管理をしていない会社がとるべき対処方法

勤怠管理を正しくおこなわないことで、法律違反や社会からのイメージダウンなどの大きなリスクが伴うことから、多くの企業ではしっかりとした勤怠管理がおこなわれています。しかし、もし自社で勤怠管理がおこなわれていない場合、どのようにすれば良いのでしょうか。本項目では、これから勤怠管理を始める際におこないたいことや注意点について解説します。
4-1. 従業員に勤怠管理の必要性について理解を得る
従業員に勤怠管理の重要性と必要性を理解してもらうためには、透明で具体的な説明が重要です。まず、企業としてなぜ勤怠管理を行うのか、その重要性や従業員にとってのメリットを明確に伝えましょう。法令遵守はもちろん、労働環境の改善や公平な評価制度の構築につながると説明します。
次に、勤怠管理の導入時期を明確にし、具体的な操作手順やタイムカードシステムの使い方について詳細に説明することが求められます。特に、新たに導入されるシステムや方法について従業員が困惑しないように、定期的な研修や説明会を開催することが効果的です。
さらに、勤怠管理で収集される情報の使用目的を明示し、個人情報の適切な取り扱いについても説明します。また、欠勤、遅刻、早退などに関するルールも従業員に明確に伝え、理解を促します。このようなステップを踏むことによって、従業員の理解と協力を得ることができ、適切な勤怠管理が実現します。
4-2. 勤務実績と申告内容の乖離を調査する
労働時間の自己申告制を採用している場合、勤務実態と申告内容の乖離を調査することが重要です。特に客観的な労働時間の記録がない状況では、従業員が遅刻や早退を報告していなかったり、残業の申告が過大または過小報告されているリスクがあります。また、上長の指示で休日出勤を行ったにもかかわらず、正しく申告されていないケースも頻繁に見られます。このような状況を防ぐために、自己申告内容と実際の勤務状況の定期的な比較と調査が必要です。このプロセスを通じて、正確な勤怠データを把握し、発見された乖離を是正することで、法令遵守と公正な労務管理を実現します。
4-3. 長時間労働を早急に是正する
長時間労働が常態化している場合、勤怠管理の導入と改善は急務です。まず、長時間労働が発生していないかを詳細に調査しましょう。過去の記録が不足していても、従業員の声や業務内容の見直しを通じて状況を把握することが重要です。過度な残業が慢性化している場合は、すぐに改善策を講じる必要があります。具体的な対策として、業務の効率化、リソースの適正配分、チームの再編成、労働時間の見直しなどがあります。これにより、長時間労働の根本原因を解消し、持続可能な業務環境を整えましょう。適切な勤怠管理システムの導入も考慮し、労働基準法を遵守した労務管理を実現しましょう。
4-4. クラウド型勤怠管理システムの導入を検討してみる
クラウド型勤怠管理システムの導入は、勤怠管理をしていない会社に対する最適な対処方法です。法律を遵守した勤怠管理の実施をサポートし、リスクを軽減します。勤怠管理システムは、勤怠に関する業務に特化したITツールで、正確なデータ収集と簡便な操作性を提供します。例えば、従業員の打刻によって記録された労働時間を一元管理し、本社にいながら全国の拠点の勤怠状況をリアルタイムに確認することが可能です。
また、パソコンのログインや入退室管理システムと連携できるため、不正打刻や打刻忘れなどの問題も回避できます。これにより、担当者や従業員の負担を軽減し、効率的な勤怠管理を実現します。スマホアプリによる打刻やGPS機能での位置情報付与など、利便性の高い機能も備えているため、導入を強く検討する価値があります。
5. 自社に合ったシステムを見つけるためのポイント


勤怠管理システムには、①タイムレコーダー型、②社内サーバーを活用するオンプレミス型、③インターネットを活用して管理するクラウド型の3つに分類されることが大半です。
以上3つのシステムから、自社に合ったシステムを見つけるために『自社の勤務ルールとの相性』を優先して検討されることをおすすめします。例えば、自社で一般的と考えられていた勤務ルールが、一般的には珍しい場合があります。
自社に合ったシステムを見つけるためには次のようなポイントを意識しましょう。
- 自社の課題を洗い出す
- 他のシステムと連携できる
- サポート体制が整っている
- 法令遵守をサポートする
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
5-1. 自社の課題を洗い出す
自社にあった勤怠管理システムを導入するには、まずどのような課題があるかを洗い出しましょう。自社の課題を洗い出すことで、どのような機能が備わった勤怠管理システムが必要かが明確になります。例えば有給休暇の管理に課題を感じていれば、有給休暇の管理機能が備わったシステムを選びましょう。
5-2. 他のシステムと連携できる
勤怠管理システムはその他のシステムと連携可能です。他のシステムと連携することで、より業務を効率的に進められるでしょう。例えば給与計算システムと連携させれば、従業員それぞれの勤怠情報から自動的に給与計算に反映ができます。給与計算システム以外にも勤怠管理システムと連携できるシステムはさまざまです。まずはどのようなシステムと連携させたいかを確認しましょう。
5-3. サポート体制が整っている
勤怠管理システムを導入する際はサポート体制が整っているかも確認しましょう。勤怠管理システムを導入したからといって、運用を始めるとさまざまな疑問点が出てくる可能性があります。そのため、勤怠管理をする管理者が問い合わせできるサポート体制が整っているシステムを選ぶのがおすすめです。サポート体制が整っていれば、導入時の設定についての不明点も解消できます。
5-4. 法令遵守をサポートする
勤怠に関する法令は更新されることがあります。法令が更新されるたびに新たなルールに適応していかなければなりません。このようなルールへの対応を自社でおこなっていると、時間がかかってしまうだけでなく、認識のミスにつながりかねません。そのため、自動で改正に適用できるようなシステムを選びましょう。このようなシステムであれば常に法令を遵守した運用が可能です。
6. 勤怠時間を管理することは企業の義務!
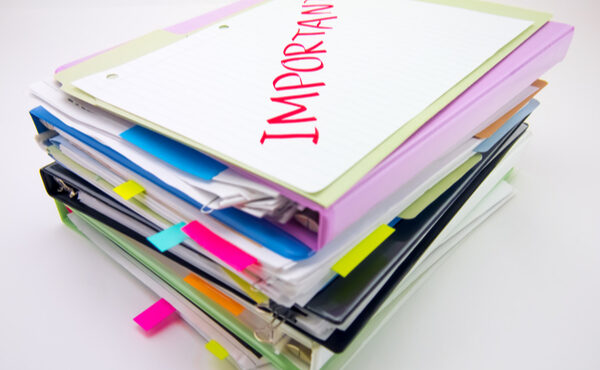
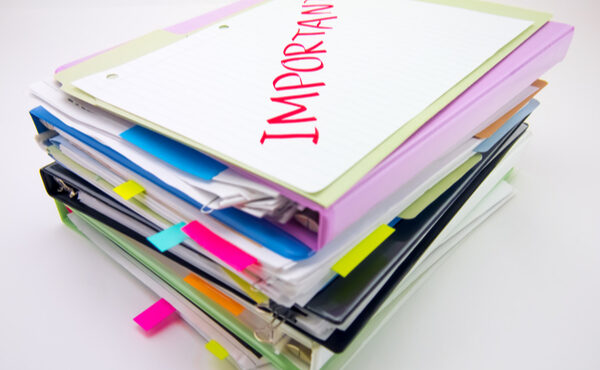
いかがでしたか。勤怠管理を正しくこなっていない企業には大きなリスクがあります。従業員の勤怠管理を正しくおこなうことで、従業員から自社への帰属意識が生まれるだけではなく、社会から正当な評価を受ける判断材料の一つになるでしょう。
勤怠管理を正しくおこなうためには、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。勤怠管理システムであれば他のシステムとの連携や法改正への対応がスムーズになります。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
勤怠管理の関連記事
-


勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック
勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.10.18
-

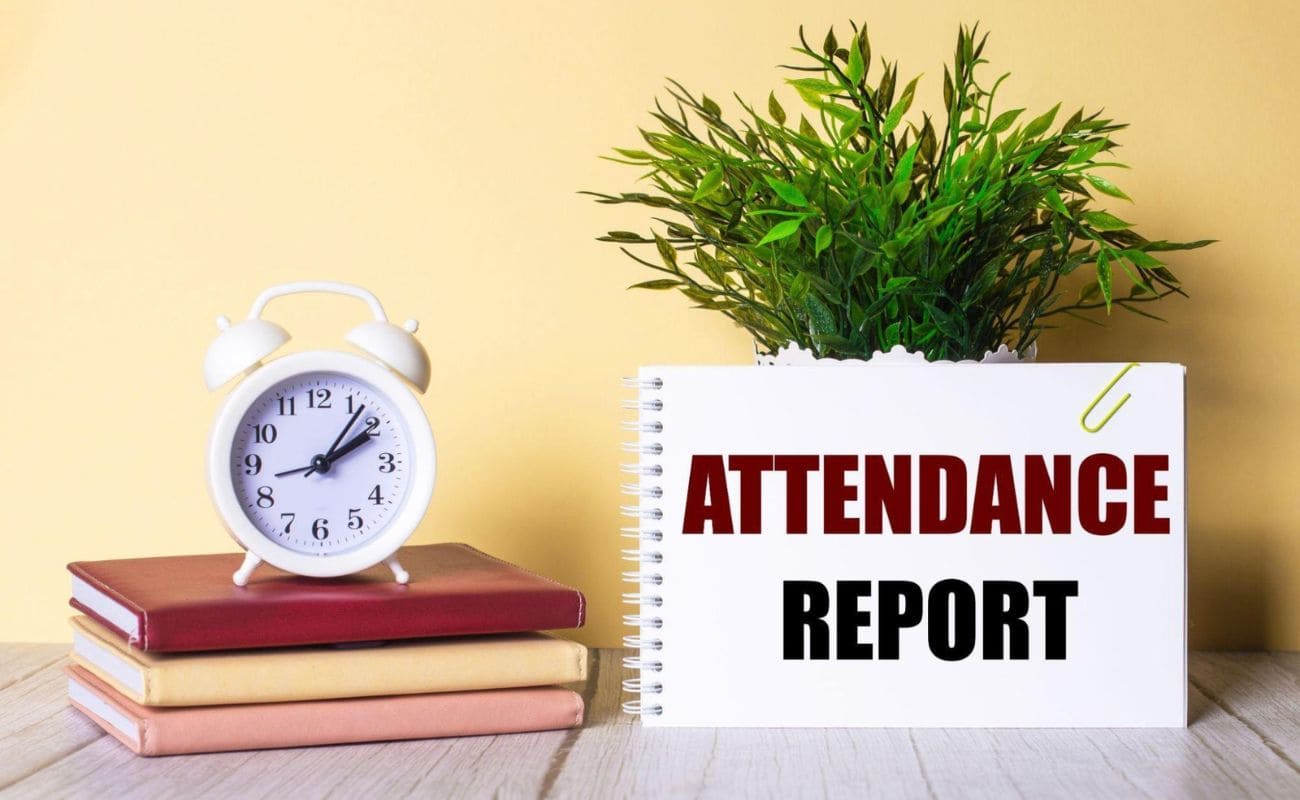
勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.07.04
-


タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.08.02




















