役員の勤怠管理は必要?従業員との違いや各種保険について解説

勤怠管理は従業員の出退勤情報について把握するためにおこなっていますが、役員には適用されるのでしょうか。実は、従業員と役員とは、分けて管理する必要があります。
今回は、役員の役割や従業員との違い、勤怠管理の必要性などについて詳しく解説します。
2019年から2023年にかけ、改正労働基準法の施行が数多くありました。中には罰則が設けられているものもあるため、確実に対応する必要があります。
法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。
資料では2019年以降でに施行された改正労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、こちらから資料のダウンロードページをご覧ください。
目次
1. 役員の役割とは

一般的に役員とは、企業内の業務執行、業務・会計の監査などの権限を持つ幹部職員を指しますが、会社法では取締役・会計参与・監査役などが該当すると定義されています。
本項目では、それぞれの役員が何について担当しているのかについて解説します。
1-1. 取締役
取締役は、株式会社を設立する際に必ず設置が求められる役職であり、取締役会を設置している場合には、取締役会のメンバーとして企業の業務遂行に関する意思決定に参加します。
また、社長=代表取締役と思われがちですが、必ずしも社長が代表取締役というわけではありません。
代表取締役が取締役会のリーダーであることに対して、社長は従業員の中の最高権力者に該当します。
しかし、多くの企業では「代表取締役社長」として代表取締役と社長を兼任していることから、社長=取締役という認識が広まっていると考えられます。
1-2. 専務取締役
専務取締役は、企業全体を統括し、自社の経営において代表取締役を補助する役割があります。
具体的な業務内容は企業によって異なりますが、「企業全体の監督と管理」や「経営方針の決定と執行」が主な業務です。企業全体の管理では、経営方針や事業戦略を達成をするために部署ごとの業務の流れを監督して、適切な指示を出します。
経営方針の執行では、社長の意思決定をサポートするナンバー2として、経営戦略や目標とする方針に対する意見を提案したり、経営戦略を執行するための具体的な指示を出すのが業務となります。
1-3. 常務取締役
常務取締役には、企業の自社業務を統括し、自社の経営において代表取締役・専務取締役を補助する役割があります。
常務取締役は「役員」の位置づけですが、「従業員よりの役員」という特徴のが特徴です。従業員の労働状況を把握し、業務効率をアップするマネジメントや、現場のリーダーを統率して意思決定をおこなう、役職者の指導・育成などが主な業務です。
1-4. 監査役
監査役は株主総会で選出され、取締役・会計参与の職務を監査します。
監査役には業務監査・会計監査の権限があると定義している企業が一般的です。監査役を設置することで、企業経営の健全性を担保する役割を担っています。不正が見つかった際には、取締役会に差止請求をしたり、株主総会で報告をしたりするという重要な役割を持っているのが監査役の特徴です。
1-5.執行役員
執行役員は、役員という名前がついていますが従業員です。「従業員でありながら経営にも関わる」という特殊な立場となるのが執行役員の特徴です。
取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行をおこなう最終責任者となります。「常務」と同じく会社法による規定はなく、社内ルールに則ったポジションなので、報酬体系も従業員と同じ定義となっています。そのため、取締役会へ参加する権利はありません。
2. 役員と従業員の違いとは

役員は労働者である従業員を雇用している側であることに対して、従業員は労働者として雇われている側です。
会社法では、役員は「使用人」と定義されていることから、役員と従業員の関係は、使用人と労働者の関係となります。
また、企業と役員の関係は委任契約もしくは準委任契約となるため、「企業から経営を依頼されている」という契約関係となります。
そのため、従業員は役職や能力などに応じて企業から給与を受け取りますが、役員は企業から株主総会で定められた任務遂行の対価として報酬を受け取ります。
3. 常勤役員と非常勤役員について
 「役員」の中でも違いが分かりづらいのが、「常勤役員」と「非常勤役員」ではないでしょうか。「常勤」「非常勤」といっているため、勤務日数で判断するように思えますが、実は常勤役員と非常勤役員の違いについて明確に定めている法律は存在しません。
「役員」の中でも違いが分かりづらいのが、「常勤役員」と「非常勤役員」ではないでしょうか。「常勤」「非常勤」といっているため、勤務日数で判断するように思えますが、実は常勤役員と非常勤役員の違いについて明確に定めている法律は存在しません。
したがって、これらの役員の設置や業務内容は、各企業の判断に委ねられることになります。一般的に常勤役員は勤務日数が企業の所定労働日数分である役員、非常勤役員は所定労働日数よりも少なくスポット的に勤務する役員を指すことが多いようです。
4. 役員に勤怠管理は必要?

従業員は給与制なので、勤務管理をする必要があります。しかし、役員は委任契約もしくは準委任契約となるため、一般的な「お給料」はありません。そのため、役員の勤務管理に関して悩んでしまう担当者も多いのではないでしょうか。
ここでは、役員に勤務管理が必要なのかを解説していきます。
4-1. 役員には労働基準法と就業規則が適用されない
労働基準法や就業規則が適用されるのは、使用人と雇用契約を結んでいる労働者になります。役員は法人と委任契約を結んでいるため、労働者にはあたらないことから労働基準法と就業規則が適用されません。
つまり、労働時間や欠勤・遅刻などの管理をする必要がないので、勤怠管理が不要となっています。
役員には、労働基準法によって定められている労働時間や残業時間の上限はなく、休憩の付与、休日や有給休暇など休日休暇の付与も一切いりません。
個別に契約している委任契約に従い、企業の経営を維持・向上させることが役員のミッションです。基本的には、働く時間などは決まっていないため、役員は勤怠管理をする必要がないということです。
4-2. 使用人兼務役員や役員から従業員になった場合には勤怠管理が必要
雇用契約のない役員には勤怠管理の必要はありませんが、委任契約と雇用契約の両方を結んでいる「使用人兼務役員」には、一部勤怠管理が必要になることがあります。
使用人兼務役員は「取締役営業部長」など、役員でありながら従業員としての役割ももっているため、委任契約と雇用契約が両方適用されます。したがって、使用者の指揮命令に基づいて実際の業務をおこなっており、労働者としての側面が強い場合は、有給休暇の付与などを含めた勤怠管理の必要性がでてきます。
また、役員から従業員なった場合、労働者として雇用契約を使用者と結ぶので、労働基準法や就業規則が適用されます。そのため、以前役員であったとしても現在従業員であるならば、勤怠管理が必要になります。
関連記事:勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!
5. 役員に対する労災、雇用、社会保険の適用について

役員と従業員の違いから勤怠管理の必要性を解説しましたが、役員の場合、保険関連をどのようにすればいいかが分かりづらいという側面があります。
ここでは役員の労災、雇用、社会保険の適用について解説していくので、従業員との違いをしっかりと理解していきましょう。
*ここで説明する役員とは、従業員として兼務していない役員であることを前提とします。
5-1. 労災保険では役員は被保険者ではない
労災保険の正式名称は労働者災害補償保険です。
雇用されている労働者が通勤途中もしくは仕事中に発生した出来事に起因した怪我や病気、障害、死亡したときに労働者もしくはその遺族に対して補償される保険です。
つまり、名前の通り対象者は労働者(従業員)ですので、役員は対象外(被保険者ではない)です。
5-2. 雇用保険では役員は被保険者ではない
雇用されている労働者の生活および雇用の安定、就職の促進のために失業した方もしくは教育訓練を受ける方に対して失業保険が給付される制度です。
制度の内容から分かるように、雇用されている労働者が対象となるため役員は対象外です。
5-3. 社会保険では役員も被保険者となる
労災保険や雇用保険とは異なり、社会保険というのは役員か否かは関係なく、企業などに使用され働いた対償として報酬を得ている人が被保険者となります。
社会保険の定義において、役員は「企業という法人に使用され報酬を得ている」という考えに該当します。そのため、役員でも社会保険には加入できます。
6. 従業員が出向先で役員となる場合の勤怠管理

勤務形態の中には、「勤めている企業では従業員、出向する先の企業で役員として勤める」というケースがあります。「基本的に従業員なので出向先では役員」という複雑な勤務形態の場合、勤怠管理は必要になるのでしょうか。
*出向することが決まり出向元を退職する形態は除外します。
6-1. 出向元では従業員であるため勤怠管理は必要
出向先で役員として勤務しても、出向元では従業員であるため、出向元側で勤務状況を把握しなければなりません。そのため、従業員が出向先で「何時に出社して何時に退社しているか」など出退勤記録を記録する必要があります。
ただし、出向で勤務先が別企業となる場合は、どのように勤務状況を管理するかを個別で決める形になります。出向元側での記録が難しいようであれば、出向先に管理を依頼するか、システムなどを利用して出向先で打刻処理をするなど、管理方法を決めておきましょう。
また、出向する従業員と出向する相手に対しては、「出向先では役員だが、出向元では従業員である」ということを理解してもらい、勤怠管理をする必要がある旨を説明しておくと安心です。
6-2. 給料の支払いは、出向元、出向先のどちらかになる
出向している従業員への給料については、出向元が支払う場合と出向先が支払う場合のどちらのパターンもあります。
出向元が従業員に給与を支払う場合は、別途出向料として出向先から出向元に支払います。出向先から出向料を支払う場合は役員報酬に該当するため、株主総会決議の範囲内の報酬であるかを確認しなければなりません。また、出向元が賞与を支給する場合は、賞与に該当する金額を出向先に請求することがあるため、事前に取り決めをしておきましょう。
7. 役員の勤怠管理の必要性は雇用形態でチェックしよう

勤怠管理は、「従業員」や「正社員」など雇用契約を結んでいる人が対象です。役員と企業には「雇用契約」がないため、勤怠管理をする必要はありません。
ただし、「役員であっても従業員としての業務もおこなっている」「従業員だけど出向先で役員として働いている」など、一般の役員とは異なる立場の方もいます。従業員であれば勤怠管理は必要なので、担当者の方は雇用形態をしっかり把握しておきましょう。
2019年から2023年にかけ、改正労働基準法の施行が数多くありました。中には罰則が設けられているものもあるため、確実に対応する必要があります。
法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。
資料では2019年以降でに施行された改正労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、こちらから資料のダウンロードページをご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
勤怠管理の関連記事
-


勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック
勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.10.18
-

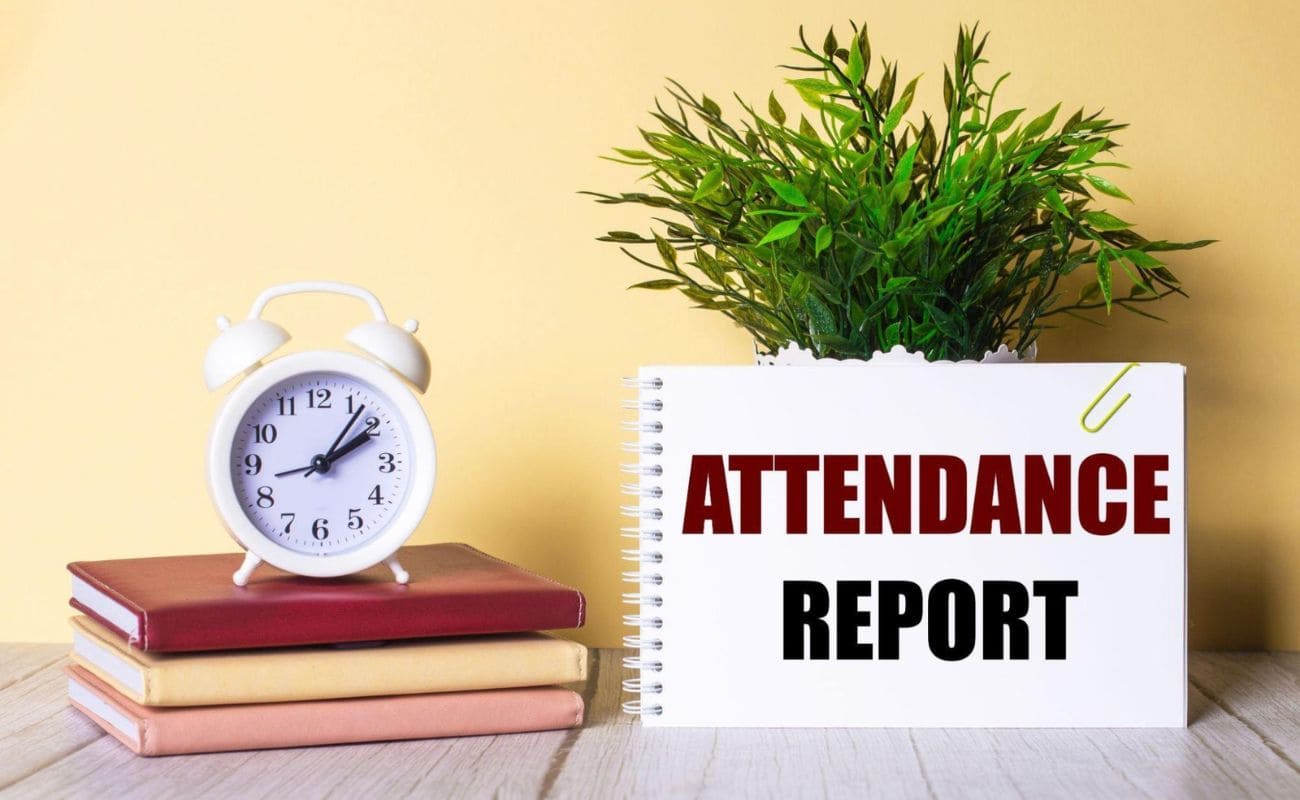
勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.07.04
-


タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.08.02




















