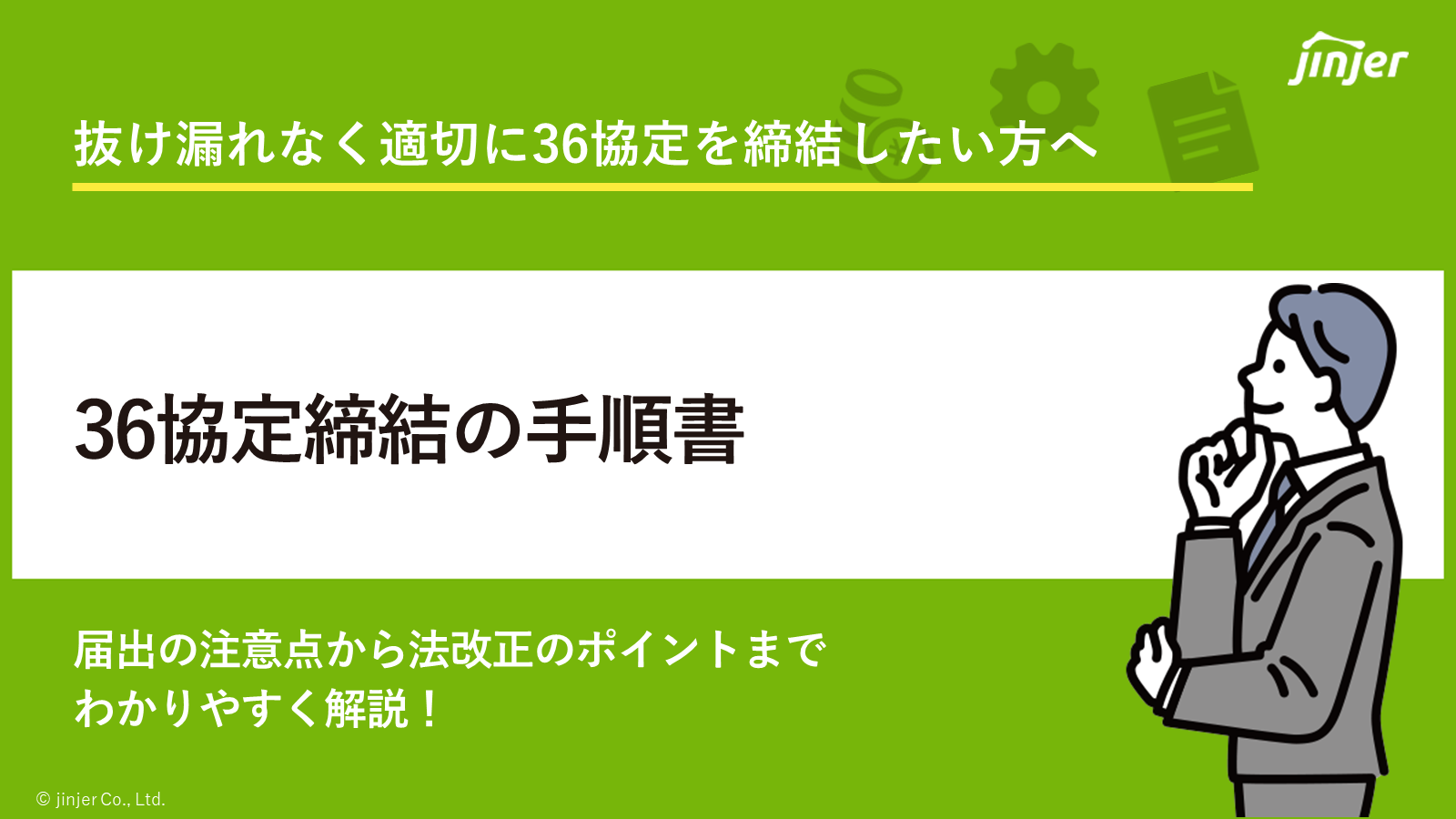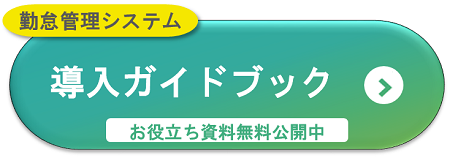36協定はすべての企業に必要?対応する勤怠管理システムの選び方を解説

勤怠管理で欠かせないのが残業時間の管理です。勤怠管理をおこなう際は36協定の内容を正確に把握しておく必要があります。
「36協定について理解できていない」
「36協定に必要な勤怠管理システムの機能を知りたい」
など、36協定に関する悩みや疑問を抱えている人事担当者は少なくありません。
本記事ではそのような問題に対し、36協定の基本と業務効率化ができる勤怠システムを解説して解決をサポートします。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 36(サブロク)協定とは?

36協定は労使協定の一つで、ほとんどの企業で締結されているものです。36協定の内容や必要性、届け出をしなかった場合の問題をまずは知っておきましょう。
1-1. 残業や休日出勤を命じる場合に必要な労使協定
36協定は労使協定の中でも特に有名な、残業や休日労働を従業員に命じる際に必要な協定です。従業員が法定労働時間の1日8時間、週に40時間を超えて労働する場合に必要です。
また、労使間で合意したうえで締結することに加え、事業場を管轄する労働基準監督署への届け出もおこなわなければいけません。そのため、36協定は簡単に締結できるものではなく、労使間の相談や届出までに要する時間を考えて事前に締結しておく必要があります。
1-2. すべての企業で届け出が必要なわけではない
36協定は従業員に「時間外労働」や「休日出勤」を命じる可能性がわずかでもある場合は、届け出をしておかなくてはいけません。時間外労働や休日出勤が一切ない企業の場合は不要です。
時間外労働に当てはまるのは、労働基準法に定められている「1日8時間」または「1週40時間」を超過した場合です。もしも36協定なしで時間外労働や休日労働を従業員にさせた場合、それが短時間であっても労働基準法に違反したことになります。
1-3. 36協定の届出なしで時間外労働させたら違法になる
従業員に時間外労働を命じる可能性がある企業は、36協定の届出を出す必要があることは前述のとおりです。
この届出を出さずに時間外労働や休日出勤をさせた場合、労働基準法違反となってその雇用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられることもあります。時間外労働や休日労働が発生する前に必ず届出をおこない、ルール違反にならないように気をつけましょう。
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
2. 36協定の締結で定められること

36協定を締結することで、勤務時間や休日にはどのような変化が生じるのか、この点についても理解しておきましょう。
2-1. 時間外労働や休日出勤ができる
先述のとおり、36協定の届出を出すことで従業員に時間外労働や休日出勤させることができるようになります。しかし、無制限に時間外労働をさせて良いというわけではありません。時間外労働には上限が定められており、36協定を結んでいてもこの上限を超えて労働させた場合は違法になります。
2-2. 時間外労働には上限がある
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年では360時間とされています。中小企業には2020年3月までの猶予期間がありましたが、現在はその期間も過ぎているため、すべての企業はこの上限を守らなくてはいけません。つまり、1日の残業はおよそ2時間が限界という計算になります。
ただし、特別な事情がある場合については、特別条項付の労使協定を締結することで、年に720時間以内、複数月の平均で80時間以内かつ単月にして100時間未満であれば時間外労働が可能です。しかし、月45時間かつ年360時間の原則を超えることができるこの特例の適用は、年半分を超えないこと、すなわち年間6ヶ月までともされています。
こうした上限は従業員の健康を守り、健全な労働環境を維持するために設定されています。厳守し、働きすぎによる問題が発生しないように気を付けましょう。
関連記事:【2021年最新版】労働基準法改正による勤怠管理への影響と罰則回避の対策
2-3. 時間外労働には割増賃金の支払いが必要
時間外労働には割増賃金が発生し、企業側には支払う義務があります。割増賃金の支払いは、1日8時間、もしくは1週間に40時間を超過した場合の「時間外労働」と「休日労働」、午後10時から午前5時までの「深夜労働」が対象になります。それぞれの割増率は以下の通りです。
・時間外労働と深夜労働は、割増率25%(月60時間超の時間外労働は割増率50%)
・休日労働は、割増率35%
3. 36協定に必要な勤怠管理システムの機能

36協定をしっかり守って労働基準法違反にならないためには、勤怠管理システムを用いて従業員の勤務状況が可視化できる環境を整えておく必要があります。そのためには、以下のような機能を備えた勤怠管理システムの導入がおすすめです。
3-1. 残業申請の提出ができる
36協定を定めている場合でも、従業員を残業させる場合には時間外労働の上限に気をつけなければいけません。個人の残業時間をしっかり把握するために、従業員が正確に申請し、それを上司が承認するといったワークフローをしっかり整えておく必要があります。
ワークフローを整備することで従業員の残業時間を的確に把握できるようになり、残業時間が超過している従業員の申請を却下することも可能になります。勤怠管理システムの中には、残業申請のワークフローが機能に搭載されているものもあります。
ワークフローに関するシステムを単独で導入するよりも、勤怠管理システムとセットになっているものを導入する方が業務を一元管理しやすいです。
3-2. 従業員や上司が残業時間を確認できる
勤怠管理システムには、従業員や上司が個人の残業時間を確認できる機能が付いています。この機能があれば視覚的にわかりやすく残業時間を把握でき、働きすぎの予防ができます。
また、残業時間の上限を超過しそうな場合、当該従業員や上司に残業時間超過の警告をメールなどで知らせてくれる機能が搭載されているものもあります。この警告機能があれば、計画的に残業ができ、気づかずに時間外労働の上限を超えてしまうという問題を解決できるでしょう。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
4. 36協定の内容を理解して適した勤怠管理システムを導入しよう

36協定は、従業員に時間外労働をさせる場合に会社と従業員の間で必ず取り交わす必要がある労使協定です。時間外労働や休日出勤を命じる場合には、必ず締結して届け出を出しておきましょう。加えて、時間外労働の上限にも注意して従業員の労働時間を管理することも忘れてはいけません。
そのためには、36協定に適した勤怠管理システムを導入することがおすすめです。人材管理や給与計算など、さまざまな業務を効率化できるため、人事担当者の負担増にお悩みの際はぜひご検討ください。
\\ 36協定対応の勤怠管理システムは「ジンジャー勤怠」がおすすめ //
36協定に正しく対応していないと場合によっては、労働基準法違反となる可能性もあります。
36協定に対応した勤怠管理システムを検討している方には、機能が豊富なジンジャー勤怠がおすすめです。
ジンジャー勤怠には、36協定に対応するためのさまざまな機能があります。
下記はその一例です。
- アラート機能で36協定違反を未然に回避
- 残業の申請・承認が可能
- 残業時間の自動集計
勤怠管理システムを活用して、36協定に問題なく対応したいと考えている方は、以下のフォームよりお気軽にご相談ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25