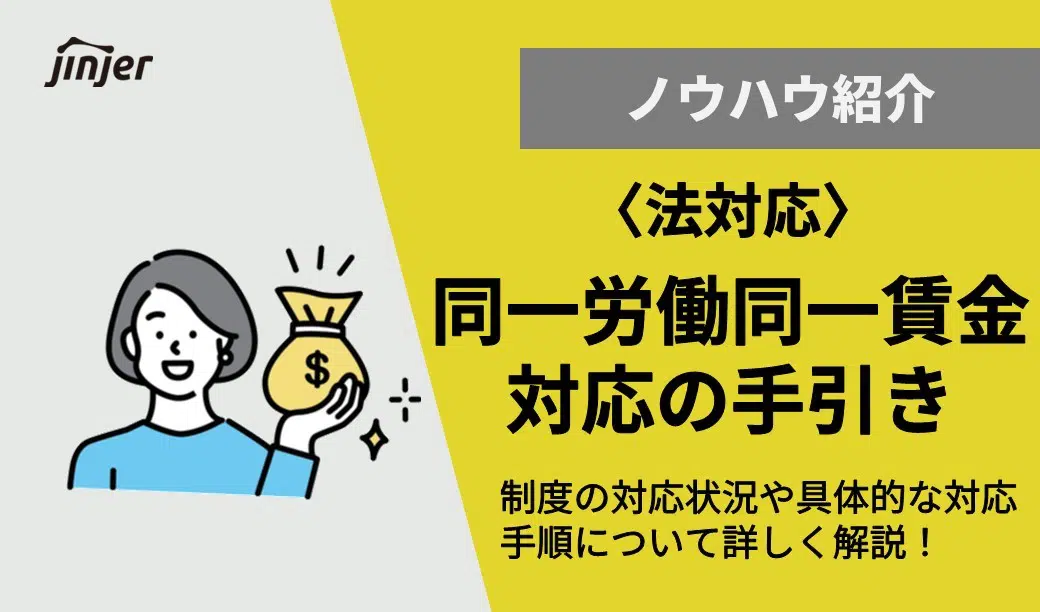パートタイム・有期雇用労働法に定められた罰則の詳細を解説
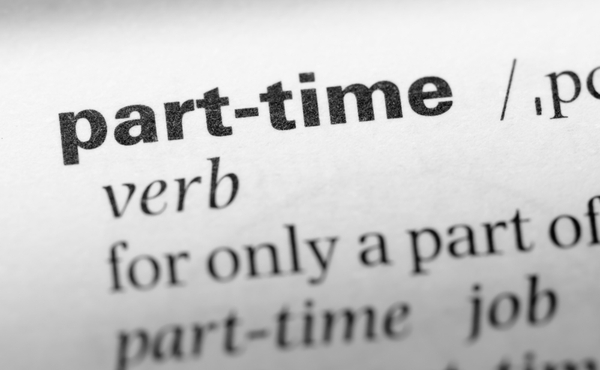
働き方改革の一環として、2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が改正施行されました。しかし施行されたからといって、すぐに会社の実態を法律に合わせるのも難しいのではないでしょうか。この記事ではパートタイム・有期雇用労働法の罰則にはどのようなものがあるのか、違反しないための対策などについて説明します。
▼パートタイム・有期雇用労働法と併せて知りたい「同一労働同一賃金」についてはこちら
同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて
目次
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1.パートタイム・有期雇用労働法に定められた罰則とは?

パートタイム・有期雇用労働法とは正式な名称を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。この法律にある罰則は二つです。それぞれについて説明します。
1-1.雇用時に特定事項を明示しない
一つは第6条第1項違反です。
その内容は「第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。」というものです。
罰則については第31条に「第三十一条 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」と定められています。[注1]
第6条第1項の内容を簡単にいうと、短時間・有期雇用労働者を雇ったときは、特定事項を明示しなければならないというものです。特定事項は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」の第2条に「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善に関する相談窓口」と規定されています。[注2]
違反した場合はまず行政指導が行われます。行政指導を行っても改善が見られない場合に、労働者1人につき、契約ごとに10万円以下の過料が科せられるのです。
またパートタイム・有期雇用労働法以外に、労働基準法でも雇い入れの際は労働条件の明示が定められています。こちらに違反をすると30万円以下の罰金です。
[注1]短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索
[注2]短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法による賞与規定を詳しく解説
1-2.行政指導に対して報告をしない、または虚偽の報告をする
もう一つ罰則があるのはパートタイム・有期雇用労働法の第18条第1項です。
その内容は「第十八条 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」というものです。罰則については同法第30条に「第三十条 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」とされています。[注1]
この条文はパートタイマーや有期雇用者の雇用を改善するために、労働局が行政指導を行えると定めたものです。労働局からの求めに対して報告をしなかったり、嘘の報告をしたりすると過料が科せられます。
1-3.同一労働同一賃金は?
パートタイム・有期雇用労働法は、従来パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)と呼ばれていました。しかし2018年に成立した働き方改革関連法により、パートタイム労働法も同一労働同一賃金を謳って2020年4月に改正施行され、今の名称に改められたのです。
改正後のパートタイム・有期雇用労働法では、不合理な待遇の禁止や差別的取扱いの禁止が規定されたのが主な改正点です。しかし、これらには現在のところ罰則はありません。
ただし、人材流出や損害賠償などのリスクは生じるため、注意が必要です。
当サイトでは、同一労働同一賃金に関して、基礎知識や合理的な待遇差の考え方について解説した資料を無料で配布しております。同一労働同一賃金への対応に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「同一労働同一賃金 対応の手引き」をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:同一労働同一賃金はいつから適用された?ガイドラインの考え方や対策について
2.パートタイム・有期雇用労働法による罰則の種類

パートタイム・有期雇用労働法の罰則は過料のみです。過料とはなにかについて説明します。
2-1.過料とは
過料とは行政上の義務違反に対する罰です。ただし過料が科されても前科はつきません。また過料が科されたことに対して弁明する機会も設けられています。弁明の内容によっては過料を支払わなくてもよいケースもあります。
2-2.罰金、科料との違い
過料と一緒にしてしまいがちなものとして罰金と科料があります。罰金、科料は裁判の判決によって下される財産刑です。このため過料とは異なり前科がつくのが大きな違いです。過料と違って弁明の機会はなく、判決で決まってしまえば財産が強制的に徴収されてしまいます。
もしも払うお金がないときは、労役場に留置されて罰金分の労役をしなくてはなりません。過料についても科された金額を払わなければ、財産を差し押さえられることもありますが、労役場留置はないのが異なる点です。
なお罰金と科料との違いは金額だけで中身は同じものです。罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満です。
また過料と科料は読み方が同じで間違えそうになってしまいます。しかし今説明したように、両者は性質がまったく異なるものです。そのため過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と読んで区別することもあります。
2-3.行政指導は罰則?
先ほども少し説明しましたが、パートタイム・有期雇用労働法第18条第1項で、法律の実効性を高めるために労働局による行政指導ができると規定されています。この行政指導は罰則ではなく、あくまで指導です。
しかし、同条第2項で「厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。」と規定されており、指導に従わない場合は事業者名や行政指導に従っていない旨を公表できます。
もしも公表されるようなことになれば、企業の信用に傷がついてしまいます。罰則ではありませんが、大きなダメージを受ける可能性があります。
3.パートタイム・有期雇用労働法による罰則に違反しないために

パートタイム・有期雇用労働法で罰則が定められた規定は2つしかありません。これらの罰則が適用されないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
3-1.「雇用時に特定事項を明示しない」で違反をしないために
雇用時にはパートタイム・有期雇用労働法だけではなく労働基準法でも明示すべき事項が定められています。明示しなければならない項目をしっかりと把握して漏れがないようにしましょう。
またこの規定に違反した場合でも、いきなり過料が科せられるわけではなく、まずは行政指導があります。行政指導があった際はただちに改善しましょう。
3-2.「行政指導に対して報告をしない、または虚偽の報告をする」で違反をしないために
行政指導が入ってしまった場合には、真摯に受け止めて指導事項を改善していきましょう。報告も虚偽を交えることなく、きちんと対応していれば過料まで科されることはないはずです。
4.会社の実態を法律に合わせていく

パートタイム・有期雇用労働法に定められた罰則は、今のところ2つだけで、同一労働同一賃金については罰則がありません。しかし罰則がないからといってそれらを無視していると、従業員から民事訴訟を起こされる可能性などがあります。
パートタイム・有期雇用労働法に定められた規定をきちんと理解して、早めに会社の実態を法律に合わせていくことが大切です。
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08