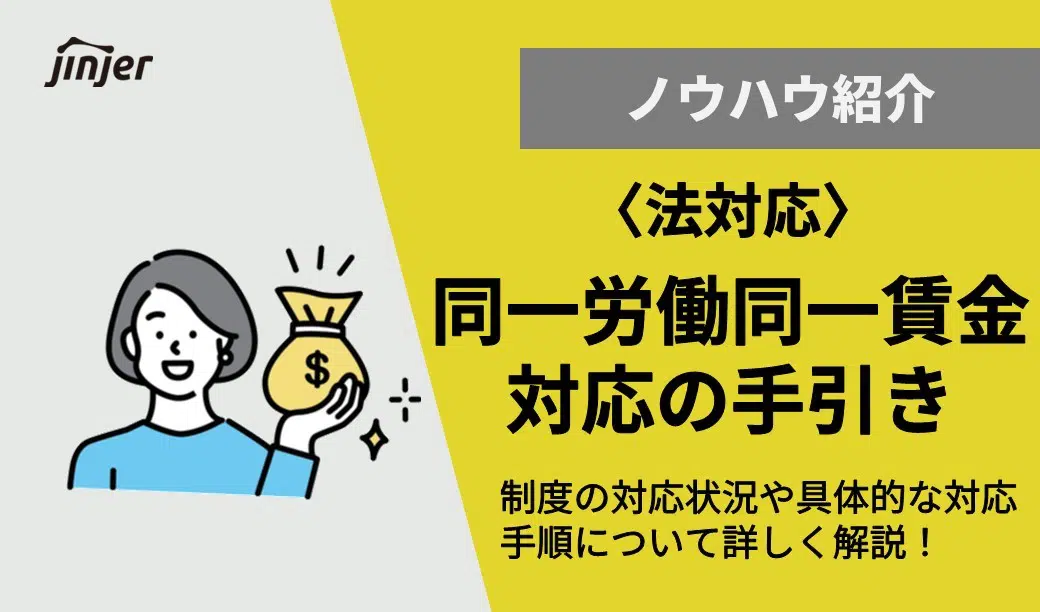同一労働同一賃金はいつから適用された?ガイドラインの考え方や対策について
更新日: 2024.3.25
公開日: 2022.1.21
OHSUGI
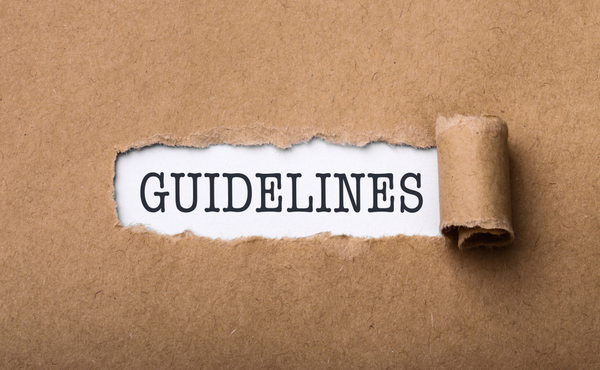
2018年6月29日の働き方改革関連法の成立に伴い、すべての企業を対象とした「同一労働同一賃金」が導入されました。すでに大企業では2020年4月より適用されており、中小企業も一定の猶予期間があるものの、同一労働同一賃金の導入が進んでいます。
これから同一労働同一賃金の実現に向けて取り組む企業は、同一労働同一賃金が適用されたタイミングを改めて確認しておきましょう。
この記事では、同一労働同一賃金の導入時期や、同一労働同一賃金の導入に欠かせないガイドラインの内容、企業が取り組むべき同一労働同一賃金の対策について詳しく解説していきます。
▼そもそも「同一労働同一賃金とは?」という方はこちら
同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて
目次
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 同一労働同一賃金はいつから適用された?大企業・中小企業それぞれの導入時期を解説

そもそも同一労働同一賃金がいつから施行されたかというと、2020年4月1日からです。同一労働同一賃金は2020年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」で整備されたものです。
パートタイム・有期雇用労働法が適用されたのは、大企業では2020年4月1日から、中小企業では1年の猶予期間を経た2021年4月1日からです。つまり、大企業・中小企業ともに同一労働同一賃金の適用がすでにスタートしており、不合理な待遇差の解消に向けた取り組みが必要です。
なお、厚生労働省によると、中小企業とは以下の定義のいずれかを満たす事業者のことを指します。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | |
| その他(製造業、建築業、運輸業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
不合理な待遇差の解消のため、就業規則の見直しなどが必要になった場合、労働者への説明が求められるケースがあります。同一労働同一賃金の実現に向けて、中小企業も早めの準備をおこないましょう。
参考:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲|厚生労働省
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法の内容を分かりやすく解説
関連記事:同一労働同一賃金が中小企業に適用されどう変わった?
2. 同一労働同一賃金ガイドラインの考え方4つのポイント

厚生労働省は同一労働同一賃金の導入を目指す企業を対象として、「同一労働同一賃金ガイドライン」を作成しています。同一労働同一賃金ガイドラインには、同一労働同一賃金の実現のために企業が対応しなければならない4つの取組内容が記載されています。
厚生労働省のガイドラインの要点を順に解説します。
2-1. 基本給・昇給の不合理な待遇差をなくす
基本給には、企業の給与体系によって「労働者の能力又は経験に応じて支払うもの」「業績又は成果に応じて支払うもの」「勤続年数に応じて支払うもの」など、さまざまなものがあります。
厚生労働省のガイドラインでは、いずれの形態の基本給でも、「実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給」をおこなうよう求めています。
また、昇給についても雇用形態によらず、「同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給」をおこなう必要があります。
2-2. 賞与も労働者の貢献に応じて支給する
基本給だけでなく、毎年の賞与(ボーナス)の不合理な待遇差をなくすことも大切です。厚生労働省のガイドラインに基づき、賞与は「同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給」をおこないましょう。
なお、派遣労働者の場合、派遣元の企業は原則として、派遣先労働者と同等の賞与を支給する必要があります。
関連記事:同一労働同一賃金で業務における責任の程度はどう変化する?
関連記事:労使協定方式や同一労働同一賃金における派遣会社の責任について
関連記事:同一労働同一賃金で就業規則の見直しは必要?待遇差の要素や注意点
2-3. 各種手当も同一の労働に対し同一の支給をおこなう
また、各種手当についても同一の労働に対し、原則的に同一の支給をおこなわなければなりません。
厚生労働省のガイドラインでは、各種手当として「役職手当」「特殊作業手当」「特殊勤務手当」「精皆勤手当」「時間外労働手当」「深夜・休日労働手当」「通勤手当・出張旅費」「食事手当」「単身赴任手当」「地域手当」などを挙げています。
これらの手当について、正社員と非正規雇用労働者の間で差別的取扱いをせず、条件が同じ場合は同一の支給をおこなう必要があります。
関連記事:同一労働同一賃金で各種手当はどうなる?最高裁判例や待遇差に関して
関連記事:同一労働同一賃金で交通費はどうなる?判例や課税について解説
2-4. 福利厚生や教育訓練の機会を均等化する
雇用形態によらず、福利厚生や教育訓練の機会を均等化することも大切です。厚生労働省のガイドラインでは、以下のようなものを福利厚生の具体例として例示しています。
- 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用
- 転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用住宅
- 慶弔休暇
- 健康診断に伴う勤務免除・有給保障
- 病気休職
- 法定外の有給休暇その他の休暇
とくに病気休職の場合、無期雇用労働者の場合は正社員と同一の付与を、有期雇用労働者の場合も労働契約期間を考慮したうえで同等の付与をおこなう必要があります。
また、教育訓練の機会についても、「同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施」が求められます。
関連記事:同一労働同一賃金における福利厚生の待遇差や実現するメリットとは
3. 企業が取り組むべき同一労働同一賃金の対策

これから同一労働同一賃金に取り組む企業は、厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を確認しましょう。
パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書は、同一労働同一賃金の実現に向けて、社内制度の点検や改定をおこなうための手順を示したパンフレットです。厚生労働省の手順書によると、企業が取り組むべき同一労働同一賃金の対策は6つのステップに分かれています。
参考:パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書|厚生労働省
労働者の雇用形態を確認する
短時間労働者や有期雇用労働者を雇用している企業は、まずパートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)の対象となる労働者をリストアップします。
待遇の状況を確認する
賃金・賞与・各種手当・福利厚生や教育訓練の4点について、正社員と非正規雇用労働者の間で待遇の違いがあるかどうかチェックします。わかりやすく整理するため、非正規雇用労働者の区分ごとに書き出し、文書化しておくことをおすすめします。
待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認する
正社員と非正規雇用労働者の間で待遇の違いが存在する場合、なぜ取り扱いに差があるのかを確認します。それぞれの働き方や役割の違いに応じ、合理的でバランスのとれた待遇の差が設けられている場合は、同一労働同一賃金の原則に違反していません。こちらも非正規雇用労働者の区分ごとに書き出し、文書化しておきましょう。
待遇の違いが「不合理ではない」ことを説明できるようにしておく
また、パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)では、正社員と非正規雇用労働者の待遇の違いについて、企業が必要に応じ労働者に説明をおこなう義務が発生します。待遇の違いが「不合理ではない」場合も、待遇の差を設けている理由をいつでも説明できるよう、要点を整理しておきましょう。
待遇の違いに「法違反」が疑われる場合は早期の脱却を
もし正社員と非正規雇用労働者の待遇の違いに「法違反」が疑われる場合、早期の脱却が必要です。パートタイム・有期雇用労働法は、特定の罰則を設けているわけではありません。しかし、非正規雇用労働者の活躍の幅を広げ、多様な働き方を実現するため、不合理な待遇差の解消に向けて取り組みましょう。
改善計画を立てて取り組みを進める
同一労働同一賃金の実現のため、改善計画を立てましょう。経営層の目線だけでなく、必要に応じて労働者の意見を聴取し、現場の目線で改善計画を策定することが大切です。
ちなみに同一労働同一賃金を遵守しなくても罰則はありませんが、人材の流出や損害賠償などのリスクが生じるため、実現に向けて担当者は動かなければなりません。 当サイトでは、同一労働同一賃金に対して不安な点があるご担当者様向けに、「同一労働同一賃金 対応の手引き」という資料を無料で配布しております。
同一労働同一賃金の基礎知識や企業が対応すべきことなどを図を用いながら解説しておりますので、不安な点があるご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
4. いよいよ同一労働同一賃金がスタート!厚生労働省のガイドラインを確認しよう

同一労働同一賃金は、大企業では2020年4月より、中小企業では2021年4月より順次導入が進んでいます。
これから同一労働同一賃金の実現に取り組む企業は、厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」および「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」の2点を確認しましょう。
基本給に限らず、各種手当、賞与、福利厚生や教育訓練において同一労働同一賃金の原則を実現することが大切です。
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08